都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
四季花鳥図屏風がシンガポールへ
と言っても切手のお話です。「BLUE HEAVEN」のTakさんに教えていただき、早速買ってきました。国際文通グリーティング切手(2006/10/3発行)の図案から、酒井抱一の「四季花鳥図屏風」です。
詳しくは「弐代目・青い日記帳」をご覧いただきたいのですが、この切手は単なる記念切手ではありません。国際云々の名の通り、何と同じ図柄のものがシンガポールでも発売されるのです。(郵政公社としては初めての試みだそうです。)そんな栄えある第一号に、我らが(?)抱一の「四季花鳥図屏風」が選ばれた。これは私のような、にわか抱一ファンにもたまらない切手だと思います。
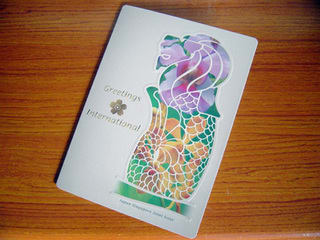
特製ケースの表紙は、シンガポールのシンボルでもあるマーライオンです。蘭のデザインが鮮やかでした。

中はなかなか豪華です。切手はシールタイプのもので、上の4点がシンガポールのお花(国花「バンダ ミス ジョアキム」など。)、下の2点が抱一の「四季花鳥図屏風」の絵柄でした。

抱一の2点です。同じ「四季花鳥図屏風」ですが、上は陽明文庫所蔵の「タチアオイと白鷺」、下は京都国立博物館蔵の「カキツバタとバン」が採用されています。ちなみに陽明文庫蔵の作品は、先日のアートコレクション展(ホテルオークラ)でも展示されていました。



切手に疎い私は全く知らなかったのですが、これまでにも抱一の図柄が採用されたことが幾度かあったようです。まず有名なものでは、代表作の「夏秋草図屏風」が挙げられるかと思います。これは1970年、大阪万博の開催を記念して発売されました。それに最近では、1997年の「第52回国民体育大会記念郵便切手」と2003年の「郵政公社設立記念80円切手」です。ここでは「四季花鳥図巻」が採用されています。また以前、西アフリカのガンビア共和国が発行した「花鳥十二ヵ月図」の切手も流通していたことがあったようです。詳細は不明ですが、日本でも販売されていたそうなので、お持ちの方もいらっしゃるやもしれません。
「四季花鳥図屏風」のデザインによる国際文通グリーティング切手は、全国の郵便局にて500円(切手料額460円)で販売されています。これを機に、風流な抱一の花鳥画にて美しく封書を彩ってみてはいかがでしょうか。
詳しくは「弐代目・青い日記帳」をご覧いただきたいのですが、この切手は単なる記念切手ではありません。国際云々の名の通り、何と同じ図柄のものがシンガポールでも発売されるのです。(郵政公社としては初めての試みだそうです。)そんな栄えある第一号に、我らが(?)抱一の「四季花鳥図屏風」が選ばれた。これは私のような、にわか抱一ファンにもたまらない切手だと思います。
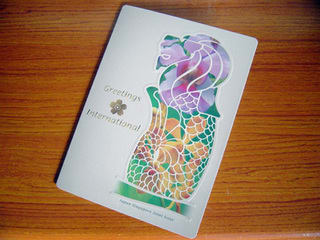
特製ケースの表紙は、シンガポールのシンボルでもあるマーライオンです。蘭のデザインが鮮やかでした。

中はなかなか豪華です。切手はシールタイプのもので、上の4点がシンガポールのお花(国花「バンダ ミス ジョアキム」など。)、下の2点が抱一の「四季花鳥図屏風」の絵柄でした。

抱一の2点です。同じ「四季花鳥図屏風」ですが、上は陽明文庫所蔵の「タチアオイと白鷺」、下は京都国立博物館蔵の「カキツバタとバン」が採用されています。ちなみに陽明文庫蔵の作品は、先日のアートコレクション展(ホテルオークラ)でも展示されていました。



切手に疎い私は全く知らなかったのですが、これまでにも抱一の図柄が採用されたことが幾度かあったようです。まず有名なものでは、代表作の「夏秋草図屏風」が挙げられるかと思います。これは1970年、大阪万博の開催を記念して発売されました。それに最近では、1997年の「第52回国民体育大会記念郵便切手」と2003年の「郵政公社設立記念80円切手」です。ここでは「四季花鳥図巻」が採用されています。また以前、西アフリカのガンビア共和国が発行した「花鳥十二ヵ月図」の切手も流通していたことがあったようです。詳細は不明ですが、日本でも販売されていたそうなので、お持ちの方もいらっしゃるやもしれません。
「四季花鳥図屏風」のデザインによる国際文通グリーティング切手は、全国の郵便局にて500円(切手料額460円)で販売されています。これを機に、風流な抱一の花鳥画にて美しく封書を彩ってみてはいかがでしょうか。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
「広重 二大街道浮世絵展」 千葉市美術館 10/9
千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)
「東海道・木曾街道 - 広重 二大街道浮世絵展」
9/5-10/9(会期終了)

会期最終日の駆け込みで見てきました。千葉市美術館で今日まで開催されていた「広重 二大街道浮世絵展」です。広重の名作「東海道五拾三次」と「木曾街道六十九次」を、ともに初摺りの作品にて全部拝見出来るという贅沢な展覧会でした。
著名な「東海道五拾三次」を初摺りの作品で見るのはともかく、あまり聞き慣れない「木曾街道六十九次」を拝見するのは初めてかもしれません。ちなみに「木曾街道」とは、五街道の一つである中仙道の別称です。江戸・板橋から高崎、それに軽井沢を経由し、佐久方面から諏訪、さらには中津川と関ヶ原を抜けて、草津から京・三条大橋へと向かいます。陽光眩しい駿河路を抜ける東海道と比較すると、遠回りでかつ山がちなので、あまり利用されなかったのではないかと勘ぐってしまいますが、実際にはそれこそ「東西二大街道」の一つとしてたくさんの行き来があったそうです。そしてこの「木曾街道六十九次」では、そんな往時の賑わいを情緒豊かに表現しています。あたかも近世の日本へタイムスリップしたかのような旅情気分を味わいました。

「木曾街道六十九次」のうち、24枚ほどは、美人画の巨匠でもある渓斎英泉の手がけた作品です。つまりこの作品は、広重と英泉の共作と言っても良いでしょう。大胆なデフォルメを凝らしながら、全体の構図には見通しが良い広重と、風景を比較的忠実に描き写しながらも、時に圧倒的な自然の険しさを伝える迫力ある英泉の作品。旅行く人々の情緒は英泉の方が上手く表現されていますが、美感溢れる風景の一コマを鋭く切り取っているのは広重です。当時、初めに描かれた英泉の作品には人気がなく、広重の手に渡ってようやく知名度が増したそうですが、ともに補完し合うかのような別々の魅力を味わうのもまた面白いと思いました。
初摺りの「木曾街道」+「東海道」も見応え十分ですが、それ以上に重要なのは、広重の旅行絵日記の中で唯一現存する作品という、「甲州日記写生帳」(1841)でした。残念ながら、公開はその見開き一ページ分のみで、他は数点のパネル写真が出ているだけでしたが、広重が風景をどのようにして捉えたのかという、その片鱗を楽しめる作品だったと思います。ちなみにこれは、明治時代にイギリスへ渡り、今回何と110年ぶりに里帰りをした作品なのだそうです。これでは次に何時公開されるか見当もつきません。良いタイミングで拝見出来ました。

広重風景画の最高峰とされる「木曾街道六十九次之内 洗馬」の幽玄さは格別です。不気味に照る満月と、おどろおどろしく靡く柳の木の連なり。川面からは夜のジメジメした湿り気が漂い、まるで幽霊でも出てくるような荒涼とした景色が広がります。そして足早に過ぎ行く舟。奥に佇む家々がまるで山の頂ように見えるのも印象的でした。夜の静寂を巧みに表した作品です。
良く出来た図録もまた楽しめます。予想以上に充実した展覧会でした。
「東海道・木曾街道 - 広重 二大街道浮世絵展」
9/5-10/9(会期終了)

会期最終日の駆け込みで見てきました。千葉市美術館で今日まで開催されていた「広重 二大街道浮世絵展」です。広重の名作「東海道五拾三次」と「木曾街道六十九次」を、ともに初摺りの作品にて全部拝見出来るという贅沢な展覧会でした。
著名な「東海道五拾三次」を初摺りの作品で見るのはともかく、あまり聞き慣れない「木曾街道六十九次」を拝見するのは初めてかもしれません。ちなみに「木曾街道」とは、五街道の一つである中仙道の別称です。江戸・板橋から高崎、それに軽井沢を経由し、佐久方面から諏訪、さらには中津川と関ヶ原を抜けて、草津から京・三条大橋へと向かいます。陽光眩しい駿河路を抜ける東海道と比較すると、遠回りでかつ山がちなので、あまり利用されなかったのではないかと勘ぐってしまいますが、実際にはそれこそ「東西二大街道」の一つとしてたくさんの行き来があったそうです。そしてこの「木曾街道六十九次」では、そんな往時の賑わいを情緒豊かに表現しています。あたかも近世の日本へタイムスリップしたかのような旅情気分を味わいました。

「木曾街道六十九次」のうち、24枚ほどは、美人画の巨匠でもある渓斎英泉の手がけた作品です。つまりこの作品は、広重と英泉の共作と言っても良いでしょう。大胆なデフォルメを凝らしながら、全体の構図には見通しが良い広重と、風景を比較的忠実に描き写しながらも、時に圧倒的な自然の険しさを伝える迫力ある英泉の作品。旅行く人々の情緒は英泉の方が上手く表現されていますが、美感溢れる風景の一コマを鋭く切り取っているのは広重です。当時、初めに描かれた英泉の作品には人気がなく、広重の手に渡ってようやく知名度が増したそうですが、ともに補完し合うかのような別々の魅力を味わうのもまた面白いと思いました。
初摺りの「木曾街道」+「東海道」も見応え十分ですが、それ以上に重要なのは、広重の旅行絵日記の中で唯一現存する作品という、「甲州日記写生帳」(1841)でした。残念ながら、公開はその見開き一ページ分のみで、他は数点のパネル写真が出ているだけでしたが、広重が風景をどのようにして捉えたのかという、その片鱗を楽しめる作品だったと思います。ちなみにこれは、明治時代にイギリスへ渡り、今回何と110年ぶりに里帰りをした作品なのだそうです。これでは次に何時公開されるか見当もつきません。良いタイミングで拝見出来ました。

広重風景画の最高峰とされる「木曾街道六十九次之内 洗馬」の幽玄さは格別です。不気味に照る満月と、おどろおどろしく靡く柳の木の連なり。川面からは夜のジメジメした湿り気が漂い、まるで幽霊でも出てくるような荒涼とした景色が広がります。そして足早に過ぎ行く舟。奥に佇む家々がまるで山の頂ように見えるのも印象的でした。夜の静寂を巧みに表した作品です。
良く出来た図録もまた楽しめます。予想以上に充実した展覧会でした。
コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )
「ピカソとモディリアーニの時代」 Bunkamura ザ・ミュージアム 10/1
Bunkamura ザ・ミュージアム(渋谷区道玄坂2-24-1)
「リール近代美術館所蔵 ピカソとモディリアーニの時代」
9/2-10/22

フランス北部、ベルギーとの国境に面した街リールから、20世紀絵画の充実したコレクションがやって来ました。表題のピカソやモディリアーニを初めとして、ブラック、レジェ、ルオー、ミロ、それにビュッフェなど、約100点ほどの作品が並ぶ展覧会です。
キュビズムでは、お馴染みのブラックとピカソよりも、一風変わったロランスの静物画と彫刻に惹かれました。特に、力強い造形に迫力のある「瓶のある静物」(1917)と、逞しい魂の宿る女性のオブジェ「座る女像柱」(1930)は魅力的です。静物画では、木炭やチョークを駆使したコラージュ風の画面が面白く、まるで二人の人間が抱き合うかのようなその構図も、シンプルでありながら力強く感じました。そしてオブジェでは、それこそ古代の祭儀にでも使うようなシンボリックな女性に目を奪われます。秘められたパワーがブロンズの表面から滲み出していました。実に神秘的な彫像です。

モディリアーニは少々苦手な画家でしたが、マチエールに妙味がある「肌着を持って座る裸婦」(1917)には素直に惹かれました。面長のふくよかな裸女が一名、胸元に肌着を寄せて佇んでいます。深いワイン色の背景と女性の赤らんだ肌、そして清潔感のある白い肌着が、調和しながらも鮮やかなコントラストを描いていました。そして画肌に見るその温もりです。オレンジ色がかったその艶やかな体が、色香を仄かに醸し出していました。モディリアーニの作品の中では、意外なほど逞しく、また彫刻のような立体感を思わせる作品かと思います。


大好きなクレーやミロ、それにカンディンスキーとくれば楽しめないはずがありません。中でもクレーの「のみ込まれた島」(1923)のたたえる美しい詩情には感銘しました。透き通るような瑞々しいブルーに包み込まれ、またまさにのみ込まれている孤島。天には星が瞬き、可愛らしい魚が気持ちよさそうに駆けています。ちなみにクレーでは、一見カンディンスキーの画風を思わせるような「17種類の香辛料」(1931)も優れていました。薄い水色のドットに浸食された画面に、伸びやかな線がゆらゆらと泳いでいます。魔術師のように空間を操る線が自在に動き廻り、その痕跡を数字で書き留めていた。せめぎあう色の遊びが何とも微笑ましい作品です。

最終章では、それまでの展示の展開からするとやや違和感すら抱く、ビュフェの険しい絵画が心に留まりました。激しく強いタッチでありながらも、どこか無機質で生気のない線が画面をザクザクと切り刻んでいます。宗教的な主題の作品も見応えがありましたが、それこそあまりにも物静かな「メロンのある静物」(1949)が一番印象的でした。ビュフェの白は、清潔でも美でもなく、ただ死を思わせるような物悲しい色です。描かれた事物がまるで突きつけられるように、敢然と前に立ちはだかっていました。
ボーシャンやランスコワなど、あまり聞き慣れない画家の作品を数多く展示されています。20世紀前半のフランス絵画を楽しむには絶好の展覧会です。今月22日までの開催されています。
「リール近代美術館所蔵 ピカソとモディリアーニの時代」
9/2-10/22

フランス北部、ベルギーとの国境に面した街リールから、20世紀絵画の充実したコレクションがやって来ました。表題のピカソやモディリアーニを初めとして、ブラック、レジェ、ルオー、ミロ、それにビュッフェなど、約100点ほどの作品が並ぶ展覧会です。
キュビズムでは、お馴染みのブラックとピカソよりも、一風変わったロランスの静物画と彫刻に惹かれました。特に、力強い造形に迫力のある「瓶のある静物」(1917)と、逞しい魂の宿る女性のオブジェ「座る女像柱」(1930)は魅力的です。静物画では、木炭やチョークを駆使したコラージュ風の画面が面白く、まるで二人の人間が抱き合うかのようなその構図も、シンプルでありながら力強く感じました。そしてオブジェでは、それこそ古代の祭儀にでも使うようなシンボリックな女性に目を奪われます。秘められたパワーがブロンズの表面から滲み出していました。実に神秘的な彫像です。

モディリアーニは少々苦手な画家でしたが、マチエールに妙味がある「肌着を持って座る裸婦」(1917)には素直に惹かれました。面長のふくよかな裸女が一名、胸元に肌着を寄せて佇んでいます。深いワイン色の背景と女性の赤らんだ肌、そして清潔感のある白い肌着が、調和しながらも鮮やかなコントラストを描いていました。そして画肌に見るその温もりです。オレンジ色がかったその艶やかな体が、色香を仄かに醸し出していました。モディリアーニの作品の中では、意外なほど逞しく、また彫刻のような立体感を思わせる作品かと思います。


大好きなクレーやミロ、それにカンディンスキーとくれば楽しめないはずがありません。中でもクレーの「のみ込まれた島」(1923)のたたえる美しい詩情には感銘しました。透き通るような瑞々しいブルーに包み込まれ、またまさにのみ込まれている孤島。天には星が瞬き、可愛らしい魚が気持ちよさそうに駆けています。ちなみにクレーでは、一見カンディンスキーの画風を思わせるような「17種類の香辛料」(1931)も優れていました。薄い水色のドットに浸食された画面に、伸びやかな線がゆらゆらと泳いでいます。魔術師のように空間を操る線が自在に動き廻り、その痕跡を数字で書き留めていた。せめぎあう色の遊びが何とも微笑ましい作品です。

最終章では、それまでの展示の展開からするとやや違和感すら抱く、ビュフェの険しい絵画が心に留まりました。激しく強いタッチでありながらも、どこか無機質で生気のない線が画面をザクザクと切り刻んでいます。宗教的な主題の作品も見応えがありましたが、それこそあまりにも物静かな「メロンのある静物」(1949)が一番印象的でした。ビュフェの白は、清潔でも美でもなく、ただ死を思わせるような物悲しい色です。描かれた事物がまるで突きつけられるように、敢然と前に立ちはだかっていました。
ボーシャンやランスコワなど、あまり聞き慣れない画家の作品を数多く展示されています。20世紀前半のフランス絵画を楽しむには絶好の展覧会です。今月22日までの開催されています。
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )
「館蔵 秋の優品展」 五島美術館 10/1
五島美術館(世田谷区上野毛3-9-25)
「館蔵 秋の優品展 - 絵画・墨跡と李朝の陶芸 - 」
9/2-10/22

所蔵の佐竹本三十六歌仙絵が出品されると聞き、初めて五島美術館へ行ってきました。美術館御自慢の古美術コレクションにて構成された「秋の優品展」です。歌仙絵を中心とした鎌倉時代の絵画と、古写経や墨跡、それに李朝(朝鮮)の陶芸品などが展示されていました。

藤原元輔(908-990)は、かの清少納言の父としても知られる平安時代の高名な歌人です。「佐竹本三十六歌仙絵 藤原元輔」(13世紀)ではまず、束帯の後ろに伸びているような白い下襲(したがさね)が、まるで羽のようにひらひらと靡く様子が印象に残りました。そして透き通るような束帯の黒も、また口元に鮮やかに色付く紅色も美しく映えている。おっとりした顔をやや下に屈めて見つめる表情は、どこか物憂げです。十分な余白にポツンと佇むその姿が何とも儚く感じられました。
歌仙絵は何も佐竹本だけではありません。その他「業兼本三十六歌仙絵 猿丸大夫」(14世紀)や「後鳥羽院本三十六歌仙絵 平兼盛」(14世紀)なども、古来の詩情に思いを馳せるのにはピッタリの名品でした。また、それぞれの歌の優劣を競う「時代不同歌合戦」も興味深い作品です。左右の歌人たちが、これ見よがしに歌を披露し合う姿が目に浮かびます。
李朝の陶芸では、「粉青白地掻落牡丹文扁壺」(15世紀)が一推しです。楕円形の壷の側面に描かれた大きな牡丹の花。そのデフォルメされたような大胆な描写は、まるで鳳凰が大きく翼を広げている姿のようにも見えます。また側面にも、それこそ空間を埋め尽くすかのように所狭しと花が描かれていました。率直に申し上げて、この他に多く展示されていた李朝の茶碗は良さが全く分からなかったのですが、この壷だけは格別の味わいがあったと思います。
国宝の「紫式部日記絵巻」が今月14日から出品されるそうです。展覧会は22日まで開催されています。
「館蔵 秋の優品展 - 絵画・墨跡と李朝の陶芸 - 」
9/2-10/22

所蔵の佐竹本三十六歌仙絵が出品されると聞き、初めて五島美術館へ行ってきました。美術館御自慢の古美術コレクションにて構成された「秋の優品展」です。歌仙絵を中心とした鎌倉時代の絵画と、古写経や墨跡、それに李朝(朝鮮)の陶芸品などが展示されていました。

藤原元輔(908-990)は、かの清少納言の父としても知られる平安時代の高名な歌人です。「佐竹本三十六歌仙絵 藤原元輔」(13世紀)ではまず、束帯の後ろに伸びているような白い下襲(したがさね)が、まるで羽のようにひらひらと靡く様子が印象に残りました。そして透き通るような束帯の黒も、また口元に鮮やかに色付く紅色も美しく映えている。おっとりした顔をやや下に屈めて見つめる表情は、どこか物憂げです。十分な余白にポツンと佇むその姿が何とも儚く感じられました。
歌仙絵は何も佐竹本だけではありません。その他「業兼本三十六歌仙絵 猿丸大夫」(14世紀)や「後鳥羽院本三十六歌仙絵 平兼盛」(14世紀)なども、古来の詩情に思いを馳せるのにはピッタリの名品でした。また、それぞれの歌の優劣を競う「時代不同歌合戦」も興味深い作品です。左右の歌人たちが、これ見よがしに歌を披露し合う姿が目に浮かびます。
李朝の陶芸では、「粉青白地掻落牡丹文扁壺」(15世紀)が一推しです。楕円形の壷の側面に描かれた大きな牡丹の花。そのデフォルメされたような大胆な描写は、まるで鳳凰が大きく翼を広げている姿のようにも見えます。また側面にも、それこそ空間を埋め尽くすかのように所狭しと花が描かれていました。率直に申し上げて、この他に多く展示されていた李朝の茶碗は良さが全く分からなかったのですが、この壷だけは格別の味わいがあったと思います。
国宝の「紫式部日記絵巻」が今月14日から出品されるそうです。展覧会は22日まで開催されています。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「アート・スコープ 2005/2006」 原美術館 10/1
原美術館(品川区北品川4-7-25)
「アート・スコープ 2005/2006 - インターフェース・コンプレックス」
9/9-10/22

昨年に引き続き開催された、原美術館の「アート・スコープ」展です。去年は殆ど良い印象を持ちませんでしたが、今年はそれなりに楽しめました。日本からは森弘治と名和晃平、ドイツからはカーチャ・シュトルンツとゲオルグ・ヴィンターが、それぞれに作品を発表、展示しています。私は断然、日本人アーティスト、つまり森と名和の作品が印象に残りました。
名和晃平のオブジェは、その真っ白な空間に置かれた展示形態を含め、インスタレーション的な魅力に溢れています。まず、たくさんのガラス玉に閉じ込められた鹿の剥製が見つめる「Water Cell」(2006)からして美しい作品です。液体の入った透明な直方体の中で、気泡がゆっくりと上へ向かっている。その姿は、まるでふつふつと魂が沸き立つような、生命の誕生を司る培養液でした。そして白く輝く照明も、この樹脂を美しく演出しています。白い静寂に包まれる感覚です。
二つの立方体、「Air Cell」(2006)も見事でした。こちらはアクリル製のキューブに透明なドットがいくつも挟み込まれた作品ですが、そのドットが見る角度によって色々と表情を変えていきます。上から眺めると、ドットがまるで底なし沼のような白みへ突き刺さり、また横から見るとあたかも原子運動のようにハコの中を飛び回っている。閉じ込められながらも、四方八方に群がり、また無限の直線を引いていました。これは視覚を操られる作品です。しばらく見ていると酔ってしまうほどでした。
森弘治のビデオ・インスタレーションでは、大きなスクリーンを使って映し出された「美術のための応援」(2006)にインパクトがありました。これは、大仰な振り付けと絶叫が華々しい大学の応援団が、それこそ美術のために応援を繰り広げる作品です。一見するとその姿が滑稽に感じられますが、しばらく拝見していると、そのひた向きな応援に力強さを感じ、何やらその気迫に包み込まれてしまいます。私はこの純粋さを買いたいと思いました。

ドイツ人アーティストでは、シュトルンツの「恐怖への招待」(2005)が印象的です。シンバルのようなオブジェがいくつも並び、まるでバンドかオーケストラのような共同体を形成しています。そして注目すべきなのは、その奥に映し出されるシルエットです。オブジェと並んで立つと自分の姿が写し出されます。あたかもここで自分が演奏しているかのような演出です。
昨年同様、展示から、アーティストを相互の国へ派遣するという「アート・スコープ」のコンセプトは感じられませんでしたが、作品自体には見応えのあるものも目立ちました。今年1月のSCAIの個展などで楽しめた名和ファン(?)には、特におすすめしたいと思います。今月22日までの開催です。
「アート・スコープ 2005/2006 - インターフェース・コンプレックス」
9/9-10/22

昨年に引き続き開催された、原美術館の「アート・スコープ」展です。去年は殆ど良い印象を持ちませんでしたが、今年はそれなりに楽しめました。日本からは森弘治と名和晃平、ドイツからはカーチャ・シュトルンツとゲオルグ・ヴィンターが、それぞれに作品を発表、展示しています。私は断然、日本人アーティスト、つまり森と名和の作品が印象に残りました。
名和晃平のオブジェは、その真っ白な空間に置かれた展示形態を含め、インスタレーション的な魅力に溢れています。まず、たくさんのガラス玉に閉じ込められた鹿の剥製が見つめる「Water Cell」(2006)からして美しい作品です。液体の入った透明な直方体の中で、気泡がゆっくりと上へ向かっている。その姿は、まるでふつふつと魂が沸き立つような、生命の誕生を司る培養液でした。そして白く輝く照明も、この樹脂を美しく演出しています。白い静寂に包まれる感覚です。
二つの立方体、「Air Cell」(2006)も見事でした。こちらはアクリル製のキューブに透明なドットがいくつも挟み込まれた作品ですが、そのドットが見る角度によって色々と表情を変えていきます。上から眺めると、ドットがまるで底なし沼のような白みへ突き刺さり、また横から見るとあたかも原子運動のようにハコの中を飛び回っている。閉じ込められながらも、四方八方に群がり、また無限の直線を引いていました。これは視覚を操られる作品です。しばらく見ていると酔ってしまうほどでした。
森弘治のビデオ・インスタレーションでは、大きなスクリーンを使って映し出された「美術のための応援」(2006)にインパクトがありました。これは、大仰な振り付けと絶叫が華々しい大学の応援団が、それこそ美術のために応援を繰り広げる作品です。一見するとその姿が滑稽に感じられますが、しばらく拝見していると、そのひた向きな応援に力強さを感じ、何やらその気迫に包み込まれてしまいます。私はこの純粋さを買いたいと思いました。

ドイツ人アーティストでは、シュトルンツの「恐怖への招待」(2005)が印象的です。シンバルのようなオブジェがいくつも並び、まるでバンドかオーケストラのような共同体を形成しています。そして注目すべきなのは、その奥に映し出されるシルエットです。オブジェと並んで立つと自分の姿が写し出されます。あたかもここで自分が演奏しているかのような演出です。
昨年同様、展示から、アーティストを相互の国へ派遣するという「アート・スコープ」のコンセプトは感じられませんでしたが、作品自体には見応えのあるものも目立ちました。今年1月のSCAIの個展などで楽しめた名和ファン(?)には、特におすすめしたいと思います。今月22日までの開催です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ハーディングをFMで聴く NHK音楽祭2006
NHK-FM ベストオブクラシック(10/5 19:00 - ) NHK音楽祭2006(1)
曲 モーツァルト 交響曲第6番 K.43
ピアノ協奏曲第20番 K.466
ブラームス 交響曲第2番 作品73
指揮 ダニエル・ハーディング
演奏 マーラー・チェンバー・オーケストラ
ピアノ ラルス・フォークト
収録:NHKホール(生中継) 2006/10/5
実際にホールへ足を運びたかったのですが、都合がつかなかったので録音で楽しむことにしました。今日から始まったNHK音楽祭より、ハーディング&マーラー・チェンバー・オーケストラの演奏会です。

ハーディングは聴衆へのサービス精神に溢れた指揮者だと思います。これほど音楽をダイナミックに分かり易い形で、しかもそれこそ楽しく演奏出来る方も珍しいのではないでしょうか。K.466では、第二楽章をロマン風味にこってりと味付け、その一方で三楽章を颯爽に流していました。もちろん、単なるインテンポ系の演奏ではありません。時折揺れ動くフレージングがまるでジャズのスイングのような効果をもたらし、時に音の流れを断ち切るかのような乾いた金管が緊張感を与えている。聴かせどころはテンポを落として、とても丁寧に演奏していたのが印象的でした。明暗の表裏一体となったモーツァルトです。
ブラームスでは響きのバランス感が優れています。音の情報量が極めて多い演奏です。木管と弦、それに金管が、それぞれに主張しながらも美しく合わせ重なって聞こえてきました。木管を強調する際には弦を控えめに、また金管を強めに吹かせる際は一瞬の間合いを入れる。音量バランスへの配慮が絶妙です。フォルテでも単に音が増幅するわけではありません。
刹那的な第二楽章がとても濃厚でした。特に終結部では、まるで煙のようにもやもやと立ち上がりながらも分厚い響きが訪れるワーグナーのような音楽になっていたのには驚きました。贅肉を徹底して削ぎ落とし、鮮烈な音の渦を作り出す古楽器系の演奏の面白さだけでなく、時に往年の名指揮者が聴かせたようなロマン的な音楽を加味するのもハーディングの良さなのかもしれません。(後者への志向が強いとさえ思いました。)
ノリントン、ルイージ、そしてアーノンクールと続く今年のNHK音楽祭は聞き逃せません。今後もチェックしていきたいです。
曲 モーツァルト 交響曲第6番 K.43
ピアノ協奏曲第20番 K.466
ブラームス 交響曲第2番 作品73
指揮 ダニエル・ハーディング
演奏 マーラー・チェンバー・オーケストラ
ピアノ ラルス・フォークト
収録:NHKホール(生中継) 2006/10/5
実際にホールへ足を運びたかったのですが、都合がつかなかったので録音で楽しむことにしました。今日から始まったNHK音楽祭より、ハーディング&マーラー・チェンバー・オーケストラの演奏会です。

ハーディングは聴衆へのサービス精神に溢れた指揮者だと思います。これほど音楽をダイナミックに分かり易い形で、しかもそれこそ楽しく演奏出来る方も珍しいのではないでしょうか。K.466では、第二楽章をロマン風味にこってりと味付け、その一方で三楽章を颯爽に流していました。もちろん、単なるインテンポ系の演奏ではありません。時折揺れ動くフレージングがまるでジャズのスイングのような効果をもたらし、時に音の流れを断ち切るかのような乾いた金管が緊張感を与えている。聴かせどころはテンポを落として、とても丁寧に演奏していたのが印象的でした。明暗の表裏一体となったモーツァルトです。
ブラームスでは響きのバランス感が優れています。音の情報量が極めて多い演奏です。木管と弦、それに金管が、それぞれに主張しながらも美しく合わせ重なって聞こえてきました。木管を強調する際には弦を控えめに、また金管を強めに吹かせる際は一瞬の間合いを入れる。音量バランスへの配慮が絶妙です。フォルテでも単に音が増幅するわけではありません。
刹那的な第二楽章がとても濃厚でした。特に終結部では、まるで煙のようにもやもやと立ち上がりながらも分厚い響きが訪れるワーグナーのような音楽になっていたのには驚きました。贅肉を徹底して削ぎ落とし、鮮烈な音の渦を作り出す古楽器系の演奏の面白さだけでなく、時に往年の名指揮者が聴かせたようなロマン的な音楽を加味するのもハーディングの良さなのかもしれません。(後者への志向が強いとさえ思いました。)
ノリントン、ルイージ、そしてアーノンクールと続く今年のNHK音楽祭は聞き逃せません。今後もチェックしていきたいです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
10月の予定と9月の記録
芸術の秋ということで、今月は興味深い展覧会やコンサートが目白押しです。毎月恒例の「予定と振り返り」です。
10月の予定
展覧会
「アート・スコープ2005/2006」 原美術館( - 10/22)
「ピカソとモディリアーニの時代」 Bunkamura ザ・ミュージアム( - 10/22)
「秋の優品展 - 絵画・墨跡と李朝の陶芸 - 」 五島美術館( - 10/22)
「HASHI(橋村奉臣)展/石内都展」 東京都写真美術館( - 10/29、 - 11/5)
「国宝 伴大納言絵巻展」 出光美術館(10/7-11/5)
「赤と黒の芸術 楽茶碗」 三井記念美術館( - 11/12)
「ウィーン美術アカデミー名品展」 損保ジャパン東郷青児美術館( - 11/12)
「コネクティング・ワールド」 ICC( - 11/26)
「ベルギー王立美術館展」 国立西洋美術館( - 12/10)
「ダリ回顧展」 上野の森美術館( - 2007/1/4)
コンサート
「新国立劇場2006/2007シーズン」 モーツァルト「イドメネオ」(9/20-30)
「藤原歌劇団」 ロッシーニ「ランスへの旅」(10/20-22)
9月の記録(リンクは私の感想です。)
展覧会
「不思議の国・沖縄と芹沢けい介」 静岡市立芹沢けい介美術館 (2日)
「コレクション 20年の熱情2 時代を超える個性」 静岡県立美術館 (2日)
「インゴ・マウラー」展 東京オペラシティアートギャラリー (10日)
「麻生知子展 『あ、そう』他」 トーキョーワンダーサイト (11日)
「Gold - 金色の織りなす異空間 - 」 大倉集古館 (16日)
「浅井忠と関西美術院展」 府中市美術館 (16日)
「国宝 風神雷神図屏風 - 宗達・光琳・抱一 - 」 出光美術館 (16日)
「花鳥の詩」 山種美術館 (23日)
「モダン・パラダイス」 東京国立近代美術館 (23日)
ギャラリー
「長沢明展」 ガレリアグラフィカ (9日)
「三瀬夏之介展」 Bunkamura Gallery Arts&Crafts (9日)
「小林正人『初期作品』展」 シュウゴアーツ (9日)
「『三千世界』 内海聖史」 ヴァイスフェルト (30日)
「天明屋尚展/池田学展」 ミヅマアートギャラリー (30日)
コンサート
「新国立劇場2006/2007シーズン」 ヴェルディ「ドン・カルロ」/マルティネス他 (1日)
秋の上野は燃えています。初日からもの凄い混雑だったと聞くダリ展や、西洋美術館のベルギー展は早めに拝見する予定です。また出光の伴大納言展は、作品展示に期間の制約があります。(全巻実物展示は10/7-15、10/31-11/5のみ。)頃を見計らって行きたいです。
コンサートは他にも気になる公演がたくさんありますが、最近どうも予定通りに聴くことが出来ません。まずは最小限に、国内団体による二つのオペラだけを挙げてみました。「イドメネオ」はもちろんのこと、あまり上演機会のない「ランスへの旅」は大好きなオペラなので非常に楽しみです。
6月は小遠征ということで、静岡の二つの美術館へ足を伸ばしてきました。それ以外では、やはり出光の風神雷神図が一番に挙げられると思います。風神雷神図の響宴だけでなく、抱一の紅白梅図屏風なども楽しめました。
それでは今月もどうぞよろしくお願いします。
*ブログリンクを一部更新しました。
10月の予定
展覧会
「アート・スコープ2005/2006」 原美術館( - 10/22)
「ピカソとモディリアーニの時代」 Bunkamura ザ・ミュージアム( - 10/22)
「秋の優品展 - 絵画・墨跡と李朝の陶芸 - 」 五島美術館( - 10/22)
「HASHI(橋村奉臣)展/石内都展」 東京都写真美術館( - 10/29、 - 11/5)
「国宝 伴大納言絵巻展」 出光美術館(10/7-11/5)
「赤と黒の芸術 楽茶碗」 三井記念美術館( - 11/12)
「ウィーン美術アカデミー名品展」 損保ジャパン東郷青児美術館( - 11/12)
「コネクティング・ワールド」 ICC( - 11/26)
「ベルギー王立美術館展」 国立西洋美術館( - 12/10)
「ダリ回顧展」 上野の森美術館( - 2007/1/4)
コンサート
「新国立劇場2006/2007シーズン」 モーツァルト「イドメネオ」(9/20-30)
「藤原歌劇団」 ロッシーニ「ランスへの旅」(10/20-22)
9月の記録(リンクは私の感想です。)
展覧会
「不思議の国・沖縄と芹沢けい介」 静岡市立芹沢けい介美術館 (2日)
「コレクション 20年の熱情2 時代を超える個性」 静岡県立美術館 (2日)
「インゴ・マウラー」展 東京オペラシティアートギャラリー (10日)
「麻生知子展 『あ、そう』他」 トーキョーワンダーサイト (11日)
「Gold - 金色の織りなす異空間 - 」 大倉集古館 (16日)
「浅井忠と関西美術院展」 府中市美術館 (16日)
「国宝 風神雷神図屏風 - 宗達・光琳・抱一 - 」 出光美術館 (16日)
「花鳥の詩」 山種美術館 (23日)
「モダン・パラダイス」 東京国立近代美術館 (23日)
ギャラリー
「長沢明展」 ガレリアグラフィカ (9日)
「三瀬夏之介展」 Bunkamura Gallery Arts&Crafts (9日)
「小林正人『初期作品』展」 シュウゴアーツ (9日)
「『三千世界』 内海聖史」 ヴァイスフェルト (30日)
「天明屋尚展/池田学展」 ミヅマアートギャラリー (30日)
コンサート
「新国立劇場2006/2007シーズン」 ヴェルディ「ドン・カルロ」/マルティネス他 (1日)
秋の上野は燃えています。初日からもの凄い混雑だったと聞くダリ展や、西洋美術館のベルギー展は早めに拝見する予定です。また出光の伴大納言展は、作品展示に期間の制約があります。(全巻実物展示は10/7-15、10/31-11/5のみ。)頃を見計らって行きたいです。
コンサートは他にも気になる公演がたくさんありますが、最近どうも予定通りに聴くことが出来ません。まずは最小限に、国内団体による二つのオペラだけを挙げてみました。「イドメネオ」はもちろんのこと、あまり上演機会のない「ランスへの旅」は大好きなオペラなので非常に楽しみです。
6月は小遠征ということで、静岡の二つの美術館へ足を伸ばしてきました。それ以外では、やはり出光の風神雷神図が一番に挙げられると思います。風神雷神図の響宴だけでなく、抱一の紅白梅図屏風なども楽しめました。
それでは今月もどうぞよろしくお願いします。
*ブログリンクを一部更新しました。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「池田学展 『景色』」 ミヅマアートギャラリー 9/30
ミヅマアートギャラリー(目黒区上目黒1-3-9 藤屋ビル5階)
「池田学展 『景色』」
9/13-10/14
恐ろしいまでに精緻に描かれたミクロな空想世界が、そのままアメーバのように増殖して巨大化しました。一つの作品をこれほど時間をかけて見たのは久しぶりです。時空間ともに交錯した世界が、細密でありながらも圧倒的なスケールにて展開されています。

展示室正面に置かれていた「興亡史」(2006)からして圧巻です。2メートル四方の紙に、まさに職人芸的な精巧なタッチ(ペンとインクのみ!)による物語絵巻が、画面からはち切れんばかりに膨張して表現されています。桜の木に城、鉄道や塔、それに滝や河などと、その描かれたモチーフを挙げるとキリがありません。そしてそれらが渾然一体となって、まるで一つの物語を紡ぐかのように連関して配されている。展覧会タイトルの「景色」はあまり適当ではありません。時に、アニメーション的にも描かれた小さな戦国武者たちが、この奇怪極まりない物体に群がり、その覇権争いを繰り広げています。あくまでもここにあるのは時間の止まった「景色」ではなく、悠久に流れ行く「歴史物語」なのです。人物の白いシルエットはその残像かもしれません。

瓦から木々まで、ともかくあるもの全てが変形しています。一つ一つがしっかりとした形を持っているのではなく、あたかもまるで生き物のように寄り合い、蠢いている。水に屋根、そして怪物や鉄道が、廻りくねって合わせ重なり、今にも崩れるかのように繋がっていました。もしかしたら随所にて既に崩落が始まっているのかもしれません。その意味では、ものの迫力よりも儚さをも感じさせる作品です。

一作を仕上げるのに一年以上かけることもあるそうですが、見る側にもそれなりの忍耐と覚悟を要求します。この壮大な絵画物語をひも解くのに一体どのくらいの時間がかかるのか。途方もなく深い世界が待ち構えていました。
当時開催中の天明屋展と合わせて、是非おすすめしたいと思います。
「池田学展 『景色』」
9/13-10/14
恐ろしいまでに精緻に描かれたミクロな空想世界が、そのままアメーバのように増殖して巨大化しました。一つの作品をこれほど時間をかけて見たのは久しぶりです。時空間ともに交錯した世界が、細密でありながらも圧倒的なスケールにて展開されています。

展示室正面に置かれていた「興亡史」(2006)からして圧巻です。2メートル四方の紙に、まさに職人芸的な精巧なタッチ(ペンとインクのみ!)による物語絵巻が、画面からはち切れんばかりに膨張して表現されています。桜の木に城、鉄道や塔、それに滝や河などと、その描かれたモチーフを挙げるとキリがありません。そしてそれらが渾然一体となって、まるで一つの物語を紡ぐかのように連関して配されている。展覧会タイトルの「景色」はあまり適当ではありません。時に、アニメーション的にも描かれた小さな戦国武者たちが、この奇怪極まりない物体に群がり、その覇権争いを繰り広げています。あくまでもここにあるのは時間の止まった「景色」ではなく、悠久に流れ行く「歴史物語」なのです。人物の白いシルエットはその残像かもしれません。

瓦から木々まで、ともかくあるもの全てが変形しています。一つ一つがしっかりとした形を持っているのではなく、あたかもまるで生き物のように寄り合い、蠢いている。水に屋根、そして怪物や鉄道が、廻りくねって合わせ重なり、今にも崩れるかのように繋がっていました。もしかしたら随所にて既に崩落が始まっているのかもしれません。その意味では、ものの迫力よりも儚さをも感じさせる作品です。

一作を仕上げるのに一年以上かけることもあるそうですが、見る側にもそれなりの忍耐と覚悟を要求します。この壮大な絵画物語をひも解くのに一体どのくらいの時間がかかるのか。途方もなく深い世界が待ち構えていました。
当時開催中の天明屋展と合わせて、是非おすすめしたいと思います。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
「天明屋尚展 『Made in Japan』」 ミヅマアートギャラリー 9/30
ミヅマアートギャラリー(目黒区上目黒1-3-9 藤屋ビル2階)
「天明屋尚展 『Made in Japan』」
9/6-10/7
ミヅマアートギャラリーで開催中の「天明屋尚展 Made in Japan」を見てきました。お馴染みの野武士イメージのドローイングから、屏風、掛軸、杉戸絵まで、その多彩な制作を楽しめる充実した個展です。
古めかしい杉戸(100年前のものだそうです。)に描かれた二点のアクリル画からしてぶっ飛んでいます。タイトルは「漢字紅葉図貝羅富異帝杉戸絵」(2000)。金地に朱の交じる紅葉が描かれた「大和魂一匹狼」と、同じく金地にまさしく琳派風燕子花の配された「一撃必殺特攻隊」が、何やら暴力的な荒々しさを醸し出して展示されていました。ちなみにこの作品は、それぞれ大和魂云々と、一撃必殺云々が、おどろおどろしい梵字風の漢字によって表現されたものです。だからこそ「漢字紅葉図貝羅富異帝杉戸絵」、つまり「漢字グラフィティ杉戸絵」という名が与えられている。また「一撃必殺」にある燕子花が光琳風ではなく、やや伸びやかな抱一風であったのも嬉しいところです。
トレーシングペーパー制の掛軸、「Transparent Scroll」(2006)も、天明屋の簡潔でかつ精緻なデッサン力を味わうことが出来ます。縦160センチ、横3メートルの大作「Made in Japan」と合わせて、刀を構える上半身裸の男性美とその魂を楽しむことが出来ました。
高さ30センチほどの透明アクリル板を屏風に仕立てた「輪廻転生図」(2006)も見応え十分です。鶴や亀、それに麒麟や鳥などの、それこそ江戸絵画にでも登場するかのような動物たちが、半ばコラージュされるかのようにしてランダムに描かれています。そして宙を舞う、まるで体操しているような全裸の男性。奇妙なモチーフがパラレルワールドを描いていました。
絵画の「武闘派」を名乗る天明屋氏ですが、それからイメージされる半ば物騒な迫力よりも、手仕事を思わせる徹底したディテールへのこだわりや、古の武士への郷愁、またはその背景に見られるスマートなダンディズム的美学に面白さがあるかと思います。今週土曜日までの開催です。
*天明屋さんと言えば、話題となった2006年ドイツ・ワールドカップの公式アートポスターを思い出します。

「天明屋尚展 『Made in Japan』」
9/6-10/7
ミヅマアートギャラリーで開催中の「天明屋尚展 Made in Japan」を見てきました。お馴染みの野武士イメージのドローイングから、屏風、掛軸、杉戸絵まで、その多彩な制作を楽しめる充実した個展です。
古めかしい杉戸(100年前のものだそうです。)に描かれた二点のアクリル画からしてぶっ飛んでいます。タイトルは「漢字紅葉図貝羅富異帝杉戸絵」(2000)。金地に朱の交じる紅葉が描かれた「大和魂一匹狼」と、同じく金地にまさしく琳派風燕子花の配された「一撃必殺特攻隊」が、何やら暴力的な荒々しさを醸し出して展示されていました。ちなみにこの作品は、それぞれ大和魂云々と、一撃必殺云々が、おどろおどろしい梵字風の漢字によって表現されたものです。だからこそ「漢字紅葉図貝羅富異帝杉戸絵」、つまり「漢字グラフィティ杉戸絵」という名が与えられている。また「一撃必殺」にある燕子花が光琳風ではなく、やや伸びやかな抱一風であったのも嬉しいところです。
トレーシングペーパー制の掛軸、「Transparent Scroll」(2006)も、天明屋の簡潔でかつ精緻なデッサン力を味わうことが出来ます。縦160センチ、横3メートルの大作「Made in Japan」と合わせて、刀を構える上半身裸の男性美とその魂を楽しむことが出来ました。
高さ30センチほどの透明アクリル板を屏風に仕立てた「輪廻転生図」(2006)も見応え十分です。鶴や亀、それに麒麟や鳥などの、それこそ江戸絵画にでも登場するかのような動物たちが、半ばコラージュされるかのようにしてランダムに描かれています。そして宙を舞う、まるで体操しているような全裸の男性。奇妙なモチーフがパラレルワールドを描いていました。
絵画の「武闘派」を名乗る天明屋氏ですが、それからイメージされる半ば物騒な迫力よりも、手仕事を思わせる徹底したディテールへのこだわりや、古の武士への郷愁、またはその背景に見られるスマートなダンディズム的美学に面白さがあるかと思います。今週土曜日までの開催です。
*天明屋さんと言えば、話題となった2006年ドイツ・ワールドカップの公式アートポスターを思い出します。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「『三千世界』 内海聖史」 ヴァイスフェルト 9/30
ヴァイスフェルト(港区六本木6-8-14 コンプレックス北館3階)
「『三千世界』 内海聖史」
9/8-30(会期終了)
一昨年のMOTアニュアル展でも印象深かった内海聖史の個展です。彼の作品は、昨秋このヴァイスフェルトでも展示されていましたが、それとはまた一変した雰囲気の作品が待ち構えていました。例の重々しいドットが、あたかも色彩分割するかのように並んでいます。5×5センチほどのキャンバスに配されたドットの色彩がズラリと1000個、壁いっぱいに整然と揃うのです。

パンチ穴サイズのドットは、赤や青、それに緑や黄、さらには紫などと、何種類もの色を用いながら無数に描かれています。このドットは、かつての内海の作品に見られたように群れ、また巨大化すると、有無を言わさないその色彩に重みが感じられますが、今回のように小さなキャンバスへ分散するように描かれると、むしろ色自体の透き通るような軽さと、ドットの生み出すその形に関心が移ることが分かりました。折重なるドットが、キャンバス上にてあたかもCGを描くように立体化され、色彩同士が照応するかのように蠢き合う。深い色の連鎖に見る迫力こそ内海の醍醐味かとも思いましたが、全くそれを否定するかのようなこの軽さはとても新鮮でした。色の粒が、あたかもガラス玉のようにキラキラと輝いています。
ミニマル・アート的な味わいも感じられました。毎回の展示から目の離せないアーティストの一人です。
「『三千世界』 内海聖史」
9/8-30(会期終了)
一昨年のMOTアニュアル展でも印象深かった内海聖史の個展です。彼の作品は、昨秋このヴァイスフェルトでも展示されていましたが、それとはまた一変した雰囲気の作品が待ち構えていました。例の重々しいドットが、あたかも色彩分割するかのように並んでいます。5×5センチほどのキャンバスに配されたドットの色彩がズラリと1000個、壁いっぱいに整然と揃うのです。

パンチ穴サイズのドットは、赤や青、それに緑や黄、さらには紫などと、何種類もの色を用いながら無数に描かれています。このドットは、かつての内海の作品に見られたように群れ、また巨大化すると、有無を言わさないその色彩に重みが感じられますが、今回のように小さなキャンバスへ分散するように描かれると、むしろ色自体の透き通るような軽さと、ドットの生み出すその形に関心が移ることが分かりました。折重なるドットが、キャンバス上にてあたかもCGを描くように立体化され、色彩同士が照応するかのように蠢き合う。深い色の連鎖に見る迫力こそ内海の醍醐味かとも思いましたが、全くそれを否定するかのようなこの軽さはとても新鮮でした。色の粒が、あたかもガラス玉のようにキラキラと輝いています。
ミニマル・アート的な味わいも感じられました。毎回の展示から目の離せないアーティストの一人です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「ギョッとする江戸の絵画」(NHK教育)は明日(10/2)からです!
遅ればせながら買ってきました。詳しくはブログ「弐代目・青い日記帳」をご覧下さい。NHK教育テレビ「知るを楽しむ」のテキスト、「ギョッとする江戸の絵画」です。
NHK教育テレビ「知るを楽しむ この人この世界」(2006年10月/11月)
「ギョッとする江戸の絵画」 講師:辻惟雄氏
放送時間 毎週月曜日 午後10:25-10:50
(再放送 翌週月曜日 午前05:05-05:30)
第1回 10/2(再放送10/9) 「血染めの衝撃 - 岩佐又兵衛」
第2回 10/9(再放送10/16) 「身もだえする巨木 - 狩野山雪」
第3回 10/16(再放送10/23) 「自己流の迫力 - 白隠」
第4回 10/23(再放送10/30) 「奇想天外の仙人たち - 曾我蕭白」
第5回 11/6(再放送11/13) 「絵にしか描けない美しさ - 伊藤若冲」
第6回 11/13(再放送11/20) 「猛獣戯画 - 長沢蘆雪」
第7回 11/20(再放送11/27) 「天才は爆発する - 葛飾北斎」
第8回 11/27(再放送12/4) 「機知+滑稽・風刺の心 - 歌川国芳」
 「『この人この世界』2006年10-11月/辻惟雄/日本放送出版協会」
「『この人この世界』2006年10-11月/辻惟雄/日本放送出版協会」
教養番組用テキストということで、大変失礼ながら購入する前はさほど期待していなかったのですが、中をパラパラとめくってすぐに反省しました。この分量で税込み683円とは驚きです。(全173ページ!)新書レベルはゆうに超えるであろうその記述と、図版(カラーも含む。)、さらにはミニコラム風の図画解説と、ともかく盛りだくさんの内容でした。おそらくテレビ放送がなくとも、これだけのみで十分におすすめ出来るような冊子かと思います。まさに辻流「奇想の系譜」江戸絵画が、簡潔な言葉で、実に分かりやすく解説されていました。江戸絵画好きには必携の一冊ともなりそうです。
若冲はもちろんのこと、大御所北斎や蕭白、それに国芳など、まさにエキセントリックな江戸絵画師たちが網羅されていました。それにしても蘆雪を「猛獣戯画」と評するとは脱帽です。これ以上、蘆雪の絵画を示す適当な言葉は見当たりません。
明日はいきなり強烈な岩佐又兵衛です。見逃さないようチェックしていきたいと思います。
NHK教育テレビ「知るを楽しむ この人この世界」(2006年10月/11月)
「ギョッとする江戸の絵画」 講師:辻惟雄氏
放送時間 毎週月曜日 午後10:25-10:50
(再放送 翌週月曜日 午前05:05-05:30)
第1回 10/2(再放送10/9) 「血染めの衝撃 - 岩佐又兵衛」
第2回 10/9(再放送10/16) 「身もだえする巨木 - 狩野山雪」
第3回 10/16(再放送10/23) 「自己流の迫力 - 白隠」
第4回 10/23(再放送10/30) 「奇想天外の仙人たち - 曾我蕭白」
第5回 11/6(再放送11/13) 「絵にしか描けない美しさ - 伊藤若冲」
第6回 11/13(再放送11/20) 「猛獣戯画 - 長沢蘆雪」
第7回 11/20(再放送11/27) 「天才は爆発する - 葛飾北斎」
第8回 11/27(再放送12/4) 「機知+滑稽・風刺の心 - 歌川国芳」
 「『この人この世界』2006年10-11月/辻惟雄/日本放送出版協会」
「『この人この世界』2006年10-11月/辻惟雄/日本放送出版協会」教養番組用テキストということで、大変失礼ながら購入する前はさほど期待していなかったのですが、中をパラパラとめくってすぐに反省しました。この分量で税込み683円とは驚きです。(全173ページ!)新書レベルはゆうに超えるであろうその記述と、図版(カラーも含む。)、さらにはミニコラム風の図画解説と、ともかく盛りだくさんの内容でした。おそらくテレビ放送がなくとも、これだけのみで十分におすすめ出来るような冊子かと思います。まさに辻流「奇想の系譜」江戸絵画が、簡潔な言葉で、実に分かりやすく解説されていました。江戸絵画好きには必携の一冊ともなりそうです。
若冲はもちろんのこと、大御所北斎や蕭白、それに国芳など、まさにエキセントリックな江戸絵画師たちが網羅されていました。それにしても蘆雪を「猛獣戯画」と評するとは脱帽です。これ以上、蘆雪の絵画を示す適当な言葉は見当たりません。
明日はいきなり強烈な岩佐又兵衛です。見逃さないようチェックしていきたいと思います。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
| 次ページ » |









