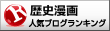自身の書いたメモによると、ハリソンさんは1763年の12月から64年の5月まで、
カフェ・ブルトンと同じ建物の3階で暮らしながら、カフェが主催する「英語の会」の講師をしていたようです。
 カフェ・ブルトンでは第7話に出て来ますが、図書館も併設しているし、
カフェ・ブルトンでは第7話に出て来ますが、図書館も併設しているし、今でいう所のカルチャーセンターみたいな事もしていたのでした。
また、イヴェントの宣伝&チケットの販売もしていたようです。
カフェのギャルソンさん達は、ルイ・セバスティアン・メルシエ著の「タブロー・ド・パリ」によると、
夜遅くまでネバっている客を追い出してから、店を寝床に作り変えて、眠っていたようです。
カフェ・ブルトンでは、店を寝床に使わず、3階で3・4人に一部屋を割り当てていたようです。
 どっちにしても辞めたら、社員寮住まいの正社員や、今問題の派遣社員のように追い出されるんでしょうか?
どっちにしても辞めたら、社員寮住まいの正社員や、今問題の派遣社員のように追い出されるんでしょうか?メルシエさんのご報告によりますと、18世紀のパリにも「カフェ難民」は存在していたような気が…。
 人間のやる事は、昔から変わらんのでしょうな。やっぱり…。
人間のやる事は、昔から変わらんのでしょうな。やっぱり…。ただ、当時は「誰でも最低限、衣食住には困らない水準の生活を送る事ができる権利がある。」
―なんて考えは、一般化していませんでしたから、
心ある人が個人的に救済するか、
「ビンボー人はしょうがねぇよな!」
―で放っておいたか何かしていたんでしょう。
客の2人が話している王子様は将来、「ベルサイユのばら」にも出てくる、あの悲劇の国王陛下となる人です。
奥様となる、本名はすごく長い皇女様も、オーストリアで美しく生い立ってらっしゃるのでしょう。
そして、ヴェルサイユの空の下ではあのオスカル様も…。
 「ハリソンさんはカノ紳士」は、集英社文庫版の「ベルばら」では、
「ハリソンさんはカノ紳士」は、集英社文庫版の「ベルばら」では、表紙とか目次とかを抜かして、話そのものが始まってから12ページにも行っていない頃の話です。
 ハリソンは自分も政治の話をしなくてはならないと思い、
ハリソンは自分も政治の話をしなくてはならないと思い、マー坊相手に飲食店にはふさわしくない、とんでもない話をし出します。
今日の続きは明日。