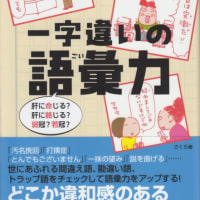映画化されるということなので、ずいぶん昔に読んだ本を再読した。
『死の棘』の妻、すなわち島尾敏雄の細君が子どもの頃の体験を書いたエッセー集である。思い出すままにぽつりぽつりと書き溜めていったものを集めたような本だが、鹿児島県によって分断された琉球弧の一角奄美大島の特徴的かつ個性豊かな風土が美しく描かれている。
本土とは明らかに異なる文化のもと、人々はゆったりとした時間の中で豊かに暮らしているように感じられる、一見ほのぼのとした本である。
しかしこの本、ただものではない。
沖縄本島から「沖縄芝居」の巡業がやってくる。島中で出迎え、島中で楽しみ、島中で見送り別れを惜しむ。
この島では生と死が一体化しているのだろうか。「洗骨」では、埋葬されて一定の期間が経った後、遺骨は掘り起こされ、川の水でていねいに洗われ、真綿にくるまれて骨壺に納められる。骨壺は上半分が土の上に出るようにうめられ、人々はいつでも骨壺の中にいる「遺骨」に会うことが出来る。死者は長く忘れられることがない。
かつて差別され忌み嫌われた癩患者は、本土では火葬することすら難しかったのであろう。奄美大島には「コーダン墓」という、癩患者専用の墓所があり、死んだ癩患者をそこで火葬に付す。
表題の作品「海辺の生と死」では、海では烏賊が誕生、島では羊の子が誕生、そして牛が人の食糧になるためにと殺される。それらの生と死を風景眺めるようにきわめて日常の出来事として描く島尾ミホの感性は何とも不思議だ。奄美の人はみんなそうなのか、それとも島尾ミホが特別なのか。
本書と島尾敏雄の『島の果て』などをもとに映画化され、今年7月公開の予定だそうだ。
島尾ミホ役が満島ひかり、島尾敏雄役が永山絢斗。

『海辺の生と死』創樹社 刊(1974年) 中公文庫(2013年)