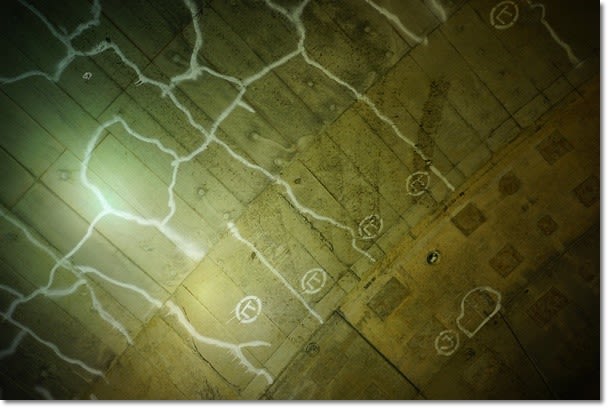先日社会科見学の機会がありました。
「神田川・環状七号線地下調節池」といってもあまりピンときませんでしたが、せっかくの機会なので参加しました。
最初にビデオを見ました。
神田川は井の頭池に源を発し、途中善福寺川、妙正寺川を合わせ最後に隅田川に注ぐ延長24.6㎞の一級河川です。
近年住宅や舗装で土がなく降った雨はしみこまず川に流れ込みます。
貯水池がなかったときは度々水害に見舞われていました。

この対策として川を掘り下げるとすると、土地の買収や家屋の移転などさまざまな問題があります。
そこで環状七号線の道路下に延長4.5㎞、内径12.5mのトンネルを建設し、神田川、善通寺川、福寺川、妙正寺川の洪水約54万㎥を貯留施設が作られました。
工事は第1期工事が昭和63年着手、第2期工事は平成7年に着手し、平成19年にすべての施設が完成しました。
担当の人が模型で説明してくれました。
数字は自分で後から追加してみました。
①善福寺川が大雨で水位があがったとします。
②危なくなったらゲートを開けて取水を開始します。
流入孔はドロップシャフトといって、上から水が落ちるとき直接だと衝撃が大きくなるので渦をまくようになっています。
③水は導水連絡管を通り調節池に流れ込みます。
④水を貯水する池です。

一通りの説明を聞いてから、実際に地下で見学しました。
エレベーターで地下43mのところまで下りました。

ここから水が流れ込んできます。
見学した日が大雨でなくてよかった。

模型での説明の③の導水連絡管の中を歩きます。
直径は6mです。
係りの人が懐中電灯で照らしてくれているので明るいですが、これがなかったら真っ暗な闇の世界です。
実際最後に灯りを消して闇を体験しました。

途中、子どもたちが描いた絵が貼られていました。
ほっとする瞬間です。

壁の落書きのようなものは、ひびや剥がれなど将来修復の必要があるものを印をつけているそうです。
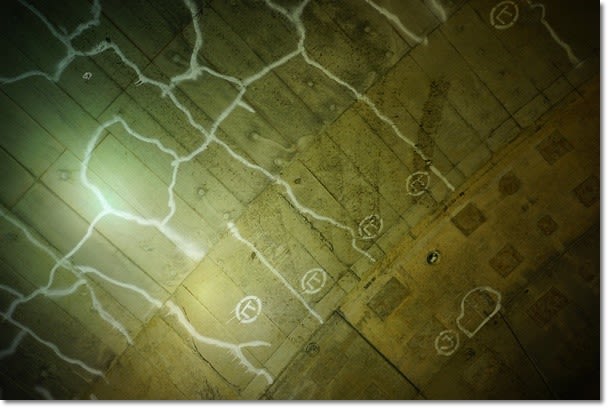
いよいよ調節池です。内径は12.5mあります。
まだ完成していなかった平成5年の台風11号では3117戸の被害がありましたが、完成後の同規模の平成16年の台風22号では46戸の被害にとどまりました。
平成28年2月までに38回の流入があり、満水になったのは平成25年9月25日の台風16号で54万㎥だったそうです。
水と一緒に泥やゴミも入ってくるそうで、雨の少ない今掃除をしているとのことでした。

環状七号線の地下43mで洪水の被害を防ぐためのこんな施設があったと初めてよくわかりました。
とても貴重なものを見せていただきました。