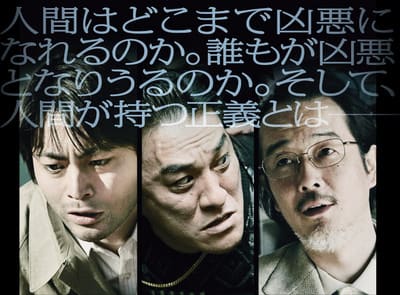TVで再三流された予告編では、福山雅治が涙していた。福山雅治が泣く映画だと刷り込まれた。なので、今か今かと泣くのを待った。よしっ、ここで泣け! という場面が繰り返し出てくるのに、福山雅治は泣かない。泣きそうにもならない。おい、ここだ、ここだろ、ここでもいいよ、ここしかないだろ、どうすりゃ、泣くんだよ、と繰り返し福山雅治に心中で呼びかけているうちに、気がつけばこちらがずっと涙くんでいた。映画に、やられてしまっているのだ。

予告編のヌードシーンを楽しみに映画館に駆けつけてみれば、予告編とはまるで違っていたり、ごく短いシーンだったりというのとは違って、泣くまでずいぶん焦らされた気がする。ははあ、ここで涙するのかと、ほっと肩の荷を下ろした気分になった。福山雅治が泣くまで約一時間、ほぼ2/3が過ぎていた。号泣は期待していなかったが、ちょっと待ち疲れて、正直、もうどこでもいいやと手を打った感じもある。しかし、やられっぱなしも癪なので、少し考えてみた。
どこで福山雅治が泣いたか、明かすわけにはいかないが、ここでなければならないという気はしない。これでもか、これでもか、とたたみ重ねて、観客の涙を絞ろうというお涙ちょうだいではないが、ここでもない、そこでもないと引き算している気はする。それは、俺に似ていない、俺の子らしくない、子どもへの引き算に、ちょっと符合するのかもしれない。男親ってそうじゃなかろうか。母親は、無条件、無前提に、子どもを愛する、もしくは愛するとされているが、父親は、無条件、無前提に、というわけにはいかない。
母親像、父親像にも、同様なところがある。女は妊娠することで否応なく母親の自覚が生まれる、もしくは生まれると思われている。父親は妊娠しないので、父親の自覚は自然には生まれない。少なくとも無自覚なほど、自らに父親を感じたり父親と信じることはないはずだ。女は子どもを産むことで、自らも母親として生まれる、生まれ変わる感じがするが、男にはそれはあり得ない。父親になる、父親になりたい、父親になった、という自覚だけが頼りではないか。いや、自覚というより、自己対象化かもしれない。
福山雅治は、子どもを対象化することで、自らを父親と対象化している。ピアノの練習に熱心ではない、飽きっぽく負けず嫌いなところがない、男としては優しすぎる、など自分からの引き算で子どもを見ている。だから、取り違えられた、他人の子どもだったとわかったとき、「やっぱり」と思ったわけだ。そう口に出して、妻から非難する目で見られたとき、(だって、俺とはちっとも似ていないじゃないか!)と心中で叫んだ。が、取り違えられた他人の子どもと知った後でも、すぐに本当の子どもと交換するわけにはいかず、親子としての生活はこれまでどおり続いていく。
それ泣くか、いま泣くか、まだ泣かないか、と私たちが待っているときは、じつは福山雅治が他人の子を育てていたと知ってからのことだ。そんな括弧付きの父親が、けな気であどけなく親を信頼しきった「我が子」の場面場面を見ているのだ。福山雅治は、括弧付きの息子として、さらに対象化して眺めざるを得ないから、泣きたくても泣けないのだ。じゃ、どうして、あそこで、あれを見て、泣いたのか。カメラだったから、写真だったからだ。それは対象化そのものだった。つまり、息子もまた、パパなる自分を対象化していた。そのことに、はじめて気づいたのだ。
以前は我が子として、今は取り違えられた他人の子どもだけれど、6年間育ててきた子どもとして、福山雅治は対象化している。当然、自己対象化は混乱する。親子ではないのだから、似ていないのは当たり前だった。なのに、俺は、あれもこれも俺とは違うと引き算して、無理なことを押しつけてきた。そういう俺ではない、俺らしくない俺を、あの子はパパの顔や姿として、足し算していた。父親と息子である前に、人と人なんだ。息子はそれにとっくに気づいていたのに、俺はまるで気づいていなかった。
福山雅治が泣いたのは、息子も同様に、パパを引き算していたが、足し算もしていたからではない。こんなパパでもお前は慕ってくれていたんだ、とそのいじらしさに感じ入ったからではない。引き算も足し算もなく、俺のすべてを、俺さえ見たことがない俺の寝顔さえ、息子はじっと見ていた。俺はどうだったか? 引き算しか見ていなかったではないか。何もかも、わかっちゃいなかった。だから、俺こそ子どもだったんだ、と心底からわかった。それで、泣いた。自分が子どもと知ったから、泣くことを自らに許した。したがって、ほかの場面ではなく、泣くのは、あの場面でなければなかった。そう思いました。
それと、映画的ないわゆる映像美を追わず、TV的な空気感を意識したカメラワークに、映画の新しい可能性を感じました。
(敬称略)