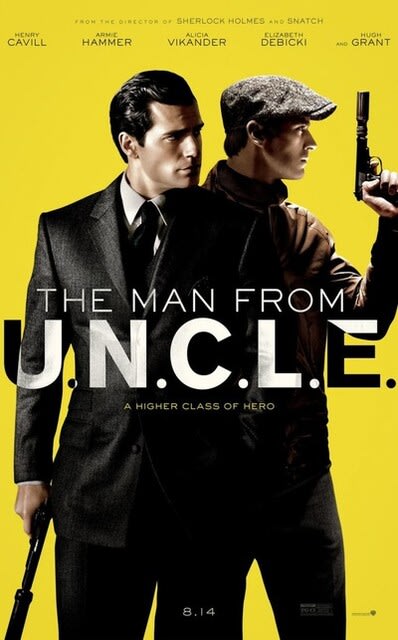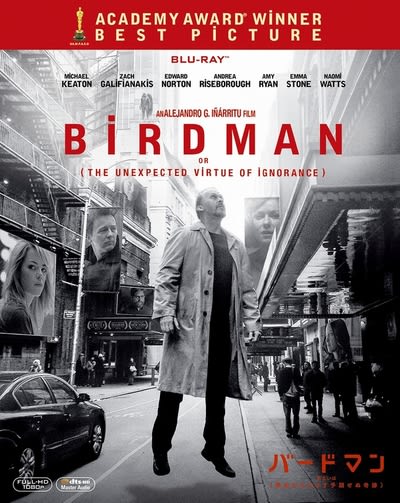CATVで放映されていた「愛の嵐」を観た。「ベニスに死す」「地獄に堕ちた勇者ども」などと並び、「愛とエロス」の芸術映画として名高い作品だが、初めて。ついでにいえば、「ベニスに」と「地獄に」も未見。耽美主義的な「芸術」映画は性に合わない。
映画は時代の表現だから、たいていの名作や傑作、あるいは先鋭的な問題作でも、昔の映画に感心することはごく少ないもの。が、この「愛の嵐」はいまでもかなりの問題作だと思った。問題視されるだろうと問題を抱えているという二重の意味で。
映画の舞台は1957年(昭和32)のウィーン。映画の製作年は1973年(昭和48)。米伊合作のイタリア映画でリリアーナ・カヴァーニなる女性監督作品。公開当時、ナチスを賛美していると欧米では上映禁止運動が起きたそうだ。
簡単にあらすじにふれると、第二次世界大戦から13年後、強制収容所の生存者ルチア(シャーロット・ランブリング)は、彼女を虐待したした男(ダーク・ボガード)と再び出会い、かつてのサドマゾ関係に堕ちていくという話。
戦時中、ナチス親衛隊将校だった男マクシミリアン(マックス)は、ウィーンの二流ホテルで夜間のフロント係になっていた。ルチアは著名なオペラ指揮者の裕福な夫人として投宿したホテルで、二人は再会する。
この映画を語るとき、かならず言及される有名なシーンがある。この映画が露呈し、孕む問題のほとんどをこのマックスの回想シーンに見出すことができる。
強制収容所を管理する親衛隊の将校クラブ。ユダヤ人少女ルチアは親衛隊の将校帽をかぶり、上半身裸にサスペンダー、粗末でだぶだぶのズボンに裸足、なのに貴婦人のようにひじ上まで覆う黒手袋をつけ、男たちの間を気怠く歌い踊っていく。
Danny A Kaysi The Night Porter Film 1974- Marlene Dietrich wenn ich mir was wunschen durfte
ルチアが歌う歌は、マレーネ・デートリッヒの「望みは何かと訊かれたら」(Marlene Dietrich - Wenn Ich Mir Was Wünschen Dürfte)
(敬称略)
映画は時代の表現だから、たいていの名作や傑作、あるいは先鋭的な問題作でも、昔の映画に感心することはごく少ないもの。が、この「愛の嵐」はいまでもかなりの問題作だと思った。問題視されるだろうと問題を抱えているという二重の意味で。
映画の舞台は1957年(昭和32)のウィーン。映画の製作年は1973年(昭和48)。米伊合作のイタリア映画でリリアーナ・カヴァーニなる女性監督作品。公開当時、ナチスを賛美していると欧米では上映禁止運動が起きたそうだ。
簡単にあらすじにふれると、第二次世界大戦から13年後、強制収容所の生存者ルチア(シャーロット・ランブリング)は、彼女を虐待したした男(ダーク・ボガード)と再び出会い、かつてのサドマゾ関係に堕ちていくという話。
戦時中、ナチス親衛隊将校だった男マクシミリアン(マックス)は、ウィーンの二流ホテルで夜間のフロント係になっていた。ルチアは著名なオペラ指揮者の裕福な夫人として投宿したホテルで、二人は再会する。
この映画を語るとき、かならず言及される有名なシーンがある。この映画が露呈し、孕む問題のほとんどをこのマックスの回想シーンに見出すことができる。
強制収容所を管理する親衛隊の将校クラブ。ユダヤ人少女ルチアは親衛隊の将校帽をかぶり、上半身裸にサスペンダー、粗末でだぶだぶのズボンに裸足、なのに貴婦人のようにひじ上まで覆う黒手袋をつけ、男たちの間を気怠く歌い踊っていく。
Danny A Kaysi The Night Porter Film 1974- Marlene Dietrich wenn ich mir was wunschen durfte
ルチアが歌う歌は、マレーネ・デートリッヒの「望みは何かと訊かれたら」(Marlene Dietrich - Wenn Ich Mir Was Wünschen Dürfte)
(敬称略)