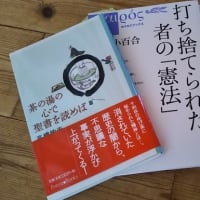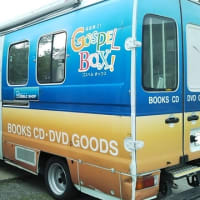くもりがちで、少し湿度があり、
蒸し暑かった今日、
久しぶりに母からの誘いもあって
弘前の実家へ行き、
ついでに「藤田記念庭園」に行きました。
(たまには母孝行しなくてはね)
藤田記念庭園は、弘前公園の西側に位置し、
弘前市民会館向かいのわかりやすい場所。
夏は花菖蒲、秋はもみじと紅葉が楽しめます。

大きな門から入ると大きな和風庭園が見えます。
入場料は大人300円、子供100円。
団体は10人以上で2割引。
(市内の高齢者は保険証など提示するとタダ。)
4月中旬~11月23日までは年中無休。
午前9時~午後5時までやっています。

さて、この藤田記念庭園の主、藤田謙一さんは、
明治6年~昭和21年の方。弘前出身で、実業家。
議員さんでもあったようです。
この方、現明治大学を卒後、熊野敏三博士(法学)の
書生さんとなり、その後、たばこ製造会社に就職。
以後60社以上の会社代表や取締役となりました。
東京商工会議所会頭を経て、日本商工会議所の初代会頭に。
日本屈指の財界人となり、藤田育英社の創設、
弘前市公会堂の寄付など多くの社会貢献をした人物らしいです。

和館です。
この庭園は、東京から庭師を招き造らせた
江戸風な景趣の庭園なのだそうです。
総面積は6600坪。
お宅の庭としては、あまりに広いです。
「和館」の中に入ると、渡り廊下でつながった
和室がたくさんありました。

和室なのに、レトロなカントリーなものもあって
興味をひきました。

電灯はこの当時ではモダンです。

天井からつるされた電灯。

なぜか水道蛇口。
色が銅いろで、レトロで素敵です。
我が家にほしいなあ。

彫刻が施された扉。
良く見ると「ぶどう」でした。


藤田庭園には「洋館」もあります。
以前、洋館に入ったので、今日は入りませんでしたが、
ここには、会議室があったり、小音楽会に利用できるホールや、
喫茶室があったりします。
「和館」「洋館」ともに文化財に指定されています。
和館のとなりには「考古館」があり、
青森県内で発見された縄文土器などが
展示されています。
一瞬、藤田庭園でなく、三内丸山遺跡に来た
錯覚に陥りましたよ。
他には茶室あり、休みどころやあずまやもあり、
1時間もあればゆったりと見られます。

さて、今日の目的は花菖蒲を見る事。
ゆっくりとご覧下さいませねえ。

色とりどりの菖蒲が咲いています。



ピンクの花菖蒲は初めて見ました。
母も珍しさにびっくり。


これも珍しいかな。

青い菖蒲はすがすがしい。

白い菖蒲は清楚でした。


途中にあったのはたぶん「とくさ」だと思います。
まるでミニの竹のようです。
ここの庭園は、庭園と言うより、
里山風情な面もあり、
シダ類があり、笹があり、
ドクダミなどの野草がたくさんあります。
花菖蒲の手前には池があって、
そこには鯉がたくさんいます。
人の声に反応して寄ってきます。
えさも売られているので、
人が来たらもらえると思っているのでしょう。



でも、あげませんでしたけど・・・(笑)
池の近くにはシオカラトンボまで。

見えますか?
そして、池の向こうには、滝があります。


ここからは岩木山も見えますが、残念ながら今日は
くもりで山はあまり見えませんでした。
新しいあずまやで少し休んで・・・
そこにはおもしろい傘立てがありました。

良く見ると・・・

「傘も一緒に休みましょう」

「杖も一緒に休みましょう」
の文字が書かれていました。

更に石畳をのぼると、里山の風情が加わり、
草木が茂り、涼しい風が吹いてきます。
最後は、これです。


水琴窟です。
さっそくひしゃくで水をくみ、
下に落としてみると・・・

なんともいえない涼しげな音。
どう書けばいいのでしょうか。
金属音に近いような、それでいて不快でなく、
よく響いています。
ひしゃくから落ちた水滴が、
地中の瓶の底にたまった水を打ち、
その音が共鳴して聞こえるそうです。
いいですよ~水琴窟。

お昼には、公園近くの「松味屋」さんに寄って
おそばを食べて帰りました。

とろろそば。700円。
とろろがクリーミーでした。
よくおそばとからんでました。
こしのあるおそばでしたよ。
それにしても藤田記念庭園の管理は
かなり大変だろうと思いました。
あの広さですもの。
植物の管理、建物の管理・・・
今日も、割と年輩の方々が、
池の周りの草とりをしていました。
蒸し暑いのに。ご苦労様です。
こうした隠れた管理者達がいてこそですよね。
見えない所にしっかりと人材とお金を
惜しまない・・・。
これが維持管理の秘訣なんでしょうねえ。
大したもんですね。
ここあでした。
蒸し暑かった今日、
久しぶりに母からの誘いもあって
弘前の実家へ行き、
ついでに「藤田記念庭園」に行きました。
(たまには母孝行しなくてはね)
藤田記念庭園は、弘前公園の西側に位置し、
弘前市民会館向かいのわかりやすい場所。
夏は花菖蒲、秋はもみじと紅葉が楽しめます。

大きな門から入ると大きな和風庭園が見えます。
入場料は大人300円、子供100円。
団体は10人以上で2割引。
(市内の高齢者は保険証など提示するとタダ。)
4月中旬~11月23日までは年中無休。
午前9時~午後5時までやっています。

さて、この藤田記念庭園の主、藤田謙一さんは、
明治6年~昭和21年の方。弘前出身で、実業家。
議員さんでもあったようです。
この方、現明治大学を卒後、熊野敏三博士(法学)の
書生さんとなり、その後、たばこ製造会社に就職。
以後60社以上の会社代表や取締役となりました。
東京商工会議所会頭を経て、日本商工会議所の初代会頭に。
日本屈指の財界人となり、藤田育英社の創設、
弘前市公会堂の寄付など多くの社会貢献をした人物らしいです。

和館です。
この庭園は、東京から庭師を招き造らせた
江戸風な景趣の庭園なのだそうです。
総面積は6600坪。
お宅の庭としては、あまりに広いです。
「和館」の中に入ると、渡り廊下でつながった
和室がたくさんありました。

和室なのに、レトロなカントリーなものもあって
興味をひきました。

電灯はこの当時ではモダンです。

天井からつるされた電灯。

なぜか水道蛇口。
色が銅いろで、レトロで素敵です。
我が家にほしいなあ。

彫刻が施された扉。
良く見ると「ぶどう」でした。


藤田庭園には「洋館」もあります。
以前、洋館に入ったので、今日は入りませんでしたが、
ここには、会議室があったり、小音楽会に利用できるホールや、
喫茶室があったりします。
「和館」「洋館」ともに文化財に指定されています。
和館のとなりには「考古館」があり、
青森県内で発見された縄文土器などが
展示されています。
一瞬、藤田庭園でなく、三内丸山遺跡に来た
錯覚に陥りましたよ。
他には茶室あり、休みどころやあずまやもあり、
1時間もあればゆったりと見られます。

さて、今日の目的は花菖蒲を見る事。
ゆっくりとご覧下さいませねえ。

色とりどりの菖蒲が咲いています。



ピンクの花菖蒲は初めて見ました。
母も珍しさにびっくり。


これも珍しいかな。

青い菖蒲はすがすがしい。

白い菖蒲は清楚でした。


途中にあったのはたぶん「とくさ」だと思います。
まるでミニの竹のようです。
ここの庭園は、庭園と言うより、
里山風情な面もあり、
シダ類があり、笹があり、
ドクダミなどの野草がたくさんあります。
花菖蒲の手前には池があって、
そこには鯉がたくさんいます。
人の声に反応して寄ってきます。
えさも売られているので、
人が来たらもらえると思っているのでしょう。



でも、あげませんでしたけど・・・(笑)
池の近くにはシオカラトンボまで。

見えますか?
そして、池の向こうには、滝があります。


ここからは岩木山も見えますが、残念ながら今日は
くもりで山はあまり見えませんでした。
新しいあずまやで少し休んで・・・
そこにはおもしろい傘立てがありました。

良く見ると・・・

「傘も一緒に休みましょう」

「杖も一緒に休みましょう」
の文字が書かれていました。

更に石畳をのぼると、里山の風情が加わり、
草木が茂り、涼しい風が吹いてきます。
最後は、これです。


水琴窟です。
さっそくひしゃくで水をくみ、
下に落としてみると・・・

なんともいえない涼しげな音。
どう書けばいいのでしょうか。
金属音に近いような、それでいて不快でなく、
よく響いています。
ひしゃくから落ちた水滴が、
地中の瓶の底にたまった水を打ち、
その音が共鳴して聞こえるそうです。
いいですよ~水琴窟。

お昼には、公園近くの「松味屋」さんに寄って
おそばを食べて帰りました。

とろろそば。700円。
とろろがクリーミーでした。
よくおそばとからんでました。
こしのあるおそばでしたよ。
それにしても藤田記念庭園の管理は
かなり大変だろうと思いました。
あの広さですもの。
植物の管理、建物の管理・・・
今日も、割と年輩の方々が、
池の周りの草とりをしていました。
蒸し暑いのに。ご苦労様です。
こうした隠れた管理者達がいてこそですよね。
見えない所にしっかりと人材とお金を
惜しまない・・・。
これが維持管理の秘訣なんでしょうねえ。
大したもんですね。
ここあでした。