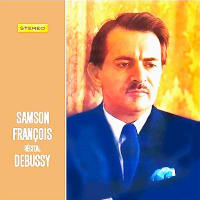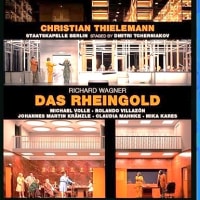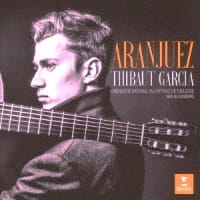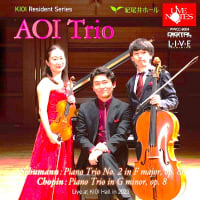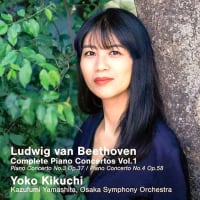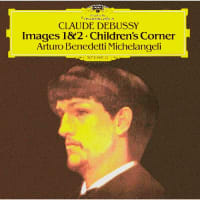ハイドン: 交響曲第92番「オックスフォード」
第96番「奇蹟」
第102番
第104番「ロンドン」
指揮: アンドレ・プレヴィン
管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1992年2月4~7日(第92番/第96番)、1993年4、5、10日(第96番/第104番)、
ウィーン、ムジークフェライン
CD:タワーレコード PROC‐1013~4(2枚組)
指揮のアンドレ・プレヴィン(1929年―2019年)は、ドイツ、ベルリンの出身。1938年と一緒にアメリカへと渡り、1943年にアメリカ合衆国市民権を獲得。ピエール・モントゥーに指揮法を学ぶ。ヒューストン交響楽団、ロンドン交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、ロサンジェルス・フィルハーモニック、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団などで音楽監督、首席指揮者などを歴任した。また、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団との関係も深かった。2009年よりNHK交響楽団の首席客演指揮者(後に名誉客演指揮者)に就任した。2019年2月28日、89歳でニューヨークで亡くなった時、NHK交響楽団は「プレヴィン氏とN響の初共演は1993年8月。・・・その人柄を映し出すかのような高い品位と優しさを兼ね備えた演奏で私達を魅了してきました。またモーツァルトやガーシュウィンのピアノ協奏曲で披露した”弾き振り”も忘れ難いものです。・・・氏が指揮を務めた東日本大震災直後の2011年3月のN響北米ツアーでは、自らバッハ”G線上のアリア”を演奏することを提案し、日本への痛切な思いを現地の聴衆に音楽を通じて届けました」と哀悼の意を表した。
アンドレ・プレヴィンは、10代の頃からジャズを演奏し、”天才少年”として注目された。1953年からは、ウェストコースト・ジャズ界の名トランペット奏者ショーティ・ロジャースの楽団に所属。1960年代までジャズ・ピアニストとして多くのレコードを製作。また、ロサンゼルス時代にはハリウッドの大手映画会社MGM専属となり、多くの映画において映画音楽の作曲や編曲、音楽監督を務めた。プレヴィンが何らかの形でかかわった作品としては、「キス・ミー・ケイト」「絹の靴下」「恋の手ほどき」「あなただけ今晩は」「マイ・フェア・レディ」「ペンチャー・ワゴン(英語版)」「ジーザス・クライスト・スーパースター」などがある。アカデミー賞は通算4回受賞。クラシック音楽の作曲家としても多くの作品を遺している。「ピアノ協奏曲」「チェロ協奏曲」「ヴァイオリン協奏曲」「ギター協奏曲」「金管五重奏のための4つの野外音楽」のほか、オペラ「欲望という名の電車」、歌曲集「ハニー・アンド・ルー」などの声楽曲も作曲した。1998年にはケネディ・センター賞を授与されたほか、イギリスではナイト(KBE)に叙勲された。
このような多彩な才能を持ち主であったアンドレ・プレヴィンが、ウィーン・フィルを指揮してハイドンの交響曲4曲を2枚に収録したのが今回のCDである。ハイドンは、弦楽四重奏曲および交響曲の古典的形式を確立したというクラシック音楽史上に不滅の足跡を残している。ハイドン以前の演奏会での主役は協奏曲や声楽曲であり、交響曲は聴衆が座席に付き終える間の音楽という脇役的存在にすぎなかった。それを、ハイドンは4楽章からなる独立した音楽ジャンルに成長させ、その結果、現在の演奏会においては、交響曲が主役の座を占めることになった。交響曲第92番が「オックスフォード」と名付けられたのは、1791年にオックスフォード大学における名誉博士号の授与式でハイドンがこれを指揮したと伝えられているため。ハイドンは、1761年にハンガリーのアイゼンシュタットのエステルハージー家の楽団の副楽長に就任したが、1790年に音楽に造詣が深いニコラウス公が亡くなり、その後を継いだアントン公が音楽に関心がないことを、ボン生まれのヴァイオリニストで当時、ロンドンで活躍していたヨハン・ペーター・ザロモンから聞き、1791年にロンドンに赴いた。ロンドンではザロモン・コンサートと名付けられた演奏会が大成功を収めることになる。交響曲第96番「奇蹟」は、ハイドンが1791年に作曲した曲。「奇蹟」という愛称は、楽曲そのものとは関係はない。この交響曲の初演時に、会場のシャンデリアが天井から落下したにも関わらず誰も怪我をしなかった、という出来事に由来したという。しかし、近年の研究では、交響曲第96番ではなく、102番であるらしいことが分かっている。
交響曲第102番は、ハイドンが1794年にロンドンで作曲した作品。1791年から1795年にかけて作曲した12曲の交響曲は「ロンドン交響曲(ザロモン交響曲)」と呼ばれているが、第102番はその中の1曲。交響曲第104番「ロンドン」は、1795年にロンドンで作曲した曲で、ハイドンの代表作の一つであり、ハイドンの最後の交響曲。「ロンドン」の愛称は曲とは直接関係はない。「ロンドン交響曲」を締めくくる曲であることで付けられたもので、曲の内容は極めて充実した作風となっており、今でも演奏会でしばしば取り上げられている。アンドレ・プレヴィンの録音と言えば、メンデルスゾーン、チャイコフスキー、ラフマニノフ、それにプロコフィエフなどを思い出す。このCDを聴く前は、正直なところ私にはプレヴィンとハイドンの相性について少々戸惑ががあったのも事実。ところが、このれらの4曲を聴き終えてみると、相性はなかなかいいどころか、明るく軽快なハイドン像がくっきりと浮かび上がる名演を聴かせてくれる。ウィーン・フィルを巧みに指揮し、ウィーン・フィルの持ち味を存分に引き出すことに成功している。ウィーン・フィルというと、毎年の元旦のニューイヤー・コンサートのイメージが強くいためか、ウィーン情緒たっぷりの演奏を思い浮かべるが、実は強靭なバネを連想させる力強さが本領なのだ。私は、たまたま2018年11月24日にサントリーホールで開催されたフランツ・ウェルザー=メスト指揮ウィーン・フィルの演奏会を聴いたが、その演奏の強靭さには驚かされた。このCDでは、プレヴィンはそんなウィーン・フィルを、手綱捌きの良い騎手の如く巧みに導いていく。表現は明るく澄みっ切って、明快この上ない。重くもなく、さりとて軽くもない。中庸さを保つが、凡庸ではない演奏内容だ。4曲の中でも白眉なのは交響曲第104番「ロンドン」の演奏である。神々しいばかりの重厚さが曲全体を覆う演奏だが、そこにはプレヴィン特有の遊び心のような親しみやすさが溢れ返っている。プレヴィンさん、長い間数々の名演奏をありがとう、合掌。(蔵 志津久)