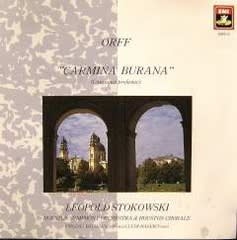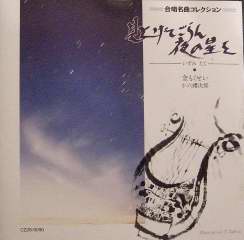
~合唱名曲コレクション~
女性合唱曲集「見上げてごらん夜の星を」
いずみたく 作曲・編曲
見上げてごらん夜の星を 永六輔作詞
明日も逢おうよ 松原雅彦作詞
ふれあい 山川啓介作詞
女ひとり 永六輔作詞
ともだち 永六輔作詞
世界は二人のために 山上路夫作詞
手のひらを太陽に やなせたかし作詞
希望 藤田敏雄作詞
愛に生き平和に生きる 岩谷時子作詞
友よ 岩谷時子作詞
12の誕生日に 武藤たずる作詞
仲間 藤田敏雄作詞
夜明けのうた 岩谷時子作詞
今、今、今 藤田敏雄作詞
指揮:中村博之
合唱:コーロ・みお
ピアノ:北野実
伴奏:アンサンブル・アカデミア
オーケストラ伴奏編曲:北野実
女声合唱組曲「金もくせい」
作曲:小六禮次郎 作詞:藤公之介
金もくせい匂えど
煉瓦坂
公園通りの金もくせい
風になれ
指揮:志水隆
副指揮:木下章子
合唱:長崎コール・ブーケ
ピアノ:小阪徳子
CD:東芝EMI CZ28 9090
東日本大震災は、多くの方々の命を奪い、平和な街や村の生活基盤を根こそぎ奪い去ってしまった。日本列島は、全世界の土地の面積比では取るに足らない小ささであるにも関わらず、全世界の1割の地震が集中しているという。これは、これからも避けては通れない試練を日本の国民に与えることを意味する。そのためには、我々は、地震や津波などの自然災害に対して、最小の被害で済むよう、常日頃の対策を万全にしておくことが欠かせまい。ただでさえ狭い国土に、どうも日本人は一カ所に集中して住みたがる傾向があるようだ。これからは、なるべく人口密度を平準化して住むことが可能なネットワーク機能を全国的に整備するなどの抜本的な対策が求めれる。“世界一地震や津波の対策が行き届いた国”と胸を張って世界に向かって言える国にすることこそが、大震災で亡くなられた方々への最大の供養となるのではないだろうか。
今回の大震災では、金子みすゞの詩がテレビ放送から常に流れ、世間の耳目が集まった。常日頃金子みすゞの詩が大好きな私としては、不幸で衝撃的な大震災の報道の狭間で辛じてほっとできる一瞬であった。それと同時に、かつてのヒット曲、いずみたく(作曲)&永六輔(作詞)コンビによる「見上げてごらん夜の星を」がいつもより多く歌われたのではないかと思う。東日本大震災チャリティーコンサートでも、演奏家と聴衆とが一緒に「見上げてごらん夜の星を」を歌ったことが伝えられていた。国難である大震災の中、日本国民が一緒になって希望をもって明るい未来を願える歌、それが「見上げてごらん夜の星を」を蘇らせたのではなかろうかとも思う。そこで、大分前に買っておいた「見上げてごらん夜の星を」をはじめとした、いずみたく(1930年―1992年)の作品と小六禮次郎の「金もくせい」が収められた女性合唱曲集のCDを取り出してきて聴いてみることにした。録音は、1981年(昭和56年)と1987年(昭和62年)と大分前のものだが、その歌の一曲、一曲は今聴いてみても少しも古臭くなく、明るい未来に向かって歌っているようにも聴こえ、何か勇気づけられるのだ。
いずみたくは、ダンプの運転手などをしながら芥川也寸志に師事したという、いわば叩き上げの作曲家である。日本レコード大賞作曲賞受賞曲を含め、生涯に作曲した数は1万5000曲にも上るという。そのいずみたくは、このCDのライナーノートに次のように記している。「・・・歌には生命があり、その生命が永続きすればする程、その歌は素晴らしいし、良い歌である。それがスタンダードナンバーである。いつの時でも、あらゆる場所で大勢が歌える歌―そんな歌をボクは三十年間作り続けたいと思って作曲してきた。今振り返ってみて、それが出来たかどうか、半信半疑であるが、今後も死ぬまで、それを信じて作り続けたいと思う」。このいずみたくの言葉の中に「あらゆる場所で大勢が歌える歌」という部分がある。今回の大震災で「見上げてごらん夜の星を」が歌われた理由はこれだ!と私は思った。今の歌はそのほとんどが年齢層で区分けされ、子供からお爺ちゃん、お婆ちゃんまで皆で一緒に歌える歌は少ない。その昔、いずみたく&永六輔コンビが活躍した時代は、皆で歌える歌が数多くあり、そんな環境の中で、いずみたくは躊躇なく皆で歌える歌を目指していたのだ。そのことこそ、今回の大震災でいずみたくの歌が歌われた理由ではないかと私は思う。
このCDには、もう一つ小六禮次郎作曲・藤公之介作詞の女声合唱組曲「金もくせい」が収められている。小六禮次郎は1949年生まれ。いずみたくとは違い、東京藝術大学音楽学部作曲科を卒業し、オペラ、交響詩まで作曲したという正統派の作曲家である(夫人は女優で歌手の賠償千恵子)。このCDのライナーノートで小六禮次郎は次のように書いている。「・・・音楽の力は弱いのです。でも音楽がひとたび人の心に入り込めば、人の感情をよびさまし、生きる喜びを充実させてくれます。思い出を歌う歌は情感をよびさます以外、何もよいところはないかもしれません。でも小さいけれど本当に大切な、『人の持つ優しい気持ち』を湧き上がらせることが出来ます。・・・」。ここに収められた女声合唱組曲「金もくせい」は、この小六の言葉がそのまま曲となったような、素敵な香りがする曲だ。ピアノ伴奏と女声合唱が幻想的な雰囲気を漂わせ、何か一時、昔懐かしい安らぎの世界へ紛れ込んだ感じにしてくれる。今回、いずみたくと小六禮次郎の曲を改めて聴いてみて、名曲は時代を超越して人の心を打つ何かを宿しているということを強く実感させられた。そして、すべての曲でコーロ・みおと長崎コール・ブーケが、女性合唱の素晴らしさをたっぷりと伝えてくれているのが何よりも嬉しいのだ。(蔵 志津久)