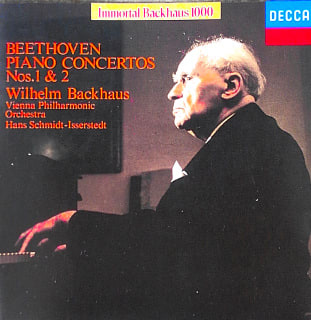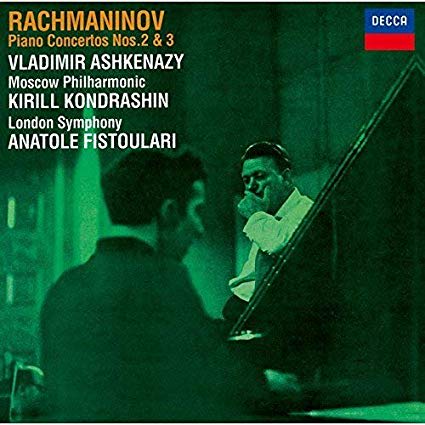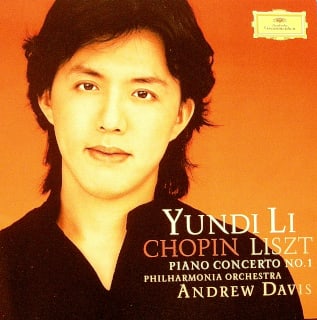ピアノ:ハンス・リヒター=ハーザー
指揮:カルロ・マリア・ジュリーニ
管弦楽:フィルハーモニア管弦楽団
録音:1963年4月20日(ピアノ協奏曲第3番)
1961年4月14日(ピアノソナタ第17番「テンペスト」)
CD:東芝EMI EMI CLASSICS CAPO‐3004
ハンス・リヒター=ハーザーは、ベートーヴェンのピアノ作品の解釈では、当時、右に出る者はいないとも言われた優れたドイツのピアニストであった。真摯な態度でベートーヴェンの作品に立ち向かい、LPレコード時代のリスナーに深い感動を与えた。現在では、忘れ去られつつあるピアニストの一人になった感のあるハンス・リヒター=ハーザーの録音を、今回、改めてCDで聴き直してみることにした。何よりもベートーヴェンをより深く知るために。
ピアノのハンス・リヒター=ハーザー(1912年―1980年)は、ドイツ、ドレスデン出身。地元のドレスデン音楽院でハンス・シュナイダーに師事。1928年から演奏活動を開始し、1930年(18歳)「ベヒシュタイン賞」を受賞。ドレスデン音楽院卒業後、一時、フリッツ・ブッシュの下でドレスデン歌劇場の副指揮者を務める。1932年から、ピアニスト兼指揮者として活躍する。第二次世界大戦中からデトモルトに移り住み、1945年から1947年までデトモルト交響楽団の音楽監督を務めた。1947年以降はピアニストに専念する。各地で演奏会を行い、ドイツ系作品、中でもベートーヴェンの優れた解釈者として知られた。また、作曲家としても多くの作品を遺した。1946年から1962年まで北西ドイツ音楽院でピアノを教え、1955年から同院院長に就任。1959年にはアメリカ・デビューを果たし、1963年にはザルツブルク音楽祭にも出演。日本にもは963年と67年の二度訪れ、67年には7夜にわたるベートーヴェンのピアノソナタ全曲演奏会を開催した。
指揮のカルロ・マリア・ジュリーニ(1914年―2005年)は、イタリア、プッリャ州出身。最初はヴァイオリンを学んだが、サンタ・チェチーリア国立アカデミア管弦楽団のヴィオラ奏者としてスタート。ヴィオラ奏者時代には、客演したブルーノ・ワルターなど当時の大指揮者の指揮に触れる機会を得る。1946年ローマRAI交響楽団首席指揮者、1950年ミラノRAI交響楽団首席指揮者、1953年ミラノ・スカラ座音楽監督、1969年シカゴ交響楽団の首席客演指揮者、1973年ウィーン交響楽団首席指揮者、1978年ロサンジェルス・フィルハーモニック音楽監督。以後、フリーの指揮者としてウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団などヨーロッパの名門オーケストラに客演。1998年に指揮活動から引退。
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調作品37は、ベートーヴェン中期の初頭を飾るピアノ協奏曲で、個性の豊かさを示した傑作と位置付けられている作品。主題の楽想、展開の技法、楽曲全体のスケールの大きさ、どれをとっても飛躍的発展を示している。そしてベートーヴェンが遺したピアノ協奏曲中唯一の短調でもある。1796年にスケッチを開始。当初は、1800年4月2日の初演を目指していたが、この時点では冒頭楽章しか出来ていなかった。それから約3年後にあたる1803年4月5日にアン・デア・ウィーン劇場において行われた公演でようやく初演にこぎ着けたものの、この時にも独奏ピアノ・パートは殆ど空白のままで、ベートーヴェン自身がピアノ独奏者として即興で乗り切ったという。独奏ピアノ・パートが完成してから最初に演奏が行われたのは、初演から1年余り経った1804年7月のこと。
この曲でのハンス・リヒター=ハーザーのピアノ演奏は、ベートーヴェンへの過度な思い入れなどは決してしない。淡々と客観的にベートーヴェンを見つめる。しかし、そのピアノタッチの何と温かいことか。全体はきっちとした構成美に貫かれているが、リスナーには少しも堅苦しさを感じさせない演奏内容なのである。弾き進むうちに、あたかもハンス・リヒター=ハーザー自身が生身のベートーヴェンとの会話をしているような、不思議な感覚にリスナーは捕らえられる。そして、いつも聴くベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番のイメージとは違う感覚に身を置くことになり、自然に静かで平穏な世界へと誘われる。ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番がこんなにも包容力のある曲だとは・・・リスナーは初めて知ることになる。カルロ・マリア・ジュリーニ指揮フィルハーモニア管弦楽団も、要所要所を抑え、ベートーヴェンの描く豊かな世界を描き切り、見事な効果を挙げている。
この曲でのハンス・リヒター=ハーザーのピアノ演奏は、一転、力強く、いつものベートーヴェン像を彷彿とさせる演奏内容を披露する。ここ頃、ベートーヴェンは、難聴に苦しめられていたわけで、その苦境を跳ねのけようとする強靭な意志の力がこの曲の背景に横たわる。ハンス・リヒター=ハーザーの演奏は、そんなベートーヴェンに寄り添い、少しの妥協を許さない厳しさが、辺り一面を覆い尽くす。そんな中でも揺るぎない構成美は毅然と存在し、ハンス・リヒター=ハーザーは、決して情緒に溺れることはない。ベートーヴェンの心の中に入り込み、あたかもその苦しみを共有するかのような演奏内容は、時代を超越し、永遠の生命力を有しているようにも感じられる。そして終楽章で見せる、未来を見つめ決然とした意志で前進するハンス・リヒター=ハーザーの演奏は、何かベートーヴェンの魂が乗り移ったようだ。でも、そんな時でもハンス・リヒター=ハーザーの演奏には、何かしら心の安らぎを感じることが出来るのだ。(蔵 志津久)