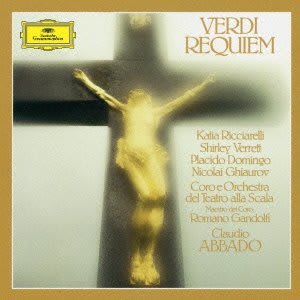~今でもトップの座にあるクラウディオ・アバドの最初の録音 ヴェルディ:レクイエム~
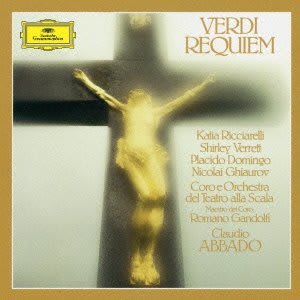
ヴェルディ:レクイエム
第1曲: レクイエムとキリエ
第2曲: 怒りの日
第3曲: 奉献誦
第4曲: サンクトゥス
第5曲: アニュス・デイ
第6曲: 永遠の光を
第7曲: われを解き放ちたまえ
指揮:クラウディオ・アバド
管弦楽:ミラノ・スカラ座管弦楽団
独唱:カーティア・リッチャレッリ(ソプラノ)
シャーリー・ヴァーレット(メゾ・ソプラノ)
プラシド・ドミンゴ(テノール)
ニコライ・ギャウロフ(バス)
合唱指揮:ロマーノ・ガンドルフィ
合唱:ミラノ・スカラ座合唱団
録音:1979年6月26~29日、11月3、4日、1980年1月7日、2月21、26日 、ミラノ、CTCスタジオ
CD:ユニバーサル・ミュージック(ドイツ・グラモフォン) UCCG-4809(2枚組)
このCDで指揮をしているクラウディオ・アバド(1933年生まれ)の今年10月の来日を首を長くして待っていたファンも多かっただろうと思うが、残念ながらクラウディオ・アバドは健康上の理由で、ルツェルン祝祭管弦楽団との今回の来日は中止となってしまった。現代の巨匠の一人に挙げられるクラウディオ・アバドは、イタリア、ミラノ出身。ヴェルディ音楽院およびウィーン音楽院で学んだ後、1959年に指揮者デビューを果す。1968年にミラノ・スカラ座の指揮者となり、1972年には音楽監督、1977年には芸術監督に就任。さらに、1979年にロンドン交響楽団の首席指揮者、1983年には同楽団の音楽監督に就任している。そして1986年に、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任した後、1990年、カラヤンの後任としてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督に就任し、これによりアバドは世界のクラシック音楽界の頂点に君臨することになる。2000年に病魔に倒れるが、回復した2003年以降は、ルツェルン祝祭管弦楽団さらに、自身が組織した若手中心のオーケストラであるマーラー室内管弦楽団やモーツァルト管弦楽団などと活動することが多くなっている。
イタリア出身のアバドの指揮するヴェルディ:レクイエムのこのCDは、管弦楽がミラノ・スカラ座管弦楽団ということに加え、魅力的な独唱陣、それに合唱:ミラノ・スカラ座合唱団という布陣を揃えた本場中の本場の演奏と言える録音なのである。独唱陣を見てみると、ソプラノのカーティア・リッチャレッリは、フレーニの後を継ぎイタリア・オペラ界屈指のプリマドンナとして一世を風靡し、現在も現役で活躍中。メゾ・ソプラノのシャーリー・ヴァーレットは、アバドお気に入りの歌手の一人で、米国が生み出した黒人歌手の逸材。ご存じテノールのプラシド・ドミンゴは、現在も現役として活躍中。そしてブルガリア出身でバスのニコライ・ギャウロフは、残念なことに2004年に亡くなったが、現役時代は、ミラノ・スカラ座には欠かせなかった名バス歌手。アバドは、この録音の後に、ヴェルディ:レクイエム を2回録音している。それらは1991年のウィーン・フィルを指揮した盤、それに2001年のベルリン・フィルとのライヴ録音盤である。ところが、今でもこの一番古い録音がアバドの代表作として高く評価されているのだ(例えば「名曲名盤300ベスト・ディスクはこれだ!」<音楽之友社刊>において1位を獲得。因みに2位は、カラヤン指揮ベルリン・フィル盤)。
このCDの演奏の特徴は、敬虔な宗教性と劇的なオペラ的要素とが巧みに融合されて、全体として実に統一感のある演奏に貫かれているということに尽きよう。ヴェルディというとオペラの巨人であることから、この曲をオペラのように劇的な面を強調した演奏が数多く見られるが、宗教性という側面を見落とすとベルディの真の意図を見失うことになる。そもそもこの曲は、イタリア・オペラ界最大の作曲家であるロッシーニを悼み、ベルディが12人の作曲家に1曲づつの作曲を呼びかけ、これをもとに一つのレクイエムを完成させようとしたことに始まる。結局、このベルディの案は実現することなく終わるが、この時ベルディは、この幻に終わったレクイエムの最終楽章「リベラ・メ」を作曲していた。丁度その時、ベルディは歌劇「運命の力」を作曲中であり、最も油の乗り切っていた時期の作曲だけに、未発表に終わっていた「リベラ・メ」の内容のレベルの高さもこれで推察できよう。さらに、ヴェルディが尊敬して止まなかったイタリアの愛国詩人アレッサンドロ・マンゾーニの死に直面し(1873年5月)、それまでお蔵入りしていた「リベラ・メ」を取り出し、新たにレクイエムを作曲しようとヴェルディは決意する。そして完成したのが、現在、モーツァルト、フォーレと並び「三大レクイエム」の一つに挙げられている傑作、ヴェルディ:レクイエムである。つまり、この曲は、もともと同郷の大作曲家ロッシーニと大詩人アレッサンドロ・マンゾーニを悼んで作曲されたもので、オペラの延長線から生まれた曲ではないのである。
このCDで、このような作曲の経緯をクラウディオ・アバドは、実によく汲み取って指揮をしていることが、演奏内容によく表れている。この結果、録音からから30年以上経った今でも、多くの人が、数あるヴェルディ:レクイエム の録音の中でもトップに挙げる理由ではないかと私には思える。ところで今年は、ヴェルディ(1813年―1901年)がワーグナーと共に生誕100年を迎えた記念すべき年である。我々日本人にとってお馴染のオペラ「椿姫」の作曲者であり、ヴェルディのことは誰でもが知っているように見えても、実は意外とヴェルディの生涯は知られていないのである。ヴェルディは、オペラ作曲者以外に何百人の農夫を雇う大農場の農園主として経営者の顔を持つ人物であることをご存じであったろうか。さらに、国会議員として政治家の顔も持っていたというから驚きである。このほか、作曲家のための著作権の確立にも尽力したり、音楽家のための老人ホーム「憩いの家」を建設したりと、オペラの作曲以外に八面六臂の大活躍をした、類まれな人物でもあったのだ。ヴェルディが死んだ時、盛大な国葬が執り行われ、あの大指揮者アルトゥーロ・トスカニーニのもと、スカラ座の合唱団が「行け、わが思いよ、黄金の翼に乗って」を歌い、20万人の人々が集まったという。シューベルトやシューマンなど、少なからぬ作曲家が不遇の死を迎えることが多い中、ヴェルディは例外であったのだ。そんなヴェルディの生涯に興味がある方は、この辺の詳細な経緯について書かれた、加藤浩子著「ヴェルディ―オペラ変革者の素顔と作品―」(平凡社新書)の一読をお薦めする。(蔵 志津久)