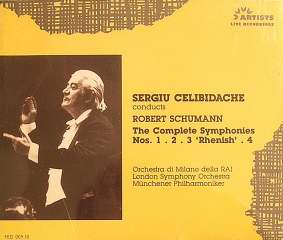シューマン:交響曲第3番「ライン」
ベートーヴェン:歌劇「エグモント」序曲
:歌劇「レオノーレ」序曲第2番
指揮:ブルーノ・ワルター
管弦楽:ニューヨーク・フィハーモニック(シューマン/ベートーヴェン「エグモント」序曲)
コロンビア交響楽団(ベートーヴェン「レオノーレ」序曲第2番)
CD:SONY classical SMK 64 488
ブルーノ・ワルター(1876年―1962年)は、ドイツの大指揮者。ウィーン宮廷歌劇場楽長、ミュンヘン宮廷歌劇場、ベルリン市立歌劇場音楽監督、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団楽長などを務め、徐々にその名声が知れ渡ることになる。しかし、ユダヤ系のワルターはナチから迫害を避けウィーンへと向かい、ウィーン国立歌劇場やウィーン・フィルへと活躍の場を移した。しかし、ここでもオーストリアがナチス・ドイツに併合されてしまい、安住の地ではなかった。この間、次女が不幸に見舞われ亡くなるなど、ワルターの人生には徐々に暗雲が立ち込めることになっていく。その後、スイス、フランスなどヨーロッパを転々とした挙句、最後にはアメリカへと旅立つ。第二次世界大戦後は、ニューヨーク・フィルの音楽顧問を務めるなど、欧米で活躍し、1960年に引退する。しかし、その引退を惜しみ、CBSレコードがワルターの指揮を後世に残すため、専属のオーケストラであるコロンビア交響楽団を急遽結成し、現在にも伝えられる名録音を残すことになる。
今回のCDは、そんな波乱万丈の指揮者人生を歩んだワルターのそれぞれの時代を代表する名録音が収録され、それらの各々の時代のワルターの指揮ぶりがCD1枚で聴き取れるという貴重なもの。それぞれの録音の日付と場所それにオーケストラ名を挙げると、シューマン:交響曲第3番「ライン」が1941年2月4日/ニューヨーク市/ニューヨーク・フィル、ベートーヴェン:歌劇「エグモント」序曲が1954年12月4日/ニューヨーク市/ニューヨーク・フィル、ベートーヴェン:歌劇「レオノーレ」序曲第2番が1960年7月1日/カリフォルニア州ハリウッド/コロンビア交響楽団。これらの録音は、それぞれの時代を反映し演奏内容となっており、ワルターという指揮者が辿ってきた各時代の音楽に対する姿勢が現れており、聴いていて興味は尽きない。そんな時代の背景はあるものの、それらの時代を超越してワルター特有の指揮の特徴ともいうものが厳然としてあることも事実である。すべての録音を通していえることは、音楽へ対する限りない愛情である。決して極度の激情に陥ることはなく、豊かな感性に裏打ちされた、温かさが身上なのだ。ウィーン/ドイツ時代は、特にこの傾向が強い。これに対し、ニューヨーク時代はがらりと変わり、激しい感情をぶつけることも多くなって行ったが、それでもその根底には音楽に対する深い愛情に包まれた、温厚な姿勢は失われていないのである。そしてその後のコロンビア交響楽団時代は、より深い洞察が加わり、ワルターが最後に到達した寂寥感にも似た境地が溢れ出て、聴くものに深い感銘を与えずにはおかない。
シューマン:交響曲第3番「ライン」の第1楽章の出だしを聴いただけで、ニューヨーク時代のワルターの特徴である力強さが滲み出て、聴くものを圧倒する。しかし、一方では、到底他の指揮者には求められない、曲への深い愛情みたいものが常に存在し、それがシューマンの音楽の世界には欠かせないロマンの濃厚さを醸しだしており、聴き応えは充分。第2楽章は、何とも郷愁たっぷりのメロディーから始まるが、ここでワルターならではの歌心が立ち上り、リスナーは、なんともゆったりとしたシューマン独特のロマン濃厚な音楽の世界に浸される。ワルターにして初めて表現できる哀愁がたっぷりと詰まった演奏なのだ。第3楽章もロマン溢れる楽章であるが、ワルターの指揮は、第2楽章以上にリスナーを深い森の中へと誘って行くようなところがあって、落ち着いた音楽を心の底から堪能することができる。第4楽章は、構成力ががっちりとした楽章であり、ワルターはこのことを意識したメリハリのある指揮を見せる。これまでの楽章と比較しての変化の妙といったものを聴き取ることができる。そして雄大な第5楽章が始まる。ワルターの指揮は、実に緻密で細部にわたって、それは丁寧に演奏する。そんな積み重ねを経て、徐々にクライマックスに持っていく手腕はさすがに並外れた技量であることを実感できる。それにしても、何とロマンの濃厚さと雄大な構想とが巧みに組み合わさった「ライン」の演奏であることよ。これ以上の「ライン」の演奏は、これからだってそうは現れることはないであろう。そんな名演だ。
このベートーヴェン:歌劇「エグモント」序曲では、ワルターはニューヨーク・フィルの持てる力をすべて出させることに成功している。分厚いオケの響きを聴くと、もうそこにはベートーヴェンの音楽の持つ、圧倒的な力強さが十二分に表現されつくされている。しかし、ワルターが他の指揮者と違うところは、そんな激しいベートーヴェンの世界にあっても常に歌ごころを失っていないところである。決して刺激的でなく、何か分厚いベールにでもくるんだような表現は、ワルターならのではの独特の指揮芸術なのである。どんなときでも優雅さを忘れない指揮、そんなことが聴きながら脳裏をよぎった。そして、最後の:歌劇「レオノーレ」序曲第2番である。この曲だけがコロンビア交響楽団の演奏だけに、これまでのニューヨーク・フィルとはがらりと様相が異なる。ゆったりとした出だしからして、それまでのワルターの世界とは一味も二味も違う。極端に言えば鬼気迫る表現とでも言ったらいいのであろうか。逆を言えば枯淡の境地とも取れなくはない。もうこれは歌劇の序曲を飛び越えて、一つの独立した交響曲のような演奏なのだ。音は豊穣に鳴り響くのではあるが、あたり一面を静寂さが支配している。これが最後にワルターが到達した音楽なのであったかもしれない。そこには、もう歌ごころを超越した、彼岸のような神々しくも、壮大な音楽が鳴り響いているのであった。そしてワルター最後の録音だけあって、音質がいいのも嬉しい。
(蔵 志津久)