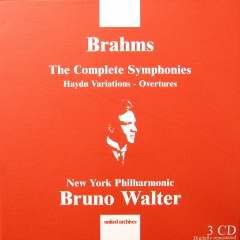R.シュトラウス:死と変容
ブラームス:交響曲第1番
指揮:ウォルフガング・サバリッシュ
録音:1987年4月30日、5月1日、NHKホール(NHK交響楽団名誉指揮者20周年記念演奏会ライヴ録音)
管弦楽:NHK交響楽団
CD:ソニー・ミュージック・ジャパン SICC1207
NHK交響楽団の桂冠名誉指揮者であったウォルフガング・サヴァリッシュが、2013年2月22日に亡くなった。享年89歳。私は、このニュースを聞いた時、「サヴァリッシュが死んでしまった。サヴァリッシュが死んでしまった」とひとり口の中でぶつぶつ言って、暫くは何も手に付かなかった。それは、私のクラシック音楽リスナー人生におけるサヴァリッシュの占める割合が高かったためだ。その昔、FMラジオ放送のクラシック音楽番組にダイアルを回すと、アナウサーの「今日は、ウォルフガング・サヴァリッシュさんの指揮、NHK交響楽団の演奏で、・・・をお送りします」という台詞が飛び込んで来たことを昨日のことのように思い出す。私は、サヴァリッシュの指揮によって、いろいろな名曲を聴き、クラシック音楽の豊かな世界を知ることが出来た。その意味から、サヴァリッシュは、私のクラシック音楽リスナー人生の師匠の一人(一方的ではあるが)であったとも思っている。
サバリッシュは、1923年にドイツ南部ミュンヘンに生まれる。ドイツのアウクスブルクやアーヘンなどの歌劇場で活躍。バイロイト音楽祭で1957年から1962年まで指揮を行う。ケルン歌劇場音楽総監督(1960年―1963年)、ハンブルク国立フィルハーモニー管弦楽団音楽総監督(1961年―1973年) を経て、 1971年にバイエルン州立歌劇場の音楽総監督に就任。ウィーン交響楽団や米フィラデルフィア管弦楽団などでも活躍した。1964年からNHK交響楽団を指揮し、以後頻繁に来日。N響の名誉指揮者(1967年1月~1994年10月)の後、1994年11月から桂冠名誉指揮者の称号を贈られた。40年間、日本のオーケストラはN響しか振らなかったというから、サヴァリッシュが如何にN響を愛していたかが窺える。
交響詩「死と変容」は、「ドン・ファン」「マクベス」に続き、R.シュトラウスが作曲した3作目の交響詩。1888年に作曲を開始し翌年に完成した。R.シュトラウスは、生来病身であり、たびたび死の危機に直面したことがあったという。そんなR.シュトラウスは、若い時から死が脳裏から離れず、その自分自身の体験を基に作曲したのが交響詩「死と変容」であると言われている。曲は、死を連想させる動機、病人の心理の動機、死との闘争の動機、少年時代の回想の動機、そして最後には、死との闘争の結果としての変容(浄化)の動機に辿り付き、曲が閉じられる。全体として暗い内容の曲ではあるが、自分自身の体験に基づいて作曲されたものだけに、内容の充実した曲に仕上がっていると同時に、25歳という若さの時の作品らしく、信念のようなエネルギーが内部に潜んでいるようにも感じられる。サヴァリッシュの指揮は、そんな作品を、一つ一つの出来事を確かめるように丁寧に、しかも奥深く演奏していく。単に暗い曲という印象よりも、変容(浄化)に向かって行くR.シュトラウスの心情が滲み出すようにタクトを振る。音楽的に見て、何とも見事な交響詩「死と変容」に仕上がっており、聴き終わった後の印象は、暗いというより、何か爽やかさが残るのは、サヴァリッシュの棒さばきによるものだろう。
ブラームスの交響曲第1番は、1855年(22歳)の時に、2台のピアノ用の曲として書き始め、1876年(43歳)に交響曲第1番として完成させた。つまり、作曲を開始してから20年以上経って完成させたという、如何にも慎重派のブラームスらしい曲である。ここでのサヴァリッシュの棒さばきは、いたずらに曲を巨大化させることなく、一音一音、ブラームスが熟考したであろう跡を辿るように演奏していく。この交響曲をこんなにも内省的に、しかも音楽的な構成美で演奏した例を、私はこれまで聴いたことがない。サヴァリッシュの持つ信念が、そのままN響に乗り移ったかのような演奏内容である。多分、サヴァリッシュは安易にエキサイトすることによって、曲が本来持つ構成力や響きの美しさが損なわれるのを極力避けたかったのではなかろうか。この真摯に曲に立ち向かうサヴァリッシュの指揮を聴くと、世の中には余りにも曲を弄んで、作曲者の意図とは遠く懸け離れた演奏が蔓延していることが脳裏に浮かぶ。その意味からこの演奏は、サヴァリッシュの音楽に対する姿勢が存分に込められた演奏であることを、肌で感じることが出来るのだ。(蔵 志津久)