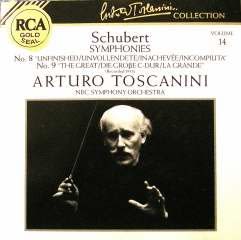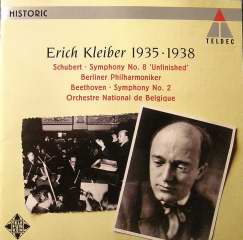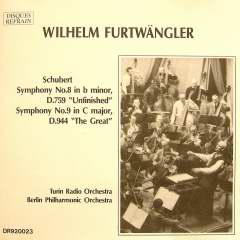シューベルト:交響曲第8番「未完成」
ワーグナー:舞台神聖祭典劇:「パルジファル」から「前奏曲と聖金曜日の音楽」
指揮:朝比奈 隆
管弦楽:東京都交響楽団
CD:フォンテック FOCD 9396
NHK交響楽団の桂冠指揮者であったサバリッシュが、テレビのインタビューに答え次のように語っていたこと思い出す。「指揮者というのは不思議な職業だ。お客さんにお尻を向けて仕事をする」と。まあ、これは外面的なことだが、内面の問題としてサバリッシュは、「楽団員がその指揮者を信じ、その指揮者の音楽的信念や素養を深く理解することによってはじめて良い演奏が生まれる」と語っていた。如何にもサバリッシュらしい言葉だと思った。普通に演奏しようとするなら、誰が指揮をしようがあまり問題にならないであろう。現に、オルフェウス室内管弦楽団のように、指揮者を置かないで長年にわたって演奏活動を展開して、高い評価を得ているアンサンブルすら存在する。下手な指揮者なら、居ない方がいいという極論さえ出てきそうだ。ウィーン・フィルなどになると、「我々の演奏の邪魔をしないのがいい指揮者だ」と言い放つ楽団員もいるそうだ。ここまで極端になると問題だが、我々リスナーにとっては、指揮者が、どのようにその曲を感じ取り、それをどう楽団員に伝え、それを楽団員がどう表現するか、そして、それらをリスナーが明確に聴き分けることができるのかが、大きな問題になるのである。つまり、指揮者の中に内在する音楽的見識が高ければ高いほど優れた指揮者なのである。朝比奈 隆(1908年―2001年)は、そんなリスナーの願いを、ものの見事にかなえてくれる偉大なる指揮者であった。
このCDは、シューベルトとワーグナーの曲を、東京交響楽団を朝比奈 隆が指揮したライブ録音盤である。シューベルトの交響曲第8番「未完成」が1955年1月25日の東京芸術劇場、ワーグナーの舞台神聖祭典劇:パルジファルから「前奏曲と聖金曜日の音楽」が1933年9月10日の東京文化会館での演奏である。最初のシューベルトの交響曲第8番「未完成」で、朝比奈 隆は、ゆっくりとしかも静かにメロディーを奏で、滋味あふれる気分が満ち溢れた演奏に終始する。「未完成交響曲」のような超有名な曲ともなると、もうどのように指揮しようが、リスナーはそう簡単には反応しなくなるものである。しかし、唯一の例外とも言えるのが、この日の朝比奈 隆指揮東京交響楽団の演奏なのである。単にロマンの香り高い演奏とか、優美な演奏とかでは到底表現しきれない、心の底から湧きあがる、シューベルトがこの曲へ込めた音楽への共感に溢れた演奏なのである。朝比奈 隆が「未完成」から受けた感動そのものを、東京交響楽団の楽団員一人一人が理解し演奏していることが手に取るように分かる。そして、それを聴くその日の聴衆の深い共感までもが、その音楽空間を通して伝わってくるようだ。「未完成交響曲」が、これほどまで現代人の我々の心を揺さぶる曲であったことを、私はこの演奏を聴いて初めて知った。決して小手先でで指揮をするのではなく、これはもう、朝比奈 隆が全身全霊で指揮をした「未完成交響曲」の記念碑的なライブ録音といっていいだろう。この朝比奈 隆の「未完成交響曲」を聴きながら、私は自然とワルターの指揮ぶりを思い出していた。
このCDの2曲目は、ワーグナーの舞台神聖祭典劇:パルジファルから「前奏曲と聖金曜日の音楽」である。ワグナーの曲は、我々日本人が聴く場合は、それなりの事前知識を持ってからの方が理解しやすい。ヨーロッパの人々にとっては半ば常識的な事柄でも、我々にとっては、理解しづらいことも少なくない。ワーグナーの音楽の根底にあるのは、要するに“ギリシャ悲劇”なのである。ワーグナーは、民族的アイデンティティを訴求するうちにギリシャ悲劇に辿りつく。このことが最初のうちは、哲学者のニーチェなどとも交流を深めることになり、それらを題材にワーグナーは歌劇の作曲に没頭する。そして、独自の音楽的な理想を実現するため、自らバイロイト音楽劇場をつくり上げ、楽劇という新しいジャンルを切り開く。音楽的には無調形式の創始者とも言われるなど、革新的な作曲者でもあった。しかし、ナチスが国威発揚のためワーグナーを利用したことによって、現在に至るまで偏見で見られることもしばしばある。舞台神聖祭典劇:パルジファルはそんなワーグナーが最後に行き着いた宗教的な曲である。話は中世スペインのモンサルヴァトール城を舞台に、傷つけられた城主のアンフォルタスを救うため、選ばれたパルジファルが、奪われた槍を奪い返す物語。前奏曲は、第1幕前奏曲のことで、「聖餐の動機」「聖杯の動機」「信仰の動機」など劇中の曲が現れてくる。聖金曜日の音楽は、この劇の第3幕で現れる曲。いずれも、神秘的で宗教的な曲であり、ヨーロッパ人の心の故郷のような雰囲気を醸し出す音楽である。そのため、朝比奈 隆指揮東京都交響楽団が、これらをどう演奏するのか、聴く前はちょっと怖いような面もなくはなかった。しかし、一旦曲が流れ始めると、深いヨーロッパの森を彷徨い、宗教的な雰囲気に包まれたかのようなワーグナー独特の分厚い音が流れ始めるではないか。いい意味で「これはヨーロッパの指揮者とオーケストラ演奏ではないのか」と思ったほどだ。東京都交響楽団がつくり出す響きの何と重厚なことか。これは朝比奈 隆が、このオーケストラの持つ潜在能力を存分に発揮させたことのほかあるまい。朝比奈 隆には、ワーグナー:楽劇「ニーベルンゲンの指輪」(日本フィル定期演奏会)のライブ録音盤があるが、今回の東京都交響楽団との演奏も、世界的レベルから見てもかなりの高さに達した演奏と断言できる。
朝比奈 隆は、大阪フィルハーモニー交響楽団(大阪フィル)の音楽総監督を長年にわたり務めたが、生まれは東京。1928年京都帝国大学法学部に入学。同大学の交響楽団に参加し、ヴィオラとヴァイオリンを担当すると同時に、指揮をメッテルに師事した。一旦就職した後、再び京都帝国大学文学部哲学科に入学し、1937年に卒業。1940年新交響楽団を指揮してプロデビューを果たす。1942年大阪放送管弦楽団の首席指揮者に就任。1943年中国大陸に渡り、上海交響楽団などを指揮。1946年中国から引き揚げる。1947年関西交響楽団(大阪フィルの母体)を結成。1950年代からはベルリン・フィルなどヨーロッパの主要なオーケストラにも招かれるようになる。1960年に関西交響楽団を大阪フィルハーモニー交響楽団に改称し、以後朝比奈 隆は、同楽団の指揮者を54年間にわたり務めることになる。1975年には大阪フィルを率いてヨーロッパ演奏旅行を行い絶賛を博す。1996年、シカゴ交響楽団を指揮し北米デビューを果たす。2001年の名古屋公演後、体の不調を訴えて入院し、同年12月29日に死去した。享年93歳。主な受賞歴は、文化功労者、文化勲章(没後従三位)、日本芸術院賞、ドイツ連邦共和国功勲章大功労十字賞、オーストリア連邦共和国一等十字勲章など。主な録音は、ベートーヴェン:交響曲全集を世界最多の7回、ブルックナー:交響曲全集を3回、ブラームス交響曲全集を3回、1984年~1987年の新日本フィルの定期演奏会におけるワーグナー:楽劇「ニーベルンゲンの指輪」など。日本指揮者協会会長、オペラ団体協議会会長、大阪音楽大学教授などを歴任した。(蔵 志津久)