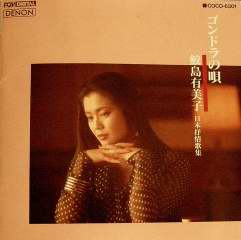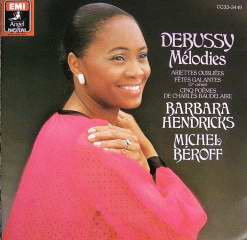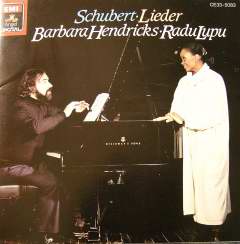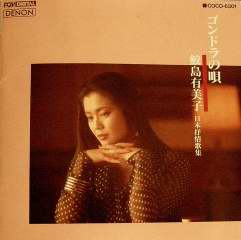
~ゴンドラの唄 鮫島有美子 日本叙情歌集~
あざみの歌 作詞:横井 弘/作曲:八洲秀章
さすらひの唄 作詞:北原白秋/作曲:中山晋平
すみれの花咲く頃 作詞:白井鐡造/作曲:デーレ
待ちましょう 作詞:矢野 亮/作曲:渡久地政信
琵琶湖周航の歌 作詞:小口太郎/作曲:吉田千秋
鎌倉 作詞:芳賀矢一/作曲:不詳
カチューシャの唄 作詞:島村抱月、相馬御風/作曲:中山晋平
ゴンドラの唄 作詞:吉井 勇/作曲:中山晋平
七里ヶ浜の哀歌(真白き富士の根) 作詞:三角/作曲:ガードン
もずが枯木で 作詞:サトウ ハチロー/作曲: 徳富 繁
春の唄 作詞:喜志邦三/作曲:内田元
山小舎の灯 作詞:米山正夫/作曲: 米山正夫
上海帰りのリル 作詞:東條寿三郎/作曲:渡久地政信
君の名は 作詞:菊田一夫/作曲:古関裕而
惜別の唄 作詞:島崎藤村/作曲:藤江英輔
銀座カンカン娘 作詞:佐伯孝夫/作曲:服部良一
リンゴの歌 作詞:サトウ ハチロー/作曲: 万城目 正
ソプラノ:鮫島有美子
編曲・指揮・ピアノ:青島広志
副指揮:富沢裕
ヴァイオリン:桑野 聖
ハープ:篠崎史子
ピアノ:佐藤允彦 他
私は「日本の歌」というジャンルがあると確信している。しかし、それでは「日本の歌」の定義を言ってみろ、と言われると一瞬「うーん」と唸ってしまう。日本の歌曲とは違うことは、割とはっきりとしている。つまり、日本の歌曲といわれる曲はというと、難しい音楽理論に基づいて、格調高く歌うものであり、芸術作品と言われているものを指すからである。やはり「日本の歌」とは違う。童謡や小学唱歌とも違う。もう少し大人の味わいも含んでなくてはならないからだ。それでは、流行歌や歌謡曲とは違うのか。流行歌や歌謡曲にはかなり近いと思うが、もう少し重さというか、歴史の流れに飲み込まれずに生き残る信念みたいものがほしいのだ。然らば演歌とはどうか。演歌になると情念みたいな主観的感覚が強すぎて、もう少し客観性がなくてはならない。ポピュラーソングとの違いを訊かれるとやはり、日本人固有の精神の濃密さがほしい、ということになろう。そんなわけで、「日本の歌」というジャンルがあることは確信しても、定義することは意外に容易ではない。そんな日本の歌を“叙情歌・愛唱歌”というジャンルで歌い続けているソプラノの鮫島有美子が、1989年(平成元年)11月19―20日に日本コロムビア第1スタジオで録音した1枚が今回のCDである(この年に生まれた人はもう22歳になっているのですね・・・)。
このCDのライナーノートに「主な出来事」という簡単な年表が載っているので、ちょっと見てみることにしよう。大正3年(1914年)から始まり、昭和29年(1954年)で終わっている。これらは若い人から見れば歴史上の事件の単なる羅列であっても、私たちの年代にとっては、後半はリアルな事件の思い出だ。今でこそ日本人がノーベル賞を受賞することは珍しくなくなったが、昭和24年(1949年)に湯川秀樹博士がノーベル物理学賞を日本人で初めて受賞したことは、敗戦で打ちひしがれた当時の日本人に自信を取り戻させたことを改めて思い出させる。昭和25年(1950年)には朝鮮戦争が勃発している。現在の北朝鮮問題は、正にこのとき始まったのだ。そして、現在、福島第一原発で放射線漏れの問題が日本を揺るがしているが、昭和29年(1954年)には、第五福竜丸の水爆実験での被爆という大問題が発生し、日本中を震撼させたことを思い出す。このライナーノートには演出家の久世光彦(1935年―2006年)が次のようなことを書いているのが目にとまったので、そのほんの一部を紹介しよう。「(日本は)新しいものへの興味ばかりで、古いものへ愛情も矜持ももたないのである。だから鮫島有美子の『ゴンドラの唄』を聴いて嬉しくなってしまった。この中には“日本の心”が暖かく流れている。“日本の風景”が煙るように浮かんでいる」。
ソプラノの鮫島有美子は、東京芸術大学音楽学部、同大学院へと進み、二期会研究生となる。1975年に二期会の歌劇「オテロ」に出演、デスデモーナ役に抜擢され、オペラ歌手としての第一歩を踏み出す。そして、1976年、ドイツ政府奨学生として、ベルリン音楽大学に留学する。1979年にベルリン音楽大学を卒業し、ヨーロッパ各国の音楽祭やリサイタル、ラジオ出演などの活動を行った。そして、旧西独のウルムの歌劇場専属歌手となり、1986年までさまざまなオペラの大役をこなしたのである。さらにその後、ヨーロッパと日本の間を駆け巡っての活躍は、各方面から絶賛を受けている。こんなクラシック音楽のいわば本流を歩む鮫島有美子が、日本の歌でのCDデビュー25周年を迎えたといのだから、日本の歌へのこだわりはかなり固いのであろう。西洋音楽のことを極めれば極めるほど、逆に自分のルーツである日本の音楽のことも極めたい、そんな欲求があったからこそ、鮫島有美子は片手間でなく、長きにわたり日本の歌を歌い続けてきたのではなかろうか。
このCDでは全部で17曲の日本の歌が収録されている。すべて鮫島有美子の完璧な歌唱力で曲の真髄を堪能できる。本格的クラシック音楽のソプラノ歌手が全精力を傾けて、日本の歌を歌っていることに大きな感動を受けるのだ。作詞、作曲、歌唱すべて甲乙つけがたい内容となっているが、ここでは、その中から幾つかを紹介してみよう。「待ちましょう」(一口に流行歌といえぬような格調高い仕上がりになり、切々とした哀愁と相俟って根強いファンも多かった)、「琵琶湖周航の歌」(昭和34年、歌声喫茶ではやり出し、いちはやくボニージャックスがとりあげてレコード化し一般に知られるきっかけをつくった)、「ゴンドラの唱」(昭和27年の年度最優秀に選ばれた黒沢昭演出・監督の東宝映画「生きる」のテーマ音楽に、この曲が使われて再び注目された)、「上海帰りのリル」(作曲の渡久地政信がこの曲を作った昭和26年頃は、赤貧いもを洗うがごとき生活だった。夜更けに作曲していると、すきま風がビューと音をたて、“とうちゃん寒いよ”と毛布を被って寝ていた娘がすり寄ってきた。そのとき、「ファ・ミ・ミ」と歌いあげる「リール、リール」のメロディが浮かんだ)、「銀座カンカン娘」(山本嘉次郎原作、灰田勝彦、高峰秀子、笠置シズ子主演の昭和24年8月封切りの新東宝映画『銀座カンカン娘』の主題歌でブギウギのリズムを使った服部良一の曲の一つ。当時、“一体、カンカン娘とは何ぞや”という議論がなされたが、誰に聞いても“知りません”という返事しかなかったという、おおらかな時代に生まれた、今聴いても名曲だと感じられる曲)。(蔵 志津久)