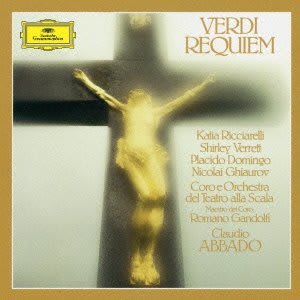シューベルト:ミサ曲第6番変ホ長調 D950
第1曲 キリエ
第2曲 グロリア 「天のいと高きところには神に栄光」
「神なる主、神の小羊」
「主のみ聖なり」
第3曲 クレド 「われは信ず、唯一の神」
「聖霊によりて」
「聖書にありしごとく」
第4曲 サンクトゥス 「聖なるかな」
「いと高きところの [神に] ホザンナ」
第5曲 ベネディクトゥス 「ほむべきかな」
「いと高きところの [神に] ホザンナ」
第6曲 アニュス・デイ 「神の小羊」
「われらに平安を与えたまえ」
指揮:カルロ・マリア・ジュリーニ
管弦楽:バイエルン放送交響楽団
ソプラノ:ルート・ツィーザク
アルト:ヤルト・ヴァン・ネス
テノール:ヘルベルト・リッペルト
テノールウォルフガング・ビュンテン
バリトン:アンドレアス・シュミット
合唱指揮:ミヒャエル・グレーザー
合唱:バイエルン放送合唱団
CD:ソニーミュージックジャパン SICC 270
シューベルトは、生涯に600曲を超す歌曲(リート)を作曲し“歌曲王”として名高い。そのほか交響曲、管弦楽曲、室内楽曲、ピアノソナタなど多くの名曲を残しており、現在でもそれらの作品は多くの人々から愛し続けられている。一方、歌劇や宗教音楽でも多くの作品を遺したのも関わらず、現在ではこれらの作品が演奏会で演奏されることは滅多にない。例えば、歌劇・劇音楽では「ヴィラ・ベッラのクラウディーネ」(ゲーテ、1815年)、「魔法の竪琴」(ホフマン、1820年)、「アルフォンゾとエストレルラ」(ショーバー、1822年)など、未完成の曲も含めれば20曲以上の作品を書き上げている。しかし、現在それらの作品が上演されることはほとんどない。
シューベルトは、生涯で45曲にも上る宗教音楽を遺している。それらは、ミサ曲が6曲、ドイツ語ミサ曲が1曲、ドイツ語ミサ曲が1曲、オラトリオが1曲、宗教合唱曲が28曲、宗教的独唱・重唱曲が6曲、宗教的カノンが2曲などである。これらの宗教音楽の中で、生前取り上げられることの多かったのが女声四重奏曲「詩篇23番D706」であるが、教会での演奏ではなく一般の演奏会で演奏されたということから、シューベルトの宗教音楽の当時の評価が窺えて興味深い。シューベルトは、宮廷礼拝堂の聖歌隊員から音楽の道に入ったわけであるので、もともと、宗教音楽に対しては関心が高かった。そのことは最初期の1812年から最晩年の1828年に至るまで宗教音楽を書き続けたことでも分かる。
ミサ曲第6番は、シューベルトの死の年、すなわち1828年6月に作曲に着手され、その年の夏に完成された最後のミサ曲であり、シューベルトの全作品の中でもとりわけ傑作の誉れ高い曲でもあり、充実した作品である。シューベルト特有の美しい旋律に覆われたミサ曲であり、保守的な内容ながら感情表現に豊かさが溢れている。初演は、シューベルトの死の翌年の1829年10月にアルザーグルトンの三位一体教会において行われた。編成は、声楽がソプラノ、アルト、テノール2、バス(またはバリトン)の独唱に、混成4部の合唱、器楽は、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット各2、トロンボーン3、ティンパニ、それに弦楽5部からなっている。
このCDでの指揮は、イタリア出身のカルロ・マリア・ジュリーニ(1914年―2005年)。サンタ・チェチーリア国立アカデミアに学び、最初はヴィオラ奏者であった。ローマRAI交響楽団首席指揮者、ミラノRAI交響楽団首席指揮者、ミラノ・スカラ座音楽監督、ウィーン交響楽団の首席指揮者、ロサンジェルス・フィルハーモニック音楽監督などを歴任。以後、フリーの指揮者としてウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウなどヨーロッパの名門オーケストラを客演する。ここでのジュリーニ指揮バイエルン放送交響楽団の演奏は、この曲の持つ荘厳さが自然の形で表現され、聴いていて深く感動させられる。そこには、祈りの姿しか見えてこない。世界で戦火が絶えない今こそ、この演奏の持つ不滅の意義がある。(蔵 志津久)