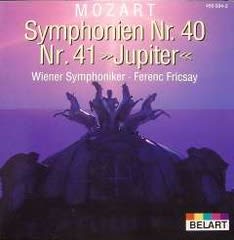オペラ「偽の女庭師」序曲 K.196
セレナード第6番 ニ長調「セレナータ・ノットゥルナ」K.239
豊嶋泰嗣(第一ヴァイオリン)
戸松智美(第二ヴァイオリン)
白尾偕子(ヴィオラ)
牧田 斉(コントラバス)
指揮:山田一雄
管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団
録音:1990年8月30日~31日、洗足学園前田ホール
CD:fontec TWFS90001(企画・販売元:タワーレコード)
このCDは、”ヤマカズ”の愛称で親しまれた伝説的指揮者の山田一雄(1912年―1991年)が、ちょうど亡くなる1年前に、それまで主にライヴ録音を中心に行ってきた氏が、モーツァルトの作品を敢えてセッション録音(スタジオ録音)で遺した貴重な録音である。最新のDSDリマスタリング技術で蘇り、録音状態が極めて良好であり、ヤマカズさんと新日本フィルの熱演を余すことなく聴くことが出来る。今から30年以上前に、日本の指揮者と日本のオーケストラが、モーツァルトの交響曲を自家薬籠中の物とし、さらに世界的レベルと言っても過言でない程の水準にまで達していたかということを、このCDを聴くことによって我々は知ることになる。
山田一雄は、東京都(東京府)出身。1931年に東京音楽学校(現東京芸術大学)ピアノ科首席卒業ののち研究課程に進む。ヨーゼフ・ローゼンストック(1895年―1985年)のもとで研鑽を積んだ後、1941年新交響楽団(略称:新響=現NHK交響楽団)の補助指揮者に就任。この新響が日本交響楽団(略称:日響)に改組後、ローゼンストックを支える立場の専任指揮者となる。翌1945年には満州国に渡り、新京やハルビンのオーケストラを指揮した。日本に引き揚げ後は、以前と同様に日響の指揮台に立ち、1949年にはマーラーの交響曲第8番「千人の交響曲」を日本初演するなどの活動を続けた。1956年ニッポン放送の「フジセイテツコンサート」用オーケストラであるNFC交響楽団を組織した。1960年から東京交響楽団、1966年から日本合唱協会、1968年から群馬交響楽団、次いで1972年から京都市交響楽団の各音楽監督等を務め、1981年には新星日本交響楽団(2001年に東京フィルハーモニー交響楽団と合併)の名誉指揮者となるなど、多くのオーケストラとの共演を重ねた。1991年7月に神奈川フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任したが、わずか1ヵ月後の8月13日に急逝した。1976年「紫綬褒章」、1979年第29回「芸術選奨」文部大臣賞、1982年「芸術祭大賞」、1983年「有馬賞」、1984年「勲四等旭日小綬章」、1985年度第42回「日本芸術院賞」などを受賞(章)。
新日本フィルハーモニー交響楽団は、日本フィルハーモニー交響楽団出身の楽員と小澤征爾や山本直純らが中心となり、新たに自主運営のオーケストラを1972年に設立したのが始まり。そして1997年には、東京都墨田区とフランチャイズ契約を結び、墨田区に完成したすみだトリフォニーホールを本拠地とした。これは、日常の練習と公演を行うという日本初の本格的フランチャイズ制の導入であり、これが現在に至るまで継承されている。現在は、音楽監督が上岡敏之、そして新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ音楽監督・Composer in Residence and Music Partnerが久石譲、さらに桂冠名誉コンサートマスターが豊嶋泰嗣という体制で臨んでおり、活発な演奏活動を展開している。この中の「新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ」とは、2004年夏、作曲家・久石譲を音楽監督に迎え、新たに立ち上げたプロジェクト。「世界中に素晴らしい曲がたくさんある。ジャンルにとらわれず魅力ある作品を多くの人々に聴いてもらおう」という願いが、このオーケストラの活動におけるテーマとして掲げられている。
モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」は、モーツァルトが作曲した最後の交響曲で、ローマ神話の最高神ユーピテルにちなんで「ジュピターの愛称を持つが、同交響曲のスケールの大きさ、輝かしく荘厳な曲想から付けられた通称であり、特に標題的な意味合いはない。完成は、1788年8月で、同年に作曲された第39番、第40番とともにモーツァルトの”3大交響曲”と呼ばれている。第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ、第2楽章 アンダンテ・カンタービレ、第3楽章 メヌエット:アレグレット、第4楽章 モルト・アレグロの4つの楽章からなる。この曲での山田一雄指揮新日本フィルの演奏は、正に乾坤一擲、スタジオ録音でありながら、ライヴ録音のような緊張感が全体に漲り、悠揚迫らざる堂々とした演奏を繰り広げる。第二次世界大戦後、日本のクラシック音楽界は欧米に追い付くことを目指し、日夜活動を展開してきたのであるが、この録音を聴く限り、さらに世界へと通じる高みへと向かいつつあることが聴きとれる。ここでの山田一雄の指揮は、明快極まりないもであり、一点の曖昧さもなく自信に満ちている。それに応えるように、新日本フィルの演奏も地に足が付き、音質も分厚く、力強いものに仕上がった。テンポも中庸を心得て安心して聴き通すことができ、申し分ない。日本人によるモーツァルトの交響曲の演奏としては、過去にこれほどまでの高みに達した演奏は、皆無と言ってよく、今後も果たしてこれを超えるものが現れるか、疑問にさえ思うほどの完成度の高い見事な出来栄えだ。
モーツァルト:オペラ「偽の女庭師」は、モーツァルトが19歳のときに書いた、3幕もののオペラ・ブッファ。バイエルン選帝侯マクシミリアン3世から作曲を依頼され1774年に完成した。初演は、翌1775年にミュンヘンのザルヴァートル劇場 で行われた。イタリア、ナポリの東南100キロほどの都市、南イタリアのラゴネグロがこのオペラの舞台で、この地の名家ドン・アルキーゼ家に女庭師として雇われてきたヴィオランテ姫が恋愛騒動に巻き込まれるというのがそのストーリー。この曲での山田一雄指揮新日本フィルの演奏は、基本的には交響曲第41番「ジュピター」と同じことが言えるが、オペラの序曲として、これから始まる劇の進行をワクワクして聴いている聴衆に向けて、語りかけるような演奏に徹したところが聴きどころ。
モーツァルト:セレナード第6番 「セレナータ・ノットゥルナ」は、1776年にザルツブルクで書かれた、管楽器を省いた小規模な編成で構成される作品。作曲された1776年は、”セレナード音楽の年”と称される程、数多くのセレナーデ(第7番や第8番など)やディヴェルティメント(第9番から第13番)などが作曲された。これは、当時のモーツァルトがザルツブルクの宮廷のお抱えの音楽家で、主に娯楽的・社交的な音楽作品を作曲したため。ここでの山田一雄指揮新日本フィルの演奏は、肩の力を抜き、リラックスした雰囲気を醸し出す。独奏者とオーケストラの掛け合いも楽し気に行われるが、そこには一本の線がピンと張られ、適度な緊張感も醸し出される心地よい見事な演奏ぶり。(蔵 志津久)