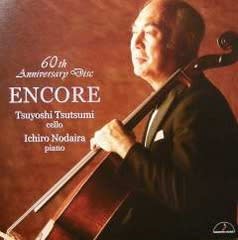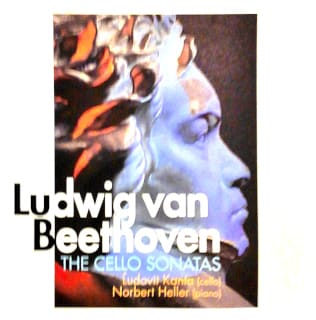
ベートーヴェン:チェロソナタ全集(第1番~第5番)
チェロ:ルドヴィート・カンタ
ピアノ:ノルベルト・ヘラー
CD:PANCE MUSIC PANU-7004~5 【TOWER RECORDSオンラインショップサイトから購入可】
ベートーヴェンのチェロソナタは5曲あるが、初期の作品が第1番と第2番、中期の作品が3番、そして後期の作品が第4番と第5番と、ちょうどベートーヴェンの生涯にわたって書かれている。この中では、第3番が一番人気となっているが、バッハの6曲の無伴奏チェロソナタと並び、5曲ともチェロソナタ史上不滅の光を放っている作品であることは間違いない。ハイドンは、それまでの弦楽四重奏曲を根底から改革し、新しい弦楽四重奏曲を生み出したが、同じように、ベートーヴェンはチェロソナタというジャンルを新たに確立し、以後、多くの作曲家がチェロソナタの傑作を世に送り出している。ベートヴェンがチェロに興味を持ったのは、ベートーヴェンがボンの選帝侯の宮廷楽団でヴィオラを弾いていた頃、チェロ奏者のロンベルクであったという。ロンベルクは、チェロのドイツ流派の創始者ともいわれ、ヴァイオリンの奏法をチェロに取り入れることに成功したチェロ奏者であった。ベートヴェンはこのロンベルクの表現力豊かな音色に魅入られて、チェロソナタを書く動機を与えられたようである。ベートーヴェンの5曲のチェロソナタは、チェロとピアノがあたかも対話するかのように書かれており、その深い内容が今でも聴く者に感銘与え続けているのだ。
このCDでチェロを演奏しているルドヴィート・カンタ(1958年生まれ)は、スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァの出身。ブラティスラヴァ音楽院、プラハ音楽アカデミーで学ぶ。プラハ音楽アカデミー在学中にスロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団の第1ソロ・チェリスト・コンサートマスターに就任。「ハラデッツ=オパヴァ・ベートーヴェンコンクール」で優勝。「プラハの春国際音楽コンクール」で銀賞と同時にチェコ・スロヴァキア文化庁特別賞を受賞。その他、チャイコフスキーコンクールなど数々のコンクールで上位入賞を果たしている。2003年、2005年の「スロヴァキア・フィル日本ツアー公演」ではドヴォルザークのチェロ協奏曲を共演し絶賛される。日本音楽コンクールの審査員を務めるなど、日本との係わりは深く、1995年より8年間、愛知県立芸術大学にて教鞭をとるなど、後進の指導にも取り組んでいる。1990年より、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の首席チェロ奏者を務めていたが、2018年3月に定年退団し、現在は名誉楽団員。
ピアノのノルベルト・ヘラーは、チェコ出身。オストラヴァ音楽院、プラハ音楽アカデミーで学ぶ。「国際ベートーヴェンコンクール」第1位、「モラヴィチ・ピアノコンクール」で第1位を受賞他、受賞歴多数。1993年から96年までチェコ・トリオのメンバーとしても活躍。古典から、現代曲まで幅広いレパートリーを持ち、テレビやラジオへの出演も多い。CD録音は多数あり、ソロではシューベルト、ベートーヴェン、ムソルグスキーが、チェコ・トリオのメンバーとしてはショスタコーヴィチ、スメタナ、シューベルトなどいずれも優れた演奏を聴かせる。中でも、1807年製のコンラート・グラフのハンマー・クラヴィアによるシューベルト全曲は、チェコ財団の「ベスト・レコーディング・オブ・ザ・イヤー賞」を受賞、2001年には、チェコ人として初めてのレコーディングである、モーツァルトの全ソナタ集を完成し、「ヨーロッパ・グスタフ・マーラー賞」を受賞した。2008年よりプラハ国際音楽院で教鞭をとる他、ヤング・プラハ国際音楽祭の審査員も務めている。
このCDでのルドヴィート・カンタは、実に深々としたチェロ演奏を聴かせる。その伸びやかなチェロの音色は、全てが自然の流れに中に息づいている。少しも作為的なものを感じることはない。一方、ノルベルト・ヘラーのピアノ演奏は、光り輝く星のようでもあり、音色がきらきらと宙に舞うごとくである。5曲のベートーヴェンのチェロソナタは、いずれもチェロとピアノが対話するように進行する。決して、独奏がチェロ、伴奏がピアノという分担ではない。その意味でカンタとヘラーは、チェロとピアノとが対話するかのように演奏しており、ベートーヴェンの意図を十分に引き出した演奏内容となっている。第1番においては、ベートーヴェンの青春の息吹を思う存分発散させる演奏内容が一際光る。第2番は、第1番の延長線上にある曲だが、より深みを増す内容となっており、二人の演奏内容もそれに合わせるかのように彫の深い表現が印象的。第3番は、ベートーヴェンのチェロソナタの中で一番の人気曲。二人の演奏は、構成力を十分に感じさせるが、決して力任せに弾き切るのではなく、精神性に力点を置いたような、しみじみとした演奏に仕上がっている。第4番は、ベートーヴェンの後期の作品であり、二人の演奏も、より一層深く、思索的な雰囲気を漂わせたものにまとめられている。最後の第5番は、第3番に次いで演奏される機会が多い作品。二人の演奏は、実に力強いもので、鋼鉄を思わせるような表現力が顔を覗かせる一方、ベートーヴェンの後期の室内楽作品らしく、透明感も合わせ持った演奏内容が誠に素晴らしい。このルドヴィート・カンタのチェロ、ノルベルト・ヘラーのピアノによるベートーヴェン:チェロソナタ全集は、“名盤”として後世に遺されて然るべき録音であることを特に強調したい。録音も秀逸。(蔵 志津久)