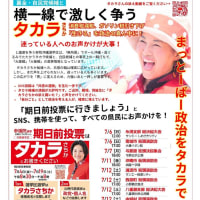5月17日(水)、参議院議員会館で辺野古の本体工事着工に抗議する院内集会と防衛省交渉が行われた。
院内集会では最初に私が、最近の工事の状況とその問題点を説明。最近までカヌー隊で頑張ったくれていたNさんが現場の状況を報告してくれた。集会には、糸数慶子参議院議員、玉城デニー衆議院議員、伊波洋一参議院議員、福島みずほ参議院議員らも来られ、激励の挨拶をされた。
防衛省の担当者らに対する交渉では、多くの問題点が明らかになった。ただ、今日(18日)は名護市で講演があり、テープおこしの時間がない。明日以降、詳しく報告したい。
とりあえず、当日の質問事項と写真だけを掲載する。



 Tさん撮影
Tさん撮影
**************
<防衛省への質問事項> 2017.5.14
1.K9護岸の着工について
沖縄防衛局は4月25日午前、キャンプ・シュワブの大浦湾に面したクバマ(小浜)で「起工式」を行い、その後、波打ち際に石材の入った袋材を5個置いた。そして、報道各社に「護岸工事に着手」という連絡を入れた。
この作業について、稲田防衛大臣、菅官房長官は当日の記者会見で、「埋立て本体の工事開始」と誇らしげに説明した。
その後4月末から防衛局は、クバマのK9護岸取付部の海岸に、石材の入った袋材を積上げ始めた。そして5月8日からは、海に石材を投下し始めた。いよいよK9護岸の基礎工の工事が始まったものと思われる。
この問題について以下のとおり質問する。
1-1.4月25日以降に投下した石材の入った袋材は、K9護岸の基礎部分ではなく、K9護岸を施工するための進入道路(取付道路)の基礎か?
5月8日以降投下している袋材に入れていない石材は、K9護岸の基礎工としての捨石か?
1-2. K9護岸の基礎工は全て陸域部からクローラクレーンを用いた巻き出し方式により施工するとされているが、K9-3護岸やK9-4護岸などの水深が深くなった箇所では、基礎工の石材を海上運搬して投入する予定はないか?
1-3.5月8日以降に始まった石材の投下では、粉塵が巻き上がり、海面も白く濁っている。(たとえば、「投下の際には粉塵が舞い上がった」「海水が白く濁る工事現場」(2017.5.9 琉球新報)、「石材を移動するたびに粉塵が巻き上がり」(2017.5.9 沖縄タイムス)、「粉塵を上げながら次々に投下される石材」(2017.5.10 沖縄タイムス)。)
石材の投下に伴い、粉塵が舞い上がり、海面が白く濁っている事実をどう考えるか?
1-4.埋立承認願書では、「海中へ投入する石材は、 採石場において洗浄し、濁りの発生が少なくなるようにして使用する」(6-14-163)とされている。投下に伴い粉塵が舞い上がり、海面が白く濁っている事実は、石材が洗浄されていないことを示していないか?
捨石、砕石等の石材の洗浄は実施しているか? 実施しているのであれば、砕石場から搬出する際の洗浄時間、そのチェック方法等について説明されたい。
1-5. K9護岸の施工にあたっては、海に大量の石材を投入することから、海域の汚濁が危惧される。しかし、汚濁防止膜はK9護岸施工箇所から遠く離れたところにしか設置されていない。K9護岸の施工にともない汚濁が拡散する恐れはないか?
1-6.埋立承認願書の「設計概要説明書」の「工事の施行順序」では、「埋立区域①-1工区については、先ず、杭打船により二重鋼管矢板を打設し、A護岸、中仕切岸壁Bを築造していく」と記載されている(P61)。また、「工程表」でも、K9護岸の着手は、A護岸、中仕切岸壁や工事用仮設道路等の着手後、本体工事開始後3ヶ月目からとされている(P63)。
今回、K9護岸を最初に着手することは、この「工事の施工順序」の変更ではないか?
1-7.また、K9護岸よりも先に施工するとされている、工事用仮設道路、中仕切護岸、海上ヤード、辺野古地先護岸工等は、それぞれ何時から実施予定か明らかにされたい。
1-8. K9護岸の着工については、埋立承認の際の「留意事項1」に基づく沖縄県との実施設計の事前協議が調っていないまま強行されている。工事を中止し、実施設計の事前協議をやり直すべきではないか?
2.キャンプ・シュワブ沿岸部の「進入道路(パネル等敷設)」、「取付道路」工事について
沖縄防衛局は、本年3月末から、キャンプ・シュワブの大浦湾に面したヤニバマからクバマまでの海岸部に石材の入った根固用袋材を置き、その上にパネル(鉄板等)を敷いて工事車両の通行路を造成した(写真④。以下、「進入道路(パネル等敷設)」と称する)。
この工事について次のとおり質問する。
2-1. この「進入道路(パネル等敷設)」は、一昨年秋にもいったん施工されたが途中で中止されたものである。防衛局は本年4月18日、県の照会に対して、今回のものは「一時的なパネル等の敷設」であり、一昨年秋の工事と同一であると回答した。
しかし、現場に設置されているのは「パネル等」だけではない。石材の入った根固用袋材も設置しているのではないか? 根固用袋材の設置数を明らかにされたい。
2-2.防衛局はこの工事について、「『建設機械や資機材運搬車両等の通行』が含まれ得ますが、施行区域内における維持・管理や工事のための各種作業を安全かつ効率的に行うための一時的なパネル等の敷設であり、『新たな道路』を建設するものではありません」と説明している(H28.1.19 防衛局回答)。
防衛局は、4月以降、この「進入道路(パネル等敷設)」を使って、キャリアダンプで石材等の資材を運び込み、K9護岸の基礎工を進めている。この「進入道路(パネル等敷設)」は、K9護岸造成のための資材運搬道路であり、「新たな道路」ではないというのは詭弁そのものである。「新たな道路」そのものではないか?
2-3. K9護岸を施工する「シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事」の「変更施工計画書」には、「敷鉄板設置撤去」として、「根固用袋材(1.6トン)」を147個設置し、さらに225㎡の範囲に鉄板を敷くとされている。
今回の「進入道路(パネル等敷設)」は、この「敷鉄板設置撤去」工事か? その関係を説明されたい。
2-4.また、「シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事」の設計変更図書には、ちょうどこの「進入道路」の位置に「付替道路」(延長:257m)を設置すると記載されている。今回の「進入道路(パネル等敷設)」と、この「付替道路」の関係を説明されたい。
今回の「進入道路(パネル等敷設)」が、この「付替道路」ではないというのなら、今後、「進入道路(パネル等敷設)」とは別に「付替道路」を設置する予定か?
2-5. 「シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事」の「変更施工計画書」には、「取付道路」として、「根固用袋材(1.6トン、146個)、被覆用袋材(耐波型4トン、42個)」を施工するとされている。
その後防衛局は、写真②のように、クバマの海岸部に石材の入った袋材を積上げ始めた。この工事は、上記「シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事」の「取付道路」か? その関係を説明されたい。
2-6.2014年12月5日に承認された設計概要変更申請にある「工事用仮設道路②」は、今回の「進入道路(パネル等敷設)」、また上記の「付替道路」、「取付道路」とどのような関係にあるのか? 今後、計画通りK9護岸の取付部まで「工事用仮設道路②」を造成するのか? この付近の「工事用仮設道路②」の計画に何らかの変更があるのか?
2-7. 「シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事」の「付替道路」は、埋立承認願書の「設計の概要」、同「設計概要説明書」に記載されているか?
また、「進入道路(パネル等敷設)」は、埋立承認願書の「設計の概要」、同「設計概要説明書」に記載されているか?
3.実施設計及び工事中の環境保全策等に係る事前協議について
本件埋立事業の承認書(2017年12月27日)には次のような留意事項が付されている。
1 工事の施工について
工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと。
2 工事中の環境保全対策等について
実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査及び事後調査などについて詳細検討し県と協議を行うこと。
防衛局は、この留意事項に基づき、2015年7月24日にK-1~K-7護岸、K-9護岸、中仕切護岸N-2~N-5についての「実施設計の事前協議書」を沖縄県に提出した。その後、防衛局は、県が、知事の埋立承認の取り消しにより実施設計の事前協議をできない旨の通知したことを理由として、2015年10月28日、実施設計及び環境保全策等に関する協議は終了したとして、「各護岸につき着工する」と一方的に通知してきた。
さらに防衛局は、2017年1月20日にK-8護岸、A護岸、斜路、中仕切護岸N-1、中仕切り岸壁A・Bについての「実施設計の事前協議書」と称する文書を県に提出した。しかし県は、この文書については、後述のように、すでに工事に着手していることを理由に事前協議書とは見なしていない。
この問題について下記のとおり質問する。
3-1.沖縄県は、上記の実施設計・環境保全対策等に関する留意事項に基づき、防衛局に対して、「当該事前協議が調うまでの間は、当該事業に係る工事は実施しないでください」(2016.12.26)、「事前協議が調わないままの工事への着手は、留意事項違反となります。本事前協議が調うまでは、埋立に関する工事を停止してください。貴局が工事を停止した時点で、事前協議として改めて質問等を行います」(2017.2.10)等と指摘してきた。
このような県の再三の指摘にもかかわらず、事前協議が調う前に工事を強行するのは何故か?
3-2.また沖縄県は、「本体部分の環境保全対策等は、本体部分全体としての対策を検討する必要があることから、まず、本体部分の護岸全体の実施設計を行い、その実施設計に基づき、環境保全対策等を工事着手前に検討すること」とも指摘してきた(2016.12.28等)。
このような県の指摘にもかかわらず、護岸全体の実施設計に基づく環境保全対策を講じないのは何故か?
3-3.上記の「留意事項1」は、埋立承認願書の「4 設計の概要」に記載のある工事全てについて事前協議を求めたものである。従って、美謝川の切替えや辺野古地区地先等についても事前協議の対象であることは言うまでもない。そのことを確認できるか?
4.サンゴ類の保全等の環境保全措置について
防衛局が提出した埋立承認願書には、サンゴ類について「事業実施前に、移植・移築等の具体的方策等について、専門家等の指導・助言を得て、可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植・移築して影響の低減を図る」と記載されている(7-10)。
K9護岸の着工等、海域での工事開始にあたってサンゴ類の保全等の環境保全措置がどのように実施されているかについて下記のとおり質問する。
4-1.防衛局は埋立承認願書等で、「サンゴ類の移植・移築は、事業実施前に行う」と説明し てきたが、今回のK9護岸の着工にあたって一帯でのサンゴ類の移植・移築は行ったか?
護岸工事と並行してサンゴ類の移植を実施するというのであれば、護岸工事による汚濁の影響により、事業実勢区域内の移植対象サンゴ類に取り返しのつかない重大な影響が生じることが危惧される。サンゴ類の移植・移築は、あくまでも「事業実施前」に行うべきではないか?
沖縄県も指示しているように、サンゴ類の移植・移築が完了するまでは本体工事に着手することは許されない。
4-2.埋立承認の際の留意事項では、「2 工事中の環境保全対策」として、「実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査---などについて詳細検討し県と協議を行うこと」とされている。サンゴ類の移植・移築について、この留意事項に基づく沖縄県との協議は行っているか?
4-3.今後、サンゴ類の移植・移築については、沖縄県知事から特別採捕許可を得る必要がある。そのための手続を開始しているか? まだであれば、何時、特別採捕許可申請をする予定か?
4-4.防衛局が発注した「シュワブ(H26)サンゴ類移植業務」の当初契約の履行期間は、2015年2月26日から平成2016年3月31日までであった。防衛局は、本体工事実施前にサンゴ類を移植・移築するために、この時期に契約を締結したのではないか?
この「シュワブ(H26)サンゴ類移植業務」の変更契約書、変更特記仕様書を提出されたい。
4-5.防衛局は、「移植・移築対象サンゴ」について、「小型サンゴ類(移植):総被度が5%以上で0.2ha以上の規模を持つ分布域の中にある長径10cm以上のサンゴ類。大型サンゴ類(移築):単独であっても長径が1mを超える群体」と説明している。
これでは、2000㎡以下の規模の分布域における長径1m以下のサンゴ類は移植対象とならず、全て破壊されてしまうことになる。総被度が5%以上で0.2ha以上の規模のサンゴ類のみに限定する理由を説明されたい。
4-6. 沖縄本島で希にしか見られないサンゴ類については、上記の基準にかかわらず、移植・移築対象とするべきではないか?
4-7. K9護岸予定地には、平成20年調査において、被度5~25%のサンゴ類分布域が確認されている(埋立承認願書 6-14-119)。K9護岸予定地には移植・移築対象サンゴ類は存在しないのか? K9護岸予定地のサンゴ類生息状況を説明されたい。
K9護岸予定地でのサンゴ類の生息状況について、写真等の調査資料を提出されたい。
4-8.防衛局は、沖縄県に対して、各種護岸整備に際して移植する予定の大型・小型サンゴ類は73,870群体になると回答した(4月24日)。
これは「各種護岸整備」に際して移植予定のサンゴ類であるが、サンゴ類は、護岸整備箇所だけではなく、護岸から離れた埋立箇所や浚渫・床掘予定箇所にも生息している。これらの箇所のサンゴ類は上記の移植対象予定数に含まれているのか?
4-9.那覇空港第2滑走路埋立事業では、サンゴ類36,960群体の移植・移築に76日間を要しているが、汚濁防止膜の設置以前からサンゴ類の移植を開始した。今回の事業で防衛局は、第4回環境監視等委員会で「移植の作業の期間は9ヶ月程度を予定している」と説明したが、この作業期間に変わりはないか?
5.海底ボーリング調査について
防衛局は、本年2月初旬以降、日本でも最大級と言われる大型調査船「ポセイドンⅠ」(4015トン)を使用し、海底ボーリング調査を再開した。さらに、3基のスパッド台船、2基のクレーン台船(大水深足場)による海底ボーリング調査も同時に実施されている。
辺野古新基地建設事業に関わる海底ボーリング調査は、2014年夏以降、23カ所の調査が終り、昨年3月の和解の時点では最後の1ヶ所が継続中だとされてきた。
ところが防衛局は、本年2月6日の福島瑞穂議員の質問に対して、「24箇所のボーリング調査のうち、---調査を中断していた1箇所については、現在、その実施の適否を含め、検討中です。他方で、護岸工事を安全かつ適切に履行するために必要な施工計画を検討するため、新たに13箇所のボーリング調査を実施する計画です」と回答した。
さらに防衛局は、沖縄県に対して13箇所だけではなく、「今後、調査箇所を更に追加することがあります」と回答した(2017.2.3)。また、本年3月3日、防衛省は我々との話し合いの中で、「今後、さらに調査箇所を追加することもあります」と説明した。ここでも防衛省は、「24箇所は事業本体の設計に必要なデータを得るため。13箇所の調査は護岸工事を安全かつ適切に履行するために必要な施工計画を検討するためのもの」と説明している。
再開された海底ボーリング調査について、下記のとおり質問する。
5-1.新たな13箇所(No20~No32)のボーリング調査は、大型調査船「ポセイドン」で実施されたと思われる。すでに「ポセイドン」は大浦湾を出たが、調査は予定通り13箇所だったのか、調査箇所の追加はあったのか?
また、スパッド台船、クレーン台船(大水深足場)による調査は何時、終了予定か?
従来から防衛局はボーリング調査が終了した箇所についてはその座標値を公開してきた。今回の調査終了地点の座標値を提供されたい。
5-2.昨年3月時点で「調査を中断していた1箇所」(No13)の調査は終了したのか? 終了したのであれば座標値を提供されたい。
5-3.防衛局が発注した「シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事」、「シュワブ(H26)二重締切護岸設工事」、「シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)」には、「確認ボーリング」(スパッド台船、大水深足場)を行うこととされている。
現在、大浦湾で行われている、大型調査船「ポセイドン」、スパッド台船、クレーン台船(大水深足場)によるボーリング調査は、これら各工事の「確認ボーリング」なのか?
5-4.沖縄県は2015年当時から、再三に渡って「ボーリング調査終了後は施行区域に張り巡らせたフロートを撤去すること」と指示してきた。現在行っている調査が「確認ボーリング」であれば、それは埋立本体工事の一部であるから、施工区域に張り巡らせたフロートはただちに撤去するべきではないか?
5-5.防衛局は、13箇所のボーリング調査については、一般競争入札の手続をとらず、「シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)」の追加変更で実施させた。
しかし、防衛局が沖縄県に提出した資料によれば、今回の13箇所の追加調査は、「シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)」の施工箇所(主にC-1護岸)だけではなく、C-3護岸や中仕切り岸壁Aの場所でも行われている。防衛局は本年3月10日、福島議員に対して一般競争入札の手続きをとらなかった理由として、「当該ボーリング調査は、ケーソン新設工事の受注者が護岸工事を安全かつ適切に実施するために必要な施工計画を検討するためのもの」であるからと回答した。
ケーソン新設工事の受注者に工事施工箇所以外のところでも調査を実施させていることからも、このボーリング調査は当該工事の施工計画を検討するためのものでないことは明らかである。この13箇所の調査は、ケーソン新設工事の「確認ボーリング」ではないのではないか?
5-6.防衛局は、「従来の24箇所の調査は、護岸本体の設計に必要なデータを得るためのもの。追加に行う13箇所の調査は護岸工事を安全かつ適切に履行するために必要な施工計画を検討するためのもの」であると説明している。
しかし、護岸本体の設計のための調査がほぼ終了したのであれば、大型ケーソンが設置されるC-1,C-2,C-3護岸、係船機能付護岸、隅角部護岸等の実施設計書の作成は何故、遅れているのか?
これらのケーソン護岸工の海底地盤の地質に何らかの問題点が見つかったため、追加のボーリング調査が必要になったのではないか?
5-7.埋立承認願書の「設計概要説明書」に付けられている地質断面図によると、大型ケーソンが設置される一帯には琉球石灰岩の層が確認されている。琉球石灰岩の地層はN値のバラツキが大きく、また地下水の影響で所々に空洞部が存在する可能性が高いが、ケーソン護岸の基礎地盤として問題はないか?
5-8.今後、C-1,C-2,C-3護岸、係船機能付護岸、隅角部護岸等について、構造変更や基礎杭の追加等、基礎地盤の支持力強化策が必要になることはないか?
5-9.海底ボーリング調査に際しては、一般的には、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可の対象ではないとされているが、それでも沖縄県との事前協議が必要である。今回のボーリング調査再開に際して、岩礁破砕許可の事前協議を行っていない理由は何故か?
6.コンクリートブロックの投下と汚濁防止膜の設置について
防衛省の武田博史報道官は、4月14日の記者会見で、「汚濁防止膜の設置を終え、現在、護岸工事に必要な資機材の準備などを進めている」と述べた(2017.4.15 琉球新報)。
汚濁防止膜の設置、そのためのコンクリートブロック投下について、次のとおり質問する。
6-1.汚濁防止膜設置のためのコンクリートブロックの投下は全て終了したのか?
防衛局は、11.2~13.9トンのコンクリートブロックを合計228個投下するとしていたが、同時に、「アンカーブロックの重量別の寸法及び個数は、今後変更される可能性があります」とも説明していた。コンクリートブロックの最終的な重量別の寸法及び個数を明らかにされたい。
またコンクリートブロックの最終的な設置位置図及びその個々の座標値を提供されたい。
6-2.防衛省は、3月3日の話し合いの後、「コンクリートブロック設置前及び設置後の写真」について、「現在整理中であることから、準備が出来次第、提出します」と回答した。速やかな写真の提供を求める。
6-3.大浦湾には、今回投下された汚濁防止膜のためのコンクリートブロックだけではなく、2015年に工事の施行区域に沿った浮標、ブイ設置のためのコンクリートブロックも投下されている。また、クレーン台船等の係留のためのコンクリートブロックも投下されているものと思われる。
現在までに大浦湾に投下した全てのコンクリートブロックについて、目的、位置図、重量別寸法、個数等を明らかにされたい。
6-4.汚濁防止膜については、海中のカーテン部を含め、全ての設置作業を終了したのか?
浮沈式、自立式汚濁防止膜の最終的な設置位置、設置延長に変更はなかったか? また、海中のカーテン丈長(7m)に変更はなかったか? これらに変更があったのであれば、最終的な設置位置、延長、カーテン丈長を明らかにされたい。
6-5.防衛局が発注した「シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事」、「シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)」の設計図書では、係留シンカーとして37.5トンのコンクリートブロックを合計50個投下するとされている。この計画に変更はないか? すでに投下されているのか?
6-6.汚濁防止膜は、護岸工から遠く離れた場所に設置され、しかも開口部が多い。さらには、大浦湾の水深30mを超える箇所でも海中のカーテン部は7mしかない。
このような汚濁防止膜で汚濁を防ぐことはできない。各工事箇所の周囲を全て囲み、海中のカーテンも海底まで届くものに変更すべきではないか?
6-7.防衛局は最近も、K9護岸予定地周辺で海水の汚濁調査等を行っていると報道されている。もしこのような調査を行っているのであれば、調査地点、調査内容を明らかにされたい。
7.今後の「設計概要変更承認申請」について
公有水面埋立法第42条第3項により準用される同法第13条の2第1項では、「埋立区域の縮小、埋立地の用途もしくは設計の概要の変更等」については、知事の許可が必要とされている。
防衛局はこの規定に基づき、2014年9月3日、「①工事用仮設道路①~③の追加、②中仕切護岸の追加、③美謝川切替ルートの変更、④辺野古ダム周辺からの土砂運搬方法の変更」について、沖縄県知事に「設計概要変更承認申請書」を提出した。この申請については、同年12月5日、仲井眞知事(当時)は、「①工事用仮設道路①~③の追加、②中仕切護岸の追加」を承認した。しかし防衛局は、「③美謝川切替ルートの変更、④辺野古ダム周辺からの土砂運搬方法の変更」については知事の承認が得られる見込みがないことから申請を取り下げた経過がある。
今後の「設計概要変更承認申請」の手続について、下記のとおり質問する。
7-1.防衛局は、上記の設計概要変更申請のうち、申請を取り下げた「③美謝川切替ルートの変更、④辺野古ダム周辺からの土砂運搬方法の変更」については、再度、申請を行わなければならないが、何時頃の申請を予定しているのか?
7-2.その後、防衛省・防衛局は、「設計概要変更申請が必要となるのは、埋立承認願書本文の『4 設計の概要』を変更する場合だけである。添付の『設計概要説明書』の変更については設計概要変更申請の対象ではない」と主張するようになった(例えば、2015年5月13日の話し合いにおける防衛省経理装備局御園氏の説明)。防衛省は、今もこの主張を続けるのか?
7-3.「埋立承認願書本文の『4 設計の概要』」は、わずか6頁弱のものにすぎず、その具体的な内容は全て「添付の『設計概要説明書』」に記載されている。
沖縄防衛局が行った2014年9月3日付の上記4点の設計概要変更申請は、「④辺野古ダム周辺からの土砂運搬方法の変更」など、「埋立承認願書本文の『4 設計の概要』」だけではなく、「添付の『設計概要説明書』」に記載された項目についても行っている。
防衛省・防衛局の上記主張は、自らが行った以前の設計概要変更申請とも矛盾するのではないか?
7-4.また、防衛省は、「仮設的なものは設計概要変更申請の対象ではない」とも主張し始めている(例えば、上記2015年5月13日の話し合いでの御園氏の説明)。防衛省は、今もこの主張を続けるのか?
しかし埋立承認願書本文の「4 設計の概要」には、「仮設道路」も含まれており、防衛局も2014年9月3日の設計概要変更申請に「①工事用仮設道路①~③の追加」を含めてきた経過がある。今になって「仮設的なものは設計概要変更申請の対象ではない」と主張するのは失当ではないか?
7-5.報道によれば「政府が翁長知事の承認が必要となる埋立て計画の設計概要の変更申請を避けることを検討している」、「知事権限で工事が足止めされるのを避ける目的で、政府は既に技術的な検討を防衛省に指示した」という(琉球新報 2016.12.22)。
このような脱法行為は許されないが、事実か?
8.ジュゴン監視等業務について
8-1.防衛省は、前回3月3日の話し合いで、「本年2月からジュゴン監視等業務で航空機による調査を再開し、さらに本年2月6日から実施された監視プラットフォームによる調査を再開した」と説明した。再開後は、ジュゴンは確認されているか? 本年2月以降のジュゴンの確認状況を明らかにされたい。
8-2.本年3月、沖縄本島北西部で国内の生息は3頭だけと言われているジュゴンの新たな個体の目撃情報が複数あることが大きく報道された(沖縄タイムス 2017.3.20等)。子どものジュゴンではないかと言われており、沖縄で繁殖した可能性が高い。
報道によれば、この情報については環境省も把握しているという。防衛局としてこの目撃情報を確認しているか?
もしジュゴンの繁殖が事実なら朗報だが、一方では、防衛省の資料でも2014年9月1日以降は大浦湾でジュゴンが確認されておらず、「個体C」のジュゴンも2015年6月24日以降は確認されていない。事業の影響は大きいと言わざるを得ない。
今回の目撃情報を受け、事業をいったん中断してジュゴンへの影響を再検討すべきではないか?
8-3.「シュワブ(H26)ジュゴン監視等業務」には、古宇利島周辺におけるジュゴンの海草藻場利用状況調査が含まれており、防衛省は本年3月、我々の求めに応じてその調査結果の概要を提出した。
何故、古宇利島周辺に限られているのか? 嘉陽沖、大浦湾内や辺野古沖での調査は行なっていないのか?
****************
<追加質問>北部訓練場、オスプレイ着陸帯の工事の不具合について
北部訓練場で昨年、実施された米軍オスプレイ着陸帯の造成工事で不具合があり、防衛局が補修工事を続けていたことが、本年2月22日の衆議院予算委員会で明らかになった。
この委員会では、防衛省の深山地方協力局長が、「本年1月、N1地区において、法面から水が染み出していること、そしてH地区においては、法面の表面の張芝の一部がずり落ちていることがそれぞれ確認されました」と認めている。その原因について同局長は、「N1地区については、法面に芝を張る作業を完了する前に雨水が内部にしみこんで脆弱となって、その後、雨水が入ってきたことが原因」、「現在、法面の一部を補修するとともに、水抜きのパイプを設置している」と説明している(以上、衆議院予算委員会議事録より)。
また防衛省は、本年3月6日の福島議員の質問に対して、「H地区については、降雨等の影響が原因であると考えられたことから、法面の一部を補修した」と回答した。
この問題について、下記のとおり質問する。
T-1.このような不具合の原因について深山局長は、「転圧も含めまして、特に工程を、何かを行わなかったためにこうしたことが出たとは我々認識しておりません。ただ、結果としてこのような不具合が生じたということは大変遺憾であるというふうに思っております」と延べるだけで、不具合の原因について説明していない。
本件工事の特記仕様書では、着陸帯の盛土は、「盛土の締固めは、路床については一層仕上がり厚20cm毎、その他は30c毎に十分に転圧する」とされている。しかし、当初は12ヶ月~14ヶ月とされていた工期を、年内返還のために工事を急がせたため、盛土の転圧が不十分となり、このような不具合が生じたことは明らかである。
防衛省としてこのような不具合が生じた原因についてどう認識しているのか説明されたい。
T-2.同予算委員会で質問した赤嶺議員も、「完成した着陸帯が雨が降っただけで補修が必要になるような工事をやっていたのかと、素人でも疑問に思います」と呆れていたが、特記仕様書通りの転圧が行われておれば、このような不具合が生じることはあり得ない。
N1地区、H地区の着陸帯造成に際しては、沖縄防衛局職員が現場に立会っていたはずである。盛土施工は、特記仕様書通りの十分な転圧が行われていたか?
また、施工中、現場でのプルフローリング試験、現場密度試験等で何らかの異常は確認されなかったのか? 盛土施工中の工事写真、各種試験データ等を提出されたい。
T-3.防衛省は、「本年2月、これに係る補修を実施した」と回答した。今後、同様の不具合が生じる恐れはないのか?
沖縄は本格的な梅雨に入り、さらに台風シーズンも近づいている。大雨が降った場合、以前のN4地区のように、着陸帯のさらなる崩落が危惧される。法面の一部の補修や水抜きパイプの設置だけで、この不具合が解消できたと考えているのか? 盛土をめくり直して、再度、やり直すべきでないか?
T-4.N1地区、G地区、H地区の4箇所の着陸帯は、すでに昨年12月21日の日米合同委員会で米軍への提供が承認され、12月26日に防衛大臣によって米軍への追加提供が官報告示された。今回のような相次ぐ不具合の発覚は、米軍への移管が早すぎたことを意味していないか?
(以上)