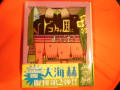会社の昼休み、娘とごはん。
今日ねー、マンガ買って帰るんだー。
と云ったら、娘きょとん。
そもそも、私、マンガって買わない。
対する娘は、いかに安く早く確実に
目当てのマンガを買おうか
日々戦っているような奴。
何買うの?なんで買うの?
と聞かれ、ちょっと照れて、
ないしょー。ジャケ買い。中身知らない。
って云ったら
そんなの本屋で定価で買うの?!
社会人め!
そーいうのはブックオフ案件だよ!
と、なぜか怒られた。
実は本屋でもなく、コンビニだったんだけどね。
そこのコンビニ、店頭に安かろう悪かろうな野菜も並べてて
にんじんやレタス、菓子パンなんかと
一緒にささっとマンガをかごに入れた。
なのにレジでおじさんたら
ただいまコミックスお買い上げで
クーポン券さしあげてますけど
お作りいたしますか?だって。
いらない、いらないから
とっとと袋にいれてくれ!
丁寧にビニールはがして
スリップまで抜きやがりました。
やっとおうちに帰り
土鍋に米と水をざぶっと汲んで
火にかけ、さて、読書タイム。
てか、マンガに対して
読書って言葉はアレだな。
中学2年生の女の子の話。
お勉強苦手。ガマン苦手。
本能のままに生きてます。
友達に助けてもらうこと多し。
でも、ちゃんとそれを知ってて
感謝もしてて
どうにかお返しもしたいなあと
思ってる。
マンガのタイトルは
「ちーちゃんはちょっと足りない」
って言います。
表紙のちーちゃんの表情にやられた。
それと、私も「ちーちゃん」って
呼ばれることもあるからね。
親近感というか、不安感というか。
ちーちゃんにはほしいものが
たくさんある。いつも満たされない。
まわりのひとにはあるのに
自分にだけないのはおかしい、と
憤る。悲しむ。だからよく泣きます。
でも、満たされてないのは彼女だけじゃない。むしろ、周りの子のほうが
その思いは強いのかもしれません。
ちーちゃんのように無分別に
泣きわめいたりはしないけど
がまんしてる分うっ積するものが多い。
そんな、自分も耐えてる子が
ちーちゃんに云うのです。
もうすぐ、大人になれる、
そしたらなんでも、ほしいものが
手に入る、って。
それを楽しみにしようって。
私は大人で、ほしいものは
たくさんあるけど、ぜんぶはとても
手に入りません。
というか、ほしいものぜんぶ持ってる、
っていう大人なんかいないんじゃない?
学生時代の友達で、たいそうなお金持ちがいて(親がね)
みんなで、宝くじもし一億あたったら
どうする?!使いきれないね!とか
いってる時に
え?ぜーんぜん足りないんだけど。
だってワインセラー地下に作るのに
いくらでしょ、そこに保管しとく
どこそこのあれとこれとそれ、
買ったらもう無いよねー
ってのたまって、
悪気ないぶんなんかもうどーしよーも
ないなこいつ!って雰囲気になりました。
人の欲は底抜けです。
悪いことばかりでもない。
ほしいものがあるから
なりたい自分があるから
私は今をがんばろうという
気持ちになるんです。
だから、マンガのなかの台詞を
少し読み替えるんなら
大人になれば、ほしいものを
どうやって手に入れたらよいか
探せるようになる
そもそも、じぶんにとって
本当にほしいものは
なんなのか、きちんと
考えられるようになる
それを楽しみに
どうにかがんばって
過酷な中学時代を
生き延びてほしいのです。
今日ねー、マンガ買って帰るんだー。
と云ったら、娘きょとん。
そもそも、私、マンガって買わない。
対する娘は、いかに安く早く確実に
目当てのマンガを買おうか
日々戦っているような奴。
何買うの?なんで買うの?
と聞かれ、ちょっと照れて、
ないしょー。ジャケ買い。中身知らない。
って云ったら
そんなの本屋で定価で買うの?!
社会人め!
そーいうのはブックオフ案件だよ!
と、なぜか怒られた。
実は本屋でもなく、コンビニだったんだけどね。
そこのコンビニ、店頭に安かろう悪かろうな野菜も並べてて
にんじんやレタス、菓子パンなんかと
一緒にささっとマンガをかごに入れた。
なのにレジでおじさんたら
ただいまコミックスお買い上げで
クーポン券さしあげてますけど
お作りいたしますか?だって。
いらない、いらないから
とっとと袋にいれてくれ!
丁寧にビニールはがして
スリップまで抜きやがりました。
やっとおうちに帰り
土鍋に米と水をざぶっと汲んで
火にかけ、さて、読書タイム。
てか、マンガに対して
読書って言葉はアレだな。
中学2年生の女の子の話。
お勉強苦手。ガマン苦手。
本能のままに生きてます。
友達に助けてもらうこと多し。
でも、ちゃんとそれを知ってて
感謝もしてて
どうにかお返しもしたいなあと
思ってる。
マンガのタイトルは
「ちーちゃんはちょっと足りない」
って言います。
表紙のちーちゃんの表情にやられた。
それと、私も「ちーちゃん」って
呼ばれることもあるからね。
親近感というか、不安感というか。
ちーちゃんにはほしいものが
たくさんある。いつも満たされない。
まわりのひとにはあるのに
自分にだけないのはおかしい、と
憤る。悲しむ。だからよく泣きます。
でも、満たされてないのは彼女だけじゃない。むしろ、周りの子のほうが
その思いは強いのかもしれません。
ちーちゃんのように無分別に
泣きわめいたりはしないけど
がまんしてる分うっ積するものが多い。
そんな、自分も耐えてる子が
ちーちゃんに云うのです。
もうすぐ、大人になれる、
そしたらなんでも、ほしいものが
手に入る、って。
それを楽しみにしようって。
私は大人で、ほしいものは
たくさんあるけど、ぜんぶはとても
手に入りません。
というか、ほしいものぜんぶ持ってる、
っていう大人なんかいないんじゃない?
学生時代の友達で、たいそうなお金持ちがいて(親がね)
みんなで、宝くじもし一億あたったら
どうする?!使いきれないね!とか
いってる時に
え?ぜーんぜん足りないんだけど。
だってワインセラー地下に作るのに
いくらでしょ、そこに保管しとく
どこそこのあれとこれとそれ、
買ったらもう無いよねー
ってのたまって、
悪気ないぶんなんかもうどーしよーも
ないなこいつ!って雰囲気になりました。
人の欲は底抜けです。
悪いことばかりでもない。
ほしいものがあるから
なりたい自分があるから
私は今をがんばろうという
気持ちになるんです。
だから、マンガのなかの台詞を
少し読み替えるんなら
大人になれば、ほしいものを
どうやって手に入れたらよいか
探せるようになる
そもそも、じぶんにとって
本当にほしいものは
なんなのか、きちんと
考えられるようになる
それを楽しみに
どうにかがんばって
過酷な中学時代を
生き延びてほしいのです。