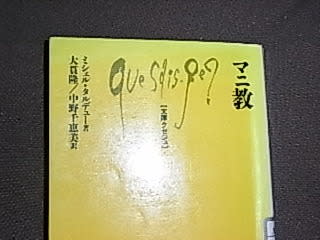
前回と同じミシェル・タルデユー著「マニ教」からマニ教についての描写を引用します。
「ベーマ祭」というマニ教の祭りについての部分を引用します。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「ベーマ」の祭典は、マニ教独自の祭典である。
「ベーマ」とは“王座”のことで、マニが座すべき座である。
「ベーマ」をめぐる祭りは彼が今なお目に見えない形で信徒の共同体を教育し、裁き、指導し続けていることを信徒たちに思い起こさせるのに役立った。
マニ教徒の「ベーマ祭」はその主要な意味づけをキリスト教の復活祭の祭典から借用したのであるが、それは実際に苦しみ、実際に死去したマニ一人についてのみの復活祭であり、つまりマニの死から生への、苦悩の夜から幸福な永遠の光への移行、肉体、この世という牢獄、輪廻転生からの解放を意味するものなのであった。
年に一度の大断食の始まりは、マニが入獄して鎖で繋がれた時にぴったり対応していた。
それと同様断食の終わりも彼が解放され昇天したと想定される日に対応した。
「ベーマ」の儀式の始まりは、磔刑(入獄)から脱体(死と昇天)に至るマニの受難についての文章の朗読で始まったことが予想される。(原典が存在しない)
その後には、とりなしの祈りとマニに捧げられる讃歌が続く。
次にマニの「福音書」に関する儀式が厳粛に挙行される。
すなわち一人の祭司がそれを信者たちに示すと、信者たちはそれに讃美を返すのである。
「ベーマ祭」の前夜は一晩中祈りと歌ですごされた。
夜明けになると太陽の最初の光が差し込むように聖所の戸を大きく開けた。
日の出の太陽とマニを同一視した曙の歌が響き渡ると同時に、聴講者達が果物や菓子類の贈り物を携えて参上し、壇の前にある黄金の三脚台や聖体拝領の机に供えた。
金の壺の中には果物のジュースが注がれた。
麻の薄布で覆われた五段の壇は、教会の頂点に座するマニの王位を象徴するもので、マニは肖像で表わされていた。
(引用ここまで)
*****
祭り前の、この一月にわたる長い断食が、イスラム教のラマダン月の断食の基となったようです。
それでも、ここに描かれているのは、地球上のどこにでもある教祖とその弟子たちのお祭りの様子のように思われます。
マニ教は、ササン朝ペルシャでゾロアスター教に破れて、それ以後表舞台からは姿を消したということです。
それ以降、中国で勢力を得た頃には、マニ教は「魔教」と呼ばれ、弾圧されたといいます。
しかし、マニ教は拝火教であるゾロアスター教の教えとは真っ向から対立するものであり、またキリスト教的要素が中国で大きな力を持つことも考えにくいです。
だとすると、マニの教えはどのように息づいてゆくのでしょうか?
同書の筆者は、マニについて、次のように述べています。
*****
(引用ここから)
マニは自分の完成図を哲学者のようにでなく、画家のように描いた。
彼の体系は理論的な熟考からではなく、色、香り、風味の感覚と結びついた行為から生じた。
例えば「食べ物の中にある快い味は、その中に混ざっている光に属する」、という具合である。
「光の大地」、すなわち「大いなる父の住処」も「そこは芳しく、虹色をしている」と感覚的な用語で述べられる。
アウグスティヌスも、「マニ教徒が穀類、葡萄、メロン、レタス、オリーブ、薔薇、すみれをとりわけ愛好したのは、これらの野菜や果物の色が“神の臨在を表わす印”であるからだ」、と記している。
(引用ここまで)
*****
このような繊細な感性には、世界の覇者といった感じはまったくありません。
何よりもこのお祭りは「マニは殺されてこの世を去った」、という敗北宣言以上のものは、大変伝わりにくいと思います。
おそらく、このお祭りのクライマックスは、果物のジュースをマニに捧げるところにあるのではないか?とは思うのですが。。
本書の翻訳者は、「後書き」に次のように自身の考えをまとめています。
西洋という範疇からは、マニ教はまさにこのように考察されるのだと思います。
彼らの言うように、マニの神学の最善のものは、イスラム教とグノーシス神学へと吸収されて消えたと思うべきなのでしょうか?
*****
(引用ここから)
マニ教は、マニが絶対二元論から始めた点に、ゾロアスター教の元来の教説が強く働いている。
マニとマニ教の神話は、この宇宙論と神論の構造において、イラン固有の産物であると言われなければならないというのがわたしの意見である。
それに対してマニ個人の主観的なシンパシーはキリスト教的グノーシス主義のイエス論にあって、それが彼の救済論と予言者論に強く現れているのではないか。
(引用ここまで)
*****
続きます。。
 wikipedia「ラマダン」より
wikipedia「ラマダン」より
ラマダーン (アラビア語)は、ヒジュラ暦の第9月。
日本ではラマダンともいう。ペルシア語など非アラビア語圏における発音ではラマザーン、ないしラマザンともいう。
この月の日の出から日没までのあいだ、イスラム教徒の義務の一つ「断食(サウム)」として、飲食を絶つことが行われる。
「ラマダーン」を断食のことと誤って捉える人も少なくないが、あくまで月名である。
ラマダーン月の開始と終了は、長老らによる新月の確認によって行われる。
雲などで新月が確認できなかった場合は1日ずれる。
夏に日が沈まない極地地方にあっては、近隣国の日の出・日没時間に合わせるなどの調整も図られる。
ラマダーン中には世界中のイスラム教徒が同じ試練を共有することから、ある種の神聖さを持つ時期であるとみなされている。
 関連記事
関連記事
ブログ内検索
マニ教 6件
ゾロアスター 7件
グノーシス 8件
弥勒 7件
ペルシア 6件
マギ 7件
キリスト 15件
聖書 15件
などあります。(重複しています)
「ベーマ祭」というマニ教の祭りについての部分を引用します。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「ベーマ」の祭典は、マニ教独自の祭典である。
「ベーマ」とは“王座”のことで、マニが座すべき座である。
「ベーマ」をめぐる祭りは彼が今なお目に見えない形で信徒の共同体を教育し、裁き、指導し続けていることを信徒たちに思い起こさせるのに役立った。
マニ教徒の「ベーマ祭」はその主要な意味づけをキリスト教の復活祭の祭典から借用したのであるが、それは実際に苦しみ、実際に死去したマニ一人についてのみの復活祭であり、つまりマニの死から生への、苦悩の夜から幸福な永遠の光への移行、肉体、この世という牢獄、輪廻転生からの解放を意味するものなのであった。
年に一度の大断食の始まりは、マニが入獄して鎖で繋がれた時にぴったり対応していた。
それと同様断食の終わりも彼が解放され昇天したと想定される日に対応した。
「ベーマ」の儀式の始まりは、磔刑(入獄)から脱体(死と昇天)に至るマニの受難についての文章の朗読で始まったことが予想される。(原典が存在しない)
その後には、とりなしの祈りとマニに捧げられる讃歌が続く。
次にマニの「福音書」に関する儀式が厳粛に挙行される。
すなわち一人の祭司がそれを信者たちに示すと、信者たちはそれに讃美を返すのである。
「ベーマ祭」の前夜は一晩中祈りと歌ですごされた。
夜明けになると太陽の最初の光が差し込むように聖所の戸を大きく開けた。
日の出の太陽とマニを同一視した曙の歌が響き渡ると同時に、聴講者達が果物や菓子類の贈り物を携えて参上し、壇の前にある黄金の三脚台や聖体拝領の机に供えた。
金の壺の中には果物のジュースが注がれた。
麻の薄布で覆われた五段の壇は、教会の頂点に座するマニの王位を象徴するもので、マニは肖像で表わされていた。
(引用ここまで)
*****
祭り前の、この一月にわたる長い断食が、イスラム教のラマダン月の断食の基となったようです。
それでも、ここに描かれているのは、地球上のどこにでもある教祖とその弟子たちのお祭りの様子のように思われます。
マニ教は、ササン朝ペルシャでゾロアスター教に破れて、それ以後表舞台からは姿を消したということです。
それ以降、中国で勢力を得た頃には、マニ教は「魔教」と呼ばれ、弾圧されたといいます。
しかし、マニ教は拝火教であるゾロアスター教の教えとは真っ向から対立するものであり、またキリスト教的要素が中国で大きな力を持つことも考えにくいです。
だとすると、マニの教えはどのように息づいてゆくのでしょうか?
同書の筆者は、マニについて、次のように述べています。
*****
(引用ここから)
マニは自分の完成図を哲学者のようにでなく、画家のように描いた。
彼の体系は理論的な熟考からではなく、色、香り、風味の感覚と結びついた行為から生じた。
例えば「食べ物の中にある快い味は、その中に混ざっている光に属する」、という具合である。
「光の大地」、すなわち「大いなる父の住処」も「そこは芳しく、虹色をしている」と感覚的な用語で述べられる。
アウグスティヌスも、「マニ教徒が穀類、葡萄、メロン、レタス、オリーブ、薔薇、すみれをとりわけ愛好したのは、これらの野菜や果物の色が“神の臨在を表わす印”であるからだ」、と記している。
(引用ここまで)
*****
このような繊細な感性には、世界の覇者といった感じはまったくありません。
何よりもこのお祭りは「マニは殺されてこの世を去った」、という敗北宣言以上のものは、大変伝わりにくいと思います。
おそらく、このお祭りのクライマックスは、果物のジュースをマニに捧げるところにあるのではないか?とは思うのですが。。
本書の翻訳者は、「後書き」に次のように自身の考えをまとめています。
西洋という範疇からは、マニ教はまさにこのように考察されるのだと思います。
彼らの言うように、マニの神学の最善のものは、イスラム教とグノーシス神学へと吸収されて消えたと思うべきなのでしょうか?
*****
(引用ここから)
マニ教は、マニが絶対二元論から始めた点に、ゾロアスター教の元来の教説が強く働いている。
マニとマニ教の神話は、この宇宙論と神論の構造において、イラン固有の産物であると言われなければならないというのがわたしの意見である。
それに対してマニ個人の主観的なシンパシーはキリスト教的グノーシス主義のイエス論にあって、それが彼の救済論と予言者論に強く現れているのではないか。
(引用ここまで)
*****
続きます。。
 wikipedia「ラマダン」より
wikipedia「ラマダン」より ラマダーン (アラビア語)は、ヒジュラ暦の第9月。
日本ではラマダンともいう。ペルシア語など非アラビア語圏における発音ではラマザーン、ないしラマザンともいう。
この月の日の出から日没までのあいだ、イスラム教徒の義務の一つ「断食(サウム)」として、飲食を絶つことが行われる。
「ラマダーン」を断食のことと誤って捉える人も少なくないが、あくまで月名である。
ラマダーン月の開始と終了は、長老らによる新月の確認によって行われる。
雲などで新月が確認できなかった場合は1日ずれる。
夏に日が沈まない極地地方にあっては、近隣国の日の出・日没時間に合わせるなどの調整も図られる。
ラマダーン中には世界中のイスラム教徒が同じ試練を共有することから、ある種の神聖さを持つ時期であるとみなされている。
 関連記事
関連記事
ブログ内検索
マニ教 6件
ゾロアスター 7件
グノーシス 8件
弥勒 7件
ペルシア 6件
マギ 7件
キリスト 15件
聖書 15件
などあります。(重複しています)















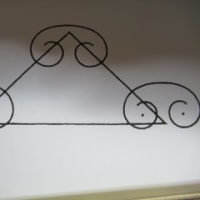









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます