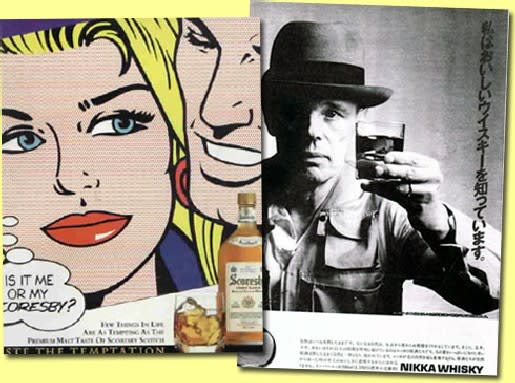(the Photo, which picked up from "Wiskyfun.com"・・)
時計は、いよいよ午後11時を回った。
(今夜はダメだ。もう、店を閉めるか・・・)
と思ったやさき、約3~4センチほどか?
店のドアが開いた。
<・・・上記、先回掲載分>
(いよいよ第4章の締めくくり。マスター本田には、新たな出会いと発見がある・・・)
毎日一回、クリック応援を! (人気ブログランキング)
(人気ブログランキング)
--------------------------------------------------
長編連載小説『フォワイエ・ポウ』
著:ジョージ青木
4章
(新たな展開)
(2)-2
(誰なのか、客か?)
店の入り口の前に、たしかに人の気配がする。
本田は、とっさに声をかけた。
「いらっしゃいませ・・・」
「どうぞ! お入りください」
遠慮がちにドアが開く。
1人の男性が店に入る。
一見したところ、その男性客は20代前半の若者である。
「あの~ 今日、初めて来るのですが・・・」
「あの~ 私のようなものがこのお店に入ってもいいんでしょうか?」
「初めてのお客さまですね。大丈夫です。どうぞ、ご遠慮なくお入りください」
いささか小柄で細身の痩せ型、細面の顔つきは青白かった。若者らしからぬ生活の疲れが見え隠れする。始終うつむき加減の若者は、たえず遠慮がちなそぶりを見せ、何故か、はにかんでいた。
「当店は、会員制でも何でもありませんから、どうぞご遠慮なくお入りください、さ、さ、どうぞ!」
若い客を招き入れた時から、本田の萎えた気分はがらりと変化した。溜まった有毒な副産物は瞬時にして蒸発。たちまち消えてなくなっていた。
「どうぞ、カウンターへ、どうぞ・・・」
ドアを開いて入ってくる若者は、なぜか足元ばかりを見ており、本田と目を合わせようとしない。絶えず、うつむき加減の若者は、のろのろと歩きカウンター席の隅っこに腰をかけようとした。
「どうぞ、こちらにおかけ下さい」
若者に声をかけた本田は、カウンターの中ほどに手を差し向けながら、グラスとお絞りでセットした位置に案内する。
「あ、ありがとうございます」
カウンター席にかけた若者は、何かにおびえているように、萎縮し、表情を崩さず、身体は、椅子に座ったまま硬直させたままである。
「今日は早い時間にお客さんがいらしてましたが、日曜日ですからね、この時間になると暇になります・・・」
ここは、まず、本田の方から声をかけた。
「何かご用意しましょう。なにが宜しいですか?」
「お酒ください、いや、あの~・・・ お酒ありますか?」
「おさけ、日本酒ですか?」
「はあ~・・・ はい、そうです」
「申し訳ございません、当店は、日本酒をおいていないんです」
「そうだ、そうですね。でしたら、ウイスキーを・・・」
「はい、分かりました。銘柄は、何が宜しいですか?」
「あ~そうか・・・」
若者は、銘柄を決めるのに戸惑っている。
というよりも、ウイスキーの銘柄がよく分かっていない。こんな若者を気の毒に思った本田は、彼に助け舟を出そうと思った。丁寧に、親切に分かりやすく、まして自尊心を傷つけないように、この若者に対応しようと決めた。
「もう、どこかでお酒飲んでらっしゃいますよね?」
「はい、ご飯食べながら、ビールを少し、それから、日本酒も飲んできました・・・」
(若者の顔が少し青白いのは、すでに酔っ払っている証拠だ、加えて、かなり飲んでいるに違いない!)
と、ここでようやく本田は気付いた。
「まだ飲めますか?」
本来、こういう質問は客に失礼であり、それなりの客に対しては侮辱にもなりかねない危険な質問であったが、この若者には、あえて質問した。
「ハア~ もう少し、飲みたいです。高くてもおいしいお酒を呑みたいのです。ですからマスター、何か、マスターのお勧めを教えて下さい。そして、それを飲みます。どのウイスキーがおいしいですか、マスターにお任せします」
いささか対応に困った。
この店を初めて訪れた客、しかもあまり洋酒のことが分かっていない若者に対し、いくら高級な酒が飲みたいと要求されても、限度を考えなければならない。
ワンショットで5千円以上、そんな高価なウイスキーもある。この店にも置いてある。がしかし、たぶん彼にはその価値が分からないはず。たとえ客からの要請があったとしても、こんな高価な酒を彼には勧められない。必ず、びっくり仰天するであろう。あれこれと、それなりに、本田はこの若者に気をつかっていた。
(ならば、どうするか?)
少し考えて、オールドパーを取り出した。
「どれをお勧めしようかな? そう、まず、バーボンよりもスコッチの方がいいでしょう。これ、オールドパーです。これにしましょう」
ボトル棚から取り出した新しいオールドパーのボトルを手に取った本田は、あらためて若者に見せた。オールドパーは、本田の好きなスコッチウイスキーのひとつであったし、もちろん、すでに封を切っているボトルもある。しかしこの際、この若者に対し、且つ、日曜日の珍客に対して、本田自身の敬意を表したく、ここは敢えて新しいボトルを開けることにした。
うつむきかげんのうつろな眼だった若者の目は、ようやく活気を取り戻し、その視線は、はっきりとボトルに向けられた。
「はあ~、オールドパー、ですね?」
「そうです」
「そう、それ頂きます。お願いします」
「はい、わかりました。それで、どうしましょう?」
「ロックにしますか、それとも水割り?・・・」
若者は即答した。
「いいえ、ストレートで、お願いします」
「はい、では、ストレートで・・・」
と、返答したものの、本田は迷った。
(大丈夫かな、かなり飲んでいるようだが、ストレートを飲んだあげく、ここで酔っ払って、あげくの果ては眠むってしまうか、まして、暴れてもらっても困るのだが・・・)
めったに使わないストレートグラスを、棚から取り出した。
小さなストレートグラスを、おもむろに若者の前に置いた。
さらに若者の座っているカウンターの正面に立ち、まったく封を切っていないオールドパーのボトルを置いた。
(ちょいと、見せておいてやろう)
目の前の若者に対し、全ての動きを見せる演出を思い立ち、即興の演出を即座に自作自演した。
彼の目の前で全ての動作を見せる。
まずはボトルの封を切って見せ、
若者の目の前にあるストレートグラスに、
封を切ったばかりのオールドパーを、
ぎりぎりグラス一杯まで、注ぎ、
グラスを満たした液体が、
グラスから溢れ出す一歩寸前で、
本田の動作は止まった。
「お待たせしました」
「オールドパーのストレートです」
「どうぞ、召し上がれ・・・」
いかにも青白く、活気のなかった若者の表情がにわかに豊かになった。腐りかかっていた目は、正常な輝きを取り戻している。そんな若者の目線は、本田の動作の一部始終を見守っていた。
「ありがとうございます、いただきます」
若者の右手が小さなストレートグラスに伸びた。そのままグラスを持ち上げると、いや、グラスに触っただけでも、その瞬間、中の液体はグラスの外にこぼれ出す。
しかし、手が伸びると同時に、今までうなだれていた顔が動き、口が突き出てきた。右手がグラスに届くのとほぼ同時に、若者の唇がグラスに届いていた。
グラスに届いた若者の唇は、半端なストローよりも上手く、グラスの中のアルコールを吸い上げる。差し出した右手が、わずかにグラスを持ち上げたときには、すでにグラスの中の液体は半分に減っていた。中身が半分になったグラスを自分の目で確かめた若者は、再び、グラスをカウンターに置いた。
「ああ~、おいしい・・・ ほんとうに、美味しいです」
にわかに若者の顔がほころび、ようやく笑みが出た。
「チューハイより、おいしいです」
(焼酎と比べてもらっては困るんだよな~)
と、言いたかったが、けっして本田は口に出さず、無言の笑顔で答えた。答えの代わりに、若者に質問した。
「お客さん、チューハイは、お好きですか? 焼酎はお好きですか?」
「・・・」
若者からは、すぐには答えが帰らなかった。
この時代、ようやく焼酎が近年の市民権を得た頃だった。今日のように、日本全国各都道府県にまたがり数え切れないほどの焼酎は市中に出回っていなかった。わずかに、麦焼酎と芋焼酎等、数点が飲み屋にある時代であった。当時のチューハイなど、今になって想えば、おしゃれな飲み物であったかもしれない。しかし当時の焼酎は、やはり、労働者っぽいノミスケノのための酒であった。
思わず(チューハイより美味しい!)と、声を発した若者は、マスターの本田に対し、いささか恥ずかしい思いをしていた。だから、本田の質問に、答えられなかった。
「今まで別の居酒屋で、今日も一人で、チューハイ飲んでいました」
「あ~ そうだったの」
「日本酒じゃなくて、焼酎飲だったの」
「そうです」
「そうなんだ」
「家でも、いや、寮で飲むのも、焼酎の水割りです」
「寮に住んでいるのですか?」
「そうです、自動車メーカーに勤めていますから、今は社員寮に住んでいます」
「そうですか・・・」
「あ、遅くなりましたが自己紹介します」
「わたしは、竹本です。それで、みんなから竹ちゃんと呼ばれています。ここでも今からは『たけちゃん』と呼んでください」
「竹本さん、竹ちゃん、はい、竹ちゃん、私、本田と申します、宜しくお願いします」
「マスターは、本田さんですね」
「・・・」
本田は微笑みながら頷いた。
竹本は、話を続けた。
「でも、お名前は直接呼べません、私からは、今から『マスター』と云います」
話し始めた若者、竹本は、なぜか元気を取り戻していた。来店した時の陰鬱な雰囲気、負け犬のような悲惨な表情は、すでに、どこかに消えてなくなっていた。
「ところでマスター、ここは初めてじゃないんです」
話題を変えた竹ちゃんは、あらためて真剣な表情になった。
「この2週間で3回、来ました。でも、いつも入り口まできたら足がすくんでしまって、店の中に入れないんです、一度はドアを開けて、店の中をのぞいたのですが・・・」
「・・・」
やさしく頷くだけにとどめた本田は、しばらく無言を通した。いや、敢えて本田から言葉をはさまないようにしながら、ひとまず、竹本の気分を楽にさせ、彼の話したい事を引き出し、詳しく聞いてみたいと思った。
「日曜日に店が開いているとは、思いませんでした・・・」
「はい、日曜日もあけますよ」
「でも今日はよかった、ようやく店に入ることができました」
竹本の話は続いた。
「僕は山口県の出身です。高校卒業して直ぐに、広島の自動車工場に就職しました。工業高校だったから、事務員ではなく工員で入社したんです。勤務シフトのほとんどが夜勤ですから、普通のサラリーマンがお酒飲むときに僕たちは仕事を始めるんです。夜勤があけたらもう朝になります。もう、くたくたです。会社の社員食堂で朝ごはんを食べたら、まっすぐ寮に帰ってお風呂に入る。ゆっくり、入れませんから、いつもカラスの行水です。ほとんどシャワーを浴びたら終わりです。だから、からだにまみれた汗と油と埃が染み付いてしまって、カラスの行水では完全に油が落ちない。だから油の臭いが染み付いているから恥ずかしくて、スーツを着ている人ばかりが集まるこんなお店には入りたくても入れないんです。こんなお店には・・・」
「いや、竹本さん・・・」
本田が若者の話しをさえぎろうとした。
本田が話かけたとたん、今度は竹本が話をさえぎった。
「マスター、竹ちゃんと呼んでください。そのほうが、僕に似合っている、マスターから竹ちゃんといっていただくほうが、僕はうれしいのです」
「では、竹ちゃんと呼びますよ」
あらためて、本田は竹ちゃんに語り始めた。
「竹ちゃん、そんなことないよ。油の臭いなんて、ぜんぜんしない。手もきれいだし、服装も清潔そのもの。私は全然気にならないし、竹ちゃんはとても工員なんかには見えません。第一私にとって、お客さんの職業なんてものは関係ない。どんな職業だって、仕事をする事はたいへん立派な事だ。私が一番嫌いな人間はね、半端な不良と安物のやくざです。ゴロゴロよたよた、まともな仕事をしないで人に迷惑かけながら遊んで生きている人間、私は大嫌いだ。そんな奴が世の中で一番みっともない!」
竹本は、静かに本田の話を聞いていた。本田の話にしっかりと耳を傾けながらも、彼の目はにわかに潤みはじめた。光るものが浮かんできた。しかし、本田の話は続く。竹本の涙をみた本田は、それでも話を途絶えさせなかった。
「とにかく雰囲気的に、竹ちゃんから漂ってくるもの、それは石鹸のにおいだ。若者には、清潔な石鹸の香りが一番にあうのですよ。だから、私から見れば竹ちゃんは、すてきな若者です。そんな若者に来ていただけるなんて、当店は大歓迎です。今度からそんな遠慮は必要ない。遠慮なく、いつでも好きな時に店に入って来てください。大丈夫だから・・・」
本田がここまで話しを続けた時、竹ちゃんの両目から大粒の涙が数滴、カウンターにこぼれた。竹本は、自分の泣き顔を隠そうとはしなかったし、涙も拭き払おうとはしなかった。カウンターの中の本田は、話を中断した。しかし、平然とした表情で若者の顔を見つめたまま、目を離そうとはしなかった。
天上に釣上げられた大きなスピーカーから、ゆとりをもって流れ出る静かなモダンジャズ。端正なピアノ演奏に語りかける、マリンバの音の流れ。ドラムからのシャープな音は、スローテンポのメロディーにめりはりをつける。流れ出るモダンジャズの曲を縫い合わせるように、2人の沈黙は続いた。
沈黙は、数分続いた。
一言も声をかけない本田に対し、ようやく竹本は口を開いた。
「マスター、お話の途中、すみません。ちょっとトイレに行ってきます」
と言いながら、トイレに駆け込んだ竹本はしばらく出てこなかった。
今、竹本がトイレでいったい何をしているのか、本田には予測がついていた。
いや、すべて分かっていた。
<・・4章・完了>
(続く-5章へ)
次回掲載予定:4月28日金曜日
*人気ブログランキング参加中! 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ
連載小説「フォワイエ・ポウ」を通してお読みになりたい方、あるいはもう一度読み直したい方、こちらのカテゴリー「長編連載小説フォワイエ・ポウ」からご覧いただけます(こちらから入れます)。
時計は、いよいよ午後11時を回った。
(今夜はダメだ。もう、店を閉めるか・・・)
と思ったやさき、約3~4センチほどか?
店のドアが開いた。
<・・・上記、先回掲載分>
(いよいよ第4章の締めくくり。マスター本田には、新たな出会いと発見がある・・・)
毎日一回、クリック応援を!
 (人気ブログランキング)
(人気ブログランキング)--------------------------------------------------
長編連載小説『フォワイエ・ポウ』
著:ジョージ青木
4章
(新たな展開)
(2)-2
(誰なのか、客か?)
店の入り口の前に、たしかに人の気配がする。
本田は、とっさに声をかけた。
「いらっしゃいませ・・・」
「どうぞ! お入りください」
遠慮がちにドアが開く。
1人の男性が店に入る。
一見したところ、その男性客は20代前半の若者である。
「あの~ 今日、初めて来るのですが・・・」
「あの~ 私のようなものがこのお店に入ってもいいんでしょうか?」
「初めてのお客さまですね。大丈夫です。どうぞ、ご遠慮なくお入りください」
いささか小柄で細身の痩せ型、細面の顔つきは青白かった。若者らしからぬ生活の疲れが見え隠れする。始終うつむき加減の若者は、たえず遠慮がちなそぶりを見せ、何故か、はにかんでいた。
「当店は、会員制でも何でもありませんから、どうぞご遠慮なくお入りください、さ、さ、どうぞ!」
若い客を招き入れた時から、本田の萎えた気分はがらりと変化した。溜まった有毒な副産物は瞬時にして蒸発。たちまち消えてなくなっていた。
「どうぞ、カウンターへ、どうぞ・・・」
ドアを開いて入ってくる若者は、なぜか足元ばかりを見ており、本田と目を合わせようとしない。絶えず、うつむき加減の若者は、のろのろと歩きカウンター席の隅っこに腰をかけようとした。
「どうぞ、こちらにおかけ下さい」
若者に声をかけた本田は、カウンターの中ほどに手を差し向けながら、グラスとお絞りでセットした位置に案内する。
「あ、ありがとうございます」
カウンター席にかけた若者は、何かにおびえているように、萎縮し、表情を崩さず、身体は、椅子に座ったまま硬直させたままである。
「今日は早い時間にお客さんがいらしてましたが、日曜日ですからね、この時間になると暇になります・・・」
ここは、まず、本田の方から声をかけた。
「何かご用意しましょう。なにが宜しいですか?」
「お酒ください、いや、あの~・・・ お酒ありますか?」
「おさけ、日本酒ですか?」
「はあ~・・・ はい、そうです」
「申し訳ございません、当店は、日本酒をおいていないんです」
「そうだ、そうですね。でしたら、ウイスキーを・・・」
「はい、分かりました。銘柄は、何が宜しいですか?」
「あ~そうか・・・」
若者は、銘柄を決めるのに戸惑っている。
というよりも、ウイスキーの銘柄がよく分かっていない。こんな若者を気の毒に思った本田は、彼に助け舟を出そうと思った。丁寧に、親切に分かりやすく、まして自尊心を傷つけないように、この若者に対応しようと決めた。
「もう、どこかでお酒飲んでらっしゃいますよね?」
「はい、ご飯食べながら、ビールを少し、それから、日本酒も飲んできました・・・」
(若者の顔が少し青白いのは、すでに酔っ払っている証拠だ、加えて、かなり飲んでいるに違いない!)
と、ここでようやく本田は気付いた。
「まだ飲めますか?」
本来、こういう質問は客に失礼であり、それなりの客に対しては侮辱にもなりかねない危険な質問であったが、この若者には、あえて質問した。
「ハア~ もう少し、飲みたいです。高くてもおいしいお酒を呑みたいのです。ですからマスター、何か、マスターのお勧めを教えて下さい。そして、それを飲みます。どのウイスキーがおいしいですか、マスターにお任せします」
いささか対応に困った。
この店を初めて訪れた客、しかもあまり洋酒のことが分かっていない若者に対し、いくら高級な酒が飲みたいと要求されても、限度を考えなければならない。
ワンショットで5千円以上、そんな高価なウイスキーもある。この店にも置いてある。がしかし、たぶん彼にはその価値が分からないはず。たとえ客からの要請があったとしても、こんな高価な酒を彼には勧められない。必ず、びっくり仰天するであろう。あれこれと、それなりに、本田はこの若者に気をつかっていた。
(ならば、どうするか?)
少し考えて、オールドパーを取り出した。
「どれをお勧めしようかな? そう、まず、バーボンよりもスコッチの方がいいでしょう。これ、オールドパーです。これにしましょう」
ボトル棚から取り出した新しいオールドパーのボトルを手に取った本田は、あらためて若者に見せた。オールドパーは、本田の好きなスコッチウイスキーのひとつであったし、もちろん、すでに封を切っているボトルもある。しかしこの際、この若者に対し、且つ、日曜日の珍客に対して、本田自身の敬意を表したく、ここは敢えて新しいボトルを開けることにした。
うつむきかげんのうつろな眼だった若者の目は、ようやく活気を取り戻し、その視線は、はっきりとボトルに向けられた。
「はあ~、オールドパー、ですね?」
「そうです」
「そう、それ頂きます。お願いします」
「はい、わかりました。それで、どうしましょう?」
「ロックにしますか、それとも水割り?・・・」
若者は即答した。
「いいえ、ストレートで、お願いします」
「はい、では、ストレートで・・・」
と、返答したものの、本田は迷った。
(大丈夫かな、かなり飲んでいるようだが、ストレートを飲んだあげく、ここで酔っ払って、あげくの果ては眠むってしまうか、まして、暴れてもらっても困るのだが・・・)
めったに使わないストレートグラスを、棚から取り出した。
小さなストレートグラスを、おもむろに若者の前に置いた。
さらに若者の座っているカウンターの正面に立ち、まったく封を切っていないオールドパーのボトルを置いた。
(ちょいと、見せておいてやろう)
目の前の若者に対し、全ての動きを見せる演出を思い立ち、即興の演出を即座に自作自演した。
彼の目の前で全ての動作を見せる。
まずはボトルの封を切って見せ、
若者の目の前にあるストレートグラスに、
封を切ったばかりのオールドパーを、
ぎりぎりグラス一杯まで、注ぎ、
グラスを満たした液体が、
グラスから溢れ出す一歩寸前で、
本田の動作は止まった。
「お待たせしました」
「オールドパーのストレートです」
「どうぞ、召し上がれ・・・」
いかにも青白く、活気のなかった若者の表情がにわかに豊かになった。腐りかかっていた目は、正常な輝きを取り戻している。そんな若者の目線は、本田の動作の一部始終を見守っていた。
「ありがとうございます、いただきます」
若者の右手が小さなストレートグラスに伸びた。そのままグラスを持ち上げると、いや、グラスに触っただけでも、その瞬間、中の液体はグラスの外にこぼれ出す。
しかし、手が伸びると同時に、今までうなだれていた顔が動き、口が突き出てきた。右手がグラスに届くのとほぼ同時に、若者の唇がグラスに届いていた。
グラスに届いた若者の唇は、半端なストローよりも上手く、グラスの中のアルコールを吸い上げる。差し出した右手が、わずかにグラスを持ち上げたときには、すでにグラスの中の液体は半分に減っていた。中身が半分になったグラスを自分の目で確かめた若者は、再び、グラスをカウンターに置いた。
「ああ~、おいしい・・・ ほんとうに、美味しいです」
にわかに若者の顔がほころび、ようやく笑みが出た。
「チューハイより、おいしいです」
(焼酎と比べてもらっては困るんだよな~)
と、言いたかったが、けっして本田は口に出さず、無言の笑顔で答えた。答えの代わりに、若者に質問した。
「お客さん、チューハイは、お好きですか? 焼酎はお好きですか?」
「・・・」
若者からは、すぐには答えが帰らなかった。
この時代、ようやく焼酎が近年の市民権を得た頃だった。今日のように、日本全国各都道府県にまたがり数え切れないほどの焼酎は市中に出回っていなかった。わずかに、麦焼酎と芋焼酎等、数点が飲み屋にある時代であった。当時のチューハイなど、今になって想えば、おしゃれな飲み物であったかもしれない。しかし当時の焼酎は、やはり、労働者っぽいノミスケノのための酒であった。
思わず(チューハイより美味しい!)と、声を発した若者は、マスターの本田に対し、いささか恥ずかしい思いをしていた。だから、本田の質問に、答えられなかった。
「今まで別の居酒屋で、今日も一人で、チューハイ飲んでいました」
「あ~ そうだったの」
「日本酒じゃなくて、焼酎飲だったの」
「そうです」
「そうなんだ」
「家でも、いや、寮で飲むのも、焼酎の水割りです」
「寮に住んでいるのですか?」
「そうです、自動車メーカーに勤めていますから、今は社員寮に住んでいます」
「そうですか・・・」
「あ、遅くなりましたが自己紹介します」
「わたしは、竹本です。それで、みんなから竹ちゃんと呼ばれています。ここでも今からは『たけちゃん』と呼んでください」
「竹本さん、竹ちゃん、はい、竹ちゃん、私、本田と申します、宜しくお願いします」
「マスターは、本田さんですね」
「・・・」
本田は微笑みながら頷いた。
竹本は、話を続けた。
「でも、お名前は直接呼べません、私からは、今から『マスター』と云います」
話し始めた若者、竹本は、なぜか元気を取り戻していた。来店した時の陰鬱な雰囲気、負け犬のような悲惨な表情は、すでに、どこかに消えてなくなっていた。
「ところでマスター、ここは初めてじゃないんです」
話題を変えた竹ちゃんは、あらためて真剣な表情になった。
「この2週間で3回、来ました。でも、いつも入り口まできたら足がすくんでしまって、店の中に入れないんです、一度はドアを開けて、店の中をのぞいたのですが・・・」
「・・・」
やさしく頷くだけにとどめた本田は、しばらく無言を通した。いや、敢えて本田から言葉をはさまないようにしながら、ひとまず、竹本の気分を楽にさせ、彼の話したい事を引き出し、詳しく聞いてみたいと思った。
「日曜日に店が開いているとは、思いませんでした・・・」
「はい、日曜日もあけますよ」
「でも今日はよかった、ようやく店に入ることができました」
竹本の話は続いた。
「僕は山口県の出身です。高校卒業して直ぐに、広島の自動車工場に就職しました。工業高校だったから、事務員ではなく工員で入社したんです。勤務シフトのほとんどが夜勤ですから、普通のサラリーマンがお酒飲むときに僕たちは仕事を始めるんです。夜勤があけたらもう朝になります。もう、くたくたです。会社の社員食堂で朝ごはんを食べたら、まっすぐ寮に帰ってお風呂に入る。ゆっくり、入れませんから、いつもカラスの行水です。ほとんどシャワーを浴びたら終わりです。だから、からだにまみれた汗と油と埃が染み付いてしまって、カラスの行水では完全に油が落ちない。だから油の臭いが染み付いているから恥ずかしくて、スーツを着ている人ばかりが集まるこんなお店には入りたくても入れないんです。こんなお店には・・・」
「いや、竹本さん・・・」
本田が若者の話しをさえぎろうとした。
本田が話かけたとたん、今度は竹本が話をさえぎった。
「マスター、竹ちゃんと呼んでください。そのほうが、僕に似合っている、マスターから竹ちゃんといっていただくほうが、僕はうれしいのです」
「では、竹ちゃんと呼びますよ」
あらためて、本田は竹ちゃんに語り始めた。
「竹ちゃん、そんなことないよ。油の臭いなんて、ぜんぜんしない。手もきれいだし、服装も清潔そのもの。私は全然気にならないし、竹ちゃんはとても工員なんかには見えません。第一私にとって、お客さんの職業なんてものは関係ない。どんな職業だって、仕事をする事はたいへん立派な事だ。私が一番嫌いな人間はね、半端な不良と安物のやくざです。ゴロゴロよたよた、まともな仕事をしないで人に迷惑かけながら遊んで生きている人間、私は大嫌いだ。そんな奴が世の中で一番みっともない!」
竹本は、静かに本田の話を聞いていた。本田の話にしっかりと耳を傾けながらも、彼の目はにわかに潤みはじめた。光るものが浮かんできた。しかし、本田の話は続く。竹本の涙をみた本田は、それでも話を途絶えさせなかった。
「とにかく雰囲気的に、竹ちゃんから漂ってくるもの、それは石鹸のにおいだ。若者には、清潔な石鹸の香りが一番にあうのですよ。だから、私から見れば竹ちゃんは、すてきな若者です。そんな若者に来ていただけるなんて、当店は大歓迎です。今度からそんな遠慮は必要ない。遠慮なく、いつでも好きな時に店に入って来てください。大丈夫だから・・・」
本田がここまで話しを続けた時、竹ちゃんの両目から大粒の涙が数滴、カウンターにこぼれた。竹本は、自分の泣き顔を隠そうとはしなかったし、涙も拭き払おうとはしなかった。カウンターの中の本田は、話を中断した。しかし、平然とした表情で若者の顔を見つめたまま、目を離そうとはしなかった。
天上に釣上げられた大きなスピーカーから、ゆとりをもって流れ出る静かなモダンジャズ。端正なピアノ演奏に語りかける、マリンバの音の流れ。ドラムからのシャープな音は、スローテンポのメロディーにめりはりをつける。流れ出るモダンジャズの曲を縫い合わせるように、2人の沈黙は続いた。
沈黙は、数分続いた。
一言も声をかけない本田に対し、ようやく竹本は口を開いた。
「マスター、お話の途中、すみません。ちょっとトイレに行ってきます」
と言いながら、トイレに駆け込んだ竹本はしばらく出てこなかった。
今、竹本がトイレでいったい何をしているのか、本田には予測がついていた。
いや、すべて分かっていた。
<・・4章・完了>
(続く-5章へ)
次回掲載予定:4月28日金曜日
*人気ブログランキング参加中!
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ 連載小説「フォワイエ・ポウ」を通してお読みになりたい方、あるいはもう一度読み直したい方、こちらのカテゴリー「長編連載小説フォワイエ・ポウ」からご覧いただけます(こちらから入れます)。