
わけいってもわけいっても青い山
山深く咲いているのは蕗(ふき)のとうだけ
うしろすがたのしぐれてゆくか
たどりきていまだ山裾
あるいて水音のどこまでも
山しづかなれば笠ぬいでゆく
樹が倒れている腰をかける
鴉(からす)啼いてわたしも一人
鈴をふりふりお四国の土になるべく
霧島は霧にかくれて赤とんぼ
まつすぐな道でさみしい
また見ることもない山が遠ざかる
おちついて死ねそうな草萠ゆる
朝は澄みきっておだやかな流れひとすじ
夕焼うつくしく今日一日つつましく
山頭火の俳句は、自由律俳句と呼ばれる。自由律とは、明治時代後期、河東碧梧桐が新傾向俳句を創作したことに始まるといわれる。「五七五の定型俳句や五七五七七の定型短歌に対し、音数にとらわれない主張、またはその作品。俳句では季語にも縛られず、心の動きをそのまま自由に、かつ自然に表現するとする主張もあるが、通常は一句一律、内容に即した律を持つという主張である。これを内在律ともいう」。(フリー百科事典)
若い頃、近所の大学の「短歌会」に部外者として参加させてもらったことがある。いわゆる現代短歌というやつで、地元で「現代短歌シンポジュウム」などもあり、第一線の歌人たちも数多く出席した。その頃から短歌の上の句で世界観を、下の句で「私」に落とし込む手法の虜になった。その頃は山頭火のことを知らなかったが、改めて山頭火を読むと、一人であることの寂しさ、素朴な味わいが心に沁みる。
種田 山頭火(たねだ さんとうか、1882年12月3日(明治15年) - 1940年10月11日(昭和15年))は「明治・大正・昭和初期にかけての俳人。自由律俳句のもっとも著名な俳人の一人。曹洞宗の僧侶。本名・種田正一。山口県西佐波令村(現・山口県防府市大道)の大地主の出身」。
「11歳の時、母が自殺。旧制山口中学(現山口県立山口高等学校)から早稲田大学文学部に入学するが神経衰弱のため中退。帰省し療養の傍ら家業である造り酒屋を手伝う。1910年(明治43年)結婚し一児をもうける。1911年(明治44年)荻原井泉水の主宰する俳句雑誌『層雲』に寄稿。1913年(大正2年)井泉水の門下となる。1916年には、『層雲』の選者に参加」。
「その後、家業の造り酒屋が父親の放蕩と自身の酒癖のため破産。妻子を連れ熊本市に移住。古本屋を営むがうまくいかず、1920年(大正9年)離婚。妻子を捨てて東京へ出奔。その後、弟と父親は自殺。1923年(大正12年)関東大震災に遭い熊本の元妻のもとへ逃げ帰る。生活苦から自殺未遂をおこしたところを市内の報恩禅寺(千体佛)住職・望月義庵に助けられ寺男となる。1924年(大正14年)得度し『耕畝』と名乗る」。
「1925年(大正15年)寺を出て雲水姿で西日本を中心に旅し句作を行う。1932年(昭和7年)郷里山口の小郡町(現・山口市小郡)に「其中庵」を結庵。1939年(昭和14年)松山市に移住し「一草庵」を結庵。翌年、この庵で生涯を閉じた。享年57」。
「自由律俳句の代表として、同じ井泉水門下の尾崎放哉と並び称される。山頭火、放哉ともに酒癖によって身を持ち崩し、師である井泉水や支持者の援助によって生計を立てていたところは似通っている。しかし、その作風は対照的で、「静」の放哉に対し山頭火の句は「動」である」。(フリー百科事典)
山深く咲いているのは蕗(ふき)のとうだけ
うしろすがたのしぐれてゆくか
たどりきていまだ山裾
あるいて水音のどこまでも
山しづかなれば笠ぬいでゆく
樹が倒れている腰をかける
鴉(からす)啼いてわたしも一人
鈴をふりふりお四国の土になるべく
霧島は霧にかくれて赤とんぼ
まつすぐな道でさみしい
また見ることもない山が遠ざかる
おちついて死ねそうな草萠ゆる
朝は澄みきっておだやかな流れひとすじ
夕焼うつくしく今日一日つつましく
山頭火の俳句は、自由律俳句と呼ばれる。自由律とは、明治時代後期、河東碧梧桐が新傾向俳句を創作したことに始まるといわれる。「五七五の定型俳句や五七五七七の定型短歌に対し、音数にとらわれない主張、またはその作品。俳句では季語にも縛られず、心の動きをそのまま自由に、かつ自然に表現するとする主張もあるが、通常は一句一律、内容に即した律を持つという主張である。これを内在律ともいう」。(フリー百科事典)
若い頃、近所の大学の「短歌会」に部外者として参加させてもらったことがある。いわゆる現代短歌というやつで、地元で「現代短歌シンポジュウム」などもあり、第一線の歌人たちも数多く出席した。その頃から短歌の上の句で世界観を、下の句で「私」に落とし込む手法の虜になった。その頃は山頭火のことを知らなかったが、改めて山頭火を読むと、一人であることの寂しさ、素朴な味わいが心に沁みる。
種田 山頭火(たねだ さんとうか、1882年12月3日(明治15年) - 1940年10月11日(昭和15年))は「明治・大正・昭和初期にかけての俳人。自由律俳句のもっとも著名な俳人の一人。曹洞宗の僧侶。本名・種田正一。山口県西佐波令村(現・山口県防府市大道)の大地主の出身」。
「11歳の時、母が自殺。旧制山口中学(現山口県立山口高等学校)から早稲田大学文学部に入学するが神経衰弱のため中退。帰省し療養の傍ら家業である造り酒屋を手伝う。1910年(明治43年)結婚し一児をもうける。1911年(明治44年)荻原井泉水の主宰する俳句雑誌『層雲』に寄稿。1913年(大正2年)井泉水の門下となる。1916年には、『層雲』の選者に参加」。
「その後、家業の造り酒屋が父親の放蕩と自身の酒癖のため破産。妻子を連れ熊本市に移住。古本屋を営むがうまくいかず、1920年(大正9年)離婚。妻子を捨てて東京へ出奔。その後、弟と父親は自殺。1923年(大正12年)関東大震災に遭い熊本の元妻のもとへ逃げ帰る。生活苦から自殺未遂をおこしたところを市内の報恩禅寺(千体佛)住職・望月義庵に助けられ寺男となる。1924年(大正14年)得度し『耕畝』と名乗る」。
「1925年(大正15年)寺を出て雲水姿で西日本を中心に旅し句作を行う。1932年(昭和7年)郷里山口の小郡町(現・山口市小郡)に「其中庵」を結庵。1939年(昭和14年)松山市に移住し「一草庵」を結庵。翌年、この庵で生涯を閉じた。享年57」。
「自由律俳句の代表として、同じ井泉水門下の尾崎放哉と並び称される。山頭火、放哉ともに酒癖によって身を持ち崩し、師である井泉水や支持者の援助によって生計を立てていたところは似通っている。しかし、その作風は対照的で、「静」の放哉に対し山頭火の句は「動」である」。(フリー百科事典)










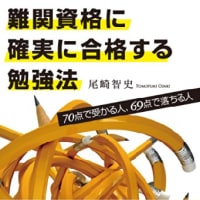
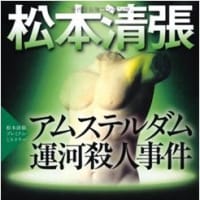
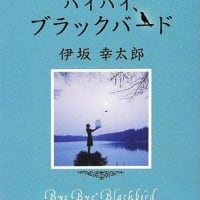

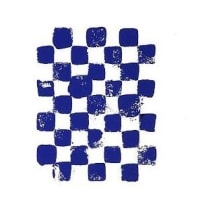
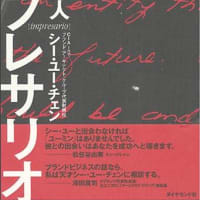



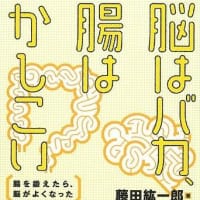
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます