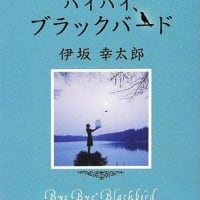ドイツ三部作の最後の作品「文づかひ」(1891年)を書いて、次作「鶏」までの18年間は主だった作品は書かれていません。軍医だった鴎外にはその時間がなかったのですね。1894年(明治27年・33歳)8月、日清戦争開戦すると、軍医部長として中国(盛京省花園口)へ上陸。翌年、1895年(明治28年・34歳)5月、日清講和条約成立に伴い、日本(宇品)に帰国後、台湾へ赴任。8月、台湾総督府陸軍局軍医部長になっています。
鴎外は、1902年(明治35年・41歳)1月、大審院判事荒木博臣の長女・志げと再婚。3月、東京に転勤。1904年(明治37年・43歳)2月、今度は日露戦争が開戦します。4月、第2軍軍医部長として、宇品から、中国へ渡ります。1904年(明治37年)から1906年(明治39年)まで日露戦争に第二軍軍医部長として出征し、1907年(明治40年)には陸軍軍医総監・陸軍省医務局長に任じられています。このころまでは文士としては翻訳が中心でした。
1909年(明治42年)に『スバル』が創刊されるとともに、鴎外の作家としての活躍が再開されます。「半日」(1909年3月)、「魔睡」(1909年6月)、問題作「ヰタ・セクスアリス」(1909年7月)と立て続けに作品を発表していきます。そして、「鶏」の発表となります。
「鶏」・・・・・・・・・・・・・・・(48歳、1909年8月、「スバル」)
「鶏」は8月に発表されました。その前の5月に次女・杏奴誕生し、7月、文学博士の学位を得ています。この小説は、小倉に赴任した少佐参謀・石田小介の借家住まいでの使用人をめぐる小話のような作品になっています。東京から新に雇った別当の虎吉。「別当」というのがよくわかりませんが、別の資料によると、「馬車には、御者と別当(車掌にあたる)が乗務員として乗り込む」とあります。(「御者」は馬車の前部に乗って馬を操り、馬車を走らせる人)
次ぎの一節がこの物語を象徴しています。
「石田はこんな事を思っている。鶏は垣を越すものと見える。坊主が酒を般若湯(はんにゃとう)ということは世間に流布しているが、鶏を鑽籬菜(さんりさい)ということは本を読まないものは知らない。鶏を貰った処が、食いたくもなかったので、生かして置こうと思った。生かして置けば垣も越す。垣も越すかも知れないということまで、初めに考えなかったのは、用意が足りないようではあるが、何を為するにもそんなeventualiteを眼中に置いては出来ようがない。鶏を飼うという事実に、こん女(雇い婆さん)が怒るという事実が附帯して来るのは、格別驚くべきわけでもないにしろ、あの垣の上に妙な首が載っていて、その首が何の遠慮もなく表情筋を伸縮させて、雄弁を揮っている処は面白い。東京にいた時、光線の反射を利用して、卓の上に載せた首が物を言うように思わせる見世物を見たことがあった。あれば見世物師が余りpretentieuxであったので、こっちの反感を起こして面白くなかった。あれよりが此方が余程面白い。石田はこんなことを思っている」。
*「鑽」;金属を切断したり削ったりするのに用いる鋼鉄製の手工具。木工に用いる鑿(のみ)にあたる。
*「籬」;竹や柴などで目を粗く編んだ垣根。ませ。ませがき。遊郭で、遊女屋の入り口の土間と店の上がり口との間の格子戸
*eventualite(仏)、エヴァンチュチュリアリテ。偶発事、不測の事件。
*pretentieux(仏)、プレタンショー。わざとらしい。気取ったの意
「かのように」・・・・・・・・(51歳、1912年1月、「中央公論」)
元岩手大学 工学部教授の宮本裕(ゆたか)さんHPに本作に関する一文がありました。
「森鴎外は本当に穏健保守の人だった。体制を壊すよりはなんとか守ろうとした。小説『かのように』のテーマは、歴史学における神話と科学の調和の問題であった。わが国の歴史は戦前においては天孫降臨から始められていた。即ち神話は絶対的に歴史に重なっていた」。
「歴史学を専攻する主人公は、学者の良心として、そのような立場を是認することはできない。だがしかし、天孫降臨神話を否定すれば、日本の大切な『御国柄』の根本が失われてしまう。子爵家に生まれた主人公は、そういう「危険思想」を公表することができない」。
「主人公は、神話と学問の間にはさまれて、ノイローゼに陥る。誰でも、そういう矛盾に気がつけば悩むであろう。そういう時、鴎外はファイヒンゲルの『かのやうにの哲学』を読んで、これを解決に使おうと考えたのであろう」。
「ファイヒンゲルによれば、すべての価値は『意識した嘘』の上に成立している。即ち『かのやうに』という仮定の上に立っている。幾何学でいう、線とは長さだけあった幅はないという仮定。あるいは、点とは位置だけあって大きさはないという仮定を考えてみるとよい。幅のない線、位置だけあって、大きさのない点などは実際に存在しないが、そういう点や線を、あるかのやうに仮定しなければ幾何学は成立しない」。
「この『かのやうに』理論を、主人公はファイヒンゲルから借用すれば、神話は事実ではないが、事実であるかのやうに扱うことによって、『御国柄』と矛盾しない歴史学が構築できることになる
そういうことに気がついた」。
「真相は、森鴎外は大逆事件に心配した山県有朋から危険思想対策を求められ、それに応じて書いたのが、この『かのやうに』であったという。妥協折衷の立場であったが、鴎外なりに矛盾を解決する方法を、ドイツの文献から探してきて、なんとか説明したことに、彼の真面目さを感じる」。
「もちろん、その矛盾は説明だけで解決するものではなく、後の歴史を見れば明らかなように、学問の真実を追究することが大事で、皇族ですら鴎外のこの説明の苦しさと欠点を理解したであろうことは、推察できる。徹底的に批判的な人間として生きて、上から送られることになった博士号ですら辞退した夏目漱石と、体制をなんとか守ろうと良心的に苦労した森鴎外」。
「二人は時間を超えて、同じ家に住んでいたらしい。明治村に二人が住んだことのある住居が保存されている。そして、二人は明治天皇の崩御の時、明治と自分たちの時代が終わったことを感じた。明治人の二人は、乃木希典の殉死にショックを受けた。そして、その感動を作品に発表した」。
「阿部一族」・・・・・・・・・(52歳、1913年1月、「中央公論」)
「阿部一族」は、「森鴎外の短編小説。1913年1月に『中央公論』誌上に発表した。1912年に発表した鴎外にとって初の歴史小説となった『興津弥五右衛門の遺書』とともに乃木希典陸軍大将の殉死に刺激されて書かれた小説で、殉死を巡る諸問題を分析し、封建主義社会の倫理の現実性をたずねた作品」。
まず、この作品に登場する細川忠利について。

<天正14年(1586)~寛永18年(1641)>「丹後国宮津城主長岡忠興の3男として生まれる。母は細川ガラシャ。慶長5年正月15歳で江戸へ証人として差し出され、関ケ原の戦には徳川秀忠の供として参加、慶長8年秀忠の意によって長岡から細川に改姓した。慶長14年月、徳川秀忠の養女、千代姫と婚姻。元和元年家督を継ぎ豊前・豊後三十六万石藩主となる。寛永9年加藤忠広が改易されると後、肥後への移封を命ぜられ五十四万石を領する。寛永14年の島原の乱には子の光尚とともに出陣した」。
内容は、次のような物語です。
「肥後藩主細川忠利の死に際して、忠勤に励んでいた阿部弥一右衛門は当然殉死を許される立場にあったが、藩主の「生き残り、息子を助けよ」との遺言により、殉死が許されなかった。しかし、生命を惜しんでいるように見る家中の目に憤激して切腹するが、命令に背いたことが問題となり、一族は藩から殉死者の遺族として扱われず、家格を著しく落とす事になった」。
「苦しんだ嫡子・権兵衛の先君の一周忌の席上で髻(もとどり)を切る行為も非礼と見られ盗賊同様の縛り首にされる。度重なる恥辱に意を決した次男・弥五兵衛を中心に一族は屋敷に立て篭もり、討手と一族の壮絶な戦いの末、全滅する」。
* 「髻」、《「本取り」の意》髪を頭の上に集めて束ねた所。また、その髪。たぶさ。
敬愛する「松岡正剛の千夜一夜」にこの小説について次のような記述がありました。長くなりますが、あらすじも書かれているのでそのまま引用します。
「阿部一族」(http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0758.html)
「かくして鴎外は、『遺書』の翌年に『阿部一族』を書く。またまた殉死を扱ったばかりでなく、『遺書』に登場した三代藩主細川忠利の死と四代光尚の代替わりの“あいだ”を凝視した。当時の殉死は『亡君許可制』であるにもかかわらず、許可なく追腹を切った者も、結果としては武家社会の誉れとして同格に扱われた。この『制度』と『生き方』が組み合っておこす矛盾や溝を原因に、さまざまな悲劇がおこる。鴎外はそこに着目する」。
「たとえば、主君に願い出て殉死を許された者はよいが、主君の許可が出ず、やむなく日々のことに従事している者には、『おめおめと生きながらえている』『命を惜しんでいる』という評が立った。鴎外自身も自分の『おめおめ』が一番嫌いだったのだが、『阿部一族』の阿部弥一右衛門も、この『命を惜しんでいる者』とみなされた一族の長だった。しかし、どうすれば弥一右衛門は『あっぱれ』に組み入ることができるのか」。
「出来事は二段、三段、四段に深まっている。鴎外がそのような段取りを作ったのではなく、事実、そういう出来事が続いた。そこを鴎外が『簡浄の文』をもって抜いてみせた。ざっとは、次のような出来事が連続しておこったのである」。
「主君の忠利が卒去した。その日から殉死者が十余人出た。荼毘に付された日には忠利が飼っていた二羽の鷹が空を舞っていたが、人々が見守るなか、その鷹が二羽とも桜の下の井戸にあっというまに飛び込んだ」。
「中陰がすぎても殉死はぽつぽつあった。17歳の内藤長十郎はかねて主君の夜のお供として病いに罹った主君の足など揉んでいたのだが、あるとき死期の近づく主君に、そのときは殉死する覚悟なのでお許し願いたい旨をおそるおそる申し出た。許可はなかったので長十郎は家来のいる折、主君の足を揉むままにその足を額に当て、再度の追腹の許可を願った。主君は軽く二度頷いた」。
「長十郎は嫁をもらったばかりであったが、母に殉死の覚悟を伝えると、少しも驚かず嫁に支度をさせなさいとだけ言った。長十郎は菩提所東光院にて腹を切った。結局、この長十郎を加えて18人の殉死者が出た。しかし弥一右衛門はそれまで主君を諌める言動をしていたせいか、忠利にはその存在が煙たく、『どうか光尚に奉公してくれい』と言うばかり、いっこうに殉死の許可をもらえない。煙たいから死んでよいというのではない。煙たい奴には武士の本懐の死などを下賜できないということなのだ」。
「18人の殉死者が出てしばらくして、『阿部はお許しがないのをさいわいに、おめおめ生きるつもりであるらしい。瓢箪に油を塗って切りでもすればいい』という噂が立った。憤然とした弥一右衛門は家の門を集めて、自分はこれから瓢箪に油を塗って切るから見届けられたいと言うと、子供たちの前で腹を切り、さらに自分で首筋を左から右に貫いて絶命した。子供たちは悲しくはあったが、これで重荷を下ろしたような気がした」。
「ところが、である。城内では誰も弥一右衛門の覚悟の死を褒めないばかりか、残された遺族への沙汰には『仕打ち』のようなものがあった。寛永19年3月、先代の一周忌がやってきた。父の死が報われていないことを知った子の権兵衛は、焼香の順番がきて先代の位牌の前に進み出たときに、脇差の小柄を抜いて自身の髻(もととり)を押し切って仏前に供えた。家来が慌てて駆け寄り、権兵衛を取り押さえて別室に連れていくと、権兵衛は『父は乱心したのではない、このままでは阿部の面目が立たない、もはや武士を捨てるつもりだ、お咎めはいくらでも受ける』と言った」。
「新しい藩主光尚はこれをまたまた不快におもい、権兵衛を押籠めにした。一族は協議のうえ、法事に下向していた大徳寺の天祐に頼んで処置を頼むのだが、権兵衛は死罪との御沙汰、ではせめて武士らしく切腹をと願い出るのだが、これも聞き入れられず、白昼の縛首となって果てた。こうして阿部一族が立て籠もることになった」。
「藩内では討手が組まれ、表門は竹内数馬が指揮をする。阿部一族のほうでは討手の襲撃を知って、次男の弥五兵衛を中心に邸内をくまなく掃除し、見苦しいものはことごとく焼き捨て、全員で密かに酒宴を開いたのち、老人や女たちはみずから自害し、幼いものたちは手ん手に刺しあった。残ったのは屈強の武士たちばかりとなった」。
「阿部一族が立て籠もった山崎の屋敷の隣に、柄本又七郎という人物がいた。弥五兵衛とは槍を習い嗜(たし)みあう仲だった。又七郎は弥五兵衛一族の『否運』に心痛していた。そこで女房を遣わせて陣中見舞をさせた。一族はこれを忝けなくおもい、『情』(なさけ)を感じる。しかし又七郎は、『情』と『義』とは異なることも知っていた。ここは『義』を採って討手に加わるべきだと決意する。そのために阿部屋敷の竹垣の結縄を切ることにした」。
「一方、討手の竹内数馬はこの討伐をもって討死するつもりであった。それまで近習として何の功績をあげていないのを、ここで主君の御恩を果たしきるつもりだったのである。そこで前夜、数馬は行水をつかい月代(さかやき)を剃り、髪には先代を偲んで『初音』を焚きしめた。白無垢白襷白鉢巻をして、肩に合印の角取紙を、腰に二尺四寸五分の正盛を差し、草鞋の緒を男結びにすると、余った緒を小刀で切って捨て、すべての準備を整えた」。
「卯の花が真っ白く咲く払暁である。怒涛のような戦闘が始まった。弥五兵衛は早々に又七郎と槍を交えたのだが、ちょっと待ていと言って奥に下がって、切腹した。切腹できたのは弥五兵衛一人、そのほかの者はことごとく討死であった。数馬も討死である。かくて阿部一族は消滅した。又七郎は傷が癒えたのち光尚に拝謁し、鉄砲十挺と屋敷地を下賜され、その裏の薮山もどうかと言われたが、これを断った」。
「阿部一族の死骸はすべて引き出されて吟味にかけられた。又七郎の槍に胸板を貫かれた弥五兵衛の傷は、誰の傷よりも立派だったので、又七郎はいよいよ面目を施した」。
「以上が鴎外の記した顛末である。いくら『お家大事』の江戸初期寛永の世の中とはいえ、異常きわまりない話である。いったいどこに『価値』の基準があるかはまったくわからない。たしかに『建前』はいくらもあるが、それとともに人間として家臣としての『本音』もあって、それがしかも『建前』の中で徹底されていく」。
「『情』と『義』も、つぶさに点検してみると、どこかで激突し、矛盾しあっている。どこに『あっぱれ』があるかもわからない。鴎外は『遺書』や『阿部一族』をまとめて『意地』という作品集に入れるのであるが、その『意地』とは、いつ発揮されるかによってまったく印象の異なるものだった」。
「しかし鴎外はそのような史実の連鎖にのみまさに目を注いだのである。もし意地や面目というものがあったとしたら、それは乃木大将のごとく最後の最後になって何かを表明すべきものもあったのである。鴎外も『鴎外最後の謎』とよばれるものを作った。自分の墓には森鴎外という文字を入れてはならない、ただ森林太郎と残してほしいと遺言したことである。『余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス』と」。
「こうした決意を鴎外がどこでしたのかは明確になっていないけれど、ぼくはあきらかに明治が瓦解していったときのこと、すなわち『興津弥五右衛門の遺書』と『阿部一族』のあたりだったと思っている」。
鴎外は、1902年(明治35年・41歳)1月、大審院判事荒木博臣の長女・志げと再婚。3月、東京に転勤。1904年(明治37年・43歳)2月、今度は日露戦争が開戦します。4月、第2軍軍医部長として、宇品から、中国へ渡ります。1904年(明治37年)から1906年(明治39年)まで日露戦争に第二軍軍医部長として出征し、1907年(明治40年)には陸軍軍医総監・陸軍省医務局長に任じられています。このころまでは文士としては翻訳が中心でした。
1909年(明治42年)に『スバル』が創刊されるとともに、鴎外の作家としての活躍が再開されます。「半日」(1909年3月)、「魔睡」(1909年6月)、問題作「ヰタ・セクスアリス」(1909年7月)と立て続けに作品を発表していきます。そして、「鶏」の発表となります。
「鶏」・・・・・・・・・・・・・・・(48歳、1909年8月、「スバル」)
「鶏」は8月に発表されました。その前の5月に次女・杏奴誕生し、7月、文学博士の学位を得ています。この小説は、小倉に赴任した少佐参謀・石田小介の借家住まいでの使用人をめぐる小話のような作品になっています。東京から新に雇った別当の虎吉。「別当」というのがよくわかりませんが、別の資料によると、「馬車には、御者と別当(車掌にあたる)が乗務員として乗り込む」とあります。(「御者」は馬車の前部に乗って馬を操り、馬車を走らせる人)
次ぎの一節がこの物語を象徴しています。
「石田はこんな事を思っている。鶏は垣を越すものと見える。坊主が酒を般若湯(はんにゃとう)ということは世間に流布しているが、鶏を鑽籬菜(さんりさい)ということは本を読まないものは知らない。鶏を貰った処が、食いたくもなかったので、生かして置こうと思った。生かして置けば垣も越す。垣も越すかも知れないということまで、初めに考えなかったのは、用意が足りないようではあるが、何を為するにもそんなeventualiteを眼中に置いては出来ようがない。鶏を飼うという事実に、こん女(雇い婆さん)が怒るという事実が附帯して来るのは、格別驚くべきわけでもないにしろ、あの垣の上に妙な首が載っていて、その首が何の遠慮もなく表情筋を伸縮させて、雄弁を揮っている処は面白い。東京にいた時、光線の反射を利用して、卓の上に載せた首が物を言うように思わせる見世物を見たことがあった。あれば見世物師が余りpretentieuxであったので、こっちの反感を起こして面白くなかった。あれよりが此方が余程面白い。石田はこんなことを思っている」。
*「鑽」;金属を切断したり削ったりするのに用いる鋼鉄製の手工具。木工に用いる鑿(のみ)にあたる。
*「籬」;竹や柴などで目を粗く編んだ垣根。ませ。ませがき。遊郭で、遊女屋の入り口の土間と店の上がり口との間の格子戸
*eventualite(仏)、エヴァンチュチュリアリテ。偶発事、不測の事件。
*pretentieux(仏)、プレタンショー。わざとらしい。気取ったの意
「かのように」・・・・・・・・(51歳、1912年1月、「中央公論」)
元岩手大学 工学部教授の宮本裕(ゆたか)さんHPに本作に関する一文がありました。
「森鴎外は本当に穏健保守の人だった。体制を壊すよりはなんとか守ろうとした。小説『かのように』のテーマは、歴史学における神話と科学の調和の問題であった。わが国の歴史は戦前においては天孫降臨から始められていた。即ち神話は絶対的に歴史に重なっていた」。
「歴史学を専攻する主人公は、学者の良心として、そのような立場を是認することはできない。だがしかし、天孫降臨神話を否定すれば、日本の大切な『御国柄』の根本が失われてしまう。子爵家に生まれた主人公は、そういう「危険思想」を公表することができない」。
「主人公は、神話と学問の間にはさまれて、ノイローゼに陥る。誰でも、そういう矛盾に気がつけば悩むであろう。そういう時、鴎外はファイヒンゲルの『かのやうにの哲学』を読んで、これを解決に使おうと考えたのであろう」。
「ファイヒンゲルによれば、すべての価値は『意識した嘘』の上に成立している。即ち『かのやうに』という仮定の上に立っている。幾何学でいう、線とは長さだけあった幅はないという仮定。あるいは、点とは位置だけあって大きさはないという仮定を考えてみるとよい。幅のない線、位置だけあって、大きさのない点などは実際に存在しないが、そういう点や線を、あるかのやうに仮定しなければ幾何学は成立しない」。
「この『かのやうに』理論を、主人公はファイヒンゲルから借用すれば、神話は事実ではないが、事実であるかのやうに扱うことによって、『御国柄』と矛盾しない歴史学が構築できることになる
そういうことに気がついた」。
「真相は、森鴎外は大逆事件に心配した山県有朋から危険思想対策を求められ、それに応じて書いたのが、この『かのやうに』であったという。妥協折衷の立場であったが、鴎外なりに矛盾を解決する方法を、ドイツの文献から探してきて、なんとか説明したことに、彼の真面目さを感じる」。
「もちろん、その矛盾は説明だけで解決するものではなく、後の歴史を見れば明らかなように、学問の真実を追究することが大事で、皇族ですら鴎外のこの説明の苦しさと欠点を理解したであろうことは、推察できる。徹底的に批判的な人間として生きて、上から送られることになった博士号ですら辞退した夏目漱石と、体制をなんとか守ろうと良心的に苦労した森鴎外」。
「二人は時間を超えて、同じ家に住んでいたらしい。明治村に二人が住んだことのある住居が保存されている。そして、二人は明治天皇の崩御の時、明治と自分たちの時代が終わったことを感じた。明治人の二人は、乃木希典の殉死にショックを受けた。そして、その感動を作品に発表した」。
「阿部一族」・・・・・・・・・(52歳、1913年1月、「中央公論」)
「阿部一族」は、「森鴎外の短編小説。1913年1月に『中央公論』誌上に発表した。1912年に発表した鴎外にとって初の歴史小説となった『興津弥五右衛門の遺書』とともに乃木希典陸軍大将の殉死に刺激されて書かれた小説で、殉死を巡る諸問題を分析し、封建主義社会の倫理の現実性をたずねた作品」。
まず、この作品に登場する細川忠利について。

<天正14年(1586)~寛永18年(1641)>「丹後国宮津城主長岡忠興の3男として生まれる。母は細川ガラシャ。慶長5年正月15歳で江戸へ証人として差し出され、関ケ原の戦には徳川秀忠の供として参加、慶長8年秀忠の意によって長岡から細川に改姓した。慶長14年月、徳川秀忠の養女、千代姫と婚姻。元和元年家督を継ぎ豊前・豊後三十六万石藩主となる。寛永9年加藤忠広が改易されると後、肥後への移封を命ぜられ五十四万石を領する。寛永14年の島原の乱には子の光尚とともに出陣した」。
内容は、次のような物語です。
「肥後藩主細川忠利の死に際して、忠勤に励んでいた阿部弥一右衛門は当然殉死を許される立場にあったが、藩主の「生き残り、息子を助けよ」との遺言により、殉死が許されなかった。しかし、生命を惜しんでいるように見る家中の目に憤激して切腹するが、命令に背いたことが問題となり、一族は藩から殉死者の遺族として扱われず、家格を著しく落とす事になった」。
「苦しんだ嫡子・権兵衛の先君の一周忌の席上で髻(もとどり)を切る行為も非礼と見られ盗賊同様の縛り首にされる。度重なる恥辱に意を決した次男・弥五兵衛を中心に一族は屋敷に立て篭もり、討手と一族の壮絶な戦いの末、全滅する」。
* 「髻」、《「本取り」の意》髪を頭の上に集めて束ねた所。また、その髪。たぶさ。
敬愛する「松岡正剛の千夜一夜」にこの小説について次のような記述がありました。長くなりますが、あらすじも書かれているのでそのまま引用します。
「阿部一族」(http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0758.html)
「かくして鴎外は、『遺書』の翌年に『阿部一族』を書く。またまた殉死を扱ったばかりでなく、『遺書』に登場した三代藩主細川忠利の死と四代光尚の代替わりの“あいだ”を凝視した。当時の殉死は『亡君許可制』であるにもかかわらず、許可なく追腹を切った者も、結果としては武家社会の誉れとして同格に扱われた。この『制度』と『生き方』が組み合っておこす矛盾や溝を原因に、さまざまな悲劇がおこる。鴎外はそこに着目する」。
「たとえば、主君に願い出て殉死を許された者はよいが、主君の許可が出ず、やむなく日々のことに従事している者には、『おめおめと生きながらえている』『命を惜しんでいる』という評が立った。鴎外自身も自分の『おめおめ』が一番嫌いだったのだが、『阿部一族』の阿部弥一右衛門も、この『命を惜しんでいる者』とみなされた一族の長だった。しかし、どうすれば弥一右衛門は『あっぱれ』に組み入ることができるのか」。
「出来事は二段、三段、四段に深まっている。鴎外がそのような段取りを作ったのではなく、事実、そういう出来事が続いた。そこを鴎外が『簡浄の文』をもって抜いてみせた。ざっとは、次のような出来事が連続しておこったのである」。
「主君の忠利が卒去した。その日から殉死者が十余人出た。荼毘に付された日には忠利が飼っていた二羽の鷹が空を舞っていたが、人々が見守るなか、その鷹が二羽とも桜の下の井戸にあっというまに飛び込んだ」。
「中陰がすぎても殉死はぽつぽつあった。17歳の内藤長十郎はかねて主君の夜のお供として病いに罹った主君の足など揉んでいたのだが、あるとき死期の近づく主君に、そのときは殉死する覚悟なのでお許し願いたい旨をおそるおそる申し出た。許可はなかったので長十郎は家来のいる折、主君の足を揉むままにその足を額に当て、再度の追腹の許可を願った。主君は軽く二度頷いた」。
「長十郎は嫁をもらったばかりであったが、母に殉死の覚悟を伝えると、少しも驚かず嫁に支度をさせなさいとだけ言った。長十郎は菩提所東光院にて腹を切った。結局、この長十郎を加えて18人の殉死者が出た。しかし弥一右衛門はそれまで主君を諌める言動をしていたせいか、忠利にはその存在が煙たく、『どうか光尚に奉公してくれい』と言うばかり、いっこうに殉死の許可をもらえない。煙たいから死んでよいというのではない。煙たい奴には武士の本懐の死などを下賜できないということなのだ」。
「18人の殉死者が出てしばらくして、『阿部はお許しがないのをさいわいに、おめおめ生きるつもりであるらしい。瓢箪に油を塗って切りでもすればいい』という噂が立った。憤然とした弥一右衛門は家の門を集めて、自分はこれから瓢箪に油を塗って切るから見届けられたいと言うと、子供たちの前で腹を切り、さらに自分で首筋を左から右に貫いて絶命した。子供たちは悲しくはあったが、これで重荷を下ろしたような気がした」。
「ところが、である。城内では誰も弥一右衛門の覚悟の死を褒めないばかりか、残された遺族への沙汰には『仕打ち』のようなものがあった。寛永19年3月、先代の一周忌がやってきた。父の死が報われていないことを知った子の権兵衛は、焼香の順番がきて先代の位牌の前に進み出たときに、脇差の小柄を抜いて自身の髻(もととり)を押し切って仏前に供えた。家来が慌てて駆け寄り、権兵衛を取り押さえて別室に連れていくと、権兵衛は『父は乱心したのではない、このままでは阿部の面目が立たない、もはや武士を捨てるつもりだ、お咎めはいくらでも受ける』と言った」。
「新しい藩主光尚はこれをまたまた不快におもい、権兵衛を押籠めにした。一族は協議のうえ、法事に下向していた大徳寺の天祐に頼んで処置を頼むのだが、権兵衛は死罪との御沙汰、ではせめて武士らしく切腹をと願い出るのだが、これも聞き入れられず、白昼の縛首となって果てた。こうして阿部一族が立て籠もることになった」。
「藩内では討手が組まれ、表門は竹内数馬が指揮をする。阿部一族のほうでは討手の襲撃を知って、次男の弥五兵衛を中心に邸内をくまなく掃除し、見苦しいものはことごとく焼き捨て、全員で密かに酒宴を開いたのち、老人や女たちはみずから自害し、幼いものたちは手ん手に刺しあった。残ったのは屈強の武士たちばかりとなった」。
「阿部一族が立て籠もった山崎の屋敷の隣に、柄本又七郎という人物がいた。弥五兵衛とは槍を習い嗜(たし)みあう仲だった。又七郎は弥五兵衛一族の『否運』に心痛していた。そこで女房を遣わせて陣中見舞をさせた。一族はこれを忝けなくおもい、『情』(なさけ)を感じる。しかし又七郎は、『情』と『義』とは異なることも知っていた。ここは『義』を採って討手に加わるべきだと決意する。そのために阿部屋敷の竹垣の結縄を切ることにした」。
「一方、討手の竹内数馬はこの討伐をもって討死するつもりであった。それまで近習として何の功績をあげていないのを、ここで主君の御恩を果たしきるつもりだったのである。そこで前夜、数馬は行水をつかい月代(さかやき)を剃り、髪には先代を偲んで『初音』を焚きしめた。白無垢白襷白鉢巻をして、肩に合印の角取紙を、腰に二尺四寸五分の正盛を差し、草鞋の緒を男結びにすると、余った緒を小刀で切って捨て、すべての準備を整えた」。
「卯の花が真っ白く咲く払暁である。怒涛のような戦闘が始まった。弥五兵衛は早々に又七郎と槍を交えたのだが、ちょっと待ていと言って奥に下がって、切腹した。切腹できたのは弥五兵衛一人、そのほかの者はことごとく討死であった。数馬も討死である。かくて阿部一族は消滅した。又七郎は傷が癒えたのち光尚に拝謁し、鉄砲十挺と屋敷地を下賜され、その裏の薮山もどうかと言われたが、これを断った」。
「阿部一族の死骸はすべて引き出されて吟味にかけられた。又七郎の槍に胸板を貫かれた弥五兵衛の傷は、誰の傷よりも立派だったので、又七郎はいよいよ面目を施した」。
「以上が鴎外の記した顛末である。いくら『お家大事』の江戸初期寛永の世の中とはいえ、異常きわまりない話である。いったいどこに『価値』の基準があるかはまったくわからない。たしかに『建前』はいくらもあるが、それとともに人間として家臣としての『本音』もあって、それがしかも『建前』の中で徹底されていく」。
「『情』と『義』も、つぶさに点検してみると、どこかで激突し、矛盾しあっている。どこに『あっぱれ』があるかもわからない。鴎外は『遺書』や『阿部一族』をまとめて『意地』という作品集に入れるのであるが、その『意地』とは、いつ発揮されるかによってまったく印象の異なるものだった」。
「しかし鴎外はそのような史実の連鎖にのみまさに目を注いだのである。もし意地や面目というものがあったとしたら、それは乃木大将のごとく最後の最後になって何かを表明すべきものもあったのである。鴎外も『鴎外最後の謎』とよばれるものを作った。自分の墓には森鴎外という文字を入れてはならない、ただ森林太郎と残してほしいと遺言したことである。『余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス』と」。
「こうした決意を鴎外がどこでしたのかは明確になっていないけれど、ぼくはあきらかに明治が瓦解していったときのこと、すなわち『興津弥五右衛門の遺書』と『阿部一族』のあたりだったと思っている」。