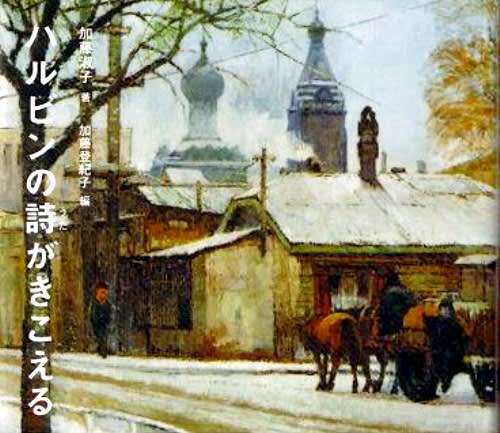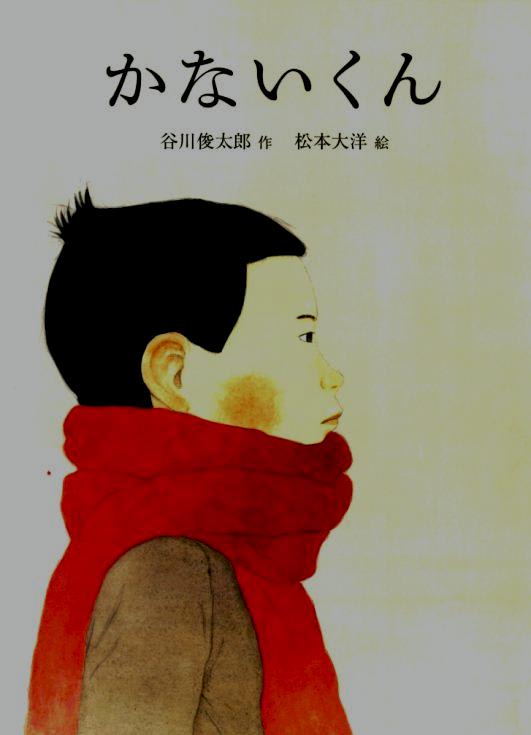この本を書かれた「佐竹直子」さんは、北海道新聞の記者をなさっています。
1940年頃から「北海道綴方教育連盟」の青年教師の方々が
次々に「赤」とされて無理無体に逮捕、監禁、拷問された事件がありました。
その方々のお一人が残された「獄中メモ」がこの著書の出発点となっています。
この本を読みながら、まず初めに思ったことは、
歴史のなかで北海道という土地は様々な人々が交錯する土地であると言うこと。
アイヌ(蝦夷)民族と呼ばれた方々、ロシアの介入、松前藩の介入、
さらに明治15年頃から始まった移住者の急激な増加などなど。
たくさんの人々が集まった土地である。
作文教育だけではなく、「生活図画教育」も行われていた土地でもある。
貧しい土地で生き抜くために、教師は子供たちに現実の生活を表現することを教えた。
それは素晴らしい教育であったと思う。
さらに、北海道では方言が入り乱れているので、その弊害を抑えるべく、
それぞれの方言の意味が繋がるような辞書を作った方もいらっしゃった。
こうして北海道という土地では、独自の素晴らしい教育があったようだ。
それが「貧困などの課題を与えて、児童の資本主義の矛盾を自覚させ、
階級意識を醸成した。」として逮捕され、11人が有罪とされた理不尽な事件となった。
この事件のなかにも、わずかな光はあった。
彼等を救おうとした弁護士の方、獄中のメモを密かに運んだ看守の方など。
以前の日記に書いたように、私がこの本に惹かれたのは、
私の小学校時代の担任の先生が作文教育に熱心だったことに繋がったからでしょう。
戦後の小学校教育で、私は素晴らしい先生に出会ったのだと改めて思ったのでした。
そしてS先生は、この事件を踏まえて作文教育に臨んでいたのではないでしょうか?
幼くて、わからなかったことが今見えてきます。
S先生は女性でした。そして小学校に初めての体育の先生がいらして、
とても自由で心に負担をかけない体育授業を行いました。
今まで出来なかったことがいつの間にか出来ているという魔法を使える先生でした。
体育嫌いだった私を、体育好きに変えて下さった大切な先生でした。
その大切な二人の先生が結婚なさったことも嬉しい出来事でした。
最後はまた私事になりましたが、自由に考え、表現することの幸福を
今更ながら幸福に思います。
この幸福がずっとずっと続きますように。
(2014年第1刷 2015年第3刷 北海道新聞社刊)日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞受賞