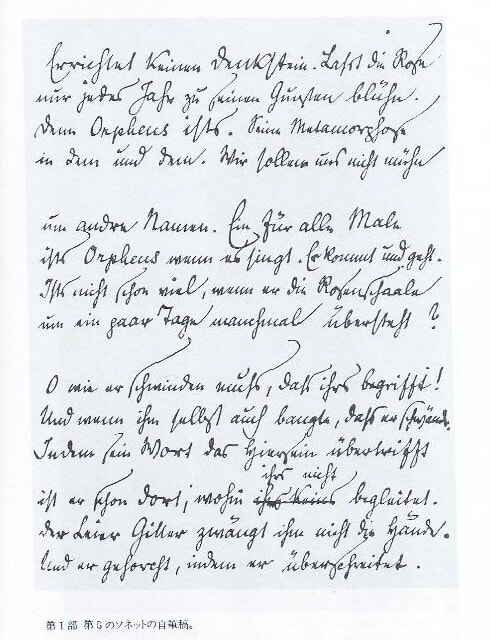音楽、それは彫像の息吹き。ひょっとして
絵画の静けさ。おまえ、言葉の終わるところにいる言葉よ。
おまえ、時間よ、消え失せる
心の方向に垂直に立つ時間よ。
おまえ、誰に向かってゆく感情?
なにに変わるのか?感情の変化?聴覚の風景にか。
おまえ、見知らぬものよ、音楽。私たちから抜けでて
成長した心の空間よ。私たちのもっとも誠実なもの、
私たちを乗り越えて 突き進んでゆくもの、――
聖なる別離――
内部が私たちを取りまくとき、
精通した遠みとして
大気の裏側としてあるものよ、
純粋に、
巨大に、
もう人の住めないところよ。
(完成詩・1906~1926年)より。
河出書房新社の「リルケ全集・10巻」には、殆ど同じ時期に書かれた「草稿・断片詩篇・1906~1926年」という作品群もあります。混乱しないためにメモを書いておきます。この「音楽に寄す」は1918年に書かれています。
さて、何故この詩を必死で(^^)探したのか?それはこの詩の最後の3行が「オルフォイスへのソネット第一部・13」の最後の3行・・・・・・
明澄に、めざめ、透きとおり、
二重の意味をもち、陽のように、大地のように、この世の生のものとなり、――
おお体験よ、感受よ、よろこびよ、――この巨大な!
・・・・・・に傾向を同じくする表現だと書かれていたからでした。「マルテの手記」のなかで、聴覚を失ったベートーヴェンの音楽を「宇宙のみが耐えうるものを宇宙に返却するもの」だと言い、大衆は「姦淫はするが、決して受胎することのない不妊の聴覚を持つ者」と言い、音楽を聴覚で楽しむものとしてとらえていないのでした。つまり音楽の沈黙の部分(静)をとらえるのだと。さらにマリー公爵夫人への手紙では、「音楽の裏側を呼び出すのだ。」とも書いています。
心の方向に垂直に立つ時間よ。
この1行は、音楽を時間の流れのうえではなく、垂直に立つ時間のなかにおいて聴くことだという意味のようです。また同じく「完成詩」のなかにある、1913年に書かれた「鳩」という詩のなかでは・・・・・・
驚愕せよ私を、律動する憤激で、音楽よ!
だが聖堂の丸天井はおまえをオルガンの響きで満たそうと待ち受けている
と言う詩行があります。この時まだリルケは「音楽」を捉えかねて、苛立ってさえいたようでした。