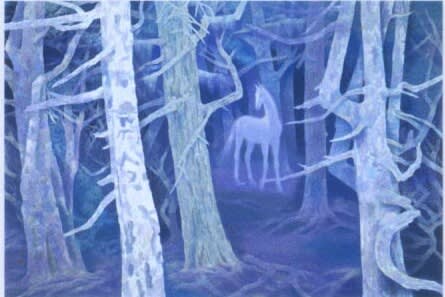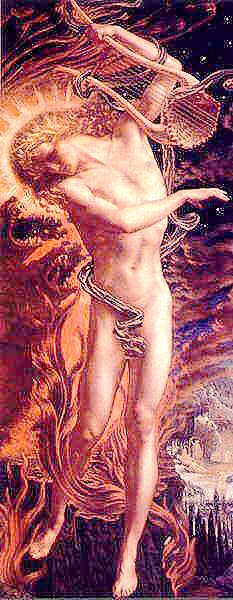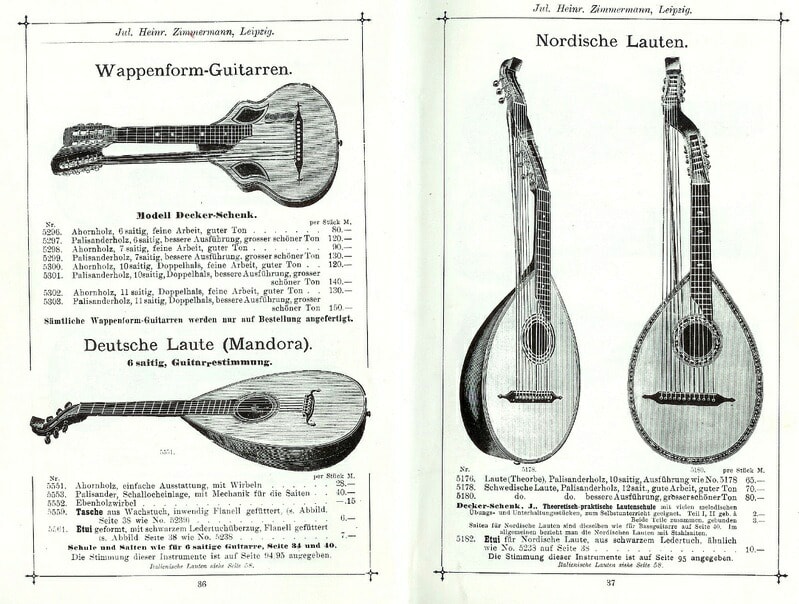とっさに手近な紙が時として
画家からその真実の筆触を
かすめ取るように、鏡もしばしば
少女らの聖らかで 無比の微笑をその内部に引きいれる、
彼女らがひとりで朝を試すとき――
または 付き添う燈火の輝きのうちにあるときに。
けれども実の顔の呼吸のなかへは、
そのあと、ひとつの反映が映るばかり。
かつて眼は暖炉の火がすすけ 長いあいだかかって
消えてゆくなかに、何を観たことか――
生の眼指し 永久に失われたものよ。
ああ 大地の、その喪失をだれが知っていよう?
にもかかわらず称賛の声をあげる者だけだ、
全体のなかへと生まれた心、それを彼は歌うだろう。
(田口義弘訳)
束の間の事柄の一回限りの表情を写し取るために、画家(ロダンか?)や詩人たちが整えられたものを用意するいとますらない時に、そこにたまたま置かれていた紙と鉛筆などが、急をしのぐ道具として使われることは、よくあることだ。
それは、鏡が、朝のひかり、夕べの灯りのなかに写しとる聖なる少女の表情が一瞬のものである時によく似ている。
けれども実の顔の呼吸のなかへは、
そのあと、ひとつの反映が映るばかり。
この「呼吸」という言葉は、リルケの詩によく表れるものの1つだが、それは「連続する現実性」と言えばいいのだろうか?鏡に映る少女の姿も、その時々の偶然の表情が、繰り返し映るということではないだろうか?
3連は暖炉の火が消えてゆく様子と、それを見つめている眼指し・・・・・・そこに「無常」と「喪失」を見たとしても、第1連に立ち戻って、また新たな息を吹き返すと考えてもいいだろう。
にもかかわらず称賛の声をあげる者だけだ、
全体のなかへと生まれた心、それを彼は歌うだろう。
ここで歌うのは、もちろん「オルフォイス」であろう。地上の創作者たちは、たくさんのものの瞬間の美しさを取りにがしながら生きているとしても、彼は歌ってくれるだろう。地上の「無常」と「喪失」はこうして救われる。
画家からその真実の筆触を
かすめ取るように、鏡もしばしば
少女らの聖らかで 無比の微笑をその内部に引きいれる、
彼女らがひとりで朝を試すとき――
または 付き添う燈火の輝きのうちにあるときに。
けれども実の顔の呼吸のなかへは、
そのあと、ひとつの反映が映るばかり。
かつて眼は暖炉の火がすすけ 長いあいだかかって
消えてゆくなかに、何を観たことか――
生の眼指し 永久に失われたものよ。
ああ 大地の、その喪失をだれが知っていよう?
にもかかわらず称賛の声をあげる者だけだ、
全体のなかへと生まれた心、それを彼は歌うだろう。
(田口義弘訳)
束の間の事柄の一回限りの表情を写し取るために、画家(ロダンか?)や詩人たちが整えられたものを用意するいとますらない時に、そこにたまたま置かれていた紙と鉛筆などが、急をしのぐ道具として使われることは、よくあることだ。
それは、鏡が、朝のひかり、夕べの灯りのなかに写しとる聖なる少女の表情が一瞬のものである時によく似ている。
けれども実の顔の呼吸のなかへは、
そのあと、ひとつの反映が映るばかり。
この「呼吸」という言葉は、リルケの詩によく表れるものの1つだが、それは「連続する現実性」と言えばいいのだろうか?鏡に映る少女の姿も、その時々の偶然の表情が、繰り返し映るということではないだろうか?
3連は暖炉の火が消えてゆく様子と、それを見つめている眼指し・・・・・・そこに「無常」と「喪失」を見たとしても、第1連に立ち戻って、また新たな息を吹き返すと考えてもいいだろう。
にもかかわらず称賛の声をあげる者だけだ、
全体のなかへと生まれた心、それを彼は歌うだろう。
ここで歌うのは、もちろん「オルフォイス」であろう。地上の創作者たちは、たくさんのものの瞬間の美しさを取りにがしながら生きているとしても、彼は歌ってくれるだろう。地上の「無常」と「喪失」はこうして救われる。