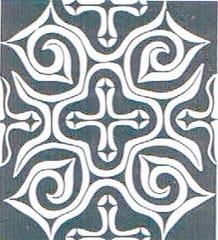知里幸惠(ちり ゆきえ)は、1903年(明治36年)生まれ。1922年(大正11年)心臓病で急死。たった19年の生涯でした。その翌年に「アイヌ神謡集」が出版されました。
この本の定本は、その大正12年の「知里幸恵編『アイヌ神謡集』・郷土研究社刊」であり、北海道立図書館北方資料研究所蔵の「知里幸恵ノート」を、編集部が閲覧して、補訂したものです。
知里幸恵は登別のアイヌの豪族の血筋を引き、豊かな大自然のなかで育ち、旭川の女子職業学校で日本語、ローマ字、英語を学びました。そして母と伯母からキリスト教を学ぶことによって、父祖伝来の信仰を深め、純化したものと思われます。
17歳の時の金田一京助との出会いが、この「アイヌ神謡」の翻訳と出版への工程をより進めたものと思われますが、「生涯の仕事に。」という決意もならず彼女は夭逝されて、ここに収められたアイヌ神謡は13編、残念ながらすべてということにはなりませんでしたが、これが「アイヌ神謡」として世に出た初めてのものでしょう。皮肉なことですが、この本がわたくしの手に届いたということは、先住民であったアイヌへの大和の侵略によって、日本語、新しい宗教がアイヌの歴史を葬り去ろうとしか過去があったからでしょう。
これはアメリカ・インディアンの口承詩にも言えることかもしれません。祖先からの知恵と信仰と言葉、自然とともに生きてゆくことは自然への感謝と信頼であること、あたりまえのようでありながら決してあたりまえではない生きることの厳しさとやさしさを、侵略者たちは崩壊したのです。
これらアイヌ神謡は、文字がなく口承ですから、言葉の音として、本文はすべてローマ字で書きおこされていて、それを知里幸恵が日本語訳したものです。こうした仕事が出来る方はめったにいなかったことでしょう。
ここで謡う神は「梟」「狐」「兎」「小狼」「海の神」「蛙」「小オキキリムイ」「沼貝」です。「オキキリムイ」とは「人祖」です。これらの「神謡」からはもっとも根源的で平和に生きる意味が問い直されてゆきます。また「神謡」は、個々の物語に固有のリフレインがひんぱんに見られます。特にわたくしが美しいと思ったのは「梟の神の自ら歌った謡」のなかにあるこのリフレインでした。しかし文字の上でのリズムしかわからないのが残念です。
銀の滴降る降るまわりに、
金の滴降る降るまわりに、
アイヌの口承文学の中で、物語性をもったものは大きく分けて「神謡」(カムイユカラ)「英雄叙事詩」「散文説話」の三つに分けることができるそうです。その「遠い声」に耳をすませていたいと思います。
* * *
《付記》
知里真志保(ちり ましほ・1909年~1961年)は、アイヌの言語学者。知里幸恵の弟です。室蘭中学校(現在の北海道室蘭栄高等学校)卒業。成績優秀だったのですが、貧困ゆえに進学できず、地元の役所に勤めました。金田一京助はその才能を惜しみ、東京杉並区の金田一家に招き、旧制第一高等学校(現在の東京大学教養学部)に8番の成績で合格しました。
金田一京助(1882年(明治15年)~1971年(昭和46年))は、アイヌ語研究で知られる日本の言語学者、民俗学者。
こうした人間関係が、歴史の記憶からうすれてゆく「アイヌ言語」と共に、文学や歴史もわたくしたちに届けられたのでしょう。
(岩波文庫 1878年第1刷・2005年第37刷)
この本の定本は、その大正12年の「知里幸恵編『アイヌ神謡集』・郷土研究社刊」であり、北海道立図書館北方資料研究所蔵の「知里幸恵ノート」を、編集部が閲覧して、補訂したものです。
知里幸恵は登別のアイヌの豪族の血筋を引き、豊かな大自然のなかで育ち、旭川の女子職業学校で日本語、ローマ字、英語を学びました。そして母と伯母からキリスト教を学ぶことによって、父祖伝来の信仰を深め、純化したものと思われます。
17歳の時の金田一京助との出会いが、この「アイヌ神謡」の翻訳と出版への工程をより進めたものと思われますが、「生涯の仕事に。」という決意もならず彼女は夭逝されて、ここに収められたアイヌ神謡は13編、残念ながらすべてということにはなりませんでしたが、これが「アイヌ神謡」として世に出た初めてのものでしょう。皮肉なことですが、この本がわたくしの手に届いたということは、先住民であったアイヌへの大和の侵略によって、日本語、新しい宗教がアイヌの歴史を葬り去ろうとしか過去があったからでしょう。
これはアメリカ・インディアンの口承詩にも言えることかもしれません。祖先からの知恵と信仰と言葉、自然とともに生きてゆくことは自然への感謝と信頼であること、あたりまえのようでありながら決してあたりまえではない生きることの厳しさとやさしさを、侵略者たちは崩壊したのです。
これらアイヌ神謡は、文字がなく口承ですから、言葉の音として、本文はすべてローマ字で書きおこされていて、それを知里幸恵が日本語訳したものです。こうした仕事が出来る方はめったにいなかったことでしょう。
ここで謡う神は「梟」「狐」「兎」「小狼」「海の神」「蛙」「小オキキリムイ」「沼貝」です。「オキキリムイ」とは「人祖」です。これらの「神謡」からはもっとも根源的で平和に生きる意味が問い直されてゆきます。また「神謡」は、個々の物語に固有のリフレインがひんぱんに見られます。特にわたくしが美しいと思ったのは「梟の神の自ら歌った謡」のなかにあるこのリフレインでした。しかし文字の上でのリズムしかわからないのが残念です。
銀の滴降る降るまわりに、
金の滴降る降るまわりに、
アイヌの口承文学の中で、物語性をもったものは大きく分けて「神謡」(カムイユカラ)「英雄叙事詩」「散文説話」の三つに分けることができるそうです。その「遠い声」に耳をすませていたいと思います。
* * *
《付記》
知里真志保(ちり ましほ・1909年~1961年)は、アイヌの言語学者。知里幸恵の弟です。室蘭中学校(現在の北海道室蘭栄高等学校)卒業。成績優秀だったのですが、貧困ゆえに進学できず、地元の役所に勤めました。金田一京助はその才能を惜しみ、東京杉並区の金田一家に招き、旧制第一高等学校(現在の東京大学教養学部)に8番の成績で合格しました。
金田一京助(1882年(明治15年)~1971年(昭和46年))は、アイヌ語研究で知られる日本の言語学者、民俗学者。
こうした人間関係が、歴史の記憶からうすれてゆく「アイヌ言語」と共に、文学や歴史もわたくしたちに届けられたのでしょう。
(岩波文庫 1878年第1刷・2005年第37刷)