空気とは何であろう? 山本七平『「空気」の研究』によると、ヘブライ語の「ルーア」が空気である。ギリシァ語訳は「プネウマ」、そしてラテン語「アニマ」である。アニマから「アニミズム」が派生する。
日本ではそれらを「霊」と訳すが、本来の意味は<風><空気>である。日本人の言う霊とはいくらか異なる。むしろ言霊(ことだま)の「たま」とか、物の怪の「もの」に近いようだ。ここでいう風・空気は、息・呼吸・気・精・精神などの意味。英語「Breath」のようです。
山本は「プネウマ(アニマ・霊)といった奇妙なものが自分たちを拘束して、一切の自由を奪い、そのため判断の自由も言論も言論の自由も失って、何かに呪縛されたようになり、時には自分たちを破滅させる決定を行わせてしまうという奇妙な事実を、そのまま事実として認め、<プネウマ(霊)の支配>というものがあるという前提に立って、これをいかに考えるべきか、またいかに対処すべきか…」
<空気>に支配されている、特にわたしたち日本人は<空気主義>あるいは<空気神教>から脱却すべきである。西洋には日本ほどに強い<空気>はない。
明治時代までは空気に対して「水を差す」という言葉が、空気対抗語として存在していたという。「そうおっしゃいますが」「それは正論ですが」「ご意見ごもっともですが」「かつての経験によれば」。空気に対抗したのが「水を差す」だったのです。
また現代社会での具体的な「空気決定方式」への対抗策として、山本氏は「飲み屋の空気」活用を提案しておられる。会社の会議でそのように決まってしまったが、その後に飲み屋に行くと、先ほどまでの会議参加者からは異論が出て来る。「先ほどは空気で決まってしまったが、しかし……」。フリートーキングからさまざまの本音が出て来る。
議場と飲み屋の票を足す。両場二重採決方式が面白い。「会議での多数決と飲み屋の多数決を合計し、決議人員を二倍ということにして、その多数で決定すれば、おそらく最も正しい決定ができるのではなかろうか」
今宵の晩酌時には窓を開け放って<風>ルーア・プネウマ・アニマを呼び込み、精霊の酒神とともに<空気>のことを再考してみようと思う。ところがいま頭の痛い課題を抱え込んでいます。近々に開催される会議、家族会議のこと。あまりの難題に「郷に入れば郷に従い、長いものには巻かれようか」「空気を読みながら紛糾を避けようか」……。このような自分はあまりにも情けない。日常はきびしい。
<2012年7月19日>
日本ではそれらを「霊」と訳すが、本来の意味は<風><空気>である。日本人の言う霊とはいくらか異なる。むしろ言霊(ことだま)の「たま」とか、物の怪の「もの」に近いようだ。ここでいう風・空気は、息・呼吸・気・精・精神などの意味。英語「Breath」のようです。
山本は「プネウマ(アニマ・霊)といった奇妙なものが自分たちを拘束して、一切の自由を奪い、そのため判断の自由も言論も言論の自由も失って、何かに呪縛されたようになり、時には自分たちを破滅させる決定を行わせてしまうという奇妙な事実を、そのまま事実として認め、<プネウマ(霊)の支配>というものがあるという前提に立って、これをいかに考えるべきか、またいかに対処すべきか…」
<空気>に支配されている、特にわたしたち日本人は<空気主義>あるいは<空気神教>から脱却すべきである。西洋には日本ほどに強い<空気>はない。
明治時代までは空気に対して「水を差す」という言葉が、空気対抗語として存在していたという。「そうおっしゃいますが」「それは正論ですが」「ご意見ごもっともですが」「かつての経験によれば」。空気に対抗したのが「水を差す」だったのです。
また現代社会での具体的な「空気決定方式」への対抗策として、山本氏は「飲み屋の空気」活用を提案しておられる。会社の会議でそのように決まってしまったが、その後に飲み屋に行くと、先ほどまでの会議参加者からは異論が出て来る。「先ほどは空気で決まってしまったが、しかし……」。フリートーキングからさまざまの本音が出て来る。
議場と飲み屋の票を足す。両場二重採決方式が面白い。「会議での多数決と飲み屋の多数決を合計し、決議人員を二倍ということにして、その多数で決定すれば、おそらく最も正しい決定ができるのではなかろうか」
今宵の晩酌時には窓を開け放って<風>ルーア・プネウマ・アニマを呼び込み、精霊の酒神とともに<空気>のことを再考してみようと思う。ところがいま頭の痛い課題を抱え込んでいます。近々に開催される会議、家族会議のこと。あまりの難題に「郷に入れば郷に従い、長いものには巻かれようか」「空気を読みながら紛糾を避けようか」……。このような自分はあまりにも情けない。日常はきびしい。
<2012年7月19日>










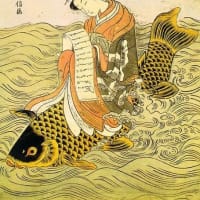



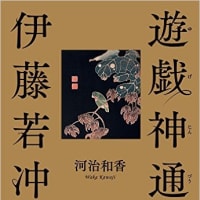





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます