知人が医療過誤を訴えて数年になる。この間の地裁・高裁の審理経緯と判決結果に多くの疑問ある中でこの本を手にした。東京地裁、最高裁に勤務経歴のある元裁判官とジャーナリストによる3日間の対談をまとめたものだが、随所に驚きと頷きが。<(傍聴に際して)なぜ裁判官に一礼するのか、裁判官に庶民の心が分かるのか>などから始まる興味深い内容は、読むほどにタイトルの「正体」「役人たち」が刻み込まれていく。<(事実関係で争いがない刑事事件や民事も貸金、賃貸借関係などでは)事実に法律を当てはめるだけ>。これはまだ何となく分かる。続く、冤罪の再審や医療過誤訴訟を含む民事では<裁判官の価値観や外から与えられる情報や刺激が決定的な意味を持つ>も想定の範囲内だが、その「価値観」や「情報」が問題なのだ。権威者が書いたと言われれば、その鑑定書を鵜呑みしていないか。<(現在の裁判官の多数派にとっては)個別的な当事者のことは記録の表面に書かれている記号としかみていない>や<自分が勝たせたいと思う側の最終準備書面を電磁文書で求めて引用、簡単に判決文を作成>という「コピペ判決」については、さもありなんと思う。一部良心的な裁判官もいるとしつつ、多くは人事と出世を念頭に置く「法服を着た役人」であり「裁判をやっている官僚」。その仕組みと実態が次々と明かされる。そして安保訴訟や原発訴訟など国の考えを追認する多くの判例をあげて「権力のチェック機構」でなく「権力の補完機構」と表現。特に最高裁は「権力の一部」となり、「憲法の番人」ではなく「権力の番人」と断言する。「あとがき」にもあるが、聞き手の鋭い記者魂と元裁判官の綿密な分析・司法批判にもとづく共著と言えるこの書。読み終えて、ますます知人の裁判の行方が気になりだした。
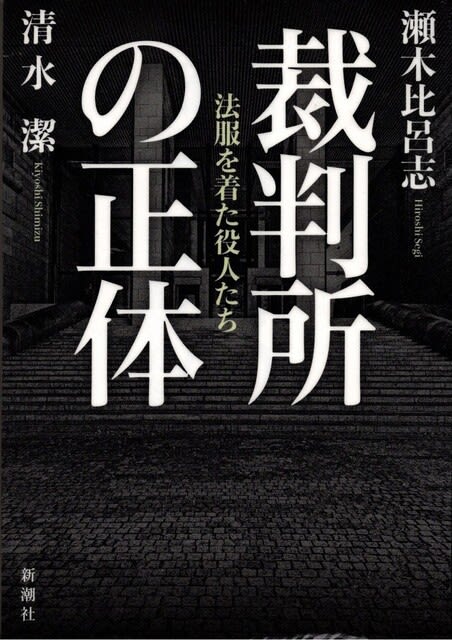




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます