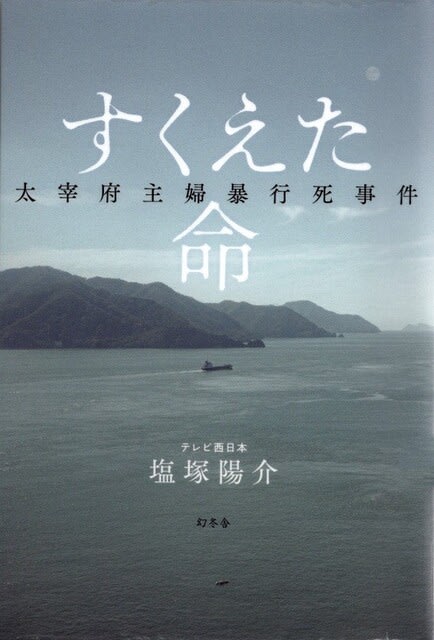弟を亡くした主人公の女性と弟の元恋人とのふたりの関係は最初からギクシャク。約束の場所に遅れてやって来た彼女は弁解するどころか、用件を早く済ませてほしいとの事務的な言葉。カーキ色のつなぎ服で目つきの悪い年下の女性、とても深い付き合いは出来ないはずだったのが意外な展開に。彼女が勤める家事代行会社のボランティア活動を手伝うことになる。様々な事情から食事を作ることや掃除も出来ない。その意思も無くした家を訪ね、持参した食材で食事を作り、部屋の掃除を行なう。特に、彼女が作る食事の内容、レパートリーの広さに目を見張る。レシピ付きのクッキング番組を見ているような手際の良さと美味しそうに出来上がった料理の数々。それらを目にし、口に運ぶ人たちの表情に変化のきざし。こうした間に知り得なかった弟の姿や彼女が抱えている事情も。ふたりの心が通わぬまま結末にむかう予感も最後にはタイトル「カフネ」の意味にしばし浸る。ポルトガル語で「愛する人の髪にそっと指を通す仕草」とか。冬陽が届く部屋で、じんわりと心温かく読み終えた。もうひとつの収穫は保存食としても彼女が作った卵味噌、早速試してみたい。

















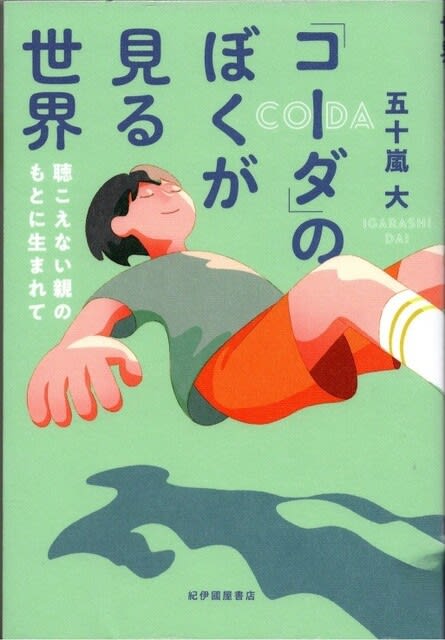


 ちか
ちか