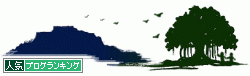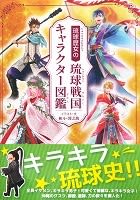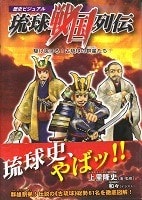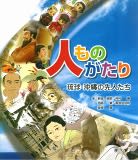時代考証や琉球エッセンス
完全無視の
琉球史マイナー人物を
乙女ゲーム風にキラキラ男子化してみるシリーズ。
昨日までに5人をUPして
目標10人の折り返し地点まで来たので
ちょっとブレイクタイム。
*
ところで、
このシリーズのテーマである
「乙女ゲーム」って
どういうものか分かりますか?
いわゆるギャルゲーの女子向け版
なんですけど、
それでもピンと来ない人のために
定義を書きますと…
女性主人公(プレーヤー)が、
登場人物である男性キャラクターを攻略して
恋愛を楽しむ、
女性向けゲームの総称。
「乙女ゲー」「乙ゲー」と略される。
(参/コトバンク)
おそらく、これなんかもそうだよね。
なので乙ゲーの中には
それはもうバリエーション豊かな
イケメンたちが多数登場します。
プレーヤーはその中から
好みの男性キャラにねらいを定めて"落とし"、
疑似恋愛を楽しむ、
というものですね。
スマホゲームの乙ゲーなんかは
テレビCMとかもやってたりするので
なんとなくイメージできるのでは?
ワタシはやったことないんですけど…
で、その中に登場する男性たちは
若い
髭なし
イケメン
基本ロンゲ
(全部長髪じゃなくても前髪は目にかかる長さ)
カラーヘアー
が基本条件のようで。
たとえ設定年齢がおじさんであろうとも
見た目は10代~20代前半という
超法規的措置
が取られているわけです。
なので髭やヘアスタイルにこだわりのある
琉球史キャラたちも
敢えて
髭無しの
サラサラヘア~の
見た目20代以下
となるわけです。
これもそう。
というわけで、
次記事では↑のおじいを
超法規的に
キラキラ男子化させてみることにします。