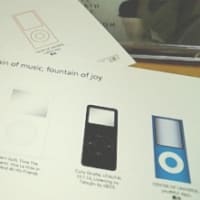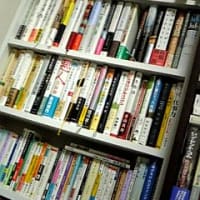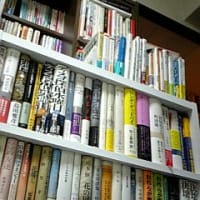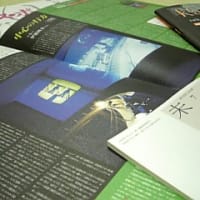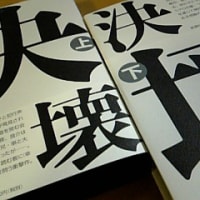その一部をご紹介。
●『小説、世界の奏でる音楽』 は、もはやなんともいえないものが奏でられている世界に入ってきているが、面白くない?と聞かれたら、いえいえがぜん面白いと答えるしかない。なにが面白いのかということをいろいろと考えてみると、それはこんなふうに小説のことをうだうだとだらだらと語っているような本や場がほかにはないというオリジナリティだし、自分のなかで起きた感情の揺れとか、揺れのなさといったようなものの原因を自分を標本のようにして分解していくという語りがほかにないからだ。また、とうぜんこれらのことはたとえ保坂和志であってもすぐに答えがでるわけではないので、そういった思考の流れ/淀みをリアルタイム風に書く方法論(「と、ここまでのことを考えてから、3日たって、また書き出しているわけだけれど」といったような言い方)をうまい形で盗んでみたいという関心もある。まあ、それらの身体的思考実験が、くどいという見方もなきにしもあらずだけれど。
は、もはやなんともいえないものが奏でられている世界に入ってきているが、面白くない?と聞かれたら、いえいえがぜん面白いと答えるしかない。なにが面白いのかということをいろいろと考えてみると、それはこんなふうに小説のことをうだうだとだらだらと語っているような本や場がほかにはないというオリジナリティだし、自分のなかで起きた感情の揺れとか、揺れのなさといったようなものの原因を自分を標本のようにして分解していくという語りがほかにないからだ。また、とうぜんこれらのことはたとえ保坂和志であってもすぐに答えがでるわけではないので、そういった思考の流れ/淀みをリアルタイム風に書く方法論(「と、ここまでのことを考えてから、3日たって、また書き出しているわけだけれど」といったような言い方)をうまい形で盗んでみたいという関心もある。まあ、それらの身体的思考実験が、くどいという見方もなきにしもあらずだけれど。
ところで今号でとりあえず第一期の最終刊となる『エクス・ポ 6号』では、保坂和志へのロングインタビューが掲載されていて、そこでは『書きあぐねている人の…』が、終わってみればあまりにも雑なことしかできていなかったので、再び「小説をめぐって」を企図したというくだりがあり、ここまで偏執的に小説のことを考える人を前にして、さすがに評論家は小説のことを語れないよなあ、と思ってしまう。まあ、フリー編集者ならともかく、文芸評論家を名乗るのならこれぐらいの時間を投資せよというのは正論かもしれないが、しかし、一方で、これはパワハラの亜種だな、という気がしないでもない。
●『グランド・ミステリー』 、『火の鳥 鳳凰編』、『火の鳥 復活編・羽衣編』は、100円だったら買うだろう。ただし、100円だからといって中身も確認せずに買うのは問題で、実際に『復活編』が朝日ソノラマの手持ちとだぶってしまい、100円にもかかわらず大きく悔いることになる。また、同じ100円でも『プラトン学園』を買わなかった、そこにある認知的不協和をいまだ合理的に説明することはできない。
、『火の鳥 鳳凰編』、『火の鳥 復活編・羽衣編』は、100円だったら買うだろう。ただし、100円だからといって中身も確認せずに買うのは問題で、実際に『復活編』が朝日ソノラマの手持ちとだぶってしまい、100円にもかかわらず大きく悔いることになる。また、同じ100円でも『プラトン学園』を買わなかった、そこにある認知的不協和をいまだ合理的に説明することはできない。
●『疲れすぎて眠れぬ夜のために 』 は、買ってはみたものの、なんだかブログのほうが読みやすく論理立って感じるのは、やっぱりそこに、筆に任せた勢いがあるからなんだろうなと思う。論理がなくとも論理を感じさせる書き方があり、しかし、それを紙で斜め読みせず向き合うと、論理を感じさせる書き方を強調しているぶん、くどく見える。これを見るにつけ、エクリチュールというものをもっと考えなければならないと思う次第。関係ないか。
は、買ってはみたものの、なんだかブログのほうが読みやすく論理立って感じるのは、やっぱりそこに、筆に任せた勢いがあるからなんだろうなと思う。論理がなくとも論理を感じさせる書き方があり、しかし、それを紙で斜め読みせず向き合うと、論理を感じさせる書き方を強調しているぶん、くどく見える。これを見るにつけ、エクリチュールというものをもっと考えなければならないと思う次第。関係ないか。
●『集中講義!アメリカ現代思想 リベラリズムの冒険』 は、一気に100ページぶんぐらい読み進めることができたけれど、頭の中になんにも残っていないことが判明したので、頭の中に残りそうなローティの章を先に読もうと思う。
は、一気に100ページぶんぐらい読み進めることができたけれど、頭の中になんにも残っていないことが判明したので、頭の中に残りそうなローティの章を先に読もうと思う。
●『あやめ 鰈 ひかがみ』 は、あんまり面白いという人はいないような気もするが、おれは意外に面白いじゃないかと思っていて、それは、やっぱり松浦の企図している幽玄のようなものに、まんまと乗せられているからなんだろうと思う。あれ?こいつって死んでたんじゃなかったっけ?と、ふと惑う瞬間。しかし2,30ページ読んだ程度でそんな謀に誑かされる甘い読み方も問題だな。
は、あんまり面白いという人はいないような気もするが、おれは意外に面白いじゃないかと思っていて、それは、やっぱり松浦の企図している幽玄のようなものに、まんまと乗せられているからなんだろうと思う。あれ?こいつって死んでたんじゃなかったっけ?と、ふと惑う瞬間。しかし2,30ページ読んだ程度でそんな謀に誑かされる甘い読み方も問題だな。
●『アキハバラ発<00年代>への問い』 は、おんなじような本を最近買ったような気もするが、また買ってしまった。差分は平野啓一郎と、おんなじような本では、web上でしか公開されなかった大澤真幸。しかし、世界で起きる新たな問題が顕になるにつれ、なんだか、だんだん読む気が失せてきた。
は、おんなじような本を最近買ったような気もするが、また買ってしまった。差分は平野啓一郎と、おんなじような本では、web上でしか公開されなかった大澤真幸。しかし、世界で起きる新たな問題が顕になるにつれ、なんだか、だんだん読む気が失せてきた。
●『All in One』 は、こんなの買うより、電子辞書首っ引きで『oracle night』なんかを訳したほうがよほど力がつくんじゃないかと思うが、当然そんな時間はないので手軽にいつでも取り組めるテキストとして。もちろん、気軽にいつでも取り組めるようなもので、本質的な力がつくわけがないのは重々承知のうえです。
は、こんなの買うより、電子辞書首っ引きで『oracle night』なんかを訳したほうがよほど力がつくんじゃないかと思うが、当然そんな時間はないので手軽にいつでも取り組めるテキストとして。もちろん、気軽にいつでも取り組めるようなもので、本質的な力がつくわけがないのは重々承知のうえです。
●『東大合格生のノートはかならず美しい』 は、確かにいい本づくりをしていると思う。図解、コラム、ポイントのバランスなど、質のいい参考書のようなつくりで、まず、そういった編集方法で学ぶところは多い。とうぜん内容についても、もしおれが高校生なら、という前提で学ぶところは多い。東大合格生のノートにみられるいくつかの法則というかルールがいくつか上げられているけれど、じつのところポイントは明快で、「自分で考えて、自分がいちばん使いやすい、参考書&問題集を、ていねいにつくる」そして、それを何度も見返しながらさらにカスタマイズしていく、というところにつきるのではないかと思う。もちろん「あいつノートはきれいなんだけどなあ」という残念な級友がいたかもしれないが、それはきっと作り方と使い方が間違っていたんだろう。早速、娘のためにコクヨが共同開発したキャンパスノートの「ドット入り罫線シリーズ」を買ったが、第一印象としては好感触のもよう。
は、確かにいい本づくりをしていると思う。図解、コラム、ポイントのバランスなど、質のいい参考書のようなつくりで、まず、そういった編集方法で学ぶところは多い。とうぜん内容についても、もしおれが高校生なら、という前提で学ぶところは多い。東大合格生のノートにみられるいくつかの法則というかルールがいくつか上げられているけれど、じつのところポイントは明快で、「自分で考えて、自分がいちばん使いやすい、参考書&問題集を、ていねいにつくる」そして、それを何度も見返しながらさらにカスタマイズしていく、というところにつきるのではないかと思う。もちろん「あいつノートはきれいなんだけどなあ」という残念な級友がいたかもしれないが、それはきっと作り方と使い方が間違っていたんだろう。早速、娘のためにコクヨが共同開発したキャンパスノートの「ドット入り罫線シリーズ」を買ったが、第一印象としては好感触のもよう。
とりあえず、ここまで。
やっぱり、ぱっとしない。
ただ、本はたまる一方で、東京もあまりの乱雑さにイライラしてきたので、とうとう無印のパルプボードボックスを買ってしまいました。

●『小説、世界の奏でる音楽』
ところで今号でとりあえず第一期の最終刊となる『エクス・ポ 6号』では、保坂和志へのロングインタビューが掲載されていて、そこでは『書きあぐねている人の…』が、終わってみればあまりにも雑なことしかできていなかったので、再び「小説をめぐって」を企図したというくだりがあり、ここまで偏執的に小説のことを考える人を前にして、さすがに評論家は小説のことを語れないよなあ、と思ってしまう。まあ、フリー編集者ならともかく、文芸評論家を名乗るのならこれぐらいの時間を投資せよというのは正論かもしれないが、しかし、一方で、これはパワハラの亜種だな、という気がしないでもない。
●『グランド・ミステリー』
●『疲れすぎて眠れぬ夜のために 』
●『集中講義!アメリカ現代思想 リベラリズムの冒険』
●『あやめ 鰈 ひかがみ』
●『アキハバラ発<00年代>への問い』
●『All in One』
●『東大合格生のノートはかならず美しい』
とりあえず、ここまで。
やっぱり、ぱっとしない。
ただ、本はたまる一方で、東京もあまりの乱雑さにイライラしてきたので、とうとう無印のパルプボードボックスを買ってしまいました。