『文藝春秋』を立ち読みする限りは(※1)、芥川賞選考委員の『グランド・フィナーレ』選評は、全体として努力賞・功労賞的な評価である。もちろんおおむね二人ほどを除いて(うちひとりは同作には触れず。でもまあこの人なら触れなくてもいいや)、獲るべき人がとった目出たいよ、というスタンスではあるのだが、なにか釈然としない。
もちろんこれは当然のことで、新人ではない新人に対する評価の言葉遣いは、たとえ言葉の手練たちであっても社会常識的にも難しいということだ。「よくやった!」ともいいにくいがいっぽう「おまえ、待たせたよなあ」と言うのも、彼らの立場としてはほとんど意味がない。
そのため、全体をとおして、新人に対するものの言い方になっているのに(たとえば、次回作に期待したい)、小説への評価はどちらかといえば辛く、それはむしろレベルの高い文芸批評的にみえる。たとえば、『グランド・フィナーレ』中の、ロシアでのテロ・チェチェンやアフリカにおける軍事虐殺のエピソードを小説構造の中に取り込めなかったことは残念だという村上龍の意見などはなんとも批評らしい(必ずしも正しい評というわけではないが)。ただ、このあたりのことを言い出すと、小説ってそこまでパーフェクトでなければならないのか?そもそも小説に賞を与えることに意味はあるのか?といった部分がよくわからなくなってくるし、だいたい、過去の若書きの人たちはどうなんだ、と思ってしまう。
芥川賞には、やはり作家歴制限をつけておいて、もし有能な作家に獲らすことができなければ、彼を落とした委員が消化しきれませんでしたと悔恨すればいいだけの話だということかもしれない。
さて、唯一、受賞に反対しているのはご存じのとおり日本の首都を幸せにしようと日夜奮闘している作家なんだかどうなんだかわからない人であり、かれの場合はどちらかというと『ニッポニア・ニッポン』への遺恨が原因のような気もするが、『グランド・フィナーレ』に対する主張は、ペドフィリー(幼児性愛)やひきこもりといった社会風俗を、阿部が小説の題材として扱う必然性がない、ということだ。
しかし、『グランド・フィナーレ』はもとより『ニッポニア・ニッポン』についても、彼が社会風俗を小説の要素として取り込んでいることは、じつのところ大きくは取りざたされていない。たとえば、今回の場合も、ふつうに考えれば奈良の事件や性犯罪者の出所後情報提供の議論ともっと結びついた論評があってもいいはずなのにそうはならない。もちろん、読みの巧みな編集者がいてプロモーションをコントロールしている、といったこともあるだろうが、このことについて、わかりやすく丁寧すぎるくらい丁寧に解説しているのが、『文学界 3月号』(※2)で、阿部と蓮實重彦の対談である(※2)。
蓮實 谷崎にも隠された悪癖みたいなものを少しづつ露呈させている作品はありますが、今まで書いてこられた作品では、阿部さんもそういう形をとっておられますよね。
現代の社会風俗というかひきこもりに似たものもあれば、ピッキングの話もすでに出てきていたし、今回はペドフィリーです。それに似た犯罪を犯す人たちがいるような社会的に状況にそれとなく同調するふりをしておられたわけでしょう。………そうやって阿部さんは現代社会風俗にどこかで足をかけておられるけれど、実はそれはほんとうの主題ではないという方向にいつも流れていくわけですね。
阿部 はい。
蓮實 たとえば前回の芥川受賞作品のモブ・ノリオさんの『介護入門』では、介護という新たな社会風俗がモロにあつかわれている。その前の金原ひとみの『蛇にピアス』もそうでしょう。そのモロのところで評価されてしまうみたいなところがありますね。私としては評価したい『介護入門』では介護そのものが真の主題ではないと思いますが、風潮としては、モロに評価されてしまうところがある。
ところが、ペドフィリーについて、あるいはドメスティック・バイオレンスが背景にあることについて「だからあの作品がいい」あるいは「いけない」とは、阿部さんの場合にはあまりに言われない。なぜなのかと思うんですが。
ということである。もちろんこれは蓮實一派的な感想なのでバランスをとる必要はあるが、それでも東京の役人の読みは、残念ながらあまりに表層的で独善的といわざるをえない。もちろん、小説はどう読んでもいいわけだから、そういった感想を禁じることはできないので、つまりはもう少し小説家らしく言葉を練る必要があった、ということかもしれない。そしてもうひとつ、書くことそして読むことだけに愚直で真摯でない人が、こういった場にいていいものかどうか、いくら忙しくても候補作を作家らしく読める人がいいんじゃないの?といった議論を少しはしたほうがいいのかもしれない。
ちなみに、社会風俗的な読み方をされない(できない)理由は、阿部の自己分析によると自分が「形式主義だから」であり、「社会風俗的な問題という縦軸の問題がドーンと作品に入り込んでくるわけだけれども、それが語りによってどんどんずらされていくのが阿部和重の作品だ」という東浩紀の読み方に合意している。結果として「社会風俗に言及されていながらほとんどの場合に構造的な有意性が剥奪されているので語りの構造を規定して」いないという蓮實の読み方が意見としては納得性が高そうだ。
------------------------
(※1)立ち読みなので、虚偽があるかもしれません。というかきっとあると思います。文藝春秋くらい買えばいいんだけど、相変わらずほかの記事で愉しそうなものもないので(イチローのインタビューくらい?).
(※2)何度も繰り返しますが最近の『文学界』は、ぼくのような市井の中途半端な文学好きにとってはかなり面白い内容になっています。
(※3)もちろん、この馴れ合いインタビューの話題はどんどんひろがり、少しは阿部和重を裸にしていて、たいへん愉しく読めます。『文学界3月号』の特集「阿部和重とこの時代」は、この対談のほかにも、『シンセミア』で芥川賞あげてもいいんじゃないの?といった評や、『プラスティック・ソウル』はどうなった?という意見などがあり、一気に阿部和重ファンになりたい方にはおすすめです。(『プラスティック・ソウル』は、『批評空間』で連載されていた長編で未完)。
------------------------
↓図書券1万円の第一弾は、予定どおり
↓『言語と文学』。本と読書のランキングに
↓残り続ける限り、いつかは書評します。

もちろんこれは当然のことで、新人ではない新人に対する評価の言葉遣いは、たとえ言葉の手練たちであっても社会常識的にも難しいということだ。「よくやった!」ともいいにくいがいっぽう「おまえ、待たせたよなあ」と言うのも、彼らの立場としてはほとんど意味がない。
そのため、全体をとおして、新人に対するものの言い方になっているのに(たとえば、次回作に期待したい)、小説への評価はどちらかといえば辛く、それはむしろレベルの高い文芸批評的にみえる。たとえば、『グランド・フィナーレ』中の、ロシアでのテロ・チェチェンやアフリカにおける軍事虐殺のエピソードを小説構造の中に取り込めなかったことは残念だという村上龍の意見などはなんとも批評らしい(必ずしも正しい評というわけではないが)。ただ、このあたりのことを言い出すと、小説ってそこまでパーフェクトでなければならないのか?そもそも小説に賞を与えることに意味はあるのか?といった部分がよくわからなくなってくるし、だいたい、過去の若書きの人たちはどうなんだ、と思ってしまう。
芥川賞には、やはり作家歴制限をつけておいて、もし有能な作家に獲らすことができなければ、彼を落とした委員が消化しきれませんでしたと悔恨すればいいだけの話だということかもしれない。
さて、唯一、受賞に反対しているのはご存じのとおり日本の首都を幸せにしようと日夜奮闘している作家なんだかどうなんだかわからない人であり、かれの場合はどちらかというと『ニッポニア・ニッポン』への遺恨が原因のような気もするが、『グランド・フィナーレ』に対する主張は、ペドフィリー(幼児性愛)やひきこもりといった社会風俗を、阿部が小説の題材として扱う必然性がない、ということだ。
しかし、『グランド・フィナーレ』はもとより『ニッポニア・ニッポン』についても、彼が社会風俗を小説の要素として取り込んでいることは、じつのところ大きくは取りざたされていない。たとえば、今回の場合も、ふつうに考えれば奈良の事件や性犯罪者の出所後情報提供の議論ともっと結びついた論評があってもいいはずなのにそうはならない。もちろん、読みの巧みな編集者がいてプロモーションをコントロールしている、といったこともあるだろうが、このことについて、わかりやすく丁寧すぎるくらい丁寧に解説しているのが、『文学界 3月号』(※2)で、阿部と蓮實重彦の対談である(※2)。
蓮實 谷崎にも隠された悪癖みたいなものを少しづつ露呈させている作品はありますが、今まで書いてこられた作品では、阿部さんもそういう形をとっておられますよね。
現代の社会風俗というかひきこもりに似たものもあれば、ピッキングの話もすでに出てきていたし、今回はペドフィリーです。それに似た犯罪を犯す人たちがいるような社会的に状況にそれとなく同調するふりをしておられたわけでしょう。………そうやって阿部さんは現代社会風俗にどこかで足をかけておられるけれど、実はそれはほんとうの主題ではないという方向にいつも流れていくわけですね。
阿部 はい。
蓮實 たとえば前回の芥川受賞作品のモブ・ノリオさんの『介護入門』では、介護という新たな社会風俗がモロにあつかわれている。その前の金原ひとみの『蛇にピアス』もそうでしょう。そのモロのところで評価されてしまうみたいなところがありますね。私としては評価したい『介護入門』では介護そのものが真の主題ではないと思いますが、風潮としては、モロに評価されてしまうところがある。
ところが、ペドフィリーについて、あるいはドメスティック・バイオレンスが背景にあることについて「だからあの作品がいい」あるいは「いけない」とは、阿部さんの場合にはあまりに言われない。なぜなのかと思うんですが。
ということである。もちろんこれは蓮實一派的な感想なのでバランスをとる必要はあるが、それでも東京の役人の読みは、残念ながらあまりに表層的で独善的といわざるをえない。もちろん、小説はどう読んでもいいわけだから、そういった感想を禁じることはできないので、つまりはもう少し小説家らしく言葉を練る必要があった、ということかもしれない。そしてもうひとつ、書くことそして読むことだけに愚直で真摯でない人が、こういった場にいていいものかどうか、いくら忙しくても候補作を作家らしく読める人がいいんじゃないの?といった議論を少しはしたほうがいいのかもしれない。
ちなみに、社会風俗的な読み方をされない(できない)理由は、阿部の自己分析によると自分が「形式主義だから」であり、「社会風俗的な問題という縦軸の問題がドーンと作品に入り込んでくるわけだけれども、それが語りによってどんどんずらされていくのが阿部和重の作品だ」という東浩紀の読み方に合意している。結果として「社会風俗に言及されていながらほとんどの場合に構造的な有意性が剥奪されているので語りの構造を規定して」いないという蓮實の読み方が意見としては納得性が高そうだ。
------------------------
(※1)立ち読みなので、虚偽があるかもしれません。というかきっとあると思います。文藝春秋くらい買えばいいんだけど、相変わらずほかの記事で愉しそうなものもないので(イチローのインタビューくらい?).
(※2)何度も繰り返しますが最近の『文学界』は、ぼくのような市井の中途半端な文学好きにとってはかなり面白い内容になっています。
(※3)もちろん、この馴れ合いインタビューの話題はどんどんひろがり、少しは阿部和重を裸にしていて、たいへん愉しく読めます。『文学界3月号』の特集「阿部和重とこの時代」は、この対談のほかにも、『シンセミア』で芥川賞あげてもいいんじゃないの?といった評や、『プラスティック・ソウル』はどうなった?という意見などがあり、一気に阿部和重ファンになりたい方にはおすすめです。(『プラスティック・ソウル』は、『批評空間』で連載されていた長編で未完)。
------------------------
↓図書券1万円の第一弾は、予定どおり
↓『言語と文学』。本と読書のランキングに
↓残り続ける限り、いつかは書評します。













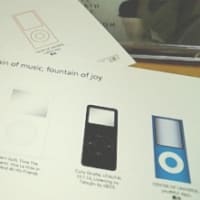
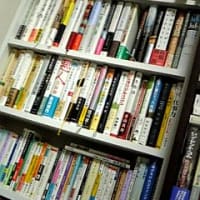
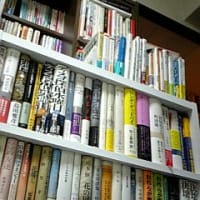

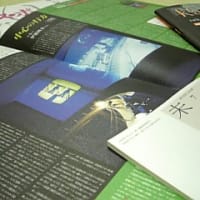

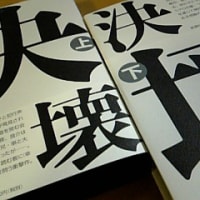

いっぽう、阿部和重本人は、『群像 3月号』の単独インタビューで、「安っぽい小説」で結構、これからも「安っぽい小説」書き続けます、「安っぽい小説」万歳、と大人っぽくかわしております。
なお、本文エントリーはいまいち洗練されていなかったので、このコメントを機会に多少改稿しました。だからといってよくなったかというとそうでもないけれど。