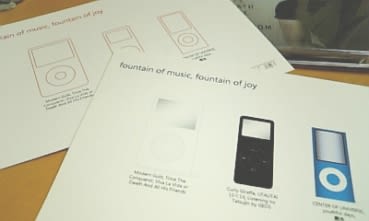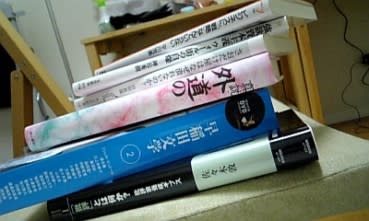『恐怖新聞』の少年チャンピオンコミックスの5~6巻あたり。鬼形礼は、比較的大きな規模の除霊に挑戦するが、例によってポルターガイストのフェイクにより失敗する。なかなかハードな除霊だったようで、鬼形は「もう金輪際、除霊なんかしないです」と、あきらめの境地に達する。しかし、この除霊、じつはかなりいいところまでいっていて、もし鬼形があと一歩がまんしていれば成功した可能性が高かった。そのことはすでに恐怖新聞により予言されていたにもかかわらず、この一回に限って、彼は気絶という体たらくで重要な紙面を見逃していた、という話。
いま、まさにそんな感じ。ああ、よくわかんない譬えですね。なんとなく、なんとなくですよー。いや、除霊的なるものに失敗したというわけではなく、もう少し踏み込めば、そこになにか煌めくようなものがあるような気がするけれど、いろいろあって突っ込んでいけない状況。そこまでやれば新しい機会を手に入れられることはわかってんだけど、きっと今は追いかけられないだろうなあ、という忸怩たる思い。で、せっかくの恐怖新聞のスクープを徒労にしてしまう。
その壁ないしは膜のようなものは、けっして高いわけでも厚いわけでもなく、どちらかといえば「やりさえすれば」越え、抜けられるようなものなんだろう。しかし、道を阻むザコキャラが意外と手ごわい。眠気、ビール、退屈、妄想、掃除、ウイスキー、買い物、踊り、ビートルズ、ハイボール、クライマックスシリーズ、ヘアスタイリング、焼酎、闘い、バッティング、乳酸菌飲料、アイフォーン……。しかし、1日が48時間があれば解決するのか?といわれれば、そうでもないような気もする。
来年度は、ハイ・アチーブな居酒屋店長なんかがプロデュースする人生ノートブックのようなものを愛用するべきなのだろうか。いやいや、これはちょっと違うなあ。だいたい、こんなようなエクセレントな習慣が続かないからダメダメの丸出だめ夫になっているわけだし。
しかし、まあ仕事、というか世の中というのはだいたいこんなもんですな。わはは。ということで、恐怖新聞ってのは、どこに電話すれば購読できるんでしょうか。
いま、まさにそんな感じ。ああ、よくわかんない譬えですね。なんとなく、なんとなくですよー。いや、除霊的なるものに失敗したというわけではなく、もう少し踏み込めば、そこになにか煌めくようなものがあるような気がするけれど、いろいろあって突っ込んでいけない状況。そこまでやれば新しい機会を手に入れられることはわかってんだけど、きっと今は追いかけられないだろうなあ、という忸怩たる思い。で、せっかくの恐怖新聞のスクープを徒労にしてしまう。
その壁ないしは膜のようなものは、けっして高いわけでも厚いわけでもなく、どちらかといえば「やりさえすれば」越え、抜けられるようなものなんだろう。しかし、道を阻むザコキャラが意外と手ごわい。眠気、ビール、退屈、妄想、掃除、ウイスキー、買い物、踊り、ビートルズ、ハイボール、クライマックスシリーズ、ヘアスタイリング、焼酎、闘い、バッティング、乳酸菌飲料、アイフォーン……。しかし、1日が48時間があれば解決するのか?といわれれば、そうでもないような気もする。
来年度は、ハイ・アチーブな居酒屋店長なんかがプロデュースする人生ノートブックのようなものを愛用するべきなのだろうか。いやいや、これはちょっと違うなあ。だいたい、こんなようなエクセレントな習慣が続かないからダメダメの丸出だめ夫になっているわけだし。
しかし、まあ仕事、というか世の中というのはだいたいこんなもんですな。わはは。ということで、恐怖新聞ってのは、どこに電話すれば購読できるんでしょうか。