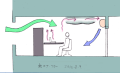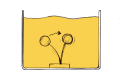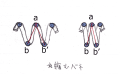本日はコミティア113が開催され3000を越えるサークルの参加がありました。
私も新刊を作って参加しましたが、天候がすぐれず8月というのに9月下旬の気温
に小雨がぱらつく中での開催とあって、人出もそれほどでもありませんでした。
この様子では又一冊も売れないのではと思いましたが、とりあえず4冊が売れて
4冊を配布できました。
今回の新刊はPCによる作画とカラー表紙という、以前からの目標を達成した物
でしたが、ページ数は最低限のイラスト本となり、いくつかの課題を残しました。
作画のスピードは速くなるものの線が散漫になって切れがなくなりました。
これは新しいペンタブレットと描画ソフトで解決するか、ペンで描いた原稿を
スキャナーで取り込むかの、どちらかを取らねばなりません。
PCのモニターで見た感じと実際に印刷された紙面が異なるので、このギャップ
を補正する方法が必要です。
また、作画中の画面が外部に流出しているらしく対策をとらねばなりません。
一方で、レイアウトがいかようにもできる自由度は捨てがたく、ウスズミによる
描画が自在にできるのでスクリーントーンを使わずにすみます。
またPC画面を見る角度が紙面を見下ろす場合に比べて首の疲労が少ないという
メリットがあります。長時間の作業で疲労の軽減は大きな意味があるのです。
また今後の視力の減退を画面の拡大で補えるという点もあると思います。
とりあえずはこの個人誌をポートレートとして就職活動に生かす方向を考えて
いますが、一方でアンチ活動を止めようとしない近隣の一部住民にたいして何らか
の方法で牽制をする必要も出てきました。彼らは私の活動を失敗させる方向に動く
ので、その動機とか目的といったものを探るのはあまり意味がなくなってきました。
手段が目的化していて、もはや利害関係すら皆無の者もこぞってアンチ活動に
参加している有様です。究極的に彼らは私の人生を潰す方向で動いていることは
疑いようがないでしょう。
旧来の引退したウォッチ界隈の諸氏にしても自分たちの活動が受け継がれて
現在の私の迫害が継続されていることに責任を取ってもらわねばならなくなる
でしょう。具体的には教唆とか先導ということになると思いますが、彼らはたかが
馴れ合いという段階ではなくなっている事を自覚すべきです。
今後のイベントの参加に関しては、継続の方向を考えていますが、イベントの
1週ほど前にアンチ活動が異常に盛り上がるという事態が繰り返されるなら、
別の方法もを取らねばならないと考えています。
私も新刊を作って参加しましたが、天候がすぐれず8月というのに9月下旬の気温
に小雨がぱらつく中での開催とあって、人出もそれほどでもありませんでした。
この様子では又一冊も売れないのではと思いましたが、とりあえず4冊が売れて
4冊を配布できました。
今回の新刊はPCによる作画とカラー表紙という、以前からの目標を達成した物
でしたが、ページ数は最低限のイラスト本となり、いくつかの課題を残しました。
作画のスピードは速くなるものの線が散漫になって切れがなくなりました。
これは新しいペンタブレットと描画ソフトで解決するか、ペンで描いた原稿を
スキャナーで取り込むかの、どちらかを取らねばなりません。
PCのモニターで見た感じと実際に印刷された紙面が異なるので、このギャップ
を補正する方法が必要です。
また、作画中の画面が外部に流出しているらしく対策をとらねばなりません。
一方で、レイアウトがいかようにもできる自由度は捨てがたく、ウスズミによる
描画が自在にできるのでスクリーントーンを使わずにすみます。
またPC画面を見る角度が紙面を見下ろす場合に比べて首の疲労が少ないという
メリットがあります。長時間の作業で疲労の軽減は大きな意味があるのです。
また今後の視力の減退を画面の拡大で補えるという点もあると思います。
とりあえずはこの個人誌をポートレートとして就職活動に生かす方向を考えて
いますが、一方でアンチ活動を止めようとしない近隣の一部住民にたいして何らか
の方法で牽制をする必要も出てきました。彼らは私の活動を失敗させる方向に動く
ので、その動機とか目的といったものを探るのはあまり意味がなくなってきました。
手段が目的化していて、もはや利害関係すら皆無の者もこぞってアンチ活動に
参加している有様です。究極的に彼らは私の人生を潰す方向で動いていることは
疑いようがないでしょう。
旧来の引退したウォッチ界隈の諸氏にしても自分たちの活動が受け継がれて
現在の私の迫害が継続されていることに責任を取ってもらわねばならなくなる
でしょう。具体的には教唆とか先導ということになると思いますが、彼らはたかが
馴れ合いという段階ではなくなっている事を自覚すべきです。
今後のイベントの参加に関しては、継続の方向を考えていますが、イベントの
1週ほど前にアンチ活動が異常に盛り上がるという事態が繰り返されるなら、
別の方法もを取らねばならないと考えています。