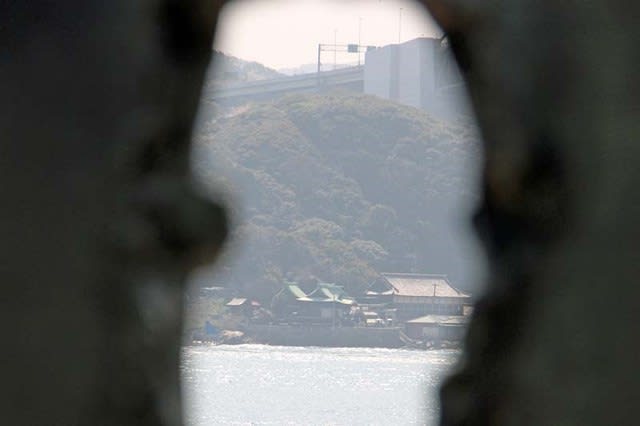2019年4月25日(木)
新緑の熊本城が好きです。
出かけました。
城内二の丸広場にある熊本県立美術館では、「浜田知明回顧展 忘れえぬかたち」が開催されています。

(「浜田知明回顧展」チラシ)

(「浜田知明回顧展」チラシ)

(熊本県立美術館)

(熊本県立美術館)
13時頃について、先ずは美術館の喫茶室「桜Cafe」のテラスで新緑を眺めながらお昼。
気持ちいいです。何を食べても美味しく感じられます。

(二の丸広場から喫茶室のテラス)

(メニュー)

(テラスからの眺め)
食事が終わって、美術館1F会場へ。

(熊本県立美術館正面入り口)

(熊本県立美術館正面入り口)

(熊本県立美術館正面入り口)

(熊本県立美術館内から)

(会場へ)

(1Fへの階段から)
熊本県立美術館には、浜田知明さんの作品を展示する常設のコーナーがあります。企画展の出口の場所にあるので、さまざまな企画展を見学した後に寄って観ています。大規模な作品の展示を観るのは、2015年8月「浜田知明のすべて展」以来になります。
浜田知明さんは、昨年7月に100歳の生涯を終えられました。
パンフレットには、「本展では、作品そのものに注視して頂くよう、浜田の言葉を記したパネルはあえて最小限にとどめます。また制作手順ではなく、主題や造形により作品を分類・展示することで、「反戦の画家」というイメージにとらわれない主題の多様性や、その中に通底する造形性をみてゆく構成とします。」と説明があります。
展示の構成は
第一章 原点のかたち
第二章 体験のかたち
第三章 制作のかたち
第四章 世のかたち
第五章 心のかたち
第六章 幻想のかたち
第七章 仕事のかたち
第八章 平面のかたち/立体のかたち
第九章 忘れえぬかたち
終章 そして兵はゆく
となっています。
浜田さんの作品の中で一番好きなのは「情報過多的人間」です。作品以上に作品名が好きなのかもしれませんが。1975年の作品で当時はこのような言葉は無かったと思います。「情報化社会」という言葉が使われ出したのも、これよりも後のことだと思います。
今回もクスッと、見つめました。
同じ作家の展覧会でも観る時観る時の自分の心境で、関心をもつ作品が変わってきます。今回は、「壁にぶちあたった男とそれを嗤う男」という作品の前で立ち止まりました。
「壁にぶちあたった男」も「それを嗤う男」も、自分自身のように私は感じます。

(「壁にぶちあたった男とそれを嗤う男」)
怒りや、笑いや、をいっぱい感じられました。展示の構成では、「第五章心のかたち」が最も印象に残りました。
5月26日(日)まで開催されています。
同時開催の「熊本地震と文化財」は7月7日(日)まで開催されています。
収蔵品で、熊本地震で壊れ、修復された作品などが展示されています。これまで観たことのない作品も多く、興味津々で観ました。

(美術館掲示板)
私は、美術的な事はわかりません。
中学校の写生大会は熊本城であっていました。春と秋にあっていたのか、春か秋にあっていたのかは忘れました。
春の写生大会の時だったと思います。熊本城のクスノキを描いたら、「新緑はそんな色じゃなかろう。」と注意?批評?されたことを、ふと思い出しました。
そんな程度なので、美術で褒められたことも、成績が良かったこともありません。
歳を重ねても新緑を描くことはありませんが、美術館に行くのは好きです。5月の熊本県立美術館に行くのは、特に好きです。
新緑がいいです。

(写真のクスノキを描いたような?)

(描いた場所付近は立ち入り禁止)

(大天守)

(二の丸広場)

(野鳥園)

(藤崎台のクスノキ・国指定天然記念物)

(護国神社前の広場)

(細川刑部邸)

(熊本市博物館)

(細川刑部邸)

(三の丸駐車場の方から熊本県立美術館)

(二の丸御門跡)

(城内いたるところに崩れた石垣が保存されている)

(百閒石垣)

(土嚢の間からも新しい息吹)

(熊本城大天守・小天守)
新緑の熊本城が好きです。
出かけました。
城内二の丸広場にある熊本県立美術館では、「浜田知明回顧展 忘れえぬかたち」が開催されています。

(「浜田知明回顧展」チラシ)

(「浜田知明回顧展」チラシ)

(熊本県立美術館)

(熊本県立美術館)
13時頃について、先ずは美術館の喫茶室「桜Cafe」のテラスで新緑を眺めながらお昼。
気持ちいいです。何を食べても美味しく感じられます。

(二の丸広場から喫茶室のテラス)

(メニュー)

(テラスからの眺め)
食事が終わって、美術館1F会場へ。

(熊本県立美術館正面入り口)

(熊本県立美術館正面入り口)

(熊本県立美術館正面入り口)

(熊本県立美術館内から)

(会場へ)

(1Fへの階段から)
熊本県立美術館には、浜田知明さんの作品を展示する常設のコーナーがあります。企画展の出口の場所にあるので、さまざまな企画展を見学した後に寄って観ています。大規模な作品の展示を観るのは、2015年8月「浜田知明のすべて展」以来になります。
浜田知明さんは、昨年7月に100歳の生涯を終えられました。
パンフレットには、「本展では、作品そのものに注視して頂くよう、浜田の言葉を記したパネルはあえて最小限にとどめます。また制作手順ではなく、主題や造形により作品を分類・展示することで、「反戦の画家」というイメージにとらわれない主題の多様性や、その中に通底する造形性をみてゆく構成とします。」と説明があります。
展示の構成は
第一章 原点のかたち
第二章 体験のかたち
第三章 制作のかたち
第四章 世のかたち
第五章 心のかたち
第六章 幻想のかたち
第七章 仕事のかたち
第八章 平面のかたち/立体のかたち
第九章 忘れえぬかたち
終章 そして兵はゆく
となっています。
浜田さんの作品の中で一番好きなのは「情報過多的人間」です。作品以上に作品名が好きなのかもしれませんが。1975年の作品で当時はこのような言葉は無かったと思います。「情報化社会」という言葉が使われ出したのも、これよりも後のことだと思います。
今回もクスッと、見つめました。
同じ作家の展覧会でも観る時観る時の自分の心境で、関心をもつ作品が変わってきます。今回は、「壁にぶちあたった男とそれを嗤う男」という作品の前で立ち止まりました。
「壁にぶちあたった男」も「それを嗤う男」も、自分自身のように私は感じます。

(「壁にぶちあたった男とそれを嗤う男」)
怒りや、笑いや、をいっぱい感じられました。展示の構成では、「第五章心のかたち」が最も印象に残りました。
5月26日(日)まで開催されています。
同時開催の「熊本地震と文化財」は7月7日(日)まで開催されています。
収蔵品で、熊本地震で壊れ、修復された作品などが展示されています。これまで観たことのない作品も多く、興味津々で観ました。

(美術館掲示板)
私は、美術的な事はわかりません。
中学校の写生大会は熊本城であっていました。春と秋にあっていたのか、春か秋にあっていたのかは忘れました。
春の写生大会の時だったと思います。熊本城のクスノキを描いたら、「新緑はそんな色じゃなかろう。」と注意?批評?されたことを、ふと思い出しました。
そんな程度なので、美術で褒められたことも、成績が良かったこともありません。
歳を重ねても新緑を描くことはありませんが、美術館に行くのは好きです。5月の熊本県立美術館に行くのは、特に好きです。
新緑がいいです。

(写真のクスノキを描いたような?)

(描いた場所付近は立ち入り禁止)

(大天守)

(二の丸広場)

(野鳥園)

(藤崎台のクスノキ・国指定天然記念物)

(護国神社前の広場)

(細川刑部邸)

(熊本市博物館)

(細川刑部邸)

(三の丸駐車場の方から熊本県立美術館)

(二の丸御門跡)

(城内いたるところに崩れた石垣が保存されている)

(百閒石垣)

(土嚢の間からも新しい息吹)

(熊本城大天守・小天守)