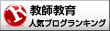バズる関西トレンド 万博、IRに熱視線! 大阪市内にホテルの新規開業、リニューアル続々…外資ホテルブランドも日本初進出の地として
夕刊フジ8/24(木)11:00

グランドプリンスホテル大阪ベイ
2年後の大阪・関西万博に続き、2029年には統合型リゾート(IR)の開業をめざす大阪では、ホテルの新規開業やリニューアルが相次いでいる。なかでも万博会場の夢洲(ゆめしま)があるベイエリアを中心とした地域はポテンシャルが高く、外資ホテルの期待も大きい。
西武ホールディングスの「西武・プリンスホテルズワールドワイド」は、大阪・南港のハイアットリージェンシー大阪をリブランドし、7月1日「グランドプリンスホテル大阪ベイ」としてオープンした。同ホテルを16年に取得した星野リゾート・リートが引き続きオーナーとなり、西武・プリンスホテルズは、アセットライト戦略(資産保有を抑える手法)に基づき、運営に特化する。フルサービスを備えたグランドプリンスホテルとしては、悲願の大阪初出店となる。
「大阪ベイエリアは今後大きく発展すると見込まれ、MICE(国際会議等)の誘致にも適している。大阪湾に面しているので絶景体験を提供できることも出店の背景にあった」と同ホテルの大崎誓也総支配人は話す。
客室数は480室で、うち星野リゾートが運営するリゾナーレ大阪が64室。20の宴会場と330台収容の大型駐車場を有しているのも強みだ。リブランド後は、老朽化する建物の改装も検討するという。
世界の注目が集まることから、外資ホテルブランドも日本初進出の地として大阪を選ぶ。
インターコンチネンタルホテルをはじめ、世界に約6000ホテルを有するIHGホテルズ&リゾーツは、5月30日、「voco大阪セントラル」を開業した。
大阪メトロ肥後橋駅から徒歩3分の西区京町堀。大正レトロの風情で親しまれてきた旧京町ビル跡地に建ち、同ビルで実際に使われていた鋼製扉や郵便ポスト、レリーフなどを再利用した斬新なデザインが印象的だ。客室でくつろげることを重視し、全191の客室には寝心地の良い寝具や環境に配慮したアメニティが揃う。地元客も気軽に集えるレストランとカフェ&バーも人気だ。
インバウンドが特に目立つ難波エリアには、タイの高級ホテルブランド「センタラグランドホテル大阪」が7月1日開業した。「タイと日本の美と文化の融合」をコンセプトにした空間を特徴とし、タイ特有の温かみのあるホスピタリティでゲストを出迎える。客室数は515室。最上階のルーフトップレストランをはじめとする8つのレストランやタイの三輪タクシー「トゥクトゥク」での送迎が自慢だ。
ホテルの開業ラッシュによる競争激化を指摘する声もあるが、西武ホールディングスの後藤高志会長兼CEOは「競争によって日本のホテル業界は強くなった。プリンスホテルも経営改革の成果をアフターコロナで発揮したい」と、自信を見せた。
■橋長初代(はしなが・はつよ) フリーライター。関西を拠点に商業施設、百貨店、専門店、アパレル、ホテルなどの動向をビジネス系メディアに寄稿。取材では現場での直感と消費者目線を重視。2019年に実家のある奈良にUターン。最近は、奈良の歴史と文化に魅了され、地元の情報誌やSNSでの発信にも力を入れている。』.
2025年4月13日の開催日までに全てのパビリオンの建築も必要不可欠の上下水道の工事も完了出来るかどうかも分かりません。
取らぬ狸の皮算用です。