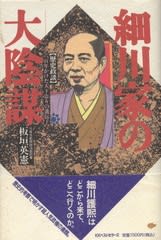これまた予想外!
先日、世界一コーヒー党が多い国が予想外で、へ~って思いましたけど、世界一紅茶党が多い国も紅茶から連想しない国が堂々のトップでした。
こちらの世界地図は、今回もビジネス系ニユースサイトQuartzが市場調査会社ユーロモニター(Euromonitor)のデータを使用して作った「紅茶党が多い国はどこ?マップ」ピンクの色が濃ければ濃いほど紅茶党が多い国を現しています。日本も若干濃いめですね。
このデータの目安になっているのは1年間で一人当たり何グラムの茶葉を消費しているか?なのですが、1位は約3キロ、2位は約2キロなので、ぶっちぎりの消費量なんです。
一般的に、紅茶が好きな人が多い国といってパっと頭に浮かぶのはイギリスですよね? でもイギリスは 3位…。なんと1位はトルコなんです! そして2位はアイルランドという結果でした。
最初にランキングのトップにトルコって出たと時は「ん?」と思ったけれど、トルコに行った時、広場でも道端でもお土産物の店先でも小さなガラスのコップに入ったレモン・チャイ、リンゴ・チャイ、ストレート・チャイを、チャイ屋さんにデリバリーしてもらって飲んでいて、私自信も1日何杯飲むんだ?ってぐらいご馳走してもらっていたのを思い出しました。それだけに、コーヒーの消費量は1日あたり0.3杯と本当に少ないんですね。
ちなみに日本は9位で1年間で一人当たりの消費量は約970グラム。これは予想外なのか? まぁ、そんなもんだよね。なのかな?[Quartz]
トルコは、トルココーヒで世界的に有名なのでコーヒが沢山飲まれていると思いましたが、さにあらずの不思議発見ですね。紅茶の健康への良い影響を発表して欲しいです。
トルココーヒー
トルコ・コーヒー (トルコ語: Türk Kahvesi - テュルク・カフヴェスィ 英語: Turkish coffee - ターキッシュ・コーヒー) は、コーヒーの淹れ方の一種。水から煮立てて、上澄みだけを飲む方法である。
2013年にユネスコの無形文化遺産にトルココーヒーの文化と伝統が登録された。
歴史
- オスマン帝国内のイエメン統治者オズデミル・パシャにより、コーヒー豆が皇帝に献上されたのが、約450年前。まずイスタンブルのタフタカレ地区でコーヒーが飲まれるようになり、その後ヨーロッパに広まる。
- 現在でもこの伝統的なコーヒーの飲用法は、中東・北アフリカ・バルカン諸国で共通している。
概略
飲み方
- 用意する道具としては、粉状にされたコーヒー豆・冷水・ティースプーン、トルコではジェズヴェ(Cezve)と呼ぶコーヒー用の鍋、それがなければ小さな手鍋。この鍋の深さはコーヒーの粉が沈むのに十分なほどであればよい。ジェズヴェは銅でできたヒシャク型で、木の把手がついている。
- コーヒーの粉はティースプーンに1杯が、1人分の分量である。コーヒーと砂糖を同じ割合でジェズヴェに入れる。水を1人あたりカップ1杯ずつ、多すぎないように注意しながらジェズヴェに入れる。煮立てて沸騰してきたら火を弱め、浮かんできた泡をカップに等分に分けて入れる。ふきこぼれる寸前に火を止めて、ジェズヴェにあるコーヒーをカップに注ぐ。粉が沈むのを待って上澄みを飲む。好みによって、カルダモンで風味をつけることがある。
コーヒー占い
- 飲み終わった後のカップにソーサーをかぶせてひっくり返し、カップの底に残った粉の状態によって飲んだ者の運勢を占う「コーヒー占い」がある。
諺について
トルコには他人に親切にせよという意味で、「1杯のコーヒーにも40年の思い出」という諺がある。トルコ語で「40」には「かなり大きな数」という意味があり、「40年の思い出」とは「長年の思い出」ということになる。つまり、他人に1杯のコーヒーをご馳走するだけで、その親切をなにかにつけて思い出してもらえるものだ、という教えになる。
参考文献
- 大島直政『遊牧民族の知恵 トルコの諺』講談社現代新書、1979年。 ISBN 4-06-145546-X














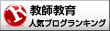

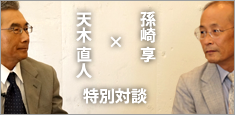
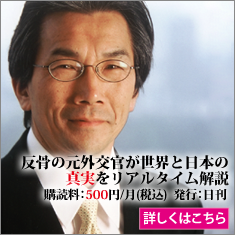


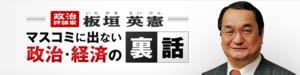


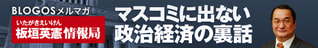
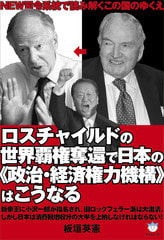
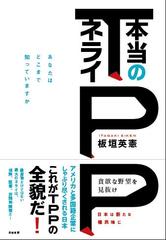
 1月開催の勉強会がDVDになりました。
1月開催の勉強会がDVDになりました。