なれる
昔、職場で3つの「なれ」ということで
慣れ→馴れ→狎れというパターンが多いので
気をつけるよう、教えられた。
私も今、新人教育の場ではかならずこの話をする。
慣れ→馴れは楽しいし、ある部分までは何事においても必要だと思う。
ただそこから狎れまでは思いの外近い。
ブログのコメントも同じかもしれない、と
ふと思った。
(ちょっとコメントについて考える機会があったからですが)
自分が書けば、必ず相手に受け入れてもらえる、という環境が
必ずしも「よい」だけのものだとは私は思わない(「悪い」でもないけれど)。
逆に、この人だったら、これくらいのことを書いても
大丈夫、というのも・・・
・・・「大丈夫」というのは、あくまで自分の希望的観測(相手への期待)
にすぎないという認識が必要かなと。
ブログではよほどひどい内容でない限り、
&たとえ相手とズレがあって、ブログ主には若干不愉快なコメントであっても
相手に悪意がないと感じられる場合、
コメントくれる相手をむげにはできないだろう(という暗黙の前提がある)。
特に以前から交流がある場合には・・・
ある種、そういうケアレスミス(という表現が正しいかどうかはわからないけれど)
や勘違い、思い込みは、お互い様だという部分もあるだろう。
コメント欄は場合によっては、知りあい同士の
交流場でもあるので、ブログ主がなにも思わなくても、
「この人どうしてこんなコメントしてるんだろう?」
とか「どうしてコメントしないんだろう?」とか
他の参加者が感じるケースもあるだろう
意識的に特定ブロガーに対し、マイナスの意思表示をするために
“コメントはずし”をできる人がいることも残念ながら経験済み。
(巡回先全員にコメントする人だったので、
私にだけコメントがないことは当然すぐにわかったけれど、
なんか他の交流者を心配させる気がして、「ま、いいか」としていたのですが
「どうせ私には関心がないのだろう」的逆ギレされてめっちゃ驚いた・・・。
・・・本当に、いろんな考え方や受け取り方があるなぁ、と。
無視することで、一体どんな反応を期待してたんだろう・・・???)
暗黙の了解やルール、ネチケットと平行しつつ
コメントやレスの意味合いや価値付けはブロガーによって全く異なるとも思う。
コメントに対し、ほぼすべて好意的解釈でウエルカムできる方もいれば
勝手知ったる(上記のお互い様許容内な)相手とのみ交流する方もいれば、
一切コメントを必要としない方もいる。
ブログ創世記には、コメント欄を閉鎖しているブロガーへの批判があったが、
今では、それもまた正しいあり方の1つとして確立している。
(余談ですが、メールや電話という別の手段があることは
時としてブラックボックスを作るなぁ、と。
これは前に大失敗;があったので、自分が使う場合は要注意であります。
ブロガー交流の基本はやはり記事とコメントだと思う頑ななヤツであった;)
親しくなる、というのは、どこかでなにかをゆるめる行為だと思う。
ただ、そのゆるめ加減は難しい。
「親しき仲にも礼儀あり」は、礼儀以前に「親しさ」の度合いが
重要なのだと思う。
ネットでもリアルでも、一方的に「親しい」と錯覚してしまうケースは
多い気がする。・・・もちろん私を含めて。
“自分なら大丈夫だ”と錯覚するのは、ある種の自信過剰と
相手の思いやり(好意的解釈を含め)ゆえだろう。
もちろん、そんなことで迷う&悩むなら、
コメントを書かなければいいだけの話だとも言えるわけだけれど。
それでも、相手と関わりを持ちたい場合は、
働き掛けなければ=書かなければ始まらない部分はある。
そこに葛藤がある。
このブログは、基本的にどんな書き込みも
ブログ主のその時の「素」(ってコレが案外クセモノなわけだが)
で対応しているつもりで、
私がイヤなものはスルーするし、自分にとってはマイナスコメントでも興味を持てばレスをさせていただく。
参加してくださる方々には
「こんなレスが欲しかったわけじゃないのに・・・」
というケースも多々あるかもしれません・・・。
同時に、私が参加させていただくコメントで
不愉快な思いをさせている危険性もある。
こういうコメント、レスを書いたほうがいいんだろうな、と
一般常識的&経験上、わかってる場合もあるのですが、
それがなにも思わずに実行できる時と、何故かできない時があるようです。
こういうコメントってこの人にはウザいだろうな、とかも同じ・・・
それでも書けない、それでも書く、そこに関しては自分に甘いと
言われても仕方がない。
・・・完全な人間はいない&完全なコミュニケーション、
完全なコメント、完全なレスはない、とも思いつつ
それもまた「狎れ」かもしれない。
様々な「狎れ」について、自戒するとともに
負荷をかけた(ている)かもしれない皆様に、ここで深く謝罪いたします。
そして、そういう私だとわかったうえで、
なおも111を訪ねて下さる皆様に、改めて深く感謝いたします。
ちなみになれ寿司のなれは「熟れ」。
なんとなくいろんなものがうまくこなれて、独特の味わいになるという
イメージが今わいた。
慣れ→熟れになれるよう頑張りたいと思います。
追記:
っと、ひさびさにごちゃごちゃ書いてしまいましたが、
「コメントしたい」という思いは「愛」だとも思う。
語らなければはじまらない思いも関係もある。
書きたければ書きたいことを書く!
あとは相手に任せるしかない。
やるだけやって、あとは
両思いになるか、片思いのままか、失恋するか、罵られるか
その結果を潔く受け入れるのみかな、と。
追記2:
当然ながら、コメントやレスの前に、ブログの方向性の差も大きい。
(これも何度も書いているけれど)
たとえば、家族だけとか、卒業生だけとか、主婦だけとか、20代だけとか、
特定エリアとか、特定のファン、特定の趣味・・・
さまざまなコミュニティ型でのコメント交流はまたまったく
性格が異なると思います。
(・・・とはいえ、密度が濃ければ濃いで、トラブルは
あるのだけれど・・・
人間はワガママな生き物であり、他者と関わりたい生き物であり、
経験の有無を通してのみ変化・進化・退化する生き物ゆえに)
昔、職場で3つの「なれ」ということで
慣れ→馴れ→狎れというパターンが多いので
気をつけるよう、教えられた。
私も今、新人教育の場ではかならずこの話をする。
慣れ→馴れは楽しいし、ある部分までは何事においても必要だと思う。
ただそこから狎れまでは思いの外近い。
ブログのコメントも同じかもしれない、と
ふと思った。
(ちょっとコメントについて考える機会があったからですが)
自分が書けば、必ず相手に受け入れてもらえる、という環境が
必ずしも「よい」だけのものだとは私は思わない(「悪い」でもないけれど)。
逆に、この人だったら、これくらいのことを書いても
大丈夫、というのも・・・
・・・「大丈夫」というのは、あくまで自分の希望的観測(相手への期待)
にすぎないという認識が必要かなと。
ブログではよほどひどい内容でない限り、
&たとえ相手とズレがあって、ブログ主には若干不愉快なコメントであっても
相手に悪意がないと感じられる場合、
コメントくれる相手をむげにはできないだろう(という暗黙の前提がある)。
特に以前から交流がある場合には・・・
ある種、そういうケアレスミス(という表現が正しいかどうかはわからないけれど)
や勘違い、思い込みは、お互い様だという部分もあるだろう。
コメント欄は場合によっては、知りあい同士の
交流場でもあるので、ブログ主がなにも思わなくても、
「この人どうしてこんなコメントしてるんだろう?」
とか「どうしてコメントしないんだろう?」とか
他の参加者が感じるケースもあるだろう
意識的に特定ブロガーに対し、マイナスの意思表示をするために
“コメントはずし”をできる人がいることも残念ながら経験済み。
(巡回先全員にコメントする人だったので、
私にだけコメントがないことは当然すぐにわかったけれど、
なんか他の交流者を心配させる気がして、「ま、いいか」としていたのですが
「どうせ私には関心がないのだろう」的逆ギレされてめっちゃ驚いた・・・。
・・・本当に、いろんな考え方や受け取り方があるなぁ、と。
無視することで、一体どんな反応を期待してたんだろう・・・???)
暗黙の了解やルール、ネチケットと平行しつつ
コメントやレスの意味合いや価値付けはブロガーによって全く異なるとも思う。
コメントに対し、ほぼすべて好意的解釈でウエルカムできる方もいれば
勝手知ったる(上記のお互い様許容内な)相手とのみ交流する方もいれば、
一切コメントを必要としない方もいる。
ブログ創世記には、コメント欄を閉鎖しているブロガーへの批判があったが、
今では、それもまた正しいあり方の1つとして確立している。
(余談ですが、メールや電話という別の手段があることは
時としてブラックボックスを作るなぁ、と。
これは前に大失敗;があったので、自分が使う場合は要注意であります。
ブロガー交流の基本はやはり記事とコメントだと思う頑ななヤツであった;)
親しくなる、というのは、どこかでなにかをゆるめる行為だと思う。
ただ、そのゆるめ加減は難しい。
「親しき仲にも礼儀あり」は、礼儀以前に「親しさ」の度合いが
重要なのだと思う。
ネットでもリアルでも、一方的に「親しい」と錯覚してしまうケースは
多い気がする。・・・もちろん私を含めて。
“自分なら大丈夫だ”と錯覚するのは、ある種の自信過剰と
相手の思いやり(好意的解釈を含め)ゆえだろう。
もちろん、そんなことで迷う&悩むなら、
コメントを書かなければいいだけの話だとも言えるわけだけれど。
それでも、相手と関わりを持ちたい場合は、
働き掛けなければ=書かなければ始まらない部分はある。
そこに葛藤がある。
このブログは、基本的にどんな書き込みも
ブログ主のその時の「素」(ってコレが案外クセモノなわけだが)
で対応しているつもりで、
私がイヤなものはスルーするし、自分にとってはマイナスコメントでも興味を持てばレスをさせていただく。
参加してくださる方々には
「こんなレスが欲しかったわけじゃないのに・・・」
というケースも多々あるかもしれません・・・。
同時に、私が参加させていただくコメントで
不愉快な思いをさせている危険性もある。
こういうコメント、レスを書いたほうがいいんだろうな、と
一般常識的&経験上、わかってる場合もあるのですが、
それがなにも思わずに実行できる時と、何故かできない時があるようです。
こういうコメントってこの人にはウザいだろうな、とかも同じ・・・
それでも書けない、それでも書く、そこに関しては自分に甘いと
言われても仕方がない。
・・・完全な人間はいない&完全なコミュニケーション、
完全なコメント、完全なレスはない、とも思いつつ
それもまた「狎れ」かもしれない。
様々な「狎れ」について、自戒するとともに
負荷をかけた(ている)かもしれない皆様に、ここで深く謝罪いたします。
そして、そういう私だとわかったうえで、
なおも111を訪ねて下さる皆様に、改めて深く感謝いたします。
ちなみになれ寿司のなれは「熟れ」。
なんとなくいろんなものがうまくこなれて、独特の味わいになるという
イメージが今わいた。
慣れ→熟れになれるよう頑張りたいと思います。
追記:
っと、ひさびさにごちゃごちゃ書いてしまいましたが、
「コメントしたい」という思いは「愛」だとも思う。
語らなければはじまらない思いも関係もある。
書きたければ書きたいことを書く!
あとは相手に任せるしかない。
やるだけやって、あとは
両思いになるか、片思いのままか、失恋するか、罵られるか
その結果を潔く受け入れるのみかな、と。
追記2:
当然ながら、コメントやレスの前に、ブログの方向性の差も大きい。
(これも何度も書いているけれど)
たとえば、家族だけとか、卒業生だけとか、主婦だけとか、20代だけとか、
特定エリアとか、特定のファン、特定の趣味・・・
さまざまなコミュニティ型でのコメント交流はまたまったく
性格が異なると思います。
(・・・とはいえ、密度が濃ければ濃いで、トラブルは
あるのだけれど・・・
人間はワガママな生き物であり、他者と関わりたい生き物であり、
経験の有無を通してのみ変化・進化・退化する生き物ゆえに)











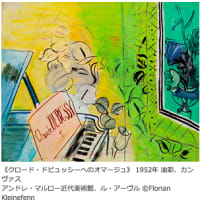
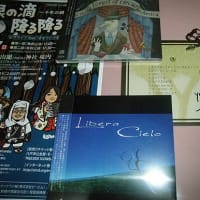












それと(ってまだ読めないか)このコメント無関係ねー。
と前提しておいて。
--
目で見えない文字のやり取りだから仕方ないと思うのよ
普段から「ただ聞いて欲しい人」と「アドバイスが欲しい人」とがいて
さらにその時の体調やら何やらで変わるんだから。
その体調までは文字では追えないものがあると思う。
日々一緒に生活している者同士でさえ、時には身近だからこそ、かな。
それを補っている一面が例えばブログだったりする訳で。
全て出している人も、一面だけの人もいてそういのが
ぐちゃぐちゃだから面白いとも思ったり。
何事もテキトーが1番なのよー。テキトーが。
悩んで解決するのなら、最初から悩む出来事にならないんだから。
そう思うのでごじゃいます。
その前にレスしちゃえー<オイオイ
や、「コメントだけでブロガーの交流は成立するのか」と
いうことを考える機会があって、あれこれ考えてるうちに
こんな記事になってしまったわけですが・・・。
私は自分のurlがないブロガーは(「ブロガー」という意味では)信用できない、
というのが基本姿勢ではあるけれど、結局はブログの有無ではなく、
相手を信用できるか(というか受け入れられるか)どうかなのかも。
(あくまで自分の基準、自分の問題としてですが)
で、なにか相手に伝えたいことがあったとして、
私がどう頑張っても、相手にそれが伝わらなければ
信用しているかどうかすら、無意味だとも思うわけで・・・。
で、それとは逆に、自分が相手の真意を受け取れないというケースもあるわけで。
そもそも真意って、わかるものなの?
とかずぶずぶ深みにはまってくわけですが。
それはきっと実はリアルでも、ネットでも。
で、その振れ幅含めて「コミュニケーション」という
ものなのかもしれないと思ったり・・・。
>時には身近だからこそ、かな。
これは絶対にありますねー。
狎れも含めて。というか、身近になればなるほど
接触度が高ければ高いほど、理解しあえればしあえるほど
違和感があった時にはギャップが大きい(相手への期待もまた大きいから)、
と思ったり。
と、またまたアレコレ書いちゃいましたが、
両思い、片思い・・・要は「愛」なのかも。(大きくまとめたな;
そういう意味ではコメントを書くのも受け取るのも
「愛」は必需品なのかもしれないなぁ、と思うのでした。
なんてことを、考えるのはキライじゃないので、
まぁ、ぐだぐだですがまたやっちゃうことだと思います。
コメントありがとうごじゃいました。