前回に続くが、三日前の土曜日午後、窯焼きパンのカフェに出かけて、今度は蒸し暑さで、さすがに庭のテーブルには座る気になれないで、パンの山積みになった店内のカフェに座った。自転車だったので、身体にべっとりとはりつい暑気は、十分な冷房でたちまち遠のいていった。あんパンとピーチのジュースと熱いコーヒーと冷水を並べて、外をながめながらゆったりとした時間を過ごした。書こうとしている映画天安門、恋人たちは、今ここにある消費の光景とは、あまりにも対照的であるのを思い出すのであった。
『天安門、恋人たち』(2006年中国・フランス製作監督ロウ・イエ)
この映画は、映画祭公開の前に試写会があり、宮崎市民ホールの小会議室で見た。タイトルの天安門(事件)があるわけでもなく、北京の北清大学の学生たちが、政治や民主化運動を語るでもない。地方都市から北京の北清大学に合格して、進学してきた美人女性ユー・ホンは、チョウ・ウエイと出会い、二人は恋人となる。学生寮の狭い部屋でくりかえされる、二人の性交シーンがえんえんとつづく。思想もなく革命もなく、愛をむさぼりあいながら、満たされぬ想いがユー・ホンを孤独に追い込んでいく。見終わって感想をしゃべるのだが、端的に言ってポルノとしか言いようが無かった、他に何があるのかと、加賀さん(今年より同映画祭実行委員長)には印象を語った。そのまま、この映画をもう一度見ようという食指はうごかなかった。
そして映画祭当日に、「お引越し」を見ようとやって来たら「天安門」であった。と加賀さんが会場の入り口に立っていて、帰ろうとしたぼくを引きとめて、天安門をこの映画館でもう一度見るようにとすすめられた。「ポルノとは、ちょっと違うと、思うんですよね・・」と彼女は言うのであった。たしかにポルノと切ってすてられない、なにかがある、やはり天安門かな、いや中国政治への批判なのか・・。なにかあるような、「とにかくもう一度見て」と乞われて、よし今度はロウ・イエが二人の恋人をどう描いたか、そこだけを追ってみようと館内に入った。
そしたら、今度は、きわめて単純な、ありふれた大学生という若き日の男女の恋物語だとすらりとついていけた。相手をすべて所有したくなる恋のすれ違いで、破れていった恋であった。こんな話は、凡庸であるものの、この主題は手練手管を使って、文学に映画で繰り返されてきている。この映画では、たいした山もなく展開もなく、落ちも平板、なんとも既知の常識そのものの恋の悲劇が進んでいくばかりであった。だからこそ、この物語が印象にのこらなかったのだ。それは壷に描かれた薄い平凡すぎるデザインであったがため、印象にのこらず、その土台の壷が、その壷の実在だけが残ってしまったのだ。その壷の正体は、しかし、試写会の会場では分らずじまいであったのだ。
見終わってありありと分ってきたのは、この壷の存在であった。それはロウ・イエが表現した中国社会、1989年の首都北京、その大学おそらく北京大学をあらわす北清大学を中心にした中国である。それは、目を疑うような大学女子寮の内部で現されていた。経済発展以前の寮である。今と対比して、近過去の風物を並べて失われた空間の美や豊かさを示す手法は多い。しかし、これとは、本質的に違うのだ。この古さには、美と豊かさなどはないのだ。4人部屋なのか、木製の2段ベッドが向き合いにあり、汚れきったあり合わせの布でし切ってある。窓もなく、片隅ではごぎぶりが這い回っているような不潔さが漂っているのだ。学生たちは、このベッドに腰掛けて、タバコの煙にまかれながら、酒を飲んだり、食い物を食ったりし、ときには空いた部屋でセックスをしたりして過ごす。一見したとき、ここは、捕虜収容所と思ったほどである。
米国のディスコ音楽ががんがんと流れ、学生たちは飲んだり、食ったり踊ったりするホールの中で二人は一目惚れとなるのだが、そこから、女子寮は、二人の性交の部屋となる。教室では、授業よりも、騒然としたムダ話が飛び交い、そしてひたすら遊びと異性を求める学生たちの姿が溢れかえっているのだ。天安門へという民主化デモへの運動は、そんなある日起こり、学生たちはディスコに大挙おしかけるお祭り騒動となって涌き上がる。たちまち銃声にけ散らされて、逃げ惑い、ユーホンも寮ににげてくるだけだ。天安門事件とは、このシーンだけが挿入された。映画が発禁になったとき、ロウ・イエは政治は主題ではない、描いても無いと言ったそうだが、はたしてそうなのか、正面切って描かないからこそ、中国の80年代政治の暗さが、観客に衝撃を与えるのではないか。先進国の欧米の知識人の中国批判を満足させる重たいリアリズムがかれらを心地よくさせたのであろうかと、思うのである。
ユー・ホウは、ある日、チョウ・ウエイの浮気を知って、かれの室に泊まろうとして激しい争いとなり、自分の室内に帰ってくる。部屋では1人の女性が、楽器、小さな竪琴を弾いている。その前を怒りのまま横切って、2段ベッドの端で、いきなりスカートをまくりパンツを膝まで押し下げると、しゃがんだまま、排泄行為に入るのだ。この光景は、一体何を意味するのか、いや排泄と見るほうが間違いだったのか、信じられないままだ。しかし、たしかにパンツを膝まで下ろし、排便するしゃがんだ姿勢で、怒りをおさえつづける姿に、排便のほかになにを想像しよというのだろうか。しかも、同じ部屋のベッドに腰を下ろして、平然と竪琴を奏でつづける相室の女性の動じぬ姿は、なにを意味するのか。以前、中国でうんこをするとき、囲いもなく溝の上の梁に一列にならんですると聞いたことがあるが、大小便の姿は、恥ずかしいものでもなく、きわめて日常的な習慣だという。そう思うしかないのであるが、しかし、この光景、しかも中国の名門大学を意味する大学寮の部屋で排便とは、このシーンを中国政府は、認められるのであろうかと、思うのだった。まさにこの光景こそ、痛烈なギャグではないか。しかし、ギャグなど挿入のしようもない、重たいリアリズムシーンが、この映画の基調ではある。
開放感のない陰々としたシーンと、激情のように沸き立つ群集シーンは、天安門のきわだつ表現である。この壷の表面で恋人たちの葛藤が深くなっていく。はじめ、せリフがないといったが、ヒロインのユー・ホウの表情が、じつは多くを語っていたのだ、性交における喜びよりも虚しさ、日常のあてどもない空白の日々、それらの空しさの表情だけが見事に表現される。それは若い学生の恋というような個人的な人生など、なんの意味をもないと、経済発展に驀進する中国社会の全体主義への絶望と重なっている。ロウ・イエは映画のシーンにこの想いを込めているのだ。それを意図したかしないかと問う以前に、かくも暗く否定的に壷を表現せざるを得なかった内面に、祖国へ突きつけるノーがあったと言えよう。それは大胆であり、巧妙であり、創造的な奇才を感じさせた。
しかし、ぼくは、この映画の表現に共感できないのだ。製作された2006年といえば、すでに中国には2億人とも2億5千万人ともいえる中間所得層が大都市を中心に誕生している。もし、部屋で大小便するような、ごぎぶりが這いずり回るような中国の未開発住居などはいっそうされていたろうし、また、こんな、その遅れなどは、いっしゅんに片付けられる都市問題に過ぎないのだ。また今や、世界中の商社や、工場、チェーン店、サービス産業が集まってきている北京やその他の大都市で、この中間層には、ぼくらと同じようなアメリカ的消費生活やライフスタイルが始まっていると思うのが妥当であろう。ゴキブリが這い回るような暗さはもはや意味をなさない。共産党一党独裁で、民主化が抑圧されている中国社会も、変わってこざるをえない。中国の暗い、鬱屈したイメージでは、89年以降の中国の本質をとらえることは出来ないのではなかろうか。われわれと同じような消費文明の巨大な危機こそ問題で、未来の危険こそ共有しているのではないかと考えられる。
こう思うときに、ロウ・イエの手法は、このままでは、早晩行き詰ってくるはずである。映画もっと、楽しくし、異相であっても未来を孕む歓楽的なシーンで、問題の所在を明らかにして、告発、解決への希望を提示するのが本筋と、ぼくは思うのである。現在、いろいろと国家の対面だけを前面に押し出している中国政府もグロバーリズムを抱え込み、次第に民衆主体にならざるをえないだろうと思う。この映画を見て、中国の共産党一党支配の人民抑圧をイメージしていく、独裁政治に過度に反応することは、問題をとらえられないかもと思うのであった。
『天安門、恋人たち』(2006年中国・フランス製作監督ロウ・イエ)
この映画は、映画祭公開の前に試写会があり、宮崎市民ホールの小会議室で見た。タイトルの天安門(事件)があるわけでもなく、北京の北清大学の学生たちが、政治や民主化運動を語るでもない。地方都市から北京の北清大学に合格して、進学してきた美人女性ユー・ホンは、チョウ・ウエイと出会い、二人は恋人となる。学生寮の狭い部屋でくりかえされる、二人の性交シーンがえんえんとつづく。思想もなく革命もなく、愛をむさぼりあいながら、満たされぬ想いがユー・ホンを孤独に追い込んでいく。見終わって感想をしゃべるのだが、端的に言ってポルノとしか言いようが無かった、他に何があるのかと、加賀さん(今年より同映画祭実行委員長)には印象を語った。そのまま、この映画をもう一度見ようという食指はうごかなかった。
そして映画祭当日に、「お引越し」を見ようとやって来たら「天安門」であった。と加賀さんが会場の入り口に立っていて、帰ろうとしたぼくを引きとめて、天安門をこの映画館でもう一度見るようにとすすめられた。「ポルノとは、ちょっと違うと、思うんですよね・・」と彼女は言うのであった。たしかにポルノと切ってすてられない、なにかがある、やはり天安門かな、いや中国政治への批判なのか・・。なにかあるような、「とにかくもう一度見て」と乞われて、よし今度はロウ・イエが二人の恋人をどう描いたか、そこだけを追ってみようと館内に入った。
そしたら、今度は、きわめて単純な、ありふれた大学生という若き日の男女の恋物語だとすらりとついていけた。相手をすべて所有したくなる恋のすれ違いで、破れていった恋であった。こんな話は、凡庸であるものの、この主題は手練手管を使って、文学に映画で繰り返されてきている。この映画では、たいした山もなく展開もなく、落ちも平板、なんとも既知の常識そのものの恋の悲劇が進んでいくばかりであった。だからこそ、この物語が印象にのこらなかったのだ。それは壷に描かれた薄い平凡すぎるデザインであったがため、印象にのこらず、その土台の壷が、その壷の実在だけが残ってしまったのだ。その壷の正体は、しかし、試写会の会場では分らずじまいであったのだ。
見終わってありありと分ってきたのは、この壷の存在であった。それはロウ・イエが表現した中国社会、1989年の首都北京、その大学おそらく北京大学をあらわす北清大学を中心にした中国である。それは、目を疑うような大学女子寮の内部で現されていた。経済発展以前の寮である。今と対比して、近過去の風物を並べて失われた空間の美や豊かさを示す手法は多い。しかし、これとは、本質的に違うのだ。この古さには、美と豊かさなどはないのだ。4人部屋なのか、木製の2段ベッドが向き合いにあり、汚れきったあり合わせの布でし切ってある。窓もなく、片隅ではごぎぶりが這い回っているような不潔さが漂っているのだ。学生たちは、このベッドに腰掛けて、タバコの煙にまかれながら、酒を飲んだり、食い物を食ったりし、ときには空いた部屋でセックスをしたりして過ごす。一見したとき、ここは、捕虜収容所と思ったほどである。
米国のディスコ音楽ががんがんと流れ、学生たちは飲んだり、食ったり踊ったりするホールの中で二人は一目惚れとなるのだが、そこから、女子寮は、二人の性交の部屋となる。教室では、授業よりも、騒然としたムダ話が飛び交い、そしてひたすら遊びと異性を求める学生たちの姿が溢れかえっているのだ。天安門へという民主化デモへの運動は、そんなある日起こり、学生たちはディスコに大挙おしかけるお祭り騒動となって涌き上がる。たちまち銃声にけ散らされて、逃げ惑い、ユーホンも寮ににげてくるだけだ。天安門事件とは、このシーンだけが挿入された。映画が発禁になったとき、ロウ・イエは政治は主題ではない、描いても無いと言ったそうだが、はたしてそうなのか、正面切って描かないからこそ、中国の80年代政治の暗さが、観客に衝撃を与えるのではないか。先進国の欧米の知識人の中国批判を満足させる重たいリアリズムがかれらを心地よくさせたのであろうかと、思うのである。
ユー・ホウは、ある日、チョウ・ウエイの浮気を知って、かれの室に泊まろうとして激しい争いとなり、自分の室内に帰ってくる。部屋では1人の女性が、楽器、小さな竪琴を弾いている。その前を怒りのまま横切って、2段ベッドの端で、いきなりスカートをまくりパンツを膝まで押し下げると、しゃがんだまま、排泄行為に入るのだ。この光景は、一体何を意味するのか、いや排泄と見るほうが間違いだったのか、信じられないままだ。しかし、たしかにパンツを膝まで下ろし、排便するしゃがんだ姿勢で、怒りをおさえつづける姿に、排便のほかになにを想像しよというのだろうか。しかも、同じ部屋のベッドに腰を下ろして、平然と竪琴を奏でつづける相室の女性の動じぬ姿は、なにを意味するのか。以前、中国でうんこをするとき、囲いもなく溝の上の梁に一列にならんですると聞いたことがあるが、大小便の姿は、恥ずかしいものでもなく、きわめて日常的な習慣だという。そう思うしかないのであるが、しかし、この光景、しかも中国の名門大学を意味する大学寮の部屋で排便とは、このシーンを中国政府は、認められるのであろうかと、思うのだった。まさにこの光景こそ、痛烈なギャグではないか。しかし、ギャグなど挿入のしようもない、重たいリアリズムシーンが、この映画の基調ではある。
開放感のない陰々としたシーンと、激情のように沸き立つ群集シーンは、天安門のきわだつ表現である。この壷の表面で恋人たちの葛藤が深くなっていく。はじめ、せリフがないといったが、ヒロインのユー・ホウの表情が、じつは多くを語っていたのだ、性交における喜びよりも虚しさ、日常のあてどもない空白の日々、それらの空しさの表情だけが見事に表現される。それは若い学生の恋というような個人的な人生など、なんの意味をもないと、経済発展に驀進する中国社会の全体主義への絶望と重なっている。ロウ・イエは映画のシーンにこの想いを込めているのだ。それを意図したかしないかと問う以前に、かくも暗く否定的に壷を表現せざるを得なかった内面に、祖国へ突きつけるノーがあったと言えよう。それは大胆であり、巧妙であり、創造的な奇才を感じさせた。
しかし、ぼくは、この映画の表現に共感できないのだ。製作された2006年といえば、すでに中国には2億人とも2億5千万人ともいえる中間所得層が大都市を中心に誕生している。もし、部屋で大小便するような、ごぎぶりが這いずり回るような中国の未開発住居などはいっそうされていたろうし、また、こんな、その遅れなどは、いっしゅんに片付けられる都市問題に過ぎないのだ。また今や、世界中の商社や、工場、チェーン店、サービス産業が集まってきている北京やその他の大都市で、この中間層には、ぼくらと同じようなアメリカ的消費生活やライフスタイルが始まっていると思うのが妥当であろう。ゴキブリが這い回るような暗さはもはや意味をなさない。共産党一党独裁で、民主化が抑圧されている中国社会も、変わってこざるをえない。中国の暗い、鬱屈したイメージでは、89年以降の中国の本質をとらえることは出来ないのではなかろうか。われわれと同じような消費文明の巨大な危機こそ問題で、未来の危険こそ共有しているのではないかと考えられる。
こう思うときに、ロウ・イエの手法は、このままでは、早晩行き詰ってくるはずである。映画もっと、楽しくし、異相であっても未来を孕む歓楽的なシーンで、問題の所在を明らかにして、告発、解決への希望を提示するのが本筋と、ぼくは思うのである。現在、いろいろと国家の対面だけを前面に押し出している中国政府もグロバーリズムを抱え込み、次第に民衆主体にならざるをえないだろうと思う。この映画を見て、中国の共産党一党支配の人民抑圧をイメージしていく、独裁政治に過度に反応することは、問題をとらえられないかもと思うのであった。











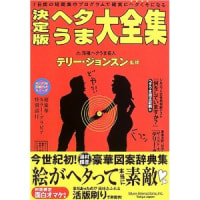













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます