年末年始に宮本常一の著作をじっくり読む(読み返す)時間をとることができた。その滋味あふれる文章にひたると、よい温泉に入ったように温まってくる感じがする。
『民俗学の旅』、『忘れられた日本人』 これらはすでに定評のある名著。それに珍しく日本以外を歩いた記録『宮本常一、アフリカとアジアを歩く』。
今回ひかれたのが、宮本の叙述の仕方。歩くように書いている。一見、「学術論文」らしくない、くだけた文章だ。しかし、このスタイルによってこそ伝えられるだろう、真実味のようなものが確かに伝わってくる。
『忘れられた日本人』に代表されるような語り方を宮本は意図的に選びとった、あるいはそこに辿りついたのではないか。『民俗学の旅』のこのくだりを読むと、どうもそう思えるのだ。
屋久島の年寄りたちの話は語り物を聞いているような感じのするものが多かったが、今『屋久島民俗誌』を読みかえしてみると、私はそれをすっかり散文にし箇条書きにし、また聞いた話を私なりに分解してしまい、ことばそのものの持っていたひびきのようなものは洗いおとしてしまっているのである。そこに住む人たちの本当の姿を物語るのは話の筋――つまり事柄そのものではなくて事柄を包んでいる情感であると思うが、そのような形で聞き取りを整理したものはほとんどない。物を調べ、それを文字で再現することがどんなにむずかしいことか。しかしその頃は情感的なものを洗いおとして鹿爪らしく散文的に書くことが学問として価値あるように思ったのである。(『民俗学の旅』講談社学術文庫:p.109、太字は小田による)
ここで述べられる「ことばのひびき」、「情感」は、話の全体から感じ取られる質感のようなものだろう。調査やインタビューをすると、確かにそういうものを感じることがある。
ここで宮本が「話の筋」という表現を使っているのが注目される。これはナラティブのプロットにあたることだろう。つまり話の個々の構成要素ではなくて、それをつなぐ潜在的な働きのことだ。この認識から出発して、宮本は分析的に事実を構成する書き方から、物語を語るようになったのだと思う。歩くように語る、そのスタイルを確立していった。その成果が例えば『忘れられた日本人』なのだ。あれを読むと、宮本の傍らで人びとの語りを聴いているような気になる。もしかしたらノートをそのまま原稿にしているのではないかという自然さがある。しかしかなり繊細に工夫をこらして、再構成しているのではないだろうか。「情感」を伝えるために。
それにしても「土佐源氏」の
秋じゃったのう。
という一行(『忘れられた日本人』岩波文庫:p.148)には、はっとする程の効果がある。
この点で、むろんそうとは名乗らないが、宮本はナラティブ・アプローチの先駆者だといえる。それもナラティブをたんに分析対象とするのではなく、自身がナラティブを語るわざをものにして、語り部となったのだ。
今、『質的研究入門』を訳し直しているけれど、ちょっと複雑な気持ちになってくる。「コード化」やら「ナラティブ分析」やらという手順を踏んでいるつもりで、宮本のいう「情感」を捉えそこなっていることも多いのではないかと思い至るから。研究方法(手順の意味での)は、自動的によい研究結果をもたらさない。対象と向き合い、その質感を捉えて、言葉にするという、それ自体伝達するのが難しい「わざ」の部分が、実は本当のところ大事なのではないか。(その点をフリックさんは、質的研究は「方法」と「わざ」とのあいだで揺れ動き続けると指摘している。)
自分は「情感的なものを洗いおとして鹿爪らしく散文的に書くことが学問として価値あるように」思ってしまってはいないか?そのような「質的研究」とは何か?ことさらに「○×法」などといって構えないし、理論武装もしない。「最先端」の装いもない。そんな自然体の宮本から学ぶことは、実はずいぶん多いのではないだろうか?
宮本は人間が生きていることの基層を見つめ続けた。それは決して古びることはないし、何らかの特殊な分野に限定されることもないベーシックなものだ。だからこそ宮本の著作に立ち返ると、常に発見があるのだと思う。
「座右の書」という言い方があるけれども、宮本の本は座って読むというよりは、旅をしながら折に触れてひもとくのが似合っていると思う。それは見落としがちなものに気づくまなざしを教えてくれる。
平凡な村はふりむく人がすくない。そこで私はそういう村に目をとめてみようとしている・・・(『忘れられた日本人』:p.61)学者たちは階層分化をやかましくいう。それも事実であろう。しかし一方では平均運動もおこっている。全国をあるいてみての感想では地域的には階層分化と同じくらいの比重をしめていると思われるが、この方は問題にしようとする人がいない。実はこの事実の中にあたらしい芽があるのではないのだろうか。(p.299)
特別に目立つものではなく、何気ないもの、ありふれたもの、日常茶飯事。そうしたものの「豊かさ」を捉えるまなざしを宮本はもっていた。それは宮本が郷里を出る際に父から与えられたことばを実践したものでもあったろう。
人の見のこしたものを見るようにせよ。その中にいつも大事なものがあるはずだ。あせることはない。自分の選んだ道をしっかり歩いていくことだ。(『民俗学の旅』p.38)
このまなざしは人にも向けられる。高知の橋の下に小屋がけをしている乞食、山陰の片田舎の百姓。こうした人びとの中に「心をとどろかすような歴史」がある。それを宮本は誠実に聴いて、受けとめ、そして語る。
どのようにささやかな人生でも、それぞれがみずからのいのちを精一ぱいに生きるものはやはりすばらしいことである。(p.194)
宮本の学問のひとつのキーワードは、「豊かさ」だと今回思った。それは物質的、量的な豊かさのことではなく、日常的な豊かさである。この点をよく表しているフレーズが、宮本が最初にして唯一アフリカを歩いたときの記録にでてくる。
多くのアフリカの文化についての報告書を読むと、いかにも貧しく低い生活をしているように思える。・・・さて、その村々を訪れてみると実にゆたかな感じがする。(『宮本常一、アフリカとアジアを歩く』岩波現代文庫:p.8)
ありふれた日常、どこにでもあるような風景、辺鄙な地域社会、あるいは「開発途上国」。そうしたところにある「豊かさ」を捉えて、それを歩くように書いていく。(「豊か」ではないと思われているところに豊かさを見出すことは、文化人類学の初心ではなかっただろうか。)これが宮本常一の方法であり、現代においても引き継ぐ価値のあるものであろう。それは、歩くように語るスタイルでエスノグラフィーを実践することだと思う。












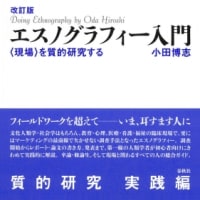







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます