今月、NHK文化センター札幌教室で「映画を通して平和をつくる」という一日講座をもった。それに関係して、勉強のつもりで「二十四の瞳」や「ひめゆりの塔」といった日本の古典的な反戦映画のDVDを買っておいた。時間が取れないまま、講座も終わった今頃になってまず「二十四の瞳」の方を観た。木下恵介監督、高峰秀子主演の1954年公開版だ。
映画評論家の佐藤忠男氏は、いわゆる「反戦映画」の大半は日本人を戦争(=アジア太平洋戦争)の悲惨な被害者として描くのみで、例えば日本軍が中国でどんな加害行為をしたのかが抜け落ちていると述べている。そしてその典型例として「二十四の瞳」を挙げている。僕はこれを読んでいたものだから、批判的な目で観始めたのだった。
しかし実際に観てみると、批判よりも何よりもかなり感動してしまった。これは名作だ。終盤で、感動シーンが怒涛のように押し寄せる。その点で先ごろ日本アカデミー賞作品賞に輝いた「フラガール」とつくりかたが似ていると思うけれど、公開当時には「二十四の瞳」の方がはるかに強い感動を観客に与えたはずだ。なぜなら生々しい戦争体験を日本人が共有していた時代、観客の感情移入はただ事ではなかったはずだからだ。
これがひとつの映画として名作だと認めた上で、僕は佐藤氏の批判もやはり当たっていると思う。高峰演ずる大石先生は、中国に出兵し戦死した元生徒たちを不憫に感じ、その墓前で涙に暮れる。しかし日本兵の彼らが中国で何をしたかはまったく触れられることはない。だから、公開当時、日本の観客は”安心して”感動することができたのだ。しかし日本軍の加害がかなり詳細に明らかになった現在において、この映画が日本人に与える感動はすわりの悪いものになってしまった。
「二十四の瞳」は、「戦後日本」の想像力の限界を典型的に示し、そしてそれを強めることにもなった映画と言える。戦後日本の想像力の限界とは、日本の戦争行為で被害を受けた「他者の視点」の欠落、「他者への想像力」の不在ということだ。
また、この映画のもうひとつの問題は、一般民衆を、大きな政治状況を把握することもできず、それに働きかけて、影響を及ぼすこともできない無力な存在として描いてしまったことだ。地域社会で生活しながらも、政治状況に対して批判的考察を行い、ときには行動を起こして国家の動静に一定の影響を与える、そうした自立した市民は日本にも実際にいた。しかし映画の中でとりあげられることはまれではなかったか(実例はあるだろうか?)。
話は変わって、この映画のロケ地香川県・小豆島は、そのことを観光資源として利用し、「二十四の瞳映画村」というのを作っている。ロケ地は映画の中に映されるだけではなくて、今度はロケ地が映画を映し出す。映画を通して変わって行った町は多いのだろうな。「幸福の黄色いハンカチ」の夕張、大林宣彦監督作品の尾道、「男はつらいよ」シリーズの葛飾柴又など。セカチューの舞台となった香川県庵治町はいっとき観光客でにぎわっていたけど、今頃はそれも昔の話になっているんじゃなかろうか。












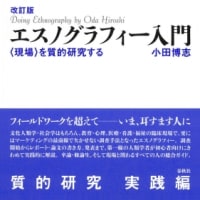







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます