きこん【気根・機根】という言葉があります。辞林21を見ると
1 物事に耐えられる気力。根気
2 仏の教えを聞いて悟りを開く
ための基盤となる衆生の宗教
的性質・能力。機。
「私には機根があるか否か」「気力があるか」もう少し平たく言えば「やる気があるか」という言い方をした場合に、その意味理解が現われてきます。今は便利な世の中、ネット検索すると次のように出てきます。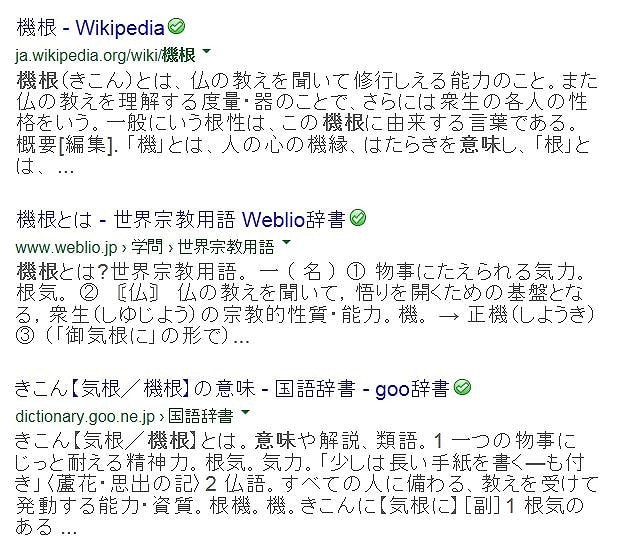

さらにYAHOO!知恵袋では、
【質問】「仏教用語の「機根」ってどういうことですか?
自分に機根が有るか無いか、有ったとしてもそのレベルは、生まれつき決まっているのですか。それとも精進によって増やせるものなのですか。
【ベストアンサー】機根とは、教えを受けて発動する潜在的な能力のことです。根とは植物の根のことで、根があれば水や養分を受けて発動し成長するのと同じです。仏教では誰もが成仏可能と説いていますから、上根・中根・下根の差はあっても、機根がまったくない人はいません。
仏道精進によって機根は高まります。
などと書かれて、信仰に生きる人間の潜在的な行動能力とでも理解できそうです。
世の中の宗教がらみの殺戮がくり広げられている離接的偶然を見せつけられて、自分の身の周りにも必ずや生じるに違いなく、その可能性大の危機意識が培われ・・・危機感の醸成・・・軍靴の音をそこに聞こえてしまう人も多いようです。
『日本的霊性』の鈴木大拙先生が、太平洋戦争がはじまる前に東本願寺で信徒の方々や知識階層の方々を前に「無心ということ」と題した講演を行なった時の講演会記録があります。書籍として刊行されたのは1939年(昭和14年)5月で、講演は四回ですが補足して六講
第一講 無心とは何か
第二講 無心の探究
第三講 無心の活動
第四講 無心の完成
第五講 無心の生活
第六講 無心の体験
が、岩波書店鈴木大拙全集ならば第七巻のP116項から掲載されていて、角川ソフィア文庫ならば『Mushin・無心ということ』の一冊になっています。
「機根」の話から大拙先生の話になってしまいましたが、先生のこの『無心ということ』にこの「機根」を語った「機根の問題」という講義録があります。
<『無心ということ』「機根の問題>
これは心理学的に差別の世界を見ると、いろいろの型の人があるのです。根機というのは、型ということです。その根機----すなわちその型の差異によりて、宗教的にまたその向かうところを異にするというわけです。何も上根だから悪いということではない。その根機のいかんによって、これが良い、あれは向かぬというようなことだろうと思うんです。キリスト教のようなタイプの人はその方向へ向くし、マホメット教のようなタイプはの人はマホメット教の方へ行く。マホメット教は軍人的に勇敢であるいは殺伐す。何でも触れるものはことごとくこれを斬るというような、戦闘的な気分に満ちているのがマホメット教です。そういうような気風の人が、それゆえ、そういう風な宗教的信仰に行くのです。インドでは宗教的にやたらに喧嘩するのですが、そのし始めはマホメット教のものだときいています。支那でもマホメット教の人は喧嘩好きのような傾向があるということです。日本でも日蓮宗の人はなかなか鼻息はあらく、戦闘的できついところがあるように思います。そういっては、日蓮宗の人に叱られるかもしれぬが、日蓮聖人は徹底的な喧嘩好きということではなかったようです。もちろんそういうことは、初めにあったようです。またそうなくてはならぬ事情もあったでしょう。鎌倉で街頭演説をやられたようなことは、だいぶ近代的であるが、こういうふうなやり方、そうしてそれがために滝の口で斬られんとするような騒ぎも出て来たのでしょうが、ああいうように徹底して闘争気分で押し通そうというようなところが、日蓮聖人の性格の一面にあったのでしょう。それは日蓮聖人は、魚師の子だということですが、ああいう境遇におられる人々というものは、反抗意識、戦闘気分などいうものがあるものなのです。共産主義にいう階級闘争というようなものも、プロレタリアがし始めたのです。資本家階級、統治者階級などという上層のものに対して階級闘争をやるというのが、やはりああいう魚師----一部プロレタリア層の人としての、日蓮聖人にも、性格的に反抗気分があったものだろうと推考せられる。お釈迦様のような方、法然上人というような方は、その系統が貴族層に属するというので、あまり喧嘩腰にものを言われるというような傾向が内容ようです。他を容れるような傾向というものは常に圧迫を受けている人の中には出ないだろうと信じます。それが自然に宗派の上に現われてくるのはもとよりやむを得ないでしょう。そこで日蓮聖人は末期に近づくに従ってきわめて円熟せられて、若い時のような闘争気分は柔らいで来たように考えますが、一部の信者たちは、聖人の闘争気分に燃えた時代に、むしろ同気相求むの傾向があるようです。今日でもお題目を唱えて団扇太鼓を叩いて勇ましく行進するのは、必ずしも排他心と言わなくとも、一種抗争気質の動くのを見ると言ってよかろうと思う。禅僧の坊さんが、托鉢に出かけても日蓮宗のところでは門前払いを食わされるということもありますが、浄土宗や真宗の家に行くと、ものをもらって来るときいています。そういうようなことが自然に各宗派にあるものです。その祖師すなわち開山さんの気分、個性がその宗風に出て来ている。そういうようなことえで各人にはいろいろの個性というものがあるのです。(以上角川ソフィア文庫p102-p103・全集第七巻p199-p120)
何とも今聞くと強烈な印象を受けます、差別的な文章ではないかと言われても不思議ではない文章です。大拙先生が69歳のころの叫(たけ)びなのであって、打ち消すことは出来ません。
※注:引用文中「根機」という言葉が使われていますが、
ということで「機根」という表題ですが「根機」で語られています。
しかし、仏教ひとつをとってもタイプが自然に各宗派にあり、その祖師すなわち開山さんの気分、個性がその宗風に出て来ている、というわけです。古い話なのですが、今も通用している部分が大いにあるように思います。
宗教という段階でとらえれば、奴隷の宗教、闘争の宗教などといわれ、巷にその手の評論的本が流行ります。
この『無心ということ』の第一講「無心とは何か」に戻りますが、大拙先生は浄土教、真宗の指方立相を強く説きます。次の文章が印象的です。
<『無心ということ』「浄土のありか」>
元来、自分というものと、汝というものとの二つを分けることがいけないのです。二つに分けてしまうから伝えるということにならなくてはならぬ。しかしそうしないと自分といっているものが、自分でなくなるからやむをえない。論理の方は哲学者や宗教学者の方で言うかもしれぬが、譬喩や比類で直覚の写真を現わすことになると、その一つの方法は、詩歌、神話になって出るのである。そういう詩の文句にも現わさない、神話でも伝えないときには、どういう塩梅にして直覚の意味を表現して、そして普通の人間に納得させる方便または施設と称すべきものはなにかと考えてみると、それは浄土教の指方立相より外にない。すなわち方位によりて西方というものを立てる。そして十万億土というものを向かうにおく。そしてそこに浄土を建立せられる。(以上角川ソフィア文庫p27・全集第七巻p136)
「直覚の写真」という言い方は、私がキーを叩くときに誤ったわけではなく「写真」という言葉を大拙先生は使っています。個人的な意味理解として、「描く」に相当する意味の表現ではないかと思います。
大拙先生は一点を探究し考察する人です。
「普通の人間に納得させる方便または施設と称すべきものはなにか?」
それが西方浄土で「なむあみだぶつ」であったりするわけで、人は大いに表現する存在です。



















