「夏の日の出来事」
俺は高校二年の夏に変な女と出会った。
と、その前に、俺の話をしよう。
俺の名は、秋月海(アキヅキカイ)
だが、戸籍上は、晦(ミソカ)だ。
この晦という名前は祖父がつけたもので、親父はこれが気に入らず戸籍は晦のまま残し、通称扱いで「海」と届けを出した。
だけど、「海」はみそかと呼べないのでカイとなった。
そんなのは、生まれた頃の話で俺は「カイ」だった。
この夏、俺は東京に来ていた。
実家は米沢にある.
小さい頃から一緒に暮らしている祖父を俺は慕っていた。
一緒に暮らす前、祖父はずっと東京にいた。
祖父が東京に残した家を建て替える事になった関係で俺は東京に出て来た。
でも、一番の目的は来年の俺の受験準備だ。
祖父の家と不動産屋とホテルと塾の毎日になると思っていたのに、俺は変なモノを拾った。
祖父の家で見つけた「赤い鈴」に女の子の妖怪?が憑いていたのだ。
しかも、その女の所為でバーガー屋でバイトをする事になってしまった。
まぁ、それは自分で決めた事だし、週三日の深夜のバイトくらいなら問題は無いと思っていた。
次はその女の話だ。
「名前をつけて」と言うので俺の名、ミソカの方を付けた。
ミソカには双子が居たので、そっちには「ツゴモリ」と付けた。
ツゴモリとミソカと晦は同じ意味だ。
「ミソカ」
と俺が呼ぶと彼女は出てくる。
普段は鈴の中にいるらしい。
「何?」
「なんか、面倒だから、お前が自分の事を説明しろよ」
「え、えっーと、ワタシは妖怪じゃあなくて、神様修行中の女の子…」
「成りそこないだろ?」
「いいじゃないの。どっちでも。昔は修行してたの。今は秋月家の守り神をしてまーす」
「……ま、守り神?」
「……カイの…式神をしてます」
「使い魔をしてまーす。にしとけ」
「ひっどいーーー」
「神なのに、嘘つくからだ。しかし、お前って本当に神には見えないよな」
「悪かったわね」
「服やら、髪やらがな…。それ趣味?」
「え、今ってこういうのがいいんじゃないの?」
「良いってか、それ、どう見てもコスプレじゃん」
「コ?何?」
「短いスカートの和風メイド喫茶って感じがするんだよ」
「あの、流行ってるものを真似してみただけ」
「……お前が資料にした物が間違ってたんだな…」
「ワタシは気に入ってるよ」
「まぁ、それならいい…」
薄く淡い感じのオレンジ地にこまかいピンクの花柄の着物。
丸い小さいひらひらのついた白いエプロン、後ろで結んだリボンが長めで、
着物の丈が短くて、白い靴下に靴…。靴?
「あれ?お前、草履じゃなかったっけ?」
「替えたのよ」
替えた?…そうですか…。
「しっかし、短いな裾が」
「だって、すっごく暑いんだもん」
「まぁ、確かに…、気温が体温より暑いもんな…」
暑さなんて感じないだろうに…。
これだけ暑いと、暑苦しい格好で居られるよりはマシかもしれない…。
「だけど、歩く時、俺の前をうろちょろ飛ぶなよ。横にしろ気が散る」
「やっだー。えっちぃ」
と、俺の肩を叩くってか、どついた。
「えっちぃー、じゃない。気が散るだけだ」
「なんだ。つまんない」
つまんないって、こいつは。
「ところで、お前、双子はあの家に置いてきたのか?」
「ううん。一緒に居るよ」
「一緒に?」
「うん」
「俺まだ、見たこと無いけど…」
「ワタシと交替なのよ」
「出してみろよ」
「んー、、」
「命令していい?」
「わかった。替わるわ」
といったん彼女が消えて、男の子が現れた。
「ども、ツゴモリです」
と言ったので、俺も
「どうも、コウジロウの孫です」
と言った。
ツゴモリは、ミソカと同じように品定めと言うより、値踏みするようにじっと俺を見てきた。
そして、
「あのさ、あんた、使役する気がないなら、名前なんて付けるなよ」
と言った。
「…仕方なくだよ」
「ふん」
と横を向くツゴモリ。
ミソカもそうだが、式ってこんなに生意気なのか?
そりゃ、俺はじいさんじゃないさ。
「じいさんとどんな事してたか知らないけど、今は俺が使うんだから、俺に従えよ」
と、言った。
だけど、俺は彼らを使役する気なんて無い。
実際ミソカだって踏み切りで女の子を助けた時だけしか使っていない…。
あれだって、使うつもりじゃなかった。
「コウジロウはそんな事言わなかった」
「じいさんの昔なんて知らないよ」
知ってるさ。
俺は知ってる。
俺はじいちゃんを尊敬してるんだ。
でも、東京での顔は知らない。
それが悔しくてつい言ってしまった。
「じいさんと話した事もなかったくせに」
バチン!
と二人の間で静電気のヒドイののような反発があった。
俺は強い力に床に引き倒されていた。
「痛っ…」
そして、ツゴモリは俺に馬の乗りになって俺の首を絞めていた。
「コウジロウを悪く言うな」
「……」
「俺達の恩人だ。悪く言うな」
「…俺だって…」
「それ以上言うと殺すよ」
「俺…だって…じいちゃんが嫌いじゃない!」
そう俺が言った時、思い出したか驚いた顔になって手が緩んだ。
俺はツゴモリの手を掴んで、この体勢をひっくり返してやろうと思ったが、流石にそれは出来なかった。
だから、俺は、
「…お前、その格好で、凄んでも迫力ないぜ」
と言ってやった。
「え?」
と、ツゴモリは自分の姿を見回した。
髪こそツインテールじゃなかったが、ミソカの服のままだったのだ。
つまり、ふざけた格好のコスプレ少年が俺を襲っている図がそこにあった。
ただでさえ短い裾が上がって、太もももなにも丸出しだった。
ツゴモリは俺の手を振り払うと
「ミソカ。なんで俺の服はーーー?」
そのままの状態で俺達が停止していると…、
「男の服ってわかんなくってぇー」
と返事が返ってきた。
気が抜けた……。
「ミソカ…とりあえずツゴモリの服さ、俺と一緒でいいじゃん」
ツゴモリが消えて戻ってくると、Tシャツとブルージーンズになっていた。
「センス無ぇ…」
とポツリ、言うツゴモリ。
むかつくガキだ。
「この服はな、作業服みたいなもんだ…文句つけるな」
「あのさ、式使う時はそれなりの服あるだろ?」
「だから、俺はお前達を使う気は無いんだ」
「ふーん」
「さっきは使うなと言ったのに…」
「そっちこそ。従えと言ったのに」
「あれは、つい。第一、俺はまだ式は使えない」
「陰陽師なんだろ。お前」
「俺は、カイだ。お前って呼ぶな。それと、俺は陰陽師じゃない」
「…そう、なんだ…」
と思案顔になるツゴモリ。
「俺はただあの家から鈴を拾ってきただけだ。偶然、深川の神社に行ったけど…」
「深川の?」
「聞いてないのか?」
「ん、さっきまで寝てたから、名前がついたとしか聞いてない」
「そうか…俺が命令するなんて言ったから…交替したのか。ごめん」
そんな俺を見てたツゴモリが良い事を教えてやる、と耳打ちしてきた。
「ミソカさぁ、あんたが気に入ったんだよ」
「気に…?」
「そそ、惚れちゃったって事」
「え………ええ?何で…」
「そんなの知らないよ」
「…意味わかんね…」
「んじゃ、もう戻る」
と言ってツゴモリは俺から離れた。
そして、ミソカの事よりももっと重要な事を言った。
「今度までに服を用意しとけよ。でないと助けてやらないからな」
「…助ける?何で?…今度って何だよ」
「問題がやって来るからさ」
と言うと、静かに消えていった。
「問題?」
「暑い。何で俺がこんなことを」
「だって、彼氏になってくれるって言ったじゃない」
「ふりするだけだろ?」
俺はくそ暑い日に学校に向かう坂を上っていた。
事は三日前。
俺の深夜のバイト中レジを担当していると、女子高校生が入ってきた。
「いっらっしゃいませ」
と俺。
一応営業スマイル。
その子はまっすぐに俺の前に来てこう言った。
「なんで、あの時、ホテルに連れて行かなかったのよ!」
特に「あの時」と「ホテル」が大きく聞こえた気がしたのは勘違いじゃないだろう。
その瞬間。
客の2組のカップルと、中にいたバイトの先輩と丁度いた店長も固まったように見え たのも勘違いじゃないだろう。
「あんた、そこのホテルに泊まっているんでしょ?」
と指を指す女子高生。
「だけど、お前、何も言わなかった…く…せに…」
迂闊だった……。
この瞬間、店内の人間から俺は「ヒドイ男だ」と思われてしまったようだ。
店長が俺を呼んで、
「今日は少ないし、もうあがっていいよ。2階で話していきなさい」
と、言ってくれた。
「後で事情話しますね」
と言って、着替えに戻ろうとすると、先輩が
「なんだ?彼女をその気にさせておいて逃げたのと違うのか?」
と、誤解していた。
着替えてから二階に行くと、隅のテーブルにその子がいた。
あの日の席だ。
今から十日ほど前、踏み切りでミソカと俺はその子が自殺をしようとしたのを止めた。
電車が来るのに踏み切りに入ってゆくその子を引っ張りだしただけだ。
その後、俺達はここへ逃げ込み、名前も事情も聞かないで別れた。
だから、もう会う事も無いと思っていた。
あの日の事をきっかけに俺はここでバイトをする事になったが、それは事件には関係がないので先にすすめる。
「ここのバイトしてるって気付いたから、秋月君のいる時間教えてもらっちゃった」
と彼女は言う。
「それで何しに?まさか、ホテルに連れてけってのが用じゃないよね」
「これを返そうと思って…それに…」
どこかのブティックの袋の中にはクリーニングされた俺のパーカーが入っていた。
これはあの時、踏み切りで転んだ彼女の背中に黒い汚れが付いてしまった為、俺が渡した物だった。
「返さなくていいと言ったのに」
と俺は受け取らずに
「それはあげたから」
「もらえないし、私、こういうの着ないし」
「それじゃ、いらなくても、もう少し持ってて。本当にいらなくなったら返して」
「え?何よそれ…」
「君はそれを返すだけが目的で来たんじゃないでしょ?」
「どうして…?」
「返すだけなら、さっきレジの所で返せたじゃん。他に用事があるんじゃないの?」
「…あの…、ふりだけでいいから、彼氏になってくれませんか?」
と彼女は俺に手を合わせた。
それで、
三日後、暑い中、学校へ向かう坂を上っている訳だ。
俺はその土曜日には講習もなく、バイトも入ってなかった。
彼女からの頼みはこうだ。
彼女の親友が学校の先輩を好きになった。
どうもその先輩は自分を気にしているようだ。
だから、彼氏がいる所を見せれば諦めてくれて、親友の事を見るようになる。
だった。
それと、あの踏み切りでの事で警察が学校に来たようだ。とも言った。
まぁ、あの時、彼女は制服だったのだから仕方がない。が、あの駅を利用する生徒が多いのは助かった。
だけど、二人で居てはマズイんじゃないかと俺は言ったのだが、
「二人でバカップルしてればいいのよ」と言う。
「バ…カップル…」
彼女は髪を茶色に染めて、化粧もしていた。
あの日の、少し暗い印象とは違っていた。
そして、俺も変えるように言われた。
ツゴモリにも言われたが、俺の服はいたって普通なはずだ。
「GパンにTシャツばかりじゃ、バレちゃうよ」
と彼女は言った。
当日、俺達は時間より早く会ってあるメンズショップにいた。
スリムなブラックジーンズに黒のランニング、袖をまくれるデザインの白いシャツ。
飾りのついたベルト。と小ぶりのシルバーネックレス。靴はサンダルだった。
彼女の選んできたのを見た時は、何処のヤンキー?と思ったが、着てみるとそうはならなかった。
「素材は悪くないんだよ」
と言って彼女は「帽子はこれかな?」と言った。
そのセンスに、東京の娘は違うんだな。と俺は思った。
着て何となく気分が良くなったが、通帳の食費が消えて行った。
バイトを増やそう……。
と、俺は…切実に思った。
学校で待ち合わせをしてWデートという事なので、食事して映画を観て二組は別行動になった。
上手くいきそうな彼らの雰囲気に俺達はほっとした。
俺達は夕暮れの公園にいた。
男物を選ぶセンスも、デート中の何も知らない俺への気配りもしてくれて、出会いは最悪だったが、あれにしてもこの子は踏み切りに入る前の記憶が無いと言った。
気が付いたら、電車が目の前で、次は俺と道路に転がっていたから、という事らしかった。
この子は悪い娘じゃない。
むしろ良い娘だ。
では何故。あんなモノが憑いているんだ。
彼女には得体の知れない物がついていた。
あの所為で、踏み切りを潜る事になったんだ。
「ツゴモリ」
「……」
「お前は俺を助けると言ったよな。だったらアレは何だかわかるか?」
「女だね。髪の長い、はっきりしないから生霊かもしれない…」
「やはりそうか…」
俺は清めの塩を出すと彼女にわからないようにかけて、後ろで印を結んだ。
ツゴモリが静かに剣を抜き彼女の背中にあてる。
あてただけだが、効果はあったようだ。
彼女が倒れそうになったのを俺は支えた。
それで、終わりだ。
終わりだった…のだが…。
「…カイくん?…私、熱中症かな?」
「熱はないし、疲れただけだろ?何かジュースでも買ってくる」
すると彼女が俺を引き止めた。
じっと俺を見つめて、
「いろいろ、ありがとう」
と言って彼女は俺にキスをした。
そのまま、彼女は「帰るね」と言うと公園を抜け駅へと消えて行った。
「…結局、名前しかわからずか…」
と俺が呟くと、
「気にするのそこかよ?」
とツゴモリが言ってきた。
「ん、あぁ、生霊の方?親友さんは、三日程寝込むかもね」
と俺が言うと、
「親友だと言う相手に生霊を作っちゃうのに親友と呼べるのか?」
とツゴモリ
「それは、きっと彼女もそれに気付く、それでどうなるかは、彼女達次第さ」
しっかし、疲れた。と俺は大きく伸びをした。
そんな俺をツゴモリが見上げて言った。
「キスした事、ミソカに言うと大変な事になるかもよ」
「ミソカ。あ、そっか、俺に惚れてるって言ってたよな…」
俺はあくびをしながら答えた。
「キス…か…。あ?俺…」
「どうした?」
「俺、今のがファーストキスだ…」
俺は、俺は、そういうのは、好きな子としたかったのに。
かわいいには可愛かったけど、名前しか知らないようなのと、勢いでしちゃうなんて…有り得ないぞ。
翌日、バイト先に「ありがとう」のメッセージと共に俺のパーカーが届けられた。
彼女の背中に黒いシミはもう付く事はないだろう。
そして、会う事もなかった。
夏休みの終わり頃
祖父の家の取り壊しが済み、地鎮祭が終わった後で俺は一人で均された土地を見て回った。
「カイって、術使う時、雰囲気変わるよねぇ」
とミソカが言う。
「そう?俺は何も違わないけどな」
「最近、服もかっこいいし、どうしたの?」
「ツゴモリがうるさいんだ」
「ふーん。ワタシは今のも良いと思うなぁ」
「ん、ありがと」
今日はあのパーカーを着ていた。
ミソカの趣味はイマイチ問題ありなんだけど、似合っているし。
ツゴモリのカッコつけな所も面白いと思っていた。
あの日、ツゴモリはどこで知ったのか黒い皮ジャンとTシャツとジーンズだった。
それだけなのに、かっこよかった。
俺(あるじ)よりセンスの良い式神だなんて…。
でも、俺は、
俺とミソカとツゴモリのバラバラ感もそれで良いんじゃないかと思った。
これが、俺と双子の式神、ミソカとツゴモリの最初の事件だった。
この後の諸々の事件は俺が受験を終えて、また再び東京で暮らし始めてからになる。
終















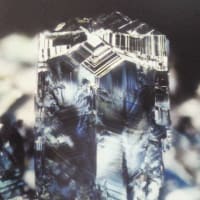

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます