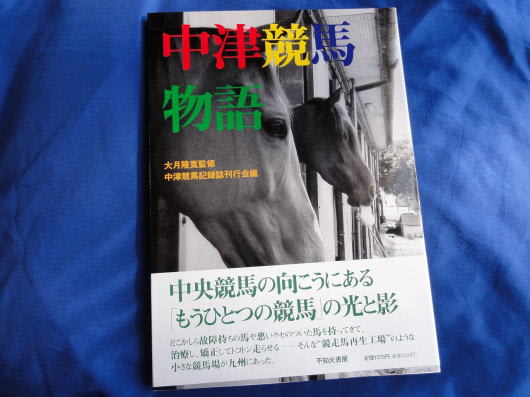豊真将は勝っても負けても角界一所作のきれいな力士である。
それは本人の性格を表しているものだと思う。
豊真将 紀行(ほうましょう のりゆき、1981年4月16日 - )は、
山口県豊浦郡豊浦町(現在の下関市)出身で錣山部屋所属の現役大相撲力士。
本名は山本 洋介(やまもと ようすけ)。
身長185cm、体重147kg、得意手は右四つ・寄り。
四股名の由来は、〈豊〉は合併のため消滅した豊浦町から、
〈真〉は本人の心、〈将〉は大将、
〈紀〉はものごとの初めを意味する出身校の監督の一字、
〈行〉は父から一字をもらったもので、父母への御礼に従うという意味が込められている。
ニックネームはマショー。最高位は東小結(2012年5月場所)。
趣味は読書、史跡巡り。好物は栗おこわ。
地元の旧豊浦町立豊浦中学校(現在の下関市立夢が丘中学校)には
校庭に立派な土俵小屋があり、山本少年はそこで高校生らと混じって鍛えられ、
地元の大会でも優秀な成績を修めていた。
そのときの後輩には境川部屋の豊響(本名:門元隆太)がいる。
中学卒業後は誘いを受けた埼玉栄高等学校に進学し故郷を離れた。
埼玉栄高校では全国大会に出場して活躍し、
学業では学年約1600人中一桁の成績を取るなど、文武共に優秀であった。
その後日本大学に進学、入学当初からレギュラー格で活躍するも、
蜂窩織炎の悪化により1年で相撲部を退部。
一時は相撲を諦め、警備員や鳶職などアルバイト中心の学生生活を送っていた。
日大相撲部の同期には白石(のちの白乃波)や里山がいる。
蜂窩織炎の状態が良化した頃、白石と里山の大相撲入りに触発され自身も再び相撲を志す。
大学を中退してアルバイト先の社長の紹介で開設されたばかりの錣山部屋に入門し、
2004年3月場所に前相撲から初土俵を踏んだ。
この時新弟子入門期限間近の22歳11か月であった。
約3年相撲から離れていたこともあり、
入門当初は母校でもある出稽古先の埼玉栄高校で、
エースの澤井豪太郎(現在の豪栄道)に歯が立たず、
1年生の佐野マービン・リー・ジュニア(元:幕下大翔勇、現在のマービンJr.)にさえ
分が悪いなど苦労したこともあったが、その年の11月場所では三段目で全勝優勝。
スピード出世で番付を上げ、翌2005年1月場所、初土俵から5場所で幕下に昇進。
幕下上位でも安定した成績を残し、同年11月場所には東幕下3枚目まで番付を上げ、
5勝2敗と勝ち越し。続く2006年1月場所で十両に昇進した。
その場所も好調で東十両12枚目で10勝5敗と勝ち越し、
翌3月場所も12勝3敗と惜しくも十両優勝を逃したが大勝した。
5月場所、初土俵からおよそ2年で新入幕(東前頭11枚目)。
豊真将の入幕は山口県出身力士としては35年ぶりだった。
そのため、地元旧豊浦町とそれを引き継いだ今の下関市はもちろん、
山口県全体で応援をしている。
NHK山口放送局のニュース番組では、場所中連日その日の取り組みの結果が、
豊響ら他の郷土力士の分とともに伝えられ、
特に「やまぐち845」では、トップ項目で扱われる日もある。
新入幕の場所で脚を傷め、また立ち合いに迷いが出たこともあって、
入幕直後は下位でややもたついていたが、
入幕4場所目の2006年11月場所は一躍成長を見せた場所になった。
初日に豊ノ島に敗れたが、その後は11日目まで10連勝で全勝の横綱・朝青龍を追った。
12日目に初めての大関戦となる栃東(現在の玉ノ井)との一番に敗れ2敗に後退したが、
その先も崩れず、優勝はならなかったものの14日目まで朝青龍の優勝を引き伸ばした。
12勝3敗の優勝次点の成績と相撲内容が評価され、敢闘賞と技能賞を同時に受賞した。
2007年1月場所は西前頭4枚目の地位で3日目には大関・琴欧洲を初対戦で破ったものの、
7勝8敗と負け越した。
翌3月場所は1月場所に続き、琴欧洲を始め幕内上位力士を相手に内容のいい相撲で
好成績を残し、11勝4敗の好成績で2度目の技能賞を受賞した。
新三役の可能性があったが、西関脇で7勝8敗だった琴奨菊が西小結、
西前頭筆頭で8勝7敗だった豊ノ島が東小結となったため、
翌5月場所は東前頭筆頭に据え置かれた。
その場所は9日目に大関・千代大海との初対戦で勝利したが、
終盤の4連敗で5勝10敗と大きく負け越した。
9月場所は西前頭筆頭で8勝7敗と勝ち越し、新三役への昇進が確実と見られたが、
西前頭3枚目で10勝5敗の琴奨菊が西小結となったため、
11月場所での小結昇進は見送られた。
翌2007年11月場所では東前頭筆頭で3勝12敗、
翌2008年1月場所では西前頭7枚目で4勝11敗と2場所連続で大敗を喫した。
後にこの不振は血中コレステロール値の異常と
その投薬治療によるものであったことが明かされた。
投薬治療を食事療法に切り替えてからは、3月場所、5月場所、7月場所を
いずれも9勝6敗と勝ち越した。
2008年7月場所後に左手首を手術したが、術後の経過が思わしくないため、
翌9月場所は西前頭2枚目の地位ながら自身初の休場(全休)となり、
再出場の11月場所も負け越したが、
幕尻(東前頭16枚目)に下がった2009年1月場所は11勝4敗の好成績をあげて
2度目の敢闘賞を受賞した。
2009年3月場所は序盤まで2勝3敗だったが、6日目からの9連勝で11勝4敗の好成績をあげて、
2場所連続3度目の敢闘賞を受賞し新三役の可能性があったが、
5月場所は東前頭筆頭に据え置かれた。
この場所は初日から14連敗と苦しんだが、
千秋楽の嘉風戦に勝利して1991年7月場所の板井以来となる15戦全敗は免れた。
取り組み後、豊真将は涙ぐみ、館内は大歓声に包まれた。
2010年5月場所で東前頭2枚目に番付を上げたが場所前に首を痛め、
初日から1勝もできないまま7日目から休場した。
2010年7月場所では東前頭13枚目まで番付を下げたが、初日から10連勝し優勝争いに加わる。
14日目の徳瀬川戦に敗れるまで幕内優勝の可能性を残し、
最終的には11勝4敗で4度目の敢闘賞を受賞した。
翌9月場所は東前頭2枚目で7勝8敗と負け越した。
2010年11月場所前には、深刻なアクシデントに見舞われた。
10月23日の秋巡業、尼崎場所で右足親指の傷口からばい菌が入る破傷風で、
30日に突然41度を超す高熱が出た。病院に駆け込んだが、
一時は意識を失うほどの重い症状で、生死をさまよう体験もした。
豊真将自身「三途川で、死んだじいちゃんが出てきた。
あんなことは人生で初めてだった…」と語った程だった。
3日間高熱はひかなかったものの完治して退院、場所前には出稽古ができるまでに回復した。
同年11月場所では東前頭3枚目で7勝8敗と負け越したが、
2大関(琴欧洲・把瑠都)に土をつけた。
なお、琴欧洲戦の勝利は2007年3月場所以来、把瑠都戦の勝利は2006年11月場所以来。
2011年7月場所は東前頭9枚目で11勝4敗の成績を挙げ、5回目の敢闘賞を受賞した。
翌9月場所では、東前頭筆頭で10勝5敗と2桁勝利を挙げ、
同年11月場所でようやく待望の新三役(西小結)昇進を果たした。
なお30歳6ヶ月での三役昇進は、1958年以降初土俵の力士としては第4位の高齢昇進だった。
しかし新小結の11月場所は初日から7連敗を喫し、
中日でやっと初白星を挙げるも9日目で負け越しが決定、4勝11敗と大きく負け越した。
東前頭4枚目へ降下した翌2012年1月場所でも7勝8敗と負け越したが、
翌3月場所は西前頭5枚目で11勝4敗の好成績を挙げ、翌5月場所は3場所ぶりに三役復帰、
現在最高位となる東小結に昇進したが、
横綱・大関陣は1人も下せず4勝11敗と大きく負け越した。
11月場所は3場所ぶりに三役復帰(西小結)したが、4勝11敗と大きく負け越した。
翌2013年1月場所は左肩腱板断裂により全休し、翌3月場所は初めて十両へ陥落した。
その場所も怪我が完治しなかったため全休した。
幕下落ちも懸念されていたが、翌5月場所の番付には西十両14枚目と十両にとどまった。
その場所では中盤に4連敗したがその後持ち直し、9勝6敗と勝ち越した。
翌7月場所も9勝6敗と勝ち越し、次の9月場所には西前頭13枚目まで大きく番付を上げた。
西十両6枚目から9勝6敗で9枚の上昇は異例である。
その9月場所では9日目に左肩のテーピングが取れ、
10日目に1年ぶりの幕内勝ち越しを決めるなど
調子を万全に近いところまで戻した様子がうかがえた。
最終的に10勝5敗と二桁勝利を挙げた。
2014年1月場所前の1月3日には虫垂炎の手術を受け、
場所直前の様子は師匠によると「手術した傷口がまだ塞がっていないので、
今場所は、途中から出場することも厳しいと思う」と言い、
このため豊真将は1月場所を休場することを選択した。
そして今場所は2度目の十両陥落となったが、奮起し14勝1敗で優勝した。
以上の経歴を見てもお解かりだと思うが、怪我に泣かされた続けた相撲人生だと思う。
普通の人ならば、心が折れてしまうところだが、
何度も立ち上がり復帰する精神力は凄いと思う。
この経歴を見ると応援せずにはいられない。
三役復帰を目指して頑張れ!豊真将!