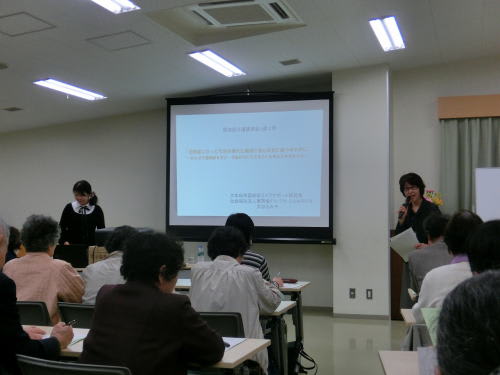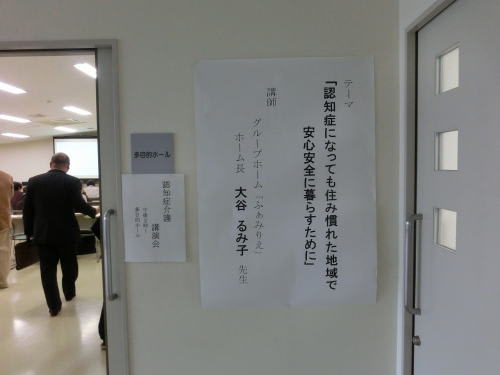長崎市唐人屋敷跡 「 福建会館天后堂 」



ランタンでは、前にある小さい方の 「 媽祖さま 」 を興福寺までお運びする


屋根に 「 五重塔 」 が置かれている

「 福建會舘 」 と書かれた山門

山門の屋根に火事除けの 「 徳 利 」 が乗せられている
今日は、唐人屋敷跡にある四堂めぐりの4番目である 「 福建会館天后堂 」 です。
福建会館(星聚堂)は、唐人屋敷が解体されたのち、
明治元年(1868)に福建省泉州出身者により創設された福建会館の前身は江戸後期に遡るが、
明治元年(1868)『八閩(はちびん)会館』として正式に発足した。
明治21年(1888)焼失。その後、明治30年(1897)に全面的に改築され、
福建会館と改称された。
会館本館(会議所)の建物は原爆により倒壊したため、
現存するのは正門と天后堂などである。
正門は、三間三戸の薬医門(やくいもん)形式で、中国風の要素も若干含んでいるが、
組物(くみもの)の形式や軒反りの様子、絵様(えよう)の細部など、
主要部は和様の造りとなっている。
これに対し、外壁煉瓦造の天后堂は架構法(かこうほう)なども純正な中国式を基調とし、
一部木鼻(きばな)や欄間(らんま)は、和様に従っている。
このように、様式的には和・中の併存であり、
中国との交流の歴史が凝縮された建造物であるといえる。
媽姐(まそ)神を祀る唐寺である。
祭神:天后聖母(媽祖)の左右に侍婢、その前に順風耳、千里眼の像が祀られている。
天明4年(1784)大火により唐人屋敷は全焼するが天后堂は残り、
寛政2年(1790)修復されたものである。