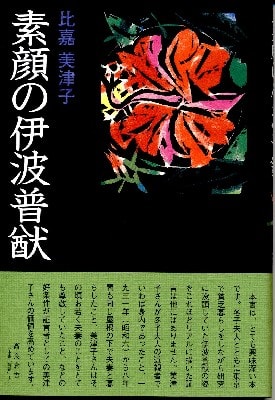私は、故郷を喪失した無名の人たちの菊の根をマルチチュードと定義したい。
往々にして、彼らは外国人であり、住む場所に違和感を覚える人たちである。そうした一群の人たちが新しい社会を創造する力をもつと、私は信じている。
私が務めていた京大経済学部は河上肇を追放した。河上肇は、マルチチュードという言葉こそ創造しなかったものの、日本におけるマルチチュード論の草分けである。
京都大学関係者は、いまも盛大に行われている「河上祭」によって、河上肇のことをよく知っているが(ただ、昔の京都大学の雰囲気が急速に消え去ろうとしているので、最近の学生やスタッフは河上のことを知らない可能性が高まってきたのかも知れない)、ご存じない方も多いと思われるので、『ウィキペディア』によって紹介しよう。
河上肇(かわかみ・はじめ、1879(明治12)~1946(昭和21)年)は、山口県玖珂郡岩国町(現在の岩国市)に旧岩国藩士の家に生まれる。山口尋常中学校(現山口県立山口高等学校)、山口高等学校文科(現山口大学)を卒業し、東京帝国大学法学部政治科に入学。
足尾銅山鉱毒事件の演説会で感激し、その場で外套、羽織、襟巻きを寄付して、『東京毎日新聞』に「特志な大学生」であると報ぜられた。1902(明治35)年、大学を卒業。その後、東京大学農科大学(現在の農学部に相当)講師などになり、読売新聞に経済記事を執筆。1905年(明治38)、教職を辞し、無我愛を主張する「無我苑」の生活に入るが、間もなく脱退し、読売新聞社に入る。性格は猪突猛進型であったらしい。

1908(明治41)年、京都帝国大学の講師となって以後は、研究生活を送る。1913(大正2)~15(大正4)年にかけて2年間のヨーロッパ留学。帰国後、教授。1916(大正4)年から『大阪朝日新聞』に『貧乏物語』を連載し、翌年出版。弘文堂が発行元である。東京で活躍している同社は、もともと、京都の出版社であった。私も、この出版社の事典に執筆している。同社のアテネ文庫は超人気をはくした。
デモクラシーの風潮の中、貧困というテーマに経済学的に取り組んだこの書は、ベストセラーになった。全体の主張は「金持ちは贅沢を止めよ」といった倫理的な教訓であった。

その後、マルクス経済学の研究を進める。1921(大正10)年、河上の論文「断片」を掲載した雑誌『改造』は発売禁止となるが、この論文は、後に、虎の門事件を起こす難波大助に影響を与えたという。1922年、櫛田民蔵が河上のマルクス主義解釈に対して、痛烈に批判した。河上はその批判を甘受した。河上のすごさは、自らの理解の浅薄さを認めたところにある。
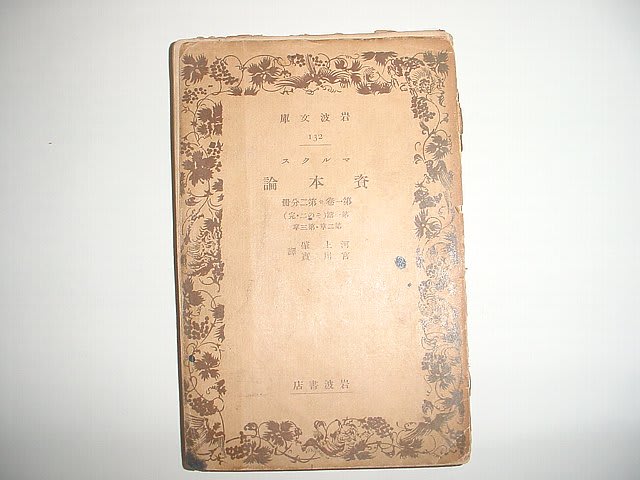
発奮した河上は、『資本論』などマルクス主義文献の翻訳を進め、河上の講義は学生にも大きな影響を与えた。1928年(昭和3)、京都帝大を辞職し、大山郁夫の下、労働農民党の結成に参加。1930(昭和5)年、京都から東京に移るが、やがて労働農民党は誤っていると批判し、大山と決別。雑誌『改造』に『第二貧乏物語』を連載し、マルクス主義の入門書として広く読まれた。これは、改造社から1930(昭和5)年に出版された。
1932(昭和7)年、日本共産党の地下運動に入る。1933(昭和8)年、中野区で検挙され、治安維持法違反で小菅監獄に収監される。収監中に自らの共産党活動に対する敗北声明を発し、大きな衝撃を与えた。また獄中で漢詩に親しみ、自ら漢詩を作るとともに、曹操や陸游の詩に親しんだ。この成果は出獄後にまとめた『陸放翁鑑賞』(放翁は陸游の号)などで見ることができる(河上肇『陸放翁鑑賞、上・下』三一書房、1949年、『河上肇全集』第20卷、岩波書店、1982年、一海知義校訂『陸放翁鑑賞』岩波書店、2004に再録)。
1937年(昭和12)出獄後は、自叙伝などの執筆をする。1941年京都に転居。第二次世界大戦終戦後、活動への復帰を予定したが、1946年に逝去。1947年、『自叙伝』(世界評論社)が刊行される。岩波書店から『河上肇全集』が出版されている(全36 巻、1982∼1986 年)。
私は、歌人、河上肇をこよなく愛する。戦争の屈服が放送された日の河上肇の歌。
「あなうれしともかくにも生きのびて戦やめるけふの日にあふ」。
共産党に入党した時の歌。
「多度利津伎布理加幣里美禮者山河遠古依天波越而来都流毛野哉」(辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるもの哉)。
これは漢詩ではなく、万葉仮名の積もりである。当局の眼に触れられたくなかったのであろう。正しい仮名の使い方かどうかは私には判定できない。
河上はすでに32歳の若さで、経済学と宗教学とを結びつけようとしていた。
古代の日本人の祖先崇拝は、死後の生活も生前の生活を踏襲するものとして、生前の生活用具を死者とともに埋葬したことに現れている。そして、古代人たちは、彼らの生活環境が、祖先の神意によって決定されると受け取っていた。氏神を護ることが共同体維持の最重要の行為になっていた。古代天皇制はこうした祖先崇拝から成立した。等々の説明を行った後、河上は、次のように書いている。当時においては、
「政治は即ち祭事たり、祭事は即ち政治たり。此の如くにして所謂政教一致の国家あり」(『京都法学会雑誌』第6巻第1号、1911年、141ページ)。
それぞれに氏族が氏神をもつ。支配した氏族が自己の氏神を支配下の氏族に押し付ける。しかし、支配する側も、支配される側も、旧来の氏神は消滅しない。氏神に階層性ができる。
「故に共同の神を生じたる後においても猶、その下には幾多の封鎖的宗教団体を存し、各種族各氏族は共同の神の外に各種族各氏族皆それぞれの神を有すること、例えば政治上において国王の下に大氏の氏上あり、大氏の氏上の下に小上の氏上ありたることその趣全く同じ」(同、144ページ)。
いまでこそ、当たり前の考え方だが、皇国史観全盛時代に、この種の発言をあえてした河上の勇気は相当に強靱なものである。
祭政一致を完成させたのは、第10代崇神天皇である。だからこそ、この天皇は、「御肇国天皇」(はつくにしらす・すめらみこと)、つまり、日本に国を作り出した最初の天皇と称されていたのである(『日本書紀』の記述)。
この考え方を発表した河上肇は、同年、那覇を訪れた。そこで、いわゆる「舌禍事件」を起こし、体制側の大憤激を買う。
その時の河上は、京大助教授であった。近代資本主義は土地の私有制を根幹としているが、この土地私有化のプロセスは、当時、沖縄に残っていた「地割(ちわり)制度」を調べると分かるのではないかと現地調査にきたのである。これもすごいことである。彼は、ドイツ語文献によるマルクス主義だけを摂取しようとしたのではなかった。河上は、もっとも重要な土地慣行調査を実行したのである。これは、当時の学問状況からは画期的なことであった。
地割制度とは、税の負担を村単位の連帯責任として科していた制度である。以前に紹介した「間切り」(まぎり)はこの単位を確定したものであった。
沖縄国際大学文学部の仲地哲夫氏の紹介によれば、沖縄の地割制度に関する調査は、仲吉朝助(1867∼1926年)を嚆矢(こうし)とする。仲吉朝助は、大田朝敷(1865∼1938年)や謝花昇(1865∼1908年)と同時代の人物である。東京帝国大学農科大学実科卒後、帰県して島尻郡役所に務め、後、沖縄県属、農商務課長、そして、1905(明治38)年、辞して沖縄県農工銀行頭取となった。東大農学科ということで河上肇との接点があった可能性がある。著作も多い。
仲吉朝助には多数の著書・論文がある。『杣山制度論』は、1900年脱稿していたが、発行されたのは1904年であった。1906年4月、『琉球新報』に「沖縄県土地整理前に於ける地割制度」を連載し、1907年11月、『琉球新報』や『砂糖月報』に発表した論稿と国頭農学校での講義ノートをまとめて『沖縄県糖業論』として発表している。なお、遺稿「琉球の地割制度」が『史学雑誌』に掲載されたのは、1928年のことであった。琉球の土地制度の研究をはじめとして、沖縄における社会経済史の研究の礎を築いた功績はきわめて大きい。仲吉朝助編の『琉球産業制度資料』は第一級の作品である。
これを柳田國男から借りた比嘉春潮は、1952年10月から翌年2月にかけて、『沖縄文化』誌上に「具志頭間切御手入」と題する論文を発表し、1959年6月には『日本の民族・文化』に「地割制度」と題する論文を発表している。
琉球の土地制度・地割制度に関する研究は、1950年代以降、地道に行われてきた。その成果のほとんどは「琉球産業制度資料」を駆使して得られたものである(http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B1132580/1/mokuji/3301.pdf)。
河上肇の着想がいかに優れていたものであるかが、以上の紹介で分かるだろう。
伊波普猷と関係の深い比嘉春潮についても紹介しておこう。
比嘉春潮(1883(明治16)年~1977(昭和52)年、94歳の長寿)は、西原町に生まれた。本名は春朝。南風原小学校の教員を振り出しに、官職に就く。1918(大正7)年、那覇区松山小学校長から『沖縄毎日新聞』、『沖縄朝日新聞』の記者となる。だが、翌年に沖縄県庁に入る。
キリスト教からトルストイズムに転向。河上肇の沖縄講演で社会主義への関心を抱く。1921(大正10)年、官憲から追われて、本土から沖縄に潜入したアナーキストを逃がすために、比嘉は、その人を宮古島に送る。その船上で柳田國男と出会う。その後、県庁を辞めて上京、改造社出版部員となる。そして柳田に師事、民俗研究を続ける。
その一方で、大正末年から昭和初期にかけて、無産者運動を側面から援助し、沖縄県出身の共産党員と交流した。また、プロレタリア・エスペラント運動にも参加。比嘉春潮は、新宿柏木の自宅を開放して、プロレタリア・エスペラント研究会を続けていた。この研究会は有名で「柏木ロンド」と呼ばれ、特異な存在だった。伊波普猷がそれに協力した。
彼の顕彰碑の碑文には、生い立ち、人柄、業績などが書かれているが、エスペランチストとしての活躍は記録されていない。そして「ここにふるさとを愛した篤学・反骨の研究者・比嘉春潮の遺徳を称え、功績を後世に伝えるためにこの碑を建立します」と、日本語と英語の文章が刻まれている(http://www.okinawatimes.co.jp/spe/kaizu20020521.html)。
地割制度と関連させて、西銘圭蔵氏が古い沖縄の婚姻制度の因習を説明されておられる(同氏、『伊波普猷―国家を超えた思想』ウィンかもがわ、2005年、59~60ページ)。
村全体で税負担が決められていたが、その総額は、村民の人数とはほとんど関係なかった。この制度下で、村の娘が結婚のために村の外に出て行ってしまうと、それだけ生産力が落ちることになる。そのために、村外の男が、村の娘を村外に連れ出して結婚することは、村人によって極力妨害された。娘を連れ出そうとする村外の男は、偽馬(木馬)に縛り付けられて、村中引きずり回され、大量の酒を無理矢理飲まされ、正体不明にさせられるという、陰湿ないじめがあった。そうした事態を回避するには、結婚したい村外の男は、相当の金額を村に寄進しなければならなかった。この金は、馬にかかわる費用を賠償しますという意味で、「馬手間」(うまてま)と呼ばれていた。こうした陰湿な結婚妨害は、地割制度のなかった宮古島。石垣島には見られなかった。地割制度がある沖縄本島以北に、馬手間は、あったのである。
さて、河上肇が舌禍事件を起こしたのは、1911(明治44)年4月3日のことであった。地割制度の調査にきた河上肇に、沖縄県当局は講演を依頼した。
この講演は素晴らしいものであった。現代人なら、拍手していたであろう。しかし、当時の沖縄県当局と『琉球新報』が激怒した。
長くなるが、素晴らしい文章なので、そのまま転載する。
「余倩ら沖縄を観察するに、沖縄は言葉、風俗、習俗、信仰、思想、その他あらゆる点に於いて内地と其の歴史を異にするが如し。而して或いは本県人を以て忠君愛国の思想に乏しと云ふ。然れどもこは決して嘆ずるべきにあらず。余は之なるが為に却って沖縄人に期待する所多大なると同時に又最も興味多く感ずるものなり。・・・今日の如く世界に於いて最も国家心の盛なる日本の一部に於いて国家心の多少薄弱なる地方の存するは最も興味あることに属す。如何となれば過去の歴史に就いて見るに、時代を支配する偉人は多くは国家的結合の薄弱なる所より生ずるの例にて、基督の猶太に於ける、釈迦の印度に於ける、何れも亡国が生み出したる千古の偉人にあらずや。若し猶太印度にして亡国にあらずんば彼者は遂に生まれざるなり。故に仮令ひ本県に忠君愛国の思想は薄弱なりとするも、現に新人物を要する新時代に於いては、余は本県人士の中より他日新時代を支配する偉大な豪傑の起こらん事を深く期待し、且つ之に対し特に多大な興味を感ぜずんばあらざるなり」(比屋根照夫『近代日本と伊波普猷』三一書房、1981年、74~75ページ)。
県令や、『琉球新報』は、これに激怒した。賢明によき日本人たらんと努力している沖縄県民を、河上が、揶揄したというのである。

もしかして、私が座った机に、私が立った教壇に、河上肇が座り、立ったのかも知れない。そうした思いが、私の心に灯をともしてくれている。マルチチュード論の先駆けが、河上によって行われていたことを、私は、迫り来る禍に怯えながらも、誇りに思う。