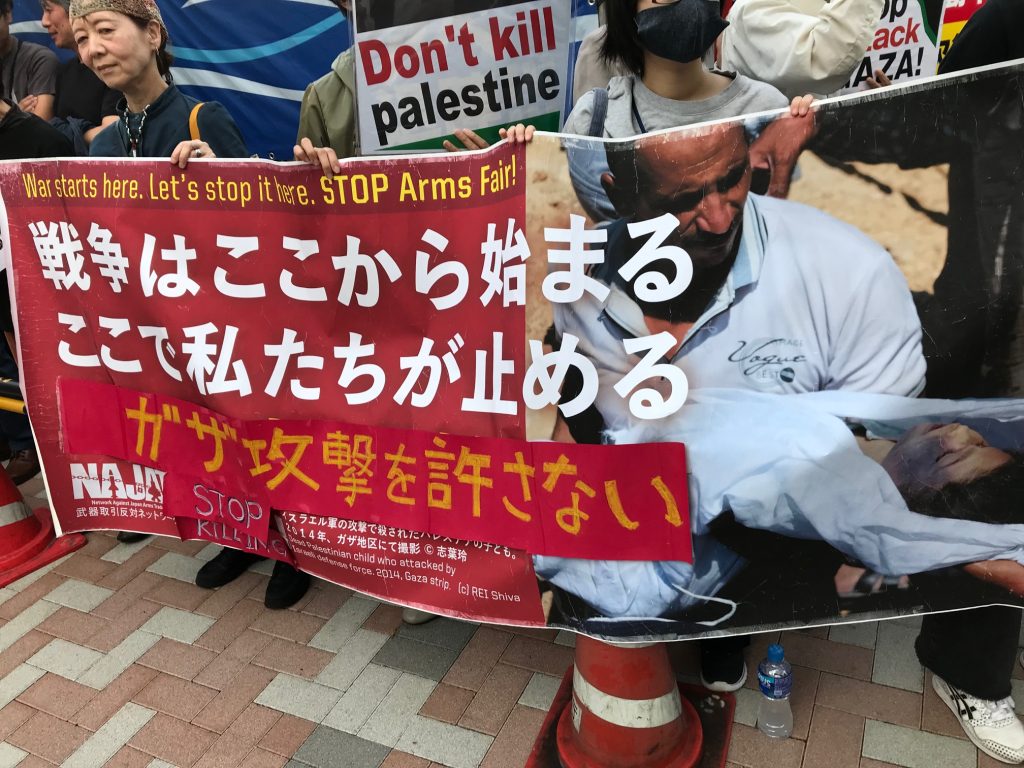ホームへルパー国賠裁判を支援する会
私たちは長年働いてきたホームヘルパー3人組です。ホームヘルパーは待機時間、移動時間などは給料に反映されないため、これまで働いてきた20年間の移動や待機時間などを計算すると、労働時間の5分の1にあたる約4年間はただ働きに相当します。
2019年11月、私たちは介護保険の制度的欠陥ゆえに介護労働の現場では労働基準法が遵守されないことが常態化しているにもかかわらず、国は適切な規制権限の行使を怠ったとして、東京地裁に本件国家賠償請求訴訟を提起しました。現在、東京高裁で争っているところです。本件訴訟は、大手各新聞をはじめ週刊誌、介護関係業界誌など多くの媒体に取り上げられ、注目を集めています。
私たちは単に、自分たちの待遇改善を訴えているだけではなく、このままではヘルパーという仕事が消滅してしまい、そのことによって介護を受けられなくなる「介護難民」が膨大に生まれてしまうことを懸念しているからです。「若者が選ぶ価値のある職業にしなければヘルパーは消滅する」、つまりこの裁判は訪問介護の持続性を問うものです。
在宅介護の登録型ヘルパーは、社会的介護の主な担い手であるにも関わらず、正当な評価はされず不当な労働条件のまま放置されてきました。サービス提供分しか賃金が支払われない「出来高払い」制度、サービス提供時間と区別して移動、待機、キャンセル、記録などの必ず発生する時間が別建てで介護報酬の対象とされず、タダ働きとなっています。「生活援助」に関する不当に低い報酬額の設定。そして、国は、「すべてが包括して介護報酬に含まれている」としながら一度たりともホームヘルパーの労働実態について調査をしてきませんでした。最低賃金以上の賃金にするために財源確保をした痕跡もなく、労働基準法違反の状態に通達を出すだけで、改善のための具体的対応をとることは全くありませんでした。
3年ごとの介護報酬改定を経て、介護保険制度は、家事・生活援助を切り捨て身体介護も含めて1時間に満たないサービスを増やし、「効率化、生産性」の名のもとに労働を細切れ化することで、介護労働者のみならずサービス利用者及び家族の人権侵害を続けてきました。その結果が、求人倍率15倍、有資格者の離職が後を立たない人手不足の現状です。事業所の倒産・閉所、廃業が止まらず、業界団体までも、公定価格の引き上げを含む介護報酬の大幅な賃上げなくして介護崩壊を招きかねないことを総力で要請するまでになっています。
超高齢化社会で介護労働者やサービス利用者の人権が守られる介護を実現するには、「ケア」を公共財とし、優先課題として国費を投入するとともに、ケアに携わる労働者を保護することが必要不可欠です。国が「労働者保護」について責任を負わないという結論になる、地裁判決を見直し、高等裁判所が公正かつ慎重な審議に基づいて判決を出すことを求めます。
著名はこちらから。
HP https://helper-saiban.net/
【特集】介護の社会化を問いなおす―ジェンダー・ケア・シングルの視点から
介護保険制度下のケア労働の実態
―ホームヘルパー国家賠償訴訟原告・伊藤みどり氏インタビュー
2022 年9 月23 日,ホームヘルパー国家賠償訴訟の原告のお一人である伊藤みどり氏に,本特集を企画した北明美がインタビューを行った。インタビューにあたっては,伊藤氏ほか2 名の原告がこれまで発表されてきた以下の資料等を参照した。
・ホームヘルパー国家賠償訴訟ホームページ,https://helper-saiban.net/
・ フォーラム労働・社会政策・ジェンダー編『連続講演会 ケア労働とジェンダー 1 回「ケア労働とジェンダー 機会均等論を超えて」講師 伊藤みどり,コメンテーター 伊田久美子』(2021 年6 月11日)報告集
・「特集 ホームヘルパ―国賠訴訟」『賃金と社会保障』No.1749(2020 年3 月上旬号)
・「 ホームヘルパー訴訟,約 1 年ぶりの法廷で原告意見陳述」『週刊金曜日』No.1391(2022年 9 月 2 日号)
ホームヘルパー国家賠償訴訟とは,2019 年11 月に,ホームヘルパー(登録型訪問介護員)として働いている藤原路加氏・伊藤みどり氏・佐藤昌子氏が,国(厚生労働省)に対して経済的および精神的損害の賠償を求め,東京地裁に提訴した訴訟である。介護保険制度とその「準市場」システムのもとで,ホームヘルパーは労働基準法さえ遵守されえない劣悪な労働条件のもとにおかれているが,それに対し国は適切に規制権限を行使してこなかったと原告は主張している。
ホームヘルパー683 人にアンケート
ヘルパーの善意に国は甘えるな~~!
★ 20 分の介護に移動が往復1 時間
★自転車を漕ぐのが仕事でない
★処遇改善加算はヘルパーに届かない
★移動手当はほぼゼロ
★猛暑、大雨、大雪等に危険手当を
★若い人に勧められる待遇に
★制度のしわ寄せはごめんだ
★年金下がり続け、移動も大変な上に無給
これでは、利用者さんの思いに応えられない!
ただ今、ヘルパー裁判やってます‼
訪問介護は「登録ヘルパー」とも言われるように非正規が8割。報酬は出来高払い制です。
訪問介護のサービスは「身体介護」「生活援助」などがありますが、担い手不足と「生活援助」の切り捨てで、訪問介護は破綻寸前に追い込まれています。
「もう黙ってられない!」とホームヘルパー3名が2019 年11 月東京地裁に国家賠償請求訴訟を提起しました。
●ホームヘルパーの賃金は安すぎ!
正規雇用のヘルパーでも平均月収は約17 万円。登録ヘルパーにいたっては約8 万円弱。これでは生活していけません!
●勤務時間の4 割は移動時間、待機時間、キャンセル時間。しかもその時間は「無給」!
拘束時間で考えると〝最低賃金〟割れしています。
●介護事業者の支払い能力を超えている。
国は事業者に「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて」という通知を出しました。しかし、訪問介護を中心に事業者の倒産は増加の一途。事業者は、今の介護報酬でそれを払えません!
●責任は〝国〟にある
現行の介護保険制度では労働基準法を守れない理不尽な仕組みであることを、国は知りながら放置しています。
未払い賃金と慰謝料を合わせて、原告1 人300 万円の損害賠償を国に求めています。
国会でも問題視!
参議院では、私たちが実施した「ヘルパー実態アンケート報告書」を手にして、議員さんが丁寧に質問してくださり、その様子はネットで中継されました。
「朝日新聞」「東京新聞」ほか大手メディアで掲載。
「現代用語の基礎知識」では、「とりわけ待機時間も移動時間もコストに換算されない登録ヘルパーの労働条件は劣悪で、これでは最低労働条件にももとる人権侵害だと、19 年藤原るからによるホームヘルパー訴訟が、国を相手取って行われた」と、2021 年の最新版に掲載。
ホームヘルパー国賠訴訟とは?
穏やかで平和な暮らしに向けてヘルパーの仕事は〝命と暮らし〟を支えること
誰もが安心してケアを受けられる介護保障を「ケアを社会の柱に」
58 大原社会問題研究所雑誌 №771/2023.1
― 伊藤さんは2011 年から非常勤の登録型訪問介護員(ホームヘルパー)のお仕事をされていますが,すでに1970 年代から労働組合で活動し,また1995 年には「女性ユニオン東京」の初代委員長に就任,2007 年にも「働く女性の全国センター」(ACW2)を設立するなど,女性の労働相談にも長く取り組んでこられました。当然,労使交渉や労働裁判等の経験も豊富です。けれども今回の裁判では,伊藤さんたち3 名の共同原告は,あえて勤め先の事業所ではなく,国に対して損害賠償を求めていますね。
伊藤 たいていの人は,ホームヘルパーも雇用される労働者なのだから,事業所と交渉したり,労働基準法や最低賃金法違反を労働基準監督署に訴えたりすべきだと考えます。ですが,私たちは,ホームヘルパーの権利侵害は,労使関係の枠を越える,介護保険制度そのものがもたらしている問題と考えるのです。日本の介護保険制度は,労働基準法も最低賃金法も守れないような仕組みになっています。実は,国(厚生労働省)も,そのことをわかっていながらその是正を怠ってきました。国が必要な規制権限を行使しようとしなかったことで,私たちホームヘルパーは,賃金不払いによる多額の経済的損害をうけ,また介護労働者としての尊厳を傷つけられる働き方を余儀なくされる精神的損害をうけたと考えています。
― 介護保険制度,とくに介護報酬の仕組みの問題を指摘されていますね。
伊藤 人手不足だと賃金が上がるはずですが,介護労働者の場合は,介護報酬,すなわち国が定める介護サービスの公定価格が,まずあって,それが政策的に引き下げられてきました。しかも,介護保険制度が始まる前の「措置制度」の時代と異なり,この介護報酬においては,必要な人件費を独立の項目として算入するという仕組みになっていません。そのため,上限となる介護報酬の低さが,低賃金に直結するだけでなく,不払い労働部分を発生させ,実質的に最低賃金を下回る違法状態を生み出しています。
たとえば訪問介護では,利用者宅から利用者宅への移動や,利用者宅から事業所への移動が必要で,それは法律上も賃金を支払うべき労働時間ですが,まったくの無給であるか,支払われても低額の手当か必要な移動時間を過少に想定した金額であるために,最低賃金を下回ってしまう場合がほとんどです。ホームヘルパーは,こうした状況のもとで,たとえば20 分と決められた身体介護をするために利用者宅まで自転車で往復40 分かかるというような仕事の仕方をさせられているのです。国の方針によって,1 回の訪問介護時間はどんどん細切れにされ,その分,訪問回数も増やさなければならなくなっていますので,こうした移動時間もますます大きな割合になっています。
地方では利用者の家まで自分の車で長時間の移動をすることがよくあるのですが,修理費等は自分持ち,ガソリン代もきちんと支給されないといったケースも珍しくありません。
移動時間のほかに,次の利用者宅の訪問介護を開始するまでの「待機」時間の問題もあります。
これも細切れになっており,使用者の指揮命令下から離れているといえるような,まとまった自由時間ではありません。また,「待機」といっても,多くの場合,事業所への業務連絡や介護記録の作成などにあてられる労働時間になっています。にもかかわらず,これらもまた,しばしば違法な不払い労働になっています。
要するに,ホームヘルパーに対する賃金は,事業所が受け取る介護報酬のなかから支払われるのですが,その介護報酬は,定められた直接的な介護時間に対する価格であって,訪問介護の仕事にともなう必然的な「移動」や「待機」,また業務そのものである介護記録作成や業務連絡等の労働に対する賃金部分は想定されていないため,その分を事業所が赤字覚悟で負担するか,不払い労働にしてしまうという事態が必然的に起こっているのです。
加えて,それどころか,突発的な事態に対応するために契約上の時間より長く介護することになったような場合は,「待機」のはずだった時間が介護時間になってしまったのに,その分についての賃金は支払われず,不払いのサービス残業になる場合さえあります。
また,訪問介護では,急な施設入所や入院,体調不良,また,認知症でヘルパーの訪問予定を忘れて外出してしまうなど,利用者からのキャンセルが日常茶飯事です。だからといって,そこに即座に,別の訪問介護や他の業務を入れることができるとは限りません。そういった場合,労働者は本来平均賃金の60%の休業手当を受ける権利があるのですが,当日やその場のキャンセルのみこの手当を支払うか,それすらもまったく支払わない事業所が大半です。訪問実績に対する出来高払いであるため,キャンセルされれば,その分の介護報酬が事業所に入らなくなる一方で,やむを得ない事情によるキャンセルに対し,そのつど利用者からキャンセル料をとるような契約はできないからです。こうした制度の矛盾のしわ寄せもまた,ヘルパーの収入の低さや不安定さの大きな原因となっています。
国(厚生労働省)は,事業所に対して,労働基準法や最低賃金法の遵守を求め,何度もそのための通達を出していますが,その一方で,必要な賃金や手当はすべて介護報酬に含まれていることになっているという一点張りです。しかし,具体的にどのように算定されているのか,私たちが何度尋ねても一切答えず,答えるための調査もしていません。
長年にわたって介護報酬が引き下げられている状況のもとでは,「移動」「待機」「記録業務」などの附帯時間を含めた賃金や休業手当を,労働基準法どおりに支払ったら,小規模の介護事業所はどんどん倒産していくだろうことをホームヘルパーたちは知っています。そうすれば,自分たちの職場がなくなってしまうだけでなく,大規模な事業所が引き受けたがらない遠距離の訪問や対応のリスク・負担が大きい,事情のある利用者の受け皿がなくなってしまいかねません。そのことが常に念頭に浮かぶのです。
― 介護報酬については,国もなり手不足を背景に,介護労働者の賃金引き上げを名目とする,いろいろな加算を設定してきていると聞いているのですが。
伊藤 そもそも加算は,ほとんどいつも介護報酬「本体」の引き下げとセットで行われるため,効果が相殺されてしまいます。また,加算の配分方法は,事業所に任せられている部分が大きいため,私たちのような登録型のホームヘルパーは対象外にされることが多いのです。
しかも加算は,最初だけは国の全額負担でなされても,そのうち,介護報酬体系に組み込まれて,その事業所の介護サービスの公定価格の引き上げに転嫁されていきます。そうすれば,加算をとった事業所と契約する利用者は,他より高い利用料を払うことになります。もっと利用時間や回数を増やすことが必要な状態なのに,負担増を恐れてそうできなくなる利用者のことを心配するような事業者ほど,加算をとらない選択をするようになるのです。加算申請のための事務手続きも煩雑で,小規模事業所ではそのための時間や人を確保できないということもあります。
人件費をきちんと項目として確保しないまま単に介護報酬を引き上げて,それに比例して介護保険料や利用料を引き上げ,それによって国の負担を常に4 分の1 程度にとどめるというやり方ではなく,私たちは,労働基準法・最低賃金法を守れるよう,人件費を積み上げ計算し,それをもとにして,国の負担で,介護報酬とは別に,事業所に人件費を補助する方式を望んでいます。
― 訪問介護においてもコロナ禍での苦労が大きかったと聞いています。
伊藤 介護や支援が必要な方々の自宅を回るホームヘルパーは,エッセンシャルワークだと言われるようになりましたが,介護事業所はワクチン接種の優先対象なのに,訪問介護のホームヘルパーは最近まで対象外とされていました。この間,私たちは,すべての利用者宅でドアをノックする前にアルコール消毒をして,利用者が濃厚接触者だと判明しても,介護を拒否することなく,完全防護でケアに入ります。自宅に帰れば自分の着ているものもマスクもエプロンも全部玄関で着替えて……という状況でした。
「ホームヘルパーがコロナを自宅に持ってくる」と言われて,訪問件数が減ったとか,濃厚接触者のケアに入ったヘルパーがたとえ陰性でも他の利用者宅には入れなくなってしまってヘルパーの収入が減り,人手不足もさらにひどくなるといったことも起きていたそうです。
― 今回の裁判では精神的損害の賠償も国に求めていますね。
伊藤 私が2011 年にヘルパーになったときは,生活援助はだいたい2 時間から1 時間だったのですが,厚労省の介護報酬改定に基づく条例によって数年後には30 分から1 時間未満が原則になり,今では一般に20 分から45 分が基準サービスとされています。身体介護も同様に,当初は1 回の訪問で2 時間から1 時間かけていたのが,今では30 分から1 時間未満が基準になり,20 分未満という時間区分さえあります。1 件あたりのサービス時間を減らしてヘルパーが1 日に何件も回るようにしたほうが経営効率がよい,つまりお年寄りの話を聞いている時間があったら次のお宅にサービスに行けというのが国の介護報酬改定の方針になったからです。
こういった政策で,サービス時間が短時間の細切れにされているため,要介護5 のようなかたでも,たとえば朝30 分,昼30 分,夕方60 分という狭い枠のなかで,「食事介助」も「排泄介助」も「口腔ケア」も「買い物」も「調理」も「洗濯」もすべてやらなければならない事態になっています。
最も人権侵害でやるせないと感じるのは,ヘルパーが来るまでおむつの中は長時間濡れたまま,さらに認知症が進むと気持ち悪くておむつをはがしてしまうので,シーツもベッドも糞便にまみれ,ご本人は裸で待っているといった事態も起きていることです。テープ式おむつの上にパッドを2 枚当てて,その上からリハビリパンツを履いてもらうといったやり方をすれば,カンジダ菌や尿路感染などにもつながるのですが,それを心配しながらもそうせざるを得ない場合もあります。
サービスの短時間化が引き起こすこの状況を目のあたりにして,私たちヘルパー自身も,精神的に非常に傷ついています。高齢者の命の尊厳が奪われていると同時に,ホームヘルパーの専門職としての仕事の尊厳も奪われているからです。
介護福祉士の養成テキストには,高齢者の尊厳を守りQOL の向上に努め,エンパワーメント・アプローチを行うこと等,あるべきケアについて書かれているのですが,現行の介護保険制度のもとでは,そうした介護はすでに不可能になりつつあります。こんな細切れ時間のなかで,そのつど本人の同意をとっていたら,時間内には「食事介助」もできないし,「排泄介助」もできません。
とくに認知症のかたは,ヘルパーが短時間で終わらせようとせかせか動いたり,高齢者をせかしたりすれば,強い不安を感じて怒りを爆発させるなど,状態が悪化することもあります。
本来,介護労働者はじっくり対話し,耳を傾け,観察するなかで,利用者のニーズと潜在的パワーをひき出す働きかけをするのですが,そのような専門性を発揮する機会が介護保険制度のもとで進められたサービスの短時間化や「生活援助」軽視の政策によって奪われていっています。このことは,介護保険制度がはじまる以前からホームヘルパーをしていたベテランの介護士が,現状に失望して辞めていく大きな理由になっています。こうした人たちは,「身体介護」だけでなく「生活援助」の重要性をよく理解していて,掃除や洗濯をしているときに利用者が無言のうちに発する危険信号に気づき,非常に早い段階で自ら対処したり,他職種と連携して改善につなげたりといった,ケアワークやソーシャルワークをしてきました。ですが,今はそのスキルを発揮しようにもできない状態におかれ,介護労働者としての尊厳を奪われたと感じているのです。
― いろいろな仕事や職場の現場を知っておられる伊藤さんにとって,ホームヘルパーとはどのようなお仕事ですか。
伊藤 私は,工場労働をはじめ,いろいろな仕事をやってきました。生きるためにやらざるを得ないと考えてきたのですが,ホームヘルパーの勉強をし,実際に介護の仕事に携わった時に,本当に面白い,やりがいのある仕事に出会ったと心から感じました。認知症のかたが徘徊したり,暴言を吐いたりといった行為も,こちらのケアの仕方によっておさまっていきます。ヘルパーに対する信頼の感情が生まれた時,それまで拒絶的だった高齢者の表情がふわっと一変します。こちらのケアを受け入れてくれたと感じられる瞬間があるのです。介護の仕事ではこうしたことを目のあたりに体験します。「人間って,すごいな」と感じますし,だからこそ続けられるんですね。ケア関係には人間の英知が凝縮しているといってもいいと思います。
ですので,それを「汚い」とか「5K」とか「大変な仕事」としかみないのは,あまりにも人間に対する理解が足りないのであって,こうしたことを皆が学んでいたら,介護の仕事を一段低くみるというようなことは起きないのではないかと思うのです。一人ひとりの人間の生命を支え,尊厳を維持する介護という仕事の価値と評価をあげていくことが必要です。
― いま裁判はどういった状況なのでしょうか。
伊藤 裁判では,原告側の意見陳述も,証人尋問の申請も却下されただけでなく,裁判官はまともに反論・立証しない国の姿勢をただそうともしませんでした。そこで2021 年9 月に裁判官全員について忌避の申立てをしたのですが,これも却下されています。2022 年8 月に審理が再開したものの,人事異動で交代した裁判官もまた,原告側が意見陳述した直後に弁論終結を宣言したため,法廷は抗議の声に包まれました。判決は2022 年11 月1 日に予定されています。
こうした経緯から判決にあまり期待はできないと覚悟していますが,仮に敗訴であっても高裁に進むつもりでいます。注文のある時だけ労働者を呼び出して働かせ,収入の最低保障もなく経費は労働者持ちというイギリスの「ゼロ時間契約」は,日本ではまだ合法化されていませんが,実際には介護保険制度のもとで登録型のホームヘルパーは限りなくそれに近い働き方をさせられています。高裁でも引きつづきこの問題を明らかにしていきたいと考えています。
― ありがとうございました。
(聞き手・まとめ 北 明美)
【補遺 伊藤みどり氏より】
2022 年11 月1 日,ホームヘルパー国賠訴訟の判決がありました。結果は予想した通り棄却となりました。
しかし現在,介護保険制度史上最悪の改悪が進められていることもあり,裁判を通してようやく介護保険の仕組みの理不尽さが理解されるようになってきました。多くのマスコミが紙面を割いてこの不当判決の記事を書いてくれました。
判決の棄却理由は,原告が訴えている未払い賃金の問題は,各事業所を労働基準監督署に訴えるべきものであり,労働基準法違反を規制する権限を行使しなかったのは国の責任だと主張する原告の訴えについては,不行使が著しく不合理と言えるような証拠がないというものでした。
ですが国が労基法を守るように通達を出しても現場でそうならないのは,介護保険制度そのものが労基法通りの賃金支払いができる仕組みになっていないからです。国は労基法が守られていないことを知りながら仕組みを変えようとしない。規制権限の不行使そのものです。
最近,施設の人員基準の3:1 では,労基法を守れずシフトも日勤が組めない状況になっていると聞きました。私たちが裁判を起こすのはいわば負ける裁判にチャレンジすることでもありましたが,国が決めた制度や仕組みに問題があることが知られるようになり,結果としては裁判を起こして良かったです。
原告は控訴することにしました。
人として、尊厳のある「生活」を営まれるよう希望いたします。
介護する人も、介護される人も。
初雪・初積雪。




エゾリス

今年も初雪、初冠雪が同じ日になってしまいました。