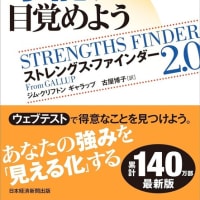先に読んでもらったブログのなかで、脳死状態になったときに延命治療を停止するかどうか、
臓器提供をするかどうかは価値判断の問題であり、
それにどう答えようと正解・不正解があるわけではないと書きました。
それに対して、3問目の脳死とは何か、植物状態との違いは何かという問題は、
事実判断に関する問いであり、これには科学的・医学的な正解があります。
私の「哲学」の授業の中で、今回の問3の問いは唯一、
国家試験に出題される可能性がある問題なので、
知らなかった人はこの機会にちゃんと覚えるようにしてください。
さて、先に考えてもらった「脳死状態になったときに延命治療を停止するかどうか、
臓器提供をするかどうか」という問いはたしかに価値判断ではありますが、
この価値判断は本来、「脳死状態とはどういうものであるのか」という事実判断を踏まえて、
その答えをあらかじめきちんと知っておいた上で初めて考えられるはずの問題です。
脳死のことをきちんと知らずに、
脳死になったときにどうするかを決められるはずないからです。
しかし、皆さんは3番の答えに自信ありますか?
3番にちゃんと答えられた人は、その事実判断に基づいて、
1番や2番の価値判断を下したと言えるでしょう。
しかし、3番の答えを知らずにテキトーに予想で答えた人は、
1番や2番の価値判断を正しく下せていたのでしょうか?
福島大学の「倫理学」という授業では、
もう少しイジワルな質問をしています。
授業の最初に次のような質問をしてみます。
「あなたは脳死臓器移植をよいことだと思いますか、悪いことだと思いますか。
その理由も書いてください。」
これをけっこう時間を取ってみんなに書いてもらった後で、続いて問2。
「ところで、脳死って何ですか? 植物状態とどう違うのか書いてください。」
とても意地悪です。
問1はよいか悪いかという価値判断を問うています。
福島大学の学生たちはみんなこれにけっこうスラスラと答えてくれます。
理由もたくさん書いてくれます。
ところがその価値判断を下す前にきちんと確定しておくべき 「脳死とは何か」 という、
事実に関わる問いに対しては、ほとんどみんな正しく答えることができません。
つまり、みんな脳死とは何かをよく知らないまま、
「脳死」という言葉の何となくのイメージだけに基づいて、
脳死臓器移植がよいか悪いかという価値判断を下してしまっているのです。
福島大学の「倫理学」の授業では、初期の頃に「倫理学的な考え方」について講義し、
倫理学的な判断というのは事実判断と価値判断の2つから成り立っていて、
一般的にはまず事実判断を確定させてから価値判断をするのが正しい順序であるが、
この順序が逆転してしまう場合もあるので気をつけなければいけない、
という話をしています。
そのことを具体例に即して体感してもらうために、こういう引っかけ問題を出しています。
授業の感想からは、この引っかけにみごとに引っかかってしまったことが、
相当印象に残った様子がうかがわれます。
「脳死臓器移植という重いテーマを用いて、倫理とはどういうものなのかということを考える授業であった。事実判断が不十分なままの価値判断がいかに滑稽であるか、授業内課題で思い知らされた。そして、脳死の概念の誕生による事実判断と価値判断の転換が非常によくわかった。」
「やっぱり脳死という大事で深いテーマだと一回聞いただけでは理解できないところもあったが、日本で臓器移植が他国より進んでいない理由を知ることができたのは大きい学びだと思う。事実判断が重要だと言っていたのが少し理解できた。軽く良いとか悪いとか決められないと思ったから、自分でも事実をもっと知らなければならない。」
「事実判断ができないと価値判断はできないはずなのに、『なんとなく』の価値判断をしてしまう恐ろしさを感じた。人を助けるための脳死臓器移植だが、手段が目的になって臓器移植のために脳死の人をつくるというのは犯罪でしかない。事実判断に必要な情報を持つことが求められると感じた。」
「今日の授業で取り上げられた『脳死』について、授業が進むほどに、私自身は脳死について無知だったと気づき、脳死というものについて正確な知識を身に付けたいと思った。正確な知識を身に付けることこそが、倫理学において、価値判断をする上で必要だと思うので、今後の倫理学の授業が進む上での意欲を駆り立ててくれた。」
「1、2番の課題を書いている時にすでに思っていたが、『脳死』という専門用語をあまり深く知らないのに、価値判断をしていることにとても疑問を感じた。そのようなことが、国会でも行われていたかもしれないと思うと、少し怖いなと思った。」
「事実判断が不十分であったことに気がついた。他の問題などについても、価値判断を下すことは授業課題などで訓練されていたが、事実判断があることが必要なのだと感じた。」
「倫理とは価値判断だけでなく事実判断も必要であるが、価値判断だけでも何かしらの考えが書けてしまうという話を聞いた時、自分の意見がまさにそれであって納得した。脳死臓器移植や植物状態について知らないことばかりなので、事実判断もできるようにしていきたい。」
「『脳死が良いことか悪いことか』という質問には答えることができるのに、『脳死とは何か』という質問には答えにつまって自分でもドキッとした。これからの講義で倫理的な脳死の問題について学んでいくのが楽しみです。」
「事実判断と価値判断の逆転、まんまと先生にだまされたなと思います。日頃気をつけようと心掛けているつもりではいましたが、自然な流れに、何の疑問も持たず書いてしまいました。そのくらい曖昧であり、逆転のリスクは高いのだと改めて感じました。最近の法改正についての報道の『脳死を人の死とする』という見出しや取り上げ方の意味がやっと分かりました。歴史も知らずに価値判断をしていたと思うと、改めておそろしいなと思います。」
「脳死だけでなく、何かの良し悪しを考える時、それがどういうものなのかもあまり考えず、なんとなくで答えを出していることに気づきました。自分の行為がひどく無責任なものに思えてきました。」
さて、看護学校の皆さんはどうだったでしょうか。
きちんと脳死とは何かをわかった上で、
脳死になったときにどうするかという価値判断を下せていたでしょうか。
問3の正解は次に読んでもらうブログのなかに書いてあるので、
各自答え合わせをしてみてください。
臓器提供をするかどうかは価値判断の問題であり、
それにどう答えようと正解・不正解があるわけではないと書きました。
それに対して、3問目の脳死とは何か、植物状態との違いは何かという問題は、
事実判断に関する問いであり、これには科学的・医学的な正解があります。
私の「哲学」の授業の中で、今回の問3の問いは唯一、
国家試験に出題される可能性がある問題なので、
知らなかった人はこの機会にちゃんと覚えるようにしてください。
さて、先に考えてもらった「脳死状態になったときに延命治療を停止するかどうか、
臓器提供をするかどうか」という問いはたしかに価値判断ではありますが、
この価値判断は本来、「脳死状態とはどういうものであるのか」という事実判断を踏まえて、
その答えをあらかじめきちんと知っておいた上で初めて考えられるはずの問題です。
脳死のことをきちんと知らずに、
脳死になったときにどうするかを決められるはずないからです。
しかし、皆さんは3番の答えに自信ありますか?
3番にちゃんと答えられた人は、その事実判断に基づいて、
1番や2番の価値判断を下したと言えるでしょう。
しかし、3番の答えを知らずにテキトーに予想で答えた人は、
1番や2番の価値判断を正しく下せていたのでしょうか?
福島大学の「倫理学」という授業では、
もう少しイジワルな質問をしています。
授業の最初に次のような質問をしてみます。
「あなたは脳死臓器移植をよいことだと思いますか、悪いことだと思いますか。
その理由も書いてください。」
これをけっこう時間を取ってみんなに書いてもらった後で、続いて問2。
「ところで、脳死って何ですか? 植物状態とどう違うのか書いてください。」
とても意地悪です。
問1はよいか悪いかという価値判断を問うています。
福島大学の学生たちはみんなこれにけっこうスラスラと答えてくれます。
理由もたくさん書いてくれます。
ところがその価値判断を下す前にきちんと確定しておくべき 「脳死とは何か」 という、
事実に関わる問いに対しては、ほとんどみんな正しく答えることができません。
つまり、みんな脳死とは何かをよく知らないまま、
「脳死」という言葉の何となくのイメージだけに基づいて、
脳死臓器移植がよいか悪いかという価値判断を下してしまっているのです。
福島大学の「倫理学」の授業では、初期の頃に「倫理学的な考え方」について講義し、
倫理学的な判断というのは事実判断と価値判断の2つから成り立っていて、
一般的にはまず事実判断を確定させてから価値判断をするのが正しい順序であるが、
この順序が逆転してしまう場合もあるので気をつけなければいけない、
という話をしています。
そのことを具体例に即して体感してもらうために、こういう引っかけ問題を出しています。
授業の感想からは、この引っかけにみごとに引っかかってしまったことが、
相当印象に残った様子がうかがわれます。
「脳死臓器移植という重いテーマを用いて、倫理とはどういうものなのかということを考える授業であった。事実判断が不十分なままの価値判断がいかに滑稽であるか、授業内課題で思い知らされた。そして、脳死の概念の誕生による事実判断と価値判断の転換が非常によくわかった。」
「やっぱり脳死という大事で深いテーマだと一回聞いただけでは理解できないところもあったが、日本で臓器移植が他国より進んでいない理由を知ることができたのは大きい学びだと思う。事実判断が重要だと言っていたのが少し理解できた。軽く良いとか悪いとか決められないと思ったから、自分でも事実をもっと知らなければならない。」
「事実判断ができないと価値判断はできないはずなのに、『なんとなく』の価値判断をしてしまう恐ろしさを感じた。人を助けるための脳死臓器移植だが、手段が目的になって臓器移植のために脳死の人をつくるというのは犯罪でしかない。事実判断に必要な情報を持つことが求められると感じた。」
「今日の授業で取り上げられた『脳死』について、授業が進むほどに、私自身は脳死について無知だったと気づき、脳死というものについて正確な知識を身に付けたいと思った。正確な知識を身に付けることこそが、倫理学において、価値判断をする上で必要だと思うので、今後の倫理学の授業が進む上での意欲を駆り立ててくれた。」
「1、2番の課題を書いている時にすでに思っていたが、『脳死』という専門用語をあまり深く知らないのに、価値判断をしていることにとても疑問を感じた。そのようなことが、国会でも行われていたかもしれないと思うと、少し怖いなと思った。」
「事実判断が不十分であったことに気がついた。他の問題などについても、価値判断を下すことは授業課題などで訓練されていたが、事実判断があることが必要なのだと感じた。」
「倫理とは価値判断だけでなく事実判断も必要であるが、価値判断だけでも何かしらの考えが書けてしまうという話を聞いた時、自分の意見がまさにそれであって納得した。脳死臓器移植や植物状態について知らないことばかりなので、事実判断もできるようにしていきたい。」
「『脳死が良いことか悪いことか』という質問には答えることができるのに、『脳死とは何か』という質問には答えにつまって自分でもドキッとした。これからの講義で倫理的な脳死の問題について学んでいくのが楽しみです。」
「事実判断と価値判断の逆転、まんまと先生にだまされたなと思います。日頃気をつけようと心掛けているつもりではいましたが、自然な流れに、何の疑問も持たず書いてしまいました。そのくらい曖昧であり、逆転のリスクは高いのだと改めて感じました。最近の法改正についての報道の『脳死を人の死とする』という見出しや取り上げ方の意味がやっと分かりました。歴史も知らずに価値判断をしていたと思うと、改めておそろしいなと思います。」
「脳死だけでなく、何かの良し悪しを考える時、それがどういうものなのかもあまり考えず、なんとなくで答えを出していることに気づきました。自分の行為がひどく無責任なものに思えてきました。」
さて、看護学校の皆さんはどうだったでしょうか。
きちんと脳死とは何かをわかった上で、
脳死になったときにどうするかという価値判断を下せていたでしょうか。
問3の正解は次に読んでもらうブログのなかに書いてあるので、
各自答え合わせをしてみてください。